🧠 概要:
概要
この記事では、推し(好きなアイドルやキャラクター)への投資が、資産形成として認識されつつある現代のファン文化を探求しています。推しは単なる浪費ではなく、感情的安定や共同体の一部として意義を持つと論じています。推し活は感情経済を基盤にし、個人の神話として形成されますが、その不安定性にも警鐘が鳴らされています。
要約(箇条書き)
- 推し活の変化: 課金が「投資」と認識されるようになった。
- 感情の可視化: 愛が数字化され、資本として流通する「感情経済」。
- 所有の概念: 推しは所有できるものではなく、心理的地権を持つことが重要。
- 推しの熱狂: 特定のIPに対する熱狂は、信仰や共同体感覚をもたらす。
- 価値喪失感: 推しが活動を停止すると「経済的損失」を感じる。
- 物語としての消費: 購入は商品ではなく、「語るべき経験」を得るための行為。
- 感情的合理性: 推しへの投資が感情的な安定をもたらす。
- 不安定な構造: 小さな変化がコミュニティ全体に影響し、自己物語の喪失を感じる。
- 幻想との共生: 推しは幻想か資産か、その答えは常に揺動する。
- 次回のテーマ: 「自己承認」と「他者の視線」の交差について深掘り。
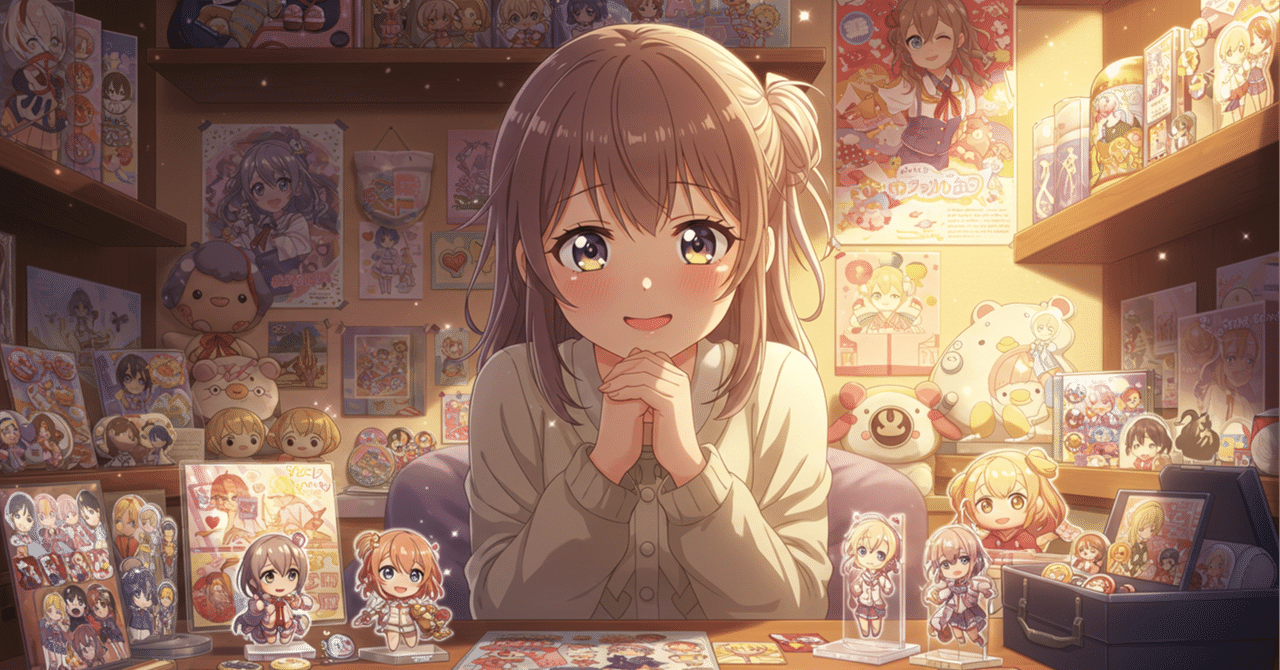
前回の推し活は…
「推しに課金するのは、投資です」──そんな言葉を、いまや誰も笑わなくなった。クラウドファンディング、リターン付きグッズ、ファンコミュニティ限定のオンライン配信。かつては“浪費”と切り捨てられていた支出が、いまでは“資産形成”のように語られている。
推し活とは、感情を可視化する行為だ。エンタメ社会学者・中山淳雄が「感情経済」と名づけたこのシステムでは、愛という曖昧な感情が、デジタル上で数値化され、資本として流通する。
CDの購入枚数、投票イベントの投票数、ファンレターの投稿回数。すべては「どれだけ推したか」の履歴として記録され、やがて“推し歴”という名の通貨に変わる。
そもそも推しとは“所有”できるものなのか?
たとえば、株式は企業の価値を数値化し、部分的に「所有」する権利を売買する。仮想通貨も、信用の塊である。では、推しは?
CDを100枚買っても、ガチャでSSRが出ても、あなたがそのキャラクターやアイドルを「保有」しているとは誰も言えない。むしろ、手に入らないことこそが、この市場の駆動力になっている。
中山氏はこれを、「仮想一等地の熱狂」と呼んだ。
人々は、特定のIP(知的財産)に“心理的地権”を持つことで、そこに居場所を見出す。これはもはや“好き”の範囲を超えている。推しは、信仰であり、共同体であり、そして“経済圏”なのだ。
だからこそ、推しが活動を終了するとき、ファンは「価値の喪失」を感じる。まるで株式が暴落したかのような喪失感、さらには「人生の投資に失敗した」という敗北感すらある。もちろん、そこに明確な利回りなどない。だが、数字では測れない何か──“推しと過ごした時間”という主観的なROI(Return on Investment)を、私たちは常に見積もっている。
それは幻想なのか?
中山氏の著作にたびたび登場するのが、「物語としての消費」という視点だ。人は商品を買うのではない。それを通じて得られる「語るべき経験」を買っている。ライブで泣いた。グッズ列で知らない人と仲良くなった。推しが自分の名前を呼んだ(気がした)。そうした断片が集積され、“推し活”という名の個人神話が形成されていく。
この個人神話の中では、「推しは資産だ」という考え方は、ある意味で正しい。現実の投資が、経済的な安定をもたらすように、推しへの投資は感情的な安定をもたらす。それはしばしば、現実世界の不条理を緩和し、未来に対するモチベーションを回復させる。つまり、推し活とは“経済的な合理性”ではなく、“生き延びるための感情的合理性”の上に成立している。
だが、その構造はあまりにも不安定だ。
新作がこない、声優が降板する、運営が迷走する。わずかな変化が、コミュニティ全体を動揺させる。推しを信じていた世界が崩れるとき、それは単なる“推しロス”ではない。自己物語そのものの喪失だ。
中山氏が警鐘を鳴らすのも、まさにこの点にある。
エンタメが生活の基盤になるということは、感情の金融化であり、それが崩れたときのダメージも“実損”に等しい。ファンの疲弊、燃え尽き、引退。それはまるで、投資家の破産にも似ている。
それでも、人はまた推しを見つける。
新しい推しに出会い、また推し活をはじめる。その繰り返しは、まるでバブル経済のようでもある。だが、それが幻想だとわかっていても、人は幻想に生きることでしか救われないのかもしれない。
「推しは幻想か、資産か」――おそらく、その答えは常に揺れている。そしてその揺れこそが、人間が“物語”という幻想に投資し続ける理由なのだろう。
次回は「“誰のために推しているのか?”」という問いから、推し活における“自己承認”と“他者の視線”の交差について深掘りしていきます。
Views: 0

