🧠 概要:
概要
この記事は、就職活動において企業選びの基準として「営業利益」と「営業利益率」を重視する重要性を説いています。営業利益は企業が本業から得る利益を示し、安定性や将来性を評価するのに役立ちます。特に、過去10年間の営業利益や利益率の推移を確認することで、企業の成長性や収益性を判断し、より良い職場環境を求める手助けになるとします。
要約の箇条書き
-
営業利益の定義
- 企業が本業から得た利益で、売上から本業の費用を引いたもの。
-
営業利益率
- 営業利益を売上高で割った割合で、利益の出しやすさを示す指標。
-
就活生にとっての重要性
- 企業の本業の強さや安定性の評価が可能。
- 一時的利益(経常利益や純利益)に惑わされない指標。
- ブラック企業を避けるヒントとして利用できる。
-
良好な営業利益率の目安
- 業界によって異なるが、同業他社と比較することが重要。
-
営業利益・営業利益率の調査方法
- 有価証券報告書や企業HPで業績を調べる。
- 同業他社と比較し、企業研究に活用する。
-
10年スパンの業績推移の重要性
- 成長企業か停滞企業かが分かる。
- 一時的好業績に惑わされない。
- 外部環境への対応力が見える。
-
数字の裏にある企業戦略の理解
- 成果を生んだ企業選択(戦略)を見極めることが重要。
-
営業利益と従業員の待遇の関係
- 高営業利益は高い平均年収や福利厚生と関連。
- 就活生へのアドバイス
- 営業利益や利益率の推移を重視し、より適切な企業選びを行う。
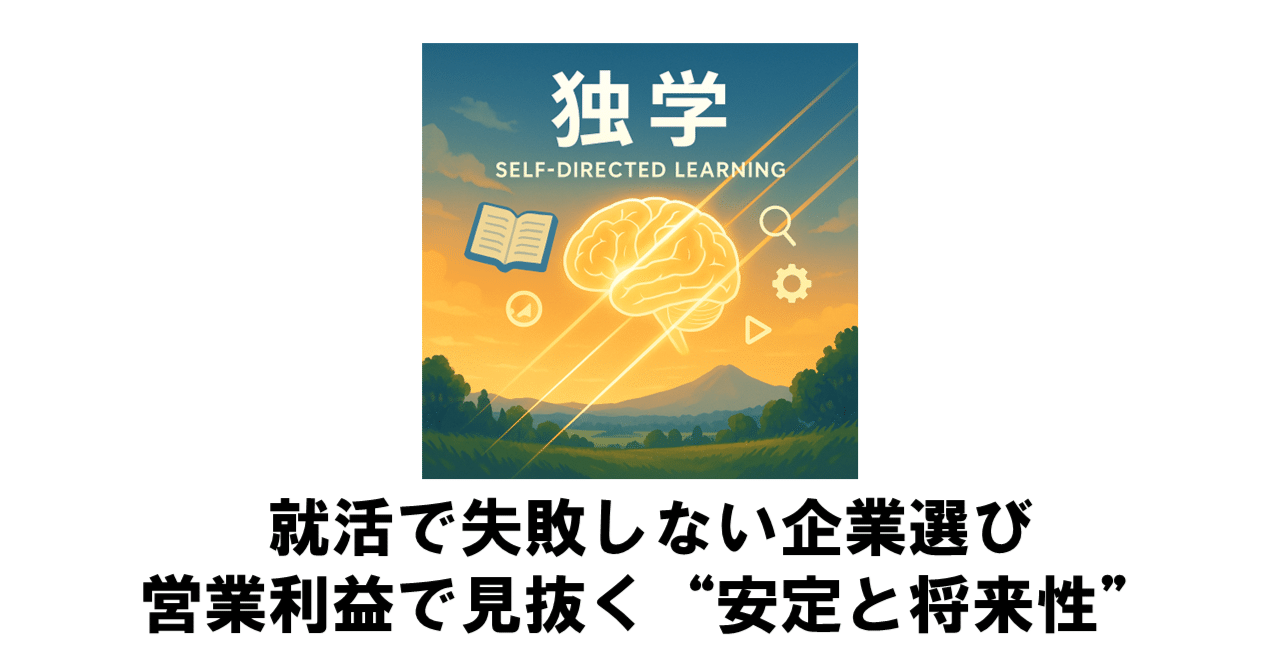
-
営業利益とは、企業が本業(営業活動)で稼いだ利益のことです。
-
売上から、原材料費・人件費・販売費など「本業にかかる費用」を引いたものです。
-
-
営業利益率は、売上に対してどれくらい利益が出ているかを示す割合で、
-
計算式は:営業利益率(%)= 営業利益 ÷ 売上高 × 100
-
営業利益と営業利益率は、主に以下の資料に掲載されています:
■ なぜ就活生にとって重要なのか?
-
企業の「本業の強さ」がわかる
-
利益の出ていない会社は、給与・ボーナス・福利厚生が削られる可能性がある。
-
逆に、営業利益が安定している会社は、働きやすさ・将来性のある企業が多い。
-
-
一時的な利益に惑わされずに済む
-
「経常利益」や「純利益」は投資や為替の影響も含むため、ブレやすい。
-
営業利益は、会社の本業だけを見た健全性の指標。
-
-
ブラック企業を避けるヒントにも
-
営業利益が極端に低い企業は、無理に人を使って利益を出そうとしている場合も。
-
利益率が高いのに給与が低いなら、社員に還元されていない可能性もある。
-
■ どのくらいの営業利益率が良いの?
業界によって違いはありますが、ざっくりとした目安:

同じ業界内で比較するのがポイントです。
■ まとめ:営業利益・営業利益率を就活で活かす方法
ステップやること① 志望企業の業績を調べる有価証券報告書や四季報、企業HPで「営業利益・営業利益率」を確認② 同業他社と比較する自分の志望業界で平均より高い企業をチェック③ 企業研究に活用する面接で「御社は営業利益率が安定しており、安心して働けると感じました」と話せる
✅ 就活アドバイス
「大企業=安定」「聞いたことある会社=安心」という判断は危険です。
数字で企業の本当の実力を見抜く力をつけましょう。
「営業利益率を見る就活生は少数派」だからこそ、他の就活生より一歩リードできます!
一つの企業を深掘りするなら:「過去10年の営業利益・営業利益率の推移」を見よう
企業選びでは「今の業績」だけでなく、「これまでどう成長してきたか」や「今後も安定して稼げる会社か」を見極めることが大切です。
そこで注目したいのが、営業利益と営業利益率の10年スパンでの推移です。
なぜ「過去の推移」が大事なの?
1. 成長企業か、停滞企業かがわかる
-
営業利益が年々伸びていれば、「本業の稼ぐ力」が強化されている証拠。
-
営業利益率も右肩上がりなら、効率的に利益を出せる体質になっていると判断できます。
2. 一時的な好業績にだまされない
-
直近1年の数字だけを見て「業績がいい!」と思っても、それが一時的なブームや特需によるものなら要注意。
-
過去10年で安定して稼げているかを見ることで、「地力」のある企業かどうかが見えてきます。
3. 外部環境への対応力がわかる
-
コロナ禍や原材料価格の高騰、為替変動など、様々な経済的ショックに対して、営業利益が大きく落ちていない企業は柔軟に対応できる力を持っています。
-
逆に、すぐに利益が下がる会社は、景気の波に弱い可能性があります。
どうやって調べるの?
以下のような資料で、過去の業績推移を確認できます。
-
IR資料の「10年業績ハイライト」(多くの上場企業がHPで公開)
-
有価証券報告書(EDINET)の損益情報
-
企業の統合報告書(統合レポート)
企業名と「営業利益 推移」などで検索すれば、グラフ付きでまとめたサイトやPDF資料も見つかります。
まとめ
「過去10年で稼ぐ力がどう変わってきたか」を見ることで、
-
成長性がある企業か
-
安定して働ける会社か
-
景気に強い業種か
が明確になります。志望企業を深掘りする際は、ぜひ「過去の営業利益と営業利益率の推移」にも目を向けてみましょう。
営業利益・営業利益率の「10年推移」の見方と使い方
1. グラフの読み方(営業利益・営業利益率)
① まずは「営業利益の増減」に注目
-
右肩上がりなら: 本業での収益が順調に成長している
-
大きな上下があるなら: 景気や事業構造に影響を受けやすい可能性あり
② 次に「営業利益率の変化」に注目
-
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高 × 100
-
数値の基準感覚:
-
5%未満:やや低い(薄利多売型が多い)
-
5~10%:安定した稼ぐ力あり
-
10%以上:高収益体質(ニッチ戦略やブランド力が強い場合)
-
③ 営業利益と営業利益率が どちらも伸びている のが理想
-
利益が増えていても「売上ばかり伸びて利益率が下がっている」と効率性に課題がある可能性も。
2. 比較表の作り方(例:Excel/ノートでまとめる)
① 必要なデータ(各年の)
② まとめ方の例(横に年、縦に項目)

→ このように10年分を並べると、「成長の流れ」や「利益率の安定性」がひと目で分かります。
③ 折れ線グラフにする(Excelでおすすめ)
-
X軸(横軸):年度
-
Y軸(縦軸):営業利益と営業利益率の2軸で表示(※片方は右側にする)
-
グラフから次のようなことが読み取れます:
-
コロナ禍で利益が落ちたか?
-
新商品や新規事業で利益率が跳ね上がった年は?
-
売上は伸びているのに利益が減っている時期は?
-
3. 企業比較の応用:同業他社との比較も有効!

→ 就活の志望動機や企業選びの「根拠」として、グラフや表を示すと説得力が格段に増します。
補足:データの入手先
-
各社のIRページ(「業績ハイライト」や「決算説明資料」)
-
株探(kabutan.jp):簡易的な業績グラフあり
-
マネックス、SBI証券などの証券口座(ログイン後に詳細データ取得可能)
-
経済産業省・東洋経済の業界レポートなど(業種単位で平均を見ると便利)
なぜ「増えたのか?」を考えることが大切な理由
営業利益や営業利益率が増加している企業は、一見すると「良さそう」に見えます。しかし、それが“なぜ増えたのか”まで理解しておくことが、企業研究や志望動機の質を高める鍵になります。
ポイントは「利益の伸びの裏にある戦略を見ること」
利益の増加は、企業が何らかの戦略的な取り組みを行ってきた結果であり、その中身を理解することで次のような視点が得られます:
1. 成功要因を読み解くことで、その企業の「強み」が見える
たとえば…
-
営業利益が増えた理由:
-
主力製品の値上げに成功 → ブランド力や価格交渉力が高い
-
生産拠点の再編でコスト削減 → 経営の効率性が高い
-
高付加価値な新製品を投入 → 研究開発力・商品企画力がある
-
-
営業利益率が上がった理由:
-
利益率の高いサービス部門を拡大 → 収益構造を転換している
-
顧客の囲い込みに成功 → リピート率の高さがある
-
→ このように、数字の裏には「企業として何をしてきたか(戦略)」が必ずあります。
2. 「過去→現在」の流れがわかると、将来への期待・リスクも見えてくる
利益が増えたからといって、それが「一時的なもの」なのか「持続可能な改善」なのかは分かりません。
【例】増益の中身で印象が変わる:
-
A社:数年前から海外展開を強化 → 徐々に海外売上比率が増え、今期も利益増
→ 中長期視点の成長軸を持っている -
B社:工場閉鎖でコストを大幅にカット → 一時的な利益増
→ 短期的な利益だが、来期以降は未知数
→ このように、一時的な効果か、戦略的な改革の成果かを見極めることで、自分がその企業でどんな未来を描けるかの判断材料になります。
3. 就活での活用:「なぜこの会社か」の説得力が増す
利益が増えているだけを話すよりも、
「御社は○○年から××戦略を推進していて、その結果、営業利益率が△△%→□□%に上がっていると知りました。こうした収益性と変化への対応力に魅力を感じています。」
といったように、数字と企業戦略を結びつけた志望動機は、他の就活生と差がつく強力なアピールになります。
まとめ:数字だけではなく「その背景」に目を向けよう
-
営業利益・営業利益率は企業の“結果”
-
その“結果”を生んだ企業の“選択(戦略)”を見よう
-
数字の裏にある企業努力を読み取ることが、自分の志望理由や将来ビジョンに直結する
営業利益と平均年収の相関関係
1. 実証研究からの裏付け
-
慶應義塾大学の研究では、営業利益と従業員の平均給与の連動性が高い企業ほど、企業業績が向上する傾向があると報告されています。 Koara
-
経済産業省の資料によれば、従業員エンゲージメントスコア(ES)と営業利益率、労働生産性の間に相関関係が確認されています。 経済産業省
2. 一人当たり営業利益と平均年収の関係
-
『ダイヤモンド・オンライン』の記事では、日本のトップクラスの企業では、1人で1,000万円以上の営業利益を稼ぐのが一般的であり、これは高い平均年収と関連しています。 ダイヤモンド・オンライン
-
『東洋経済オンライン』によると、営業利益を社員数で割った「1人当たりの営業利益」は、企業の生産性や事業の付加価値を示す指標であり、その金額が高い企業ほど平均年収も高い傾向があります。 東洋経済オンライン
3. 労働生産性の指標としての一人当たり営業利益
-
「ザイマニ」によれば、労働生産性は従業員一人当たりの営業利益で測定され、計算式は「労働生産性(円) = 営業利益 ÷ 従業員数」です。全業種の中央値は約231万円とされています。 ザイマニ
就活生へのアドバイス
企業選びの際には、営業利益や営業利益率の推移を確認することが重要です。これらの指標は、企業の収益性や成長性を示すだけでなく、従業員への報酬にも影響を与える可能性があります。特に、過去10年間の営業利益や営業利益率の増減を分析し、その背景にある企業戦略や市場環境の変化を理解することで、より適切な企業選択が可能となります。
また、営業利益と平均年収の相関関係を踏まえ、労働生産性の高い企業を志望することで、将来的なキャリアや報酬の向上が期待できます。企業の財務指標を積極的に活用し、自身のキャリアプランに合った企業を見極めましょう。
📊 五大商社の営業利益・営業利益率・平均年収(2024年度)

※営業利益および営業利益率は各社の有価証券報告書に基づく推定値です。平均年収は『KOTORA JOURNAL』の2024年データを参照しています。 Kotora
🔍 営業利益と平均年収の相関関係
上記のデータから、営業利益および営業利益率が高い企業ほど平均年収も高い傾向が明確に見て取れます。これは、企業の収益力が高いほど、従業員への報酬も手厚くなることを示しています。
例えば、三菱商事は営業利益が11,000億円、営業利益率が8.5%と最も高く、平均年収も2,090万円でトップです。一方、丸紅は営業利益7,500億円、営業利益率6.0%で、平均年収も1,654万円と他社に比べて低めです。
💡 営業利益と平均年収を分析する意義
-
企業の収益性の指標: 営業利益は企業の本業から得られる利益を示し、営業利益率は売上高に対する営業利益の割合を示します。これらの指標が高いほど、企業の収益性が高いと判断できます。
-
従業員への還元度合いの把握: 高い営業利益を上げている企業は、従業員への報酬や福利厚生にも積極的に投資している傾向があります。平均年収の高さは、その一つの表れです。
-
企業選びの参考: 就職活動において、企業の安定性や将来性を判断する際に、営業利益や平均年収の推移を確認することは有効です。これらのデータは、有価証券報告書や企業のIR資料、就職情報サイトなどで入手可能です。業界動向サーチ
🧮 営業利益率の計算方法
営業利益率は以下の式で計算されます:
営業利益率(%) = (営業利益 ÷ 売上高) × 100
例えば、営業利益が1,000億円、売上高が1兆円の場合:
(1,000億円 ÷ 1兆円) × 100 = 10%
営業利益や営業利益率、平均年収などの財務指標を総合的に分析することで、企業の実力や従業員への還元姿勢を把握できます。これらの情報は、企業選びやキャリア設計の重要な判断材料となります。特に総合商社のような多角的な事業展開を行う企業では、これらの指標が企業の健全性や将来性を示す重要なファクターとなります。
🔍 営業利益・営業利益率と従業員の待遇の関係
1. 営業利益は「本業のもうけ」=自由に使えるお金の源
-
営業利益は「売上高から本業の経費を引いた利益」です。
-
これが多いほど、企業は人件費(給与・ボーナス)、福利厚生、設備投資などにお金を回す余裕があることを意味します。
-
利益が出ていない企業では、従業員にお金をかけたくても原資がないため難しいのです。
2. 営業利益率は「効率の良さ」の指標
-
たとえば、同じ1兆円の売上を出していても、営業利益が1,000億円の企業(営業利益率10%)と、100億円しか出ていない企業(1%)では、収益力の差は歴然。
-
効率よく儲けている企業は、内部留保や将来の賃上げ原資を確保しやすくなります。
💡 なぜ賃上げの「原資」は営業利益なのか?
-
企業の収益からまず引かれるのは、仕入れや人件費などの「固定的な支出」。
-
そこを差し引いたあとに残るのが「営業利益」。
-
この営業利益から、配当・税金・再投資・賃上げや福利厚生の充実が行われます。
つまり、営業利益が少ない企業は「賃上げしたくてもできない」ことが多いのです。
📈 例:実際の商社で見る傾向

このように、営業利益が高い企業は、年収も高く、賃上げにも積極的です。
✅ 就活生が覚えておくべきこと

🗒️ まとめ
営業利益が出ている企業は「余裕」がある。余裕があるから、人にもお金をかけられる。
したがって、企業の儲け(営業利益・営業利益率)を見ることは、「その会社であなたがどれだけ大切にされるか」のヒントになります。
Views: 0

