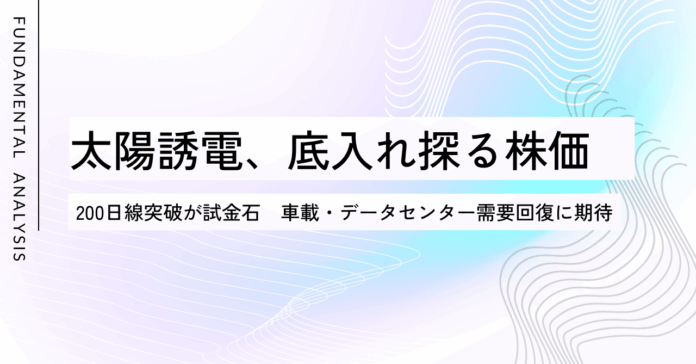🧠 概要:
概要
太陽誘電(6976)は、長期的な下降トレンドからの反発を示している。株価は底入れの兆しを見せ、200日移動平均線の突破が中長期的な投資戦略の鍵となる。主に自動車とデータセンター向けの需要回復が見込まれており、財務面も健全で、株主還元の方針も強化されている。今後の業績回復に期待する一方、経済や競争環境のリスクに留意する必要がある。
要約の箇条書き
- 底入れ兆候: 太陽誘電は過去の厳しい市場環境からの回復を示唆。
- 株価動向: 200日移動平均線の突破が中長期的な買いシグナルのポイント。
- 価格回復: 2024年7月から約5,164円が高値、2025年4月には1,739円まで急落。
- 需要回復: 車載やデータセンター向けの需要が期待される。
- ファンダメンタルズ: 2025年3月期決算では売上高が前年より5.8%増加したが、特損による純利益は大幅減。
- V字回復計画: 2026年3月期は大幅な営業利益の増加を計画。
- 財務安定性: 自己資本比率は58%を維持し、財務基盤は健全。
- 配当方針の強化: 年間90円の配当を予定し、投資家への還元を重視。
- 市場リスク: 地政学的リスクや競争激化に注意が必要。
- 投資戦略: 短期・中期・長期での投資の進め方が提案されている。
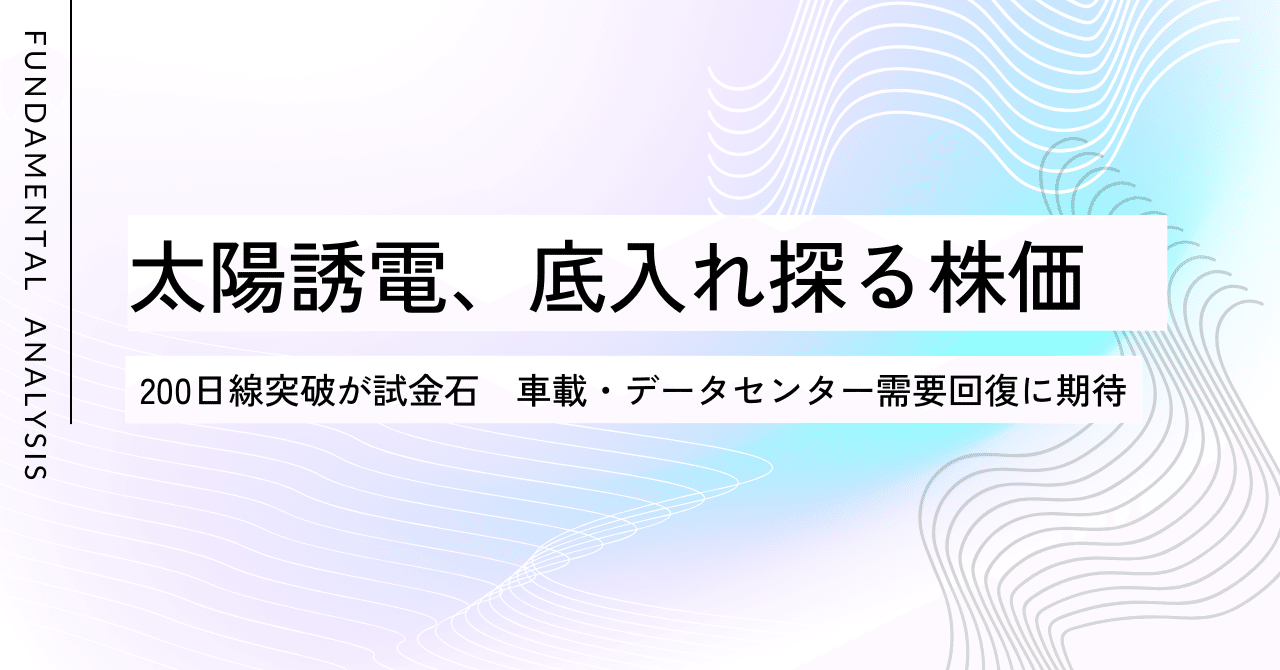
電子部品大手の太陽誘電(東証プライム:6976)は、過去数年にわたる厳しい市場環境と一時的な大幅減益という試練を経て、株価・業績両面で底入れの兆しを見せつつある。本稿では、同社の現状と将来性を、テクニカルチャートの読み解きと、ファンダメンタルズの多角的な分析を通じて深く掘り下げ、中長期的な投資戦略の指針を探る。
株価は底値圏脱出のサイン点灯か、200日線と心理的節目3,000円の攻防が焦点
太陽誘電の株価は、2024年7月につけた約5,164円の輝かしい高値から一転、厳しい下降トレンドに突入した。同年12月には2,083円まで急落し、市場のセンチメントは急速に冷え込んだ。追い打ちをかけるように、2025年4月9日には1,739円という年来安値を更新。しかし、この1,700円台後半が強固な下値支持帯として機能し、そこを起点に力強い反発を見せている。直近では2,300円から2,500円のレンジまで回復し、短期的な勢いを示す50日移動平均線(執筆時点で概ね2,200円台後半と推定)を明確に上回る水準で推移している。
[長期トレンド転換の鍵握る200日線]
依然として株価の上方に重くのしかかるのは、長期的なトレンドを示す200日移動平均線(同2,700円台前半と推定、かつ下降傾向)である。このラインを株価が明確に上抜け、かつ50日線が200日線を下から上に突き抜ける「ゴールデンクロス」が形成されれば、それは市場参加者にとって中長期的な上昇トレンドへの転換を示唆する強力な買いシグナルとなる。現状、両線はまだ距離があるものの、株価が200日線に接近する動きは注目に値する。
[オシレーター系指標は短期過熱と中期的改善の交錯]オシレーター系の指標を見ると、短期的な過熱感と中期的な改善の兆しが混在している。価格反発に伴い、短期の相対力指数(RSI、14日)は直近で70ラインに到達しており、これは一般的に「買われ過ぎ」とされる水準だ。このため、短期的には利益確定売りなどによる調整、いわゆる「押し目」形成の可能性を念頭に置く必要がある。
一方で、MACD(平滑化期間12日と26日の指数移動平均の差)は、4月の株価底値形成以降、MACDラインがシグナルライン(MACDの9日指数移動平均)を明確に上抜ける強気の買いサイン(ゴールデンクロス)を示現している。さらに、MACDヒストグラム(MACDとシグナルラインの差)もプラス圏に浮上し、その幅を拡大しつつあり、市場のモメンタムが買い方優位に転換しつつあることを示唆している。RSIの高水準が一時的な調整を促すとしても、MACDの好転は中期的な上昇期待を裏付ける。
[一目均衡表は「三役好転」への期待感]一目均衡表においても、好転の兆しが随所に見られる。株価は日々の値動きの中心を示す転換線、および中期的な方向性を示す基準線を既に上抜けており、短期的な上昇基調は鮮明だ。過去26日間の株価を現在にシフトした遅行スパンも、日々の株価を上抜けつつあり、これも買い方優位への変化を示唆する。
ただし、本格的な強気相場入りを示す「三役好転」――(1)株価が「雲」(先行スパン1と先行スパン2に挟まれた抵抗帯・支持帯)を上抜ける、(2)転換線が基準線を上抜ける(既に達成)、(3)遅行スパンが日々の株価を上抜ける(達成しつつある)――の条件を完全に満たすには、まだ株価が雲の上限を突破する必要がある。この雲の上限は、現在2,600円~2,700円近辺に位置していると推測され、前述の200日移動平均線や3月19日につけた戻り高値2,713円とほぼ同水準にある。この価格帯を出来高を伴って突破できるかが、トレンド転換の確度を高める上で極めて重要となる。
[支持線・抵抗線と出来高動向が示す市場心理]下値のサポートラインとしては、まず直近ボトムとなった1,739円を含む1,700円台後半~1,800円近辺が、二番底を形成した強固な支持帯として意識される。その上では、過去に揉み合った2,100円~2,200円付近が中期的な支持ゾーンに転換している。一方、上値のレジスタンスラインは、まず前述の2,700円台(直近高値圏、200日線、雲の上限)が最初の関門となる。ここを突破すれば、心理的節目である3,000円が次のターゲットとして浮上する。
出来高の分析も重要だ。2025年2月に業績予想の上方修正が発表され、株価がストップ高を演じた際には商いが急増した。これは、市場がポジティブなニュースに強く反応することを示している。また、4月の安値形成局面でも出来高が増加しており、これは一部投資家による投げ売り(キャピチュレーション)が一巡し、そこから買いが入った可能性を示唆する。直近の株価反発局面では、出来高は平均的な水準ながらも徐々に増加傾向にあり、上昇トレンドを裏付ける需給の改善がうかがえる。今後は、重要な抵抗線を突破する際に、さらなる出来高の増加が伴うかどうかが注目される。
総じてテクニカル面では、短期的な過熱感を警戒しつつも、中長期的には底打ち反転のシグナルが複数点灯し始めており、押し目買いの好機や、重要な抵抗線突破によるブレイクアウト戦略を検討する価値がある局面と言えよう。
本業回復と成長戦略が鍵、一時的損失乗り越え再成長へ
ファンダメンタルズ面に目を転じると、太陽誘電の経営状況は、厳しいトンネルの出口に差し掛かっているように見える。
[2025年3月期決算:特損響くも、本業には回復の兆し]2025年3月期決算は、売上高が前期比5.8%増の3,414億円、本業の儲けを示す営業利益が同15.2%増の104億円と、増収増益を達成した。これは、低迷していた情報機器(PC、スマートフォンの一部)や産業機器向け需要の持ち直しに加え、円安進行による為替差益が貢献した結果だ。しかし、経常利益は105億円と前年から23.6%の減少。さらに、親会社株主に帰属する当期純利益は、わずか23億2,800万円と、前期比72.0%減という大幅な落ち込みを記録した。この純利益急減の主因は、為替予約等に関連するデリバティブ評価損を含む為替差損の発生と、過去のカルテル問題に関連する独占禁止法関連損失引当金の繰り入れという、合計数十億円規模の特別損失の計上によるものだ。これら一過性の費用が利益を大きく圧迫し、同社の当期純利益率は約0.7%という異例の低水準に沈み、ROE(自己資本利益率)も約2%前後(前期は6%台後半と推定)へと大幅に低下、ROA(総資産利益率)も低迷した。
だが、これらの特殊要因を除けば、営業利益段階では増益を確保しており、本業の収益力は底堅さを見せ始めている。営業利益率は3.0%強と、かつての10%を超える水準には道半ばだが、顧客在庫調整の進展や、生産体制の効率化、そして前述の一過性費用が剥落すれば、利益率は改善に向かう素地がある。
[2026年3月期計画:V字回復目指すも、市場は慎重な見方も]会社側は、続く2026年3月期に向けて野心的な計画を打ち出している。売上高は3,400億円と前期並みを維持しつつ、営業利益は前期比53.8%増の160億円、純利益に至っては同243.6%増の80億円(約3.4倍)と、大幅なV字回復を目指す。この計画の背景には、自動車の電装化・電動化の加速(xEV向けコンデンサの需要増)、データセンター投資の継続(サーバー向け大容量コンデンサの需要増)といった構造的な需要増による収益性向上を見込む一方で、為替レートの前提を1ドル140円程度と、前期実績(1ドル145円程度と推定)よりも円高方向に見ているため、売上高は横ばいを見込んでいる。この計画通りに進めば、予想営業利益率は約4.7%、予想純利益率は約2.4%へと改善する見通しだ。ただし、市場コンセンサス(アナリスト予想平均)は、2026年3月期の営業利益を110億円程度と、会社計画よりもやや慎重な見方をしている。これは、太陽誘電が2025年3月期においても、期初予想を下方修正(一時は純利益ゼロ予想)した後、最終的に需要回復を受けて上方修正に転じるなど、業績予想の変動が大きいことへの警戒感の表れとも言える。電子部品市場のボラティリティの高さを考慮すれば、受注動向や主要顧客の生産計画を継続的に注視する必要がある。
https://pdf.irpocket.com/C6976/RzLT/KbxT/hqHC.pdf
[財務健全性は盤石、投資フェーズ一巡でキャッシュフロー改善へ]財務面では、自己資本比率が直近期末(2025年3月末)で約58%(前期末約60%)と、依然として55~60%台の高水準を維持している。これは電子部品業界の中でも健全な部類に入り、財務基盤の安定性は高いと評価できる。有利子負債は、MLCCの生産能力増強のための工場設備投資(群馬県の高崎工場や新潟太陽誘電など)に伴い一時的に増加したが、営業キャッシュフロー(2025年3月期は339億円の黒字)で十分にカバーできる範囲であり、有利子負債倍率(ネットD/Eレシオなど)も低位で安定している。実際、近年の積極的な設備投資フェーズは一巡しつつあり、設備投資額は2024年3月期の922億円から2025年3月期には660億円へと減少した。これにより、今後は投資キャッシュフローのマイナス幅が縮小し、フリーキャッシュフロー(営業CF-投資CF)の改善が期待される。これは、将来の成長投資や株主還元余力の拡大に繋がる。
https://www.yuden.co.jp/jp/ir/financial/financial_highlight.html
[バリュエーション:PBR1倍割れは割安感、高配当利回りも魅力]現在の株価水準(本稿執筆時点で2,400円台と仮定)におけるバリュエーション指標を見ると、2026年3月期の会社予想EPS(1株当たり純利益)約63円(80億円 ÷ 約1億2600万株)に基づけば、予想PER(株価収益率)は約38倍となる。これは、純利益が一時的な特殊要因で大きく落ち込んだ2025年3月期の実績PER(約130倍)よりは大幅に改善するものの、依然として市場平均(一般的に15倍前後)と比較すると割高に見える。しかし、これはあくまで回復途上の利益水準を反映したものであり、将来的に利益水準が平準化(例えば営業利益率10%超、純利益200億円規模など)すれば、PERはより魅力的な水準に低下する余地がある。一方、PBR(株価純資産倍率)は、直近のBPS(1株当たり純資産)約2,500円(2025年3月末の純資産約3,150億円 ÷ 約1億2600万株で試算)に対して約0.96倍と、1倍を割り込んでいる。PBR1倍割れは、一般的に株価が解散価値に近い水準で評価されており、市場が同社の将来の収益性や成長性を十分に織り込んでいない可能性、あるいは何らかのリスクを過剰に評価している可能性を示唆する。業績回復が本格化すれば、このディスカウントは解消に向かうだろう。さらに注目すべきは株主還元だ。同社は2026年3月期に年間90円の配当を予定しており、現在の株価水準(2,400円台)での配当利回りは約3.7%と比較的高水準にある。太陽誘電は2025年5月、株主還元方針を見直し、従来の連結配当性向30%目標に加え、新たにDOE(自己資本配当率)3.5%以上を目安とする方針を導入した。DOEは、純利益の変動に左右されにくい自己資本を基準とするため、業績が一時的に落ち込んだ場合でも安定的な配当を維持しやすくなる。この方針変更は、資本効率を意識しつつ、株主への安定的な利益還元を重視する姿勢の表れとして、中長期投資家からは好感されるだろう。自社株買いについては現時点では具体的な発表はないものの、資本効率向上への言及もあり、今後の財務戦略の一環として期待される。
また、市場で一時懸念された米中摩擦に絡む米国の対中追加関税リスクについて、会社側は「限定的」との見解を示しており、過度な悲観論は後退しつつある。
セグメント別動向と成長ドライバー:車載・情報インフラが中核、MLCC依存からの多角化も模索
太陽誘電の事業構造と成長戦略を詳細に見ると、その強みと課題が浮き彫りになる。
[主力MLCCは車載シフト、インダクタも堅調]製品別売上構成(2025年3月期ベースと推定)では、依然として積層セラミックコンデンサ(MLCC)が全体の約68%を占める最大の柱だ。MLCC事業は、かつて高成長を牽引したスマートフォン市場の成熟化やPC需要の低迷といった逆風にさらされたものの、近年は自動車の電装化・電動化(ADAS、EV、コネクテッドカーなど)の進展に伴う車載向けMLCCの需要拡大が力強い成長ドライバーとなっている。また、5G基地局やデータセンターサーバーといった情報インフラ向けの高性能・大容量MLCCも需要が堅調だ。2025年3月期第3四半期時点のデータでも、コンデンサ売上はPC・通信機器向け(SSDや基地局)および自動車向けが増加し、ゲーム機等の民生機器や一部産業機器向けの減少を補った。インダクタ(高周波チップコイルなど)事業は、売上構成比ではMLCCに次ぐ規模だが、スマートフォン向け高周波インダクタやPCの電源回路向けパワーインダクタを中心に堅調に推移しており、2025年3月期は前期比で+9.5%と二桁近い成長を遂げた。特にスマートフォン向けでは、高性能化に伴う搭載員数増の恩恵を受けている。
https://pdf.irpocket.com/C6976/wLlX/IdQY/pX16.pdf
[複合デバイスは苦戦、その他も減少]
一方で、複合デバイス事業(スマートフォン向けのSAW/FBARフィルタなど)は、中国系スマートフォンメーカーの需要減少や競争激化の影響を受け、2025年3月期は前期比▲12.0%と大きく落ち込んだ。この分野では、米ブロードコム(旧アバゴ)などの海外大手との競争が厳しく、収益性の改善が課題となっている。アルミ電解コンデンサ等を含む「その他」部門も、市況の影響を受け同▲10%程度の減少となった。
[成長戦略の焦点:車載・情報インフラへの集中と技術開発]太陽誘電は、現行の「中期経営計画2025」(2021~2025年度)において、「注力すべき市場」として車載、情報インフラ・産業機器を明確に定義し、経営資源を重点的に投下している。これらの市場で、MLCC、インダクタ、そして将来的には通信デバイスの3事業をバランス良く成長させる戦略を掲げる。特に車載向けでは、高温・高湿度・高振動といった過酷な環境下でも高い信頼性を維持できる高品質なMLCCやインダクタの開発・供給体制を強化している。足元の受注動向も回復を示唆している。2024年10-12月期の全社受注高は885億円と、前四半期(7-9月期)の854億円から増加に転じ、底打ち感が出ている。これは、市場全体の在庫調整が一巡し、実需が回復し始めたことを示している。特に自動車向け電子部品(ADAS関連、EVのパワートレインやバッテリーマネジメントシステム向けなど)や、AIサーバーを含むデータセンター向け(サーバー用CPU/GPU周辺の大容量・低ESLコンデンサ等)では、今後も中長期的な需要拡大が見込まれ、これらが業績成長の柱となることは確実視される。
https://www.yuden.co.jp/jp/ir/2023ar/download/pdf/yuden_ar23_j_p18_p19.pdf
[競争優位性:材料技術と高付加価値製品、ニッチ市場での展開]太陽誘電は、電子部品業界において村田製作所や京セラといった巨大企業と比較すると中堅規模ながら、独自の強みを持つ。主力のMLCC分野では、誘電体セラミック材料の組成技術や薄層化・多層化技術において高い技術力を有し、小型でありながら大容量、かつ高信頼性の製品開発で世界市場において一定のプレゼンスを確保している。特に、xEVや産業ロボット、医療機器といった高度な信頼性が要求される分野向けのハイエンド製品群は、同社の競争優位性の源泉だ。通信デバイス事業(SAW/FBARフィルタ)では、前述の通り厳しい競争環境にあるが、特定の周波数帯や中国市場など、ニッチな領域でのシェア獲得を目指している。ビジネスモデルとしては、単一製品・単一市場に依存するリスクを避けるため、MLCCとインダクタという複数の収益源を持ち、顧客の業種も民生用から車載、産業機器へと分散を図っている点は評価できる。さらに、新規事業への取り組みとして、2025年のCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)では、触れると表面の質感が変化するハプティック(触覚)デバイスを内蔵した車載インパネ用デバイスを展示するなど、センシング技術やIoT(モノのインターネット)関連ソリューションへの展開も模索している。こうした応用展開力と技術開発への継続的な投資は、中長期的な競争力維持に不可欠である。
https://pdf.irpocket.com/C6976/RzLT/KbxT/hqHC.pdf
経営計画と業界環境:計画未達からの再起、構造変化への対応が急務
[中期経営計画の総括と次期計画への課題]現行の5カ年計画「中期経営計画2025」(2021~2025年度)は最終年度を迎えるが、当初掲げた売上高4,800億円、営業利益率15%といった高い目標には未達となる見込みだ。この未達の要因としては、計画策定時には想定しきれなかったスマートフォン市場の急激な成熟化、新型コロナウイルス感染症パンデミック後のサプライチェーン混乱、そして地政学リスクの高まりによる世界経済の減速といった外部環境の激変が大きい。しかし、これらの外部要因だけでなく、ポートフォリオ戦略やコスト競争力といった内部要因についても、次期中期経営計画ではより踏み込んだ見直しと、より現実的かつ達成可能な収益力強化策が求められる。経営陣は「経済価値(収益性)と社会価値(サステナビリティ貢献)の両輪で企業価値向上を図る」との方針を掲げており、具体的な財務目標としてROE15%以上の達成を改めて目指している。
https://www.yuden.co.jp/jp/ir/2021ar/download/pdf/Yuden_AR21-J_p26-p28.pdf
[業界環境:サイクルと構造変化の波、競争は激化]電子部品業界は、シリコンサイクルとも呼ばれる需要の好不況の波が大きいことで知られる。スマートフォンやPCといった民生機器の需要が一巡したここ1~2年は調整局面にあり、多くの部品メーカーが業績の踊り場を経験した。しかし、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアード、電動化)の進展や、AI・IoT普及に伴うデータセンター投資の拡大、再生可能エネルギー関連といった構造的なメガトレンドは依然として力強く、これらの分野をターゲットとする部品需要は中長期的に拡大が見込まれる。競合状況を見ると、MLCC世界首位の村田製作所は、圧倒的な生産規模と幅広い製品ラインナップ、高い技術力で他社をリードしており、太陽誘電との規模の差は依然として大きい。ただし、村田製作所もスマートフォン需要の減速の影響は受けており、業界全体が車載・産業機器へと軸足を移す動きは共通している。TDKは、MLCC以外にもセンサーや二次電池、HDD用ヘッドなど事業ポートフォリオが多角化しており、太陽誘電との直接的な競合領域はMLCCやインダクタの一部に限られる。海外勢では、韓国のサムスン電機や台湾のヤゲオなどがMLCC市場で強力なライバルだが、太陽誘電は前述の通り、高信頼性が求められるニッチ市場や、独自の材料技術を活かした高性能品で差別化を図り、生き残りをかけている。
業界全体の課題としては、米中技術覇権争いに端を発するサプライチェーンの分断リスクや、各国政府による輸出入規制の強化が挙げられる。太陽誘電は、米国による対中制裁関税の直接的な影響は限定的と説明しているが、中国経済の減速が間接的に同社製品の需要を押し下げるリスクや、特定のレアアースなど原材料の調達リスクについては常に注意が必要だ。幸い、同社の製品群は汎用品から高付加価値品まで幅広く、需要変動に対しては生産調整で対応する柔軟性を持つ。過去には、需要急増時に供給不足に陥るほど引き合いが強い製品力も示しており、今後は変化する市場環境への迅速な対応と、安定供給能力の維持・強化が競争力の鍵となるだろう。
総合評価と投資判断:底打ち反転期待、中長期的な妙味と短期的な注意点
太陽誘電のテクニカル・ファンダメンタルズを総合的に分析すると、同社はまさに「夜明け前」の状況にあり、株価・業績ともに底打ちから反転上昇へと転じる重要な岐路に立っていると評価できる。
[テクニカル面:長期トレンド転換の初動、重要抵抗帯の突破が試金石]
テクニカル面では、長期にわたる下落トレンドからの転換を示唆する複数のサインが点灯し始めている。短期的にはRSIが高水準にあるため調整の可能性も視野に入れるべきだが、MACDの好転や一目均衡表の改善は中期的な上昇期待を後押しする。最大の注目点は、2,700円台に集中する200日移動平均線、直近戻り高値、そして一目均衡表の雲上限といった強力なレジスタンスゾーンを、出来高を伴って明確に突破できるか否かだ。これを達成できれば、市場のセンチメントは大きく好転し、3,000円の心理的節目、さらにはその上を目指す展開も期待される。
[ファンダメンタルズ面:一過性要因剥落後のV字回復に期待、PBR1倍割れは魅力]ファンダメンタルズ面では、2025年3月期決算で表面化した大幅減益の多くは一過性の特殊要因によるものであり、本業の収益力は徐々に回復基調にある。会社が計画する2026年3月期の大幅な営業増益が実現すれば、各種収益性指標は大きく改善し、現在割高に見えるPERも市場平均に近づいていくだろう。PBRが1倍を割り込んでいる現状は、業績回復期待を考慮すれば魅力的なエントリー水準と言える。特に、自動車および情報インフラという成長市場向けの製品需要の取り込みが順調に進み、為替レートが想定以上に円安で推移する、あるいはコスト構造改革が奏功すれば、会社計画を上回る業績も期待できる。
強化された株主還元方針(DOE3.5%以上の安定配当)は、配当利回り約3.7%という魅力を高め、インカムゲインを享受しながら中長期的なキャピタルゲインを狙う投資家にとって心強いサポートとなる。
留意すべきリスク要因
もちろん、楽観一辺倒ではいられない。留意すべきリスクとしては、以下の点が挙げられる。
-
マクロ経済・市況変動リスク | 世界的な景気後退懸念が再燃した場合、スマートフォンやPC市場の回復が遅れる、あるいは自動車生産が調整局面に入る可能性。
-
地政学リスク | 米中対立の先鋭化、台湾有事といった地政学的緊張がサプライチェーンを再度寸断するリスク。
-
為替変動リスク | 想定以上の円高進行は、輸出比率の高い同社の収益を圧迫する。
-
競争激化と技術陳腐化リスク | MLCCやインダクタ市場における競合他社との技術開発競争は常に激しく、新技術への対応が遅れればシェアを失う可能性がある。特に中国メーカーのキャッチアップも警戒される。
-
特定顧客への依存リスク | 主要顧客の経営戦略変更や発注量削減が業績に影響を与える可能性(具体的な依存度は非開示だが一般論として)。
これらのリスク要因を常に念頭に置きつつも、太陽誘電の堅牢な財務基盤、中核市場における構造的な需要増、そして技術開発力と高付加価値製品へのシフトといった強みを総合的に勘案すれば、中長期的に業績および株価の回復ポテンシャルは高いと判断できる。
[投資戦略:押し目買いとブレイクアウト追随、時間軸に応じたアプローチ]
現在の株価水準は、PBR1倍近辺ということもあり、中長期的な視点では下値不安が限定的で、業績改善が市場に認知されるにつれて見直し買いが入りやすい水準と言える。
-
短期投資(数週間~数ヶ月) | テクニカル指標の短期的な過熱感から、2,300円~2,400円近辺への押し目を待ってエントリーを検討。2,700円台のレジスタンス突破時には、モメンタムに乗じた短期的な追随買いも考えられるが、その際は出来高の伴いを注視。
-
中期投資(半年~1年程度) | 2,000円~2,200円のサポートゾーンまで調整する局面があれば、分割での買い増しを検討。2026年3月期の業績進捗を確認しながら、3,000円~3,500円といった水準を目指す。
-
長期投資(1年以上) | 配当利回りを享受しつつ、業界サイクルに左右されにくい車載・情報インフラ分野での同社の成長と収益体質の強化に期待。数年単位での株価回復と成長を見据え、時間分散を意識した積立投資も有効。
結論として、太陽誘電の株式は、足元の業績が底を打ち、回復への道のりを歩み始めた「ターニングポイント」にあると位置付けられる。短期的には市場のボラティリティに注意が必要だが、中長期的な視点で見れば、現在の株価水準は慎重な楽観を持って投資妙味を探る価値のある魅力的な局面にあると言えるだろう。今後の四半期ごとの業績発表や、次期中期経営計画の内容が、市場の評価を一段と高める触媒となるか注目される。
Views: 1