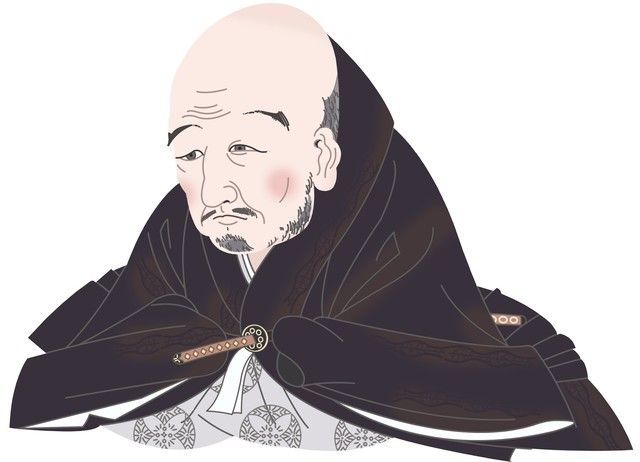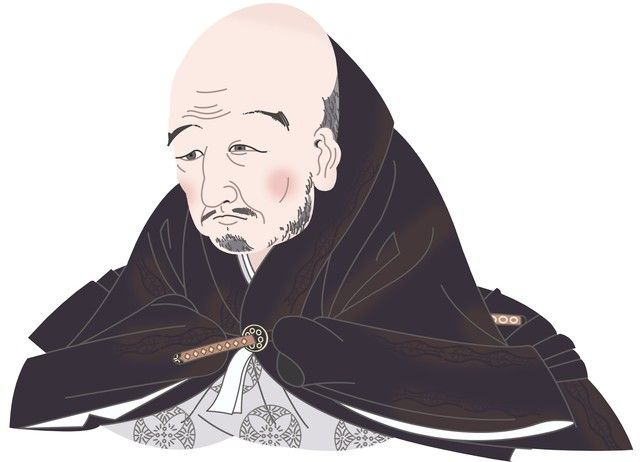
NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第32回「新之助の義」では、大坂の米屋が庶民の襲撃を受けたことをきっかけに、江戸でも不穏な空気が流れ……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)
「御三卿」で最も将軍から遠かったのは?
「そこまでやるか……」と、放送後に視聴者の声がSNSで相次いだ。陰謀を張り巡らせてきた、生田斗真演じる一橋治済(はるさだ)のことだ。なんと今回の放送では、物乞いに変装して、米の高騰に怒れる民たちの暴動を煽ったのだ。
悪役として振り切った感のある『べらぼう』の治済だが、一橋家から将軍を出すには、かなりの困難が伴ったのは事実である。
8代将軍の徳川吉宗が設けた「御三卿」のうち田安家と一橋家は、吉宗が次男と四男を独立させてつくった家だ。もう一家は、次代将軍の家重が次男を独立させてつくった清水家である。もともと御三卿は、子どもたちの養子先が見つかるまでの仮の家だったが、結果的に将軍後継者の選択肢を増やすこととなった。
表向きは御三卿の三家に上下はないことになっていたが、田安家は吉宗の次男を当主としており、創設が最も古い。そのため、四男の宗尹(むねただ)を当主とする一橋家より格上とされていた。
一方、清水家はというと、三家の中で創設が最も遅いものの、当主の徳川重好(しげよし)は家治の弟にあたり、10代将軍の家治からすれば、血筋は最も近い。
そして、そもそも家治には、聡明で体が丈夫な嫡男の家基(いえもと)がいた。将軍の座は問題なく嫡男へと継承されるはずだった。
そんな点を踏まえると、一橋家から将軍を出すのは相当にハードルが高かった。にもかかわらず、いろいろな偶然が重なり、治済の嫡男・豊千代が将軍の座を射止めることになった。
その「偶然」とは、田安家では2代当主・田安治察(はるあき)が亡くなってしまい、後に松平定信となる賢丸をはじめ他の男子は養子に出してしまっているなか、最有力候補だった将軍家の徳川家基が若くして急死してしまった。
清水家の清水重好は家治と年が近く、かつ子がいなかったことから、近い将来にまた将軍継嗣問題が発生する可能性があった。なにより自身が政争を好まなかったことから、将軍候補を辞退したとされている。そのため、おのずと一橋家から将軍を出すこととなった。
このような巡り合わせのなかで、清水家の事情以外は、すべて治済の陰謀によるものだった──というのが『べらぼう』での設定となっている。必要とあれば、治済自身が物乞いの格好をして最前線に出ることくらいのことは、やってのけてもおかしくはない。
ただ、今回の放送では、ボスキャラとして無敵のようだった治済が、尾張徳川家の徳川宗睦(むねちか)、水戸徳川家・徳川治保(はるもり)、紀伊徳川家・徳川治貞(はるさだ)と御三家に圧倒される場面もあった。
ここからは、新たな老中・松平定信が、11代将軍・家斉のもとで辣腕を振るうことになる。治済と定信のパワーバランスがどのようになるのかも気になるところだ。
https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘2054076421511845’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
🧠 編集部の感想:
大河ドラマ『べらぼう』が描く物語は、江戸時代の社会情勢を反映していて興味深いです。米価高騰に伴う民衆の暴動というテーマは、現代にも通じるメッセージがあります。特に一橋治済の陰謀がどのように展開するのか、今後のストーリーが楽しみです。
Views: 0