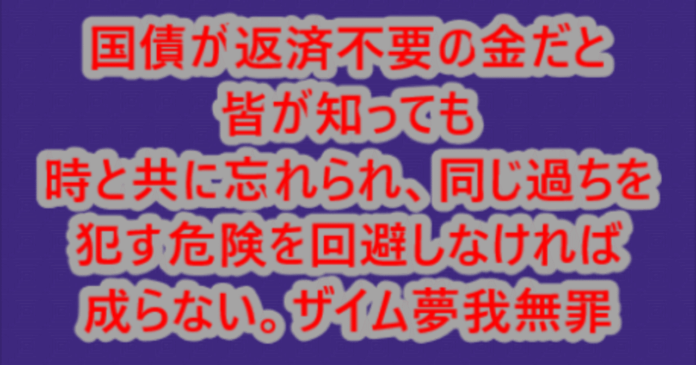🧠 概要:
概要
この記事では、日本の国債についての一般的な誤解を解説し、国債が実際には「借金」ではなく「通貨発行の間接的な手段」であると説明しています。国債の発行が経済に与える役割や、その誤解が「財政健全化」や「緊縮政策」に繋がる背景も取り上げられています。
要約
- 国債は借金ではない: 多くの人が国債を借金と見なすが、国家は通貨発行の権限を持つため、国債は「借金」ではなく「通貨発行の手段」と言える。
- 通貨供給の仕組み: 国債は政府の財政支出を支える役割があり、市中銀行や日本銀行によって通貨供給が行われる。
- 恒常的な借換え: 元本は永久にロールオーバーされるため、国債は返済義務がない実態がある。
- 経済の下支え役: 不況時においては、民間の信用創造が機能不全になり、国債発行で社会にお金を供給することが重要。
- 誤解の原因: 国債が「借金」と誤解されることにより、「財政健全化」や「緊縮政策」へと繋がる歴史的背景と制度設計の問題がある。
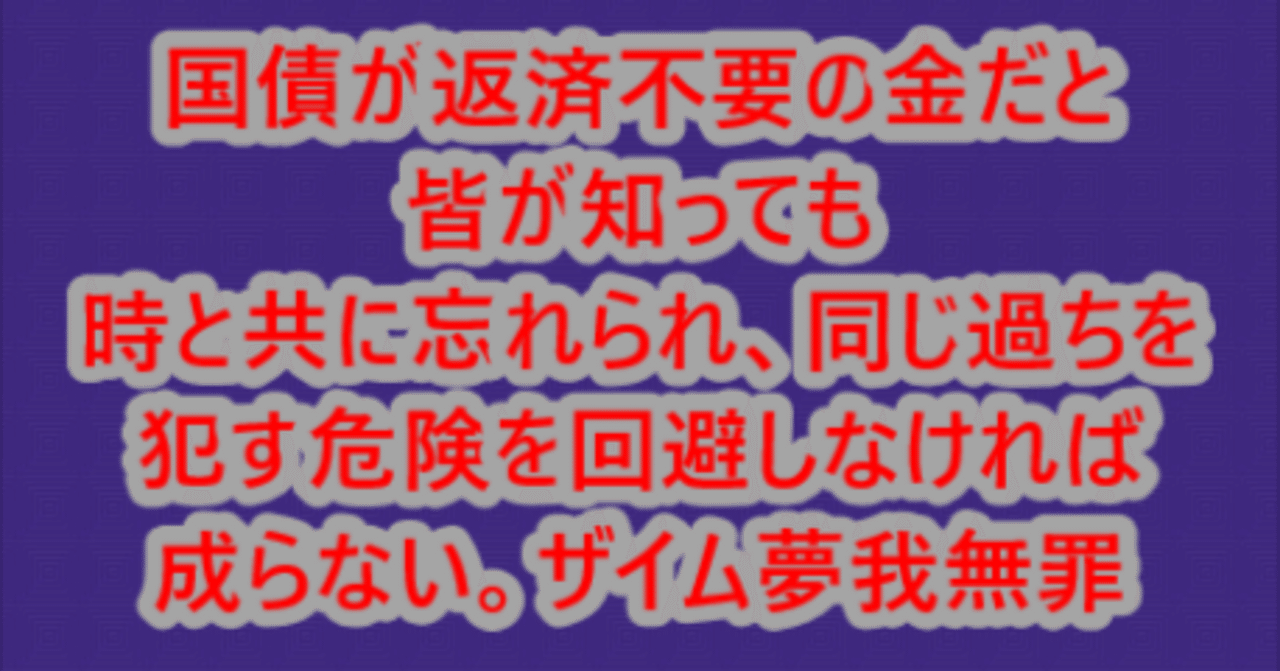
◆ 借金という誤解──家計と国家は違う
「国の借金が1000兆円を超えた」「このままでは財政が破綻する」──そういったフレーズは、新聞やテレビで何度となく繰り返されてきました。多くの国民が、「国債とは借金であり、いずれ返済が必要なものだ」と信じています。
しかし、ここで問うべきことがあります。
果たして「借金」という言葉は、国債に正確にあてはまるのでしょうか?
私たちが個人として借金をする場合、それは当然返済を前提としています。利子も支払わねばならず、返せなければ債務不履行というペナルティを受けます。これは「通貨を発行できない個人・企業」だからこそ成り立つ論理です。
ところが、国家、特に日本のような自国通貨建てで国債を発行できる政府は、それとは、まったく違います。日本政府は円を発行できる主権者であり、最終的には自らの意思で通貨供給が可能です。つまり、”円が足りなければ、発行すればよい”という選択肢を常に持っているのです。
この意味で、国債とは「借金」ではなく、「通貨発行の間接的な手段」であったと言えます。
◆ 通貨の供給装置としての国債
実際、日本政府が財政支出を拡大しようとする場合、その多くは国債発行によって賄われてきました。そして、その国債は市中銀行や日本銀行(日銀)に買い取られることで、結果的に通貨が市中に供給されます。
国債の発行→銀行の購入→日銀の買いオペ→通貨供給。
この一連の流れは、まるで自然界における雨の循環のようです。
雲が水蒸気をためて雨を降らせるように、政府が国債という「蒸気(見込み)」を発行し、銀行がそれを受け取り、日銀という大気がその雲を吸い上げて、通貨という「雨」を社会に降らせる──
まさに「間接的な通貨発行」という循環構造がここにあります。
日銀が最終的に国債を保有する形になれば、その利払いも政府に戻り、実質的には政府から政府への帳簿上の移動にすぎません。
つまり、返済の必要がないばかりか、元本が永久にロールオーバー(借換え)され続ける実態を見れば、国債は「返済を前提としない通貨のようなもの」として扱われていたのです。
◆ 国債がなぜ発行され続けるのか?
それは、民間の信用創造だけでは十分な通貨供給ができないからです。
特に不況期やデフレ下では、民間が借金を控えるため、銀行による信用創造は機能不全に陥ります。そのとき、政府が国債を発行して支出することで、社会にお金が流れ込み、経済を下支えすることが可能になるのです。
つまり、国債は「民間が借りられないときの非常用の蛇口」であり、経済に酸素を送り込む生命維持装置のような役割を果たしてきました。
次節では、この装置をなぜ「借金」と誤認してしまったのか、そしてその誤認がいかにして「財政健全化」や「緊縮政策」の呪縛へとつながっていったのか──その歴史的背景と制度設計の問題に迫っていきます。
Views: 0