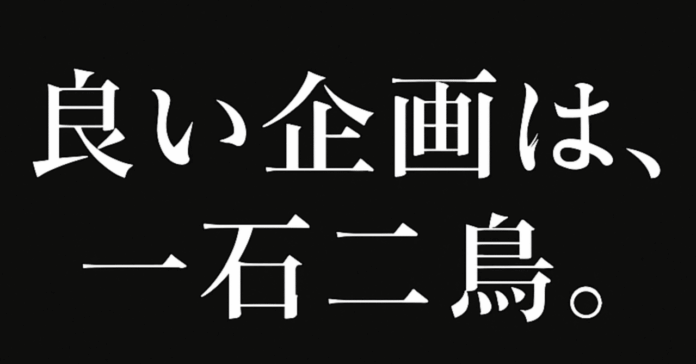🧠 概要:
概要
この記事では、著者がUber Eatsの配達員としての経験を通じて得た「一石二鳥発想法」について考察しています。さまざまな目的を持つことの重要性を強調し、複数の良い結果が得られることでモチベーションが向上することを論じています。また、他の活動(タロット占いなど)での体験も交えながら、企画や新しい取り組みを考える際に役立つ視点を提供しています。
要約(箇条書き)
- 経験からの発見: Uber Eatsの配達員を1年行い、好奇心から始めたが、そこから多くの目的が見つかる。
- 目的の多様性:
- 運動不足解消
- 新興ビジネスモデルの理解
- 地域の新発見
- 「一石二鳥」の効能: 一つの行動が複数の目的や利益をもたらすことで、視野が広がり、提案や企画がより魅力的になる。
- 心理学的背景: 「複終局性」が行動や施策のモチベーションを高めることが研究により証明されている。
- 他の事例: タロット占いを通じて得たさまざまな目的(トーク力の向上、西洋美術への興味、SNS運用力の獲得など)。
- 提案の魅力向上: 企画や新しい取り組みを考える際には、複数の目的を意識することが重要。
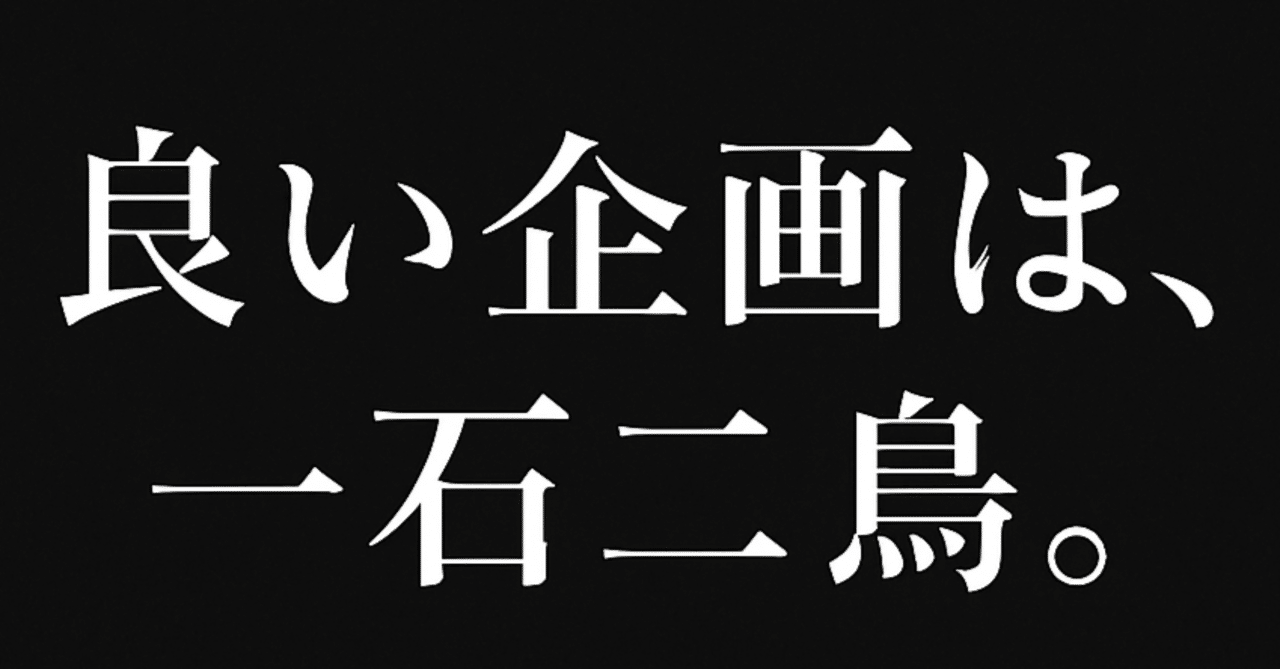
僕は以前、Uber Eatsの配達員をやってみていました。
とはいえ、その話がしたいわけではなく、この経験から、ビジネスでもプライベートでも、何か新しい取り組みを企画したり、始めたりするときのヒントがあるなと思ったので、これを「一石二鳥発想法」としてまとめていきます。
なんでUber Eats配達員?:最初は好奇心、気づけば目的だらけだった
 Uber Eatsの配達員を1年ほど副業で行っていました
Uber Eatsの配達員を1年ほど副業で行っていました
「なんでまたUber Eatsの配達員なんてやったの?」って、まあ聞かれますよね。
ぶっちゃけた話、究極的には「興味があったから」と「たまたま時間があったから」。もう、それだけ。なんか新しいことやってみたいなー、くらいの軽いノリ。
でも、いざ人に聞かれたり、自分の中で「なんでやってるんだっけ?」って考えると、これが面白いことに、後からどんどん理由というか「目的」が増えていったんですよね。
最初に意識したのは、やっぱり「ダイエットになるんじゃないか?」ってこと。当時はコロナ禍真っただ中で、運動不足が気になっていた時期。
Uber Eatsって自転車で動き回るじゃないですか。
次に、僕、本業はビジネスコンサルタントなので、「新興のビジネスモデルに肌で触れてみたい」っていうのもありました。お客さんとして使うのとは全然違う視点が得られるんじゃないか、と。実際、Uber Eatsだけじゃなくて、Woltの配達員もやってみたんですよ。そうすると、登録の仕方からアプリのUX(ユーザーエクスペリエンス)、もっと言うと配達員側のCX(カスタマーエクスペリエンス、というか働く側の体験)まで、サービスごとに結構違いがあって、「なるほどなー」と。
この経験のおかげで、ギグエコノミー界隈の解像度が自分の中でグッと上がった感じがしましたね。
それから、「道やお店に詳しくなった」こと。当時、都内に住んでたんですけど、引っ越してきても意外と行動範囲って固定化されちゃって、知らない道って多いんですよね。
でもUber Eatsで配達してると、普段通らないような道を自転車で走り回るわけです。そうすると、「あれ、こんなところにこんなお店あったんだ!」みたいな発見がたくさんあって。これも一つの楽しみでした。
こんな感じで、気づけば、
-
小銭稼ぎ
-
運動不足解消
-
新しいビジネスモデルの研究
-
地域の新規開拓・道に詳しくなる
みたいに、ぱっと考えただけでも3つも4つも目的が生まれてきたんです。だから、結構楽しんでやれてたんですよね。
「一石二鳥」の効能 | 複数の目的がもたらす価値の高まり
このUber Eats配達員の経験を通して、「ああ、何か一つのことをやるにしても、目的って一つじゃなくてもいいんだな」って強く感じたんです。
これ、普段僕が仕事で新しい企画を考えたり、プロジェクトを進めたりするときにも、実はすごく意識していることです。
よく「目的から逆算して施策を考えよう」とか言いますけど、その「目的」がガチガチに一つだけだと、視野が狭くなっちゃう。
もちろん、主目的、つまり「これを達成するためにやるんだ!」っていう一番大きな旗印は大事ですが、でも、例えば何か新しい取り組みを始めるとき、「これって、Aっていう目的も達成できるけど、よくよく考えたらBっていう効果もあるし、もしかしたらCっていう副産物も得られるかもしれないぞ?」みたいに、複数の良いことが見えてくると、ワクワクしません?
まさに「一石二鳥」。いや、場合によっては「一石三鳥」とか「一石四鳥」にだってなり得る。
企画を考える上でも、この「一石二鳥」的な発想は、提案をより魅力的にするスパイスになると思うんです。
心理学などでは”福終局性”と呼び、「一石二鳥」がモチベーションをあげるという研究もある
で、この「複数の目的を持つ」っていうのは、単に「お得だから良いよね」って話だけじゃないんですよ。実は、モチベーションにも深く関わってきます。
これって、すごく実感としてありますが、実は心理学にも「複終局性(multifinality)」という考え方があります。
https://psycnet.apa.org/record/2012-34554-002
これは、一つの行動が、複数の異なる目標を達成する可能性を持つことを指す言葉です。この「複終局性」があると、その施策や行動に対するモチベーションが自然と上がるという研究があります。例えばUber Eatsの配達だって、「お金を稼ぐため」っていう目的だけだと、続かない。けど、そこに「運動不足も解消できるし」「新しいお店も開拓できるし」「ビジネスのネタも見つかるかも」みたいに、複数の魅力的な目的がくっついてくると重い腰も上がりやすくなる。複数の目的を持つことで、行動そのものの「価値」が自分の中で高まるから、自然と「やりたい」っていう気持ちが強くなる。
企画会議なんかでも、複数のメリットが提示されると、みんな「それいいね!」ってなりやすいですよね。
占い師やってた時も、実はこれだった:目的がどんどん増えていった話
もう一つ事例を話します。
前のにも書きましたが、タロット占い師として活動していた時期もありました。これも最初は副業として「収入を得る」っていう目的が大きかったんですけど、やっていくうちにどんどん目的が複層化していったんですよね。
まず、占い師としてやっていく「トーク力」。お客さんの話を聞き出して、的確な言葉で伝えて、満足してもらう。これは「会話術を学ぶ」っていう新しい目的になりましたね。
それから、僕が主に使っていたタロットカードって、絵柄のモチーフに西洋美術とかキリスト教の知識が背景にあることが多いんですよ。
だから、「西洋美術の知見」っていう知的好奇心も刺激されました。
例えば、サルバドール・ダリがタロットカードをデザインしていたなんてことも、この時期に知りました。
あと、当時はSNSでの集客も頑張っていたので、「SNSの運用の経験」というのもありましたね。
さらに、タロットを通じて出会う人(友人の飲み会に、占いできるって誘ってもらったりとか…笑)もいたので、「新しい友人ができた」のも、大きな副産物でした。
と、気づけばたくさんの目的やメリットが生まれていました。
だから、企画案には「一石二鳥」を
というわけで、今日は僕のUber Eatsの配達員や占い師の経験、そして心理学の概念から「複数の目的を持つことのパワー」について語ってきました。
何か新しいことを始めようとするとき、あるいは新しい企画を練るとき、ついつい「これを達成するため!」と一つの目的に集中しがちです。
そこにプラスして「この企画、他にもどんないいことがあるだろう?」と視点を広げてみると、思わぬ副産物や、関係者みんながハッピーになるようなメリットが見つかるかもしれません。
すると、提案そのものがグッと魅力的になるし、関わる人たちのモチベーションも自然と高まるはずです。
企画職の方々は、結構この思考法使うんじゃないかなと思っています。
だから、提案するときは、「これにも効くし、あれも得られるかも?」って視点を忘れたくないな。って話でした。
Views: 2