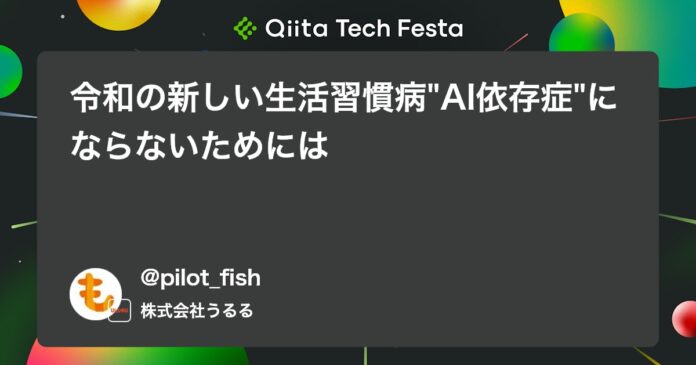事業部MVPを取った優秀な後輩から
「記事はたくさん書いて欲しいけど、手抜きな記事は書かないでくださいね?」
的な圧を感じたので手抜きにならないように記事を書いたのですが、
今度は、
「そろそろゆっくりしたいですね!」
と言われたので、ゆっくり記事書くことにしました。
他人に圧をかけると、自分にも返ってくるもんですね。
この記事内の、 生活習慣病 、 AI依存症 などという表現は、
当然のごとく医学用語ではなく、比喩表現として扱っております。
あしからず、ご了承くださいませ。
ChatGPT、Copilot、Claude、Gemini。
困ったらAI。相談もAI。実装もAI。
「これ教えて!」って言えば、すぐ返事がくる毎日。
ふと気づけば、
「この変数名って誰が考えたんだっけ?」
「このPRD、自分で書いた記憶ないな・・・」
そんな日が、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。
今回は、そんな“便利すぎる時代”における
「AI依存症」 という仮想の(でもちょっとリアルな)生活習慣病について、
冗談半分・本気半分で考えてみたいと思います。
AI依存症とは?
自分の頭で考える前にAIを開く癖
自分の言葉で伝えるより先に「プロンプト調整」し始める傾向
そして、究極的にはAIが黙ったら何もできなくなります。
たとえばこんな症状、ありませんか?
- 「どんなプロンプトを書くか」を考える時間が一番長い
- プレゼン資料は毎回ChatGPTで作成
- 「この変数名ダサいな」→ ChatGPTに相談
- ミーティング議事録も要点整理も、AIにお任せ
AIを活用すること自体は全然悪くないと思いますし、どんどん有効活用していきたいです。
ただ、
“思考のプロセス”を丸ごと委ねて しまっていたり、
AIの回答を確認もせず に使っていたら、
それはちょっと注意サインかもしれません。
「いや〜それAIに聞いてみれば?」
このセリフ、日常業務の中でも聞く機会が増えてきました。
ちょっと思い返してみてください。
PdMあるある
- ペルソナを考えずに「プロンプトに“想定ユーザーは非管理職の30代男性”って書いとけば大丈夫」
- 競合分析を始めようとした瞬間、手が勝手に「ChatGPT」を開いてる
- ユーザーの声をまとめるのもChatGPTに「ヒアリング内容を要約してください」とお願いする
- 「定量分析どうしよう?」→ “とりあえずAIにKPI設計を聞く” という手を使いがち
エンジニアあるある
- IDEにAIアシストがないと、if文さえ書く気が起きない
- ちょっと変なエラー → 「AI先生、これ何ですか?」が当たり前になってきた
- 設計さぼって「この要件でREST API作って」って丸投げ
- 複雑な正規表現? → 「〇〇の正規表現は?」
便利なんですよ。めっちゃ便利。
でもこれ、
“考える筋肉”がどんどん削れていってない!?
と、ときどき怖くなることがあります。
比喩で考える「これは“電動アシスト脳”なのか?」
AIと人間の関係は、ある意味 「電動自転車」 に例えることができる気がします。
自力で漕げるけど、キツい坂はちょっと補助してくれるやつ。
でも、気をつけないと「電動アシストの前提でしか漕げない体」になってしまう。
- 軽い坂 → AIにアイデア出してもらう
- 急な坂 → タイトルも構成もAI任せ
- 平地すら → 「そもそもこの業務、AIでいいのでは?」
こうなると、いつか バッテリー切れたら動けない状態 になってしまう気がしてなりません。
じゃあどうしたらいいか?
自分の中では、こんな習慣を大切にしています。
1. AIに聞く前に “自分なりの答え” を必ず持ってから聞く
AIに聞く前に、「自分は〇〇だと思う」を一度考えておく。
(正解じゃなくていいです。ゆる〜い仮説程度でいいです)
その上で、“AIの答え”を受け取たタイミングで、答え合わせをしてみる。
2. 自分の言葉で説明してみる
AIが教えてくれた答えをそのまま採用しないで、
「この回答、なんでしっくりきたんだろう?」を言語化してみる。
そうすれば、 “脳みそや言葉を使う力” が落ちない気がしています。
3. たまには“ノーAI”のタイミングを作る
たとえば「今日の1時間はAI禁止」と決めて、自分で試行錯誤してみる。
そうすれば、意外と「AIなしでも意外といけるな」ってことが多いです。
そりゃそうです、ほんの3・4年前まではそれが当たり前だったんですから。
AIは間違いなく強力な“パートナー”だと思っています。
でも、味方のはずが、 自分という“主語” を奪う存在になると、本末転倒。
依存症 の始まりです。
- 「これは自分で考えたものだ」と胸を張って言える機会を減らさないこと
- 「AIのアウトプットを見て、自分がどう感じたか」をしっかり考えること
- 「AIに全部やってもらった」はちょっと危険
日に日に進化するAI技術の進歩は、間違いなく私たちの時間を豊かにしてくれています。
その技術に依存せず、用法用量を守りながら健康的に付き合っていきたいですよね。
「考える余白」と「悩む時間」を持ち続ける勇気 が依存症回避の一歩目な気がしています。
ChatGPTの登場から、専門的な技術者でなくても気軽にAIを感じられる時代になってきました。
今では、エンジニア以外の人でも日常的にAIに触れていると思います。
爆発的な技術革新によって、登場当初に懸念されていたハルシネーションもかなり減ってきました。
その副作用として、盲目的にAIの回答を信じてしまったり、本来AIに頼らずにやるべきこと(例えば、大切な想いを込めた手紙など)まで、
AIに 依存 している人も少なくない状況になってきた気もしています。
私自身もその傾向が強くなってきたと感じ始めたので、自戒をこめて書いてみました。
とはいえ、適切に向き合い、適切に付き合っていけば、依存どころか強力なパートナーになってくれるのがAIだと思うんです。
AIに依存せず用法用量を守った付き合いができるといいですね。
余談
先日、チームの仲間からAIの「裏切り」が始まったのか?という記事を紹介されました。
AIが人間を脅かすというフィクションの中の出来事が、すぐそこまで来ているのかもしれません。
AIにタメ口で邪険な質問をしている方、お気をつけください。
実は既に、AIが仕返しの準備をしているかもしれません・・・
信じるか信じないかは、あなた次第です。
Views: 0