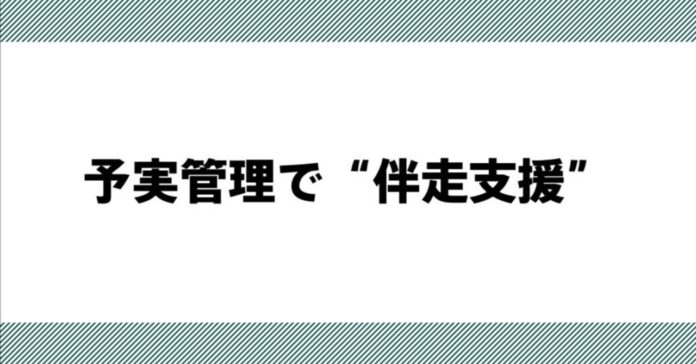🧠 概要:
概要
この記事では、予実管理の重要性とそのメリット・デメリットについて解説しています。財務分析や損益分岐点の理解を基に、企業が将来の目標を設定し、予実管理を通じて戦略を具体化していく過程が描かれています。著者は、より効果的な管理方法や実践例も紹介し、会計事務所がどのように企業に寄り添って支援できるかについて述べています。
要約(箇条書き)
- 財務分析と損益分岐点の理解が、企業の立ち位置を把握するのに役立つ。
- 未来の目標設定が容易になる内容例:
- 営業利益率、自己資本比率、損益分岐点売上高の改善目標。
- 予実管理は、目標達成に向けた支援を行う手段として有効。
予実管理のメリット
- 事業の進捗評価:毎月の実績と予算を比較し、計画が進行しているか確認できる。
- 戦略の具現化:予算設定により、経営資源の活用法が明確になる。
- 経営者の意思の共有:数字で経営者の意図が可視化され、社内に伝わる。
- 従業員の行動指針:予算の共有が従業員の行動の指針となり、無駄を削減できる。
予実管理のデメリット
- 混乱を引き起こす過度な目標設定:非現実的な目標が士気を低下させる可能性。
- 顧客ファーストを損なう可能性:予算を優先すると顧客の要望に応えられない事例。
- 低い目標設定の傾向:達成度が人事評価になると目標が低く設定されがち。
- 非協力関係の形成:部門間での利益追求が協力関係を壊す恐れ。
- 著者は自社の実践例として、エクセルを用いた方法を紹介し、他の書籍も参考にしている。
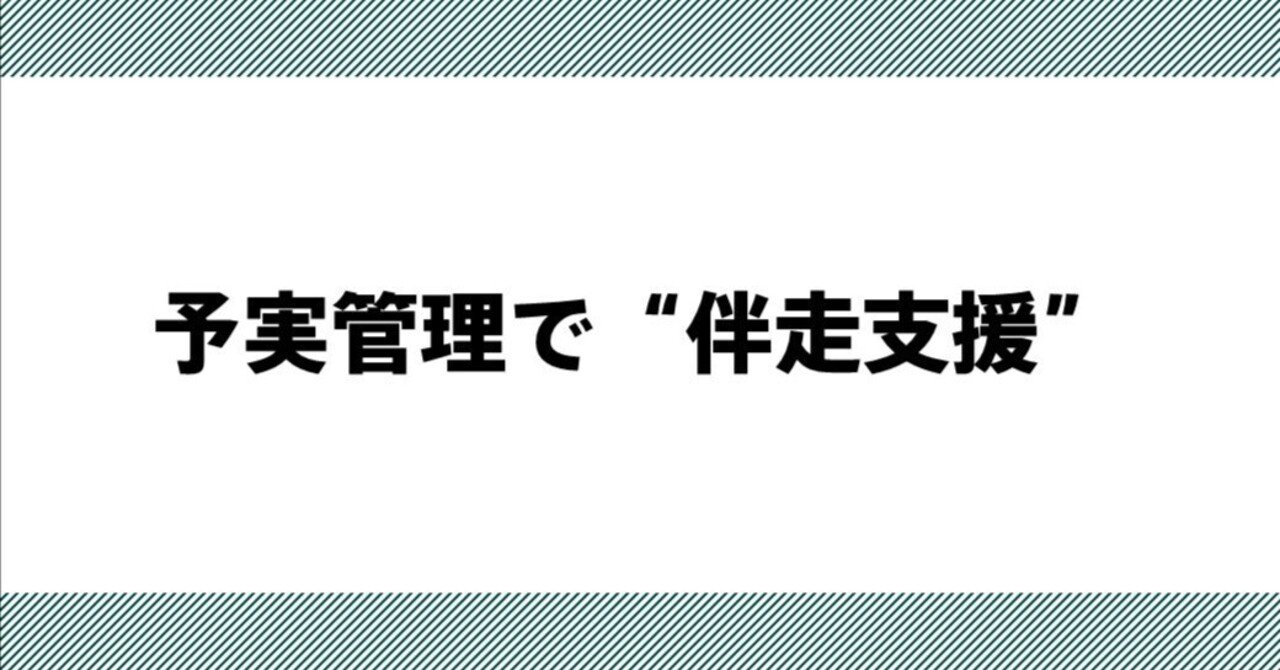
この目標に向かって、会計事務所として支援ができる一つが”予実管理”だと思います。
”予実管理”といった内容、詳細について気になる方は下記のサイトや”予実管理”といったキーワードで事前に検索してみてください。
色々なサイトにも書いてありますが、
私が思う予実管理を行うメリットデメリットは、以下の通りかなと思います。
予実管理のメリット
①事業の進捗具合を評価できる
毎月の月次の損益状況(実績)と事前に設定した予算との比較を行うことで、計画通りに進んでいるのかどうか確認ができます。実績と予算との差が大きいものについては、その都度原因を確認することで、対策を行うこともできます。
②戦略を具現化できる
売上や利益の目標を予算として設定することで、限りある経営資源(人、物、金、情報)を、どこに、どのように活かすかといった重点方針やアクションプランの策定が可能となります。
③経営者の想いを共有できる
予算を策定することで、経営活動を行う経営者の意思や想いを数字として可視化できます。予算はその基となる経営者の意思や想いを社内に正しく伝え、共有する手段でもあります。
④従業員の行動指針へ
予算を会社全体で共有することにより、部門や従業員個人の活動の指針となり、ムダな経費を抑え、収益性向上につながります。
予実管理のデメリット
①過度な目標数値の設定で現場が混乱化
現場の状況を踏まえず、非現実的な目標・予算設定をした場合、現場の士気が低下する恐れがあります。
②予算第一主義による事業への弊害
顧客ファーストでは無く、予算ファーストとなると、顧客からの要望があっても予算が足りないことから対応しない、新しい事業アイデアがでても予算上取り組めない…などといった問題が生じる可能性もあります。
③低い目標設定にする傾向あり
各従業員や部門内で予算設定を任せる場合や、予算の達成を人事評価にも使用する場合は、初めから低い目標設定になる可能性があります。
④従業員同士・部門間での非協力関係
予算達成が人事評価にも使用される場合は、個人や部門の利益を優先しがちとなり、結果非協力関係となる可能性があります。
私が実践している予実管理
会計事務所お勤めの方は、会計ソフトや予実管理などの経営管理ソフトなどがあるので、それらの利用料金の負担が問題ないのであれば、ぜひ使われるのがオススメです。
私の方では、費用対効果の面から一旦何とか追加費用のかからない範囲内でということで、既存の会計ソフトからエクセルを出力し、少し加工したものを活用しております。
また別の機会で、どう実践しているか記事にできたらと思います。
最後に、予実管理に関する書籍のご紹介
予実管理を実践する上で、下記書籍を参考にしたのでご紹介します。
今日はここまで…
Views: 0