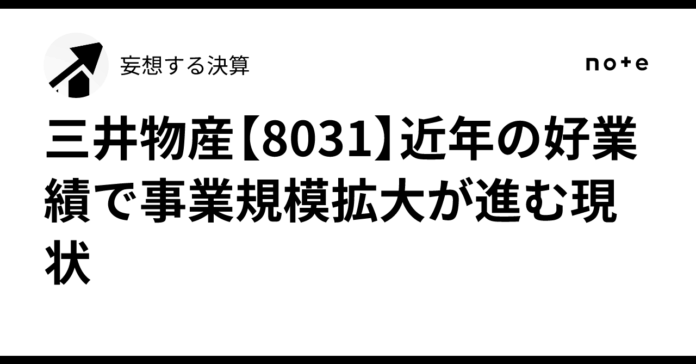🧠 概要:
概要
三井物産株式会社は、日本の3大商社の一つとして多様な事業展開を行っている。近年の好業績により事業規模の拡大が進んでおり、特に金属資源やエネルギー分野での利益が顕著に伸びている。2024年3月期までの成長投資計画も明らかとなっており、資源との相場変動に注意を払いながら、非資源分野の強化も図っている。
要約
- 企業概要: 三井物産は日本の大手商社で、多様な分野にわたる事業展開を行っている。
- 事業セグメント: 金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業、次世代・機能推進などの8つのセグメントを持つ。
- 主な事業: 金属資源、エネルギー、機械・インフラ事業が特に大きな利益を上げている。
- 最近の業績: 2022年には過去最高益9147億円を記録し、2024年3月期まで1兆円を超える見込み。
- 投資計画: 2024年から2026年の間に2.3兆円の成長投資を計画中。
- 業績変動要因: 市況変動、特に資源相場の影響を大きく受けやすい。
- 2025年の見込み: 売上高は14兆6626億円、純利益は9003億円で増収ながら減益となる見込み。
- 長期展望: 資源系事業の影響を受けつつも、事業の多様化により安定した成長が期待される。
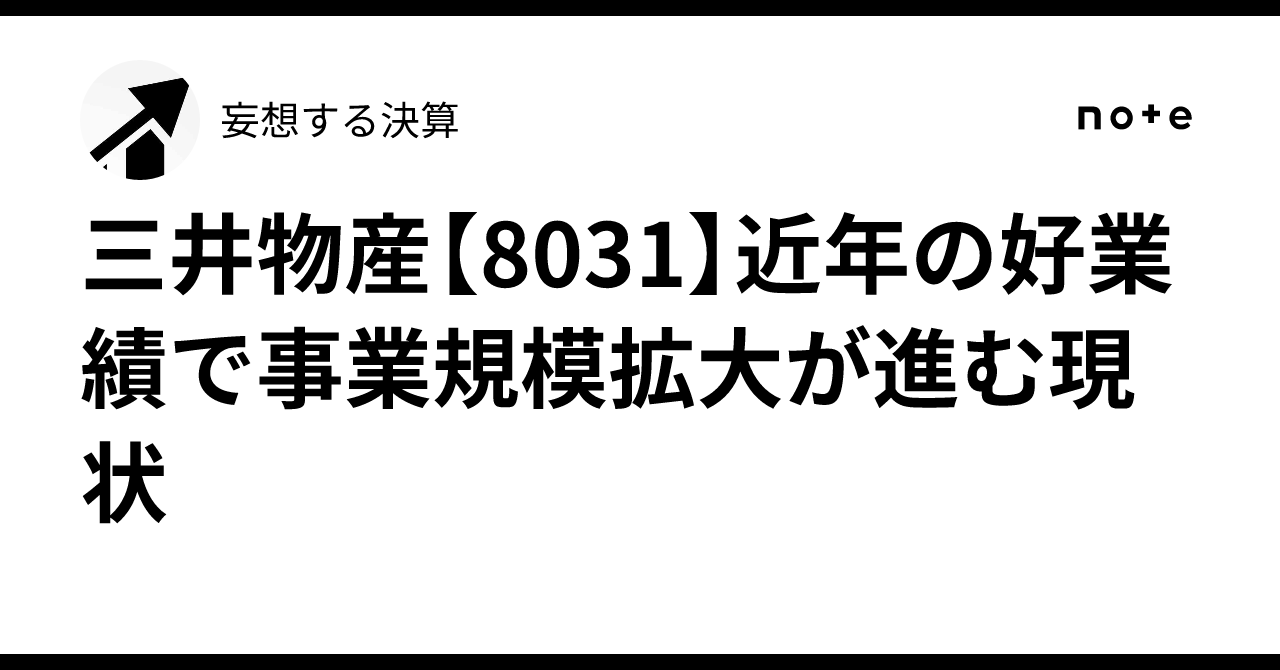
日経平均に採用されている銘柄を全て取り上げているこの、今回取り上げるのは三井物産株式会社です。
日本の3大商社とも呼ばれる大手商社の内の1つです。
事業内容

それではまずは事業内容から見ていきましょう。
三井物産の事業セグメントは以下の8つです。①金属資源:鉄鉱石・石炭・ニッケルや銅等の開発・販売など②エネルギー:原油・LNG・シェールガスなどの権益保有やトレーディングなど③機械・インフラ:電力やガス配給に海運、自動車や建機販売に船舶や航空機などを取り扱う事業④化学品:石油化学製品や肥料などを取り扱う事業⑤鉄鋼製品:鋼材や自動車部品などを取り扱う事業⑥生活産業:食料品やアパレル、ヘルスケア商品などを取り扱う事業⑦次世代・機能推進:アセットマネジメントやベンチャー投資、新規事業など
⑧その他
最大手の商社の1つであり、非常に多様な分野への投資を行っている企業となっています。

アメリカでのトラックの管理台数が1位、アジアでの病院事業所の病床数が1位など海外でも大きなシェアを持つ事業があります。
そして国内でもアンモニアの輸入シェアが6割、食料品ではトウモロコシが20%、コーヒーが35%、菜種が40%、大豆が20%など大きなシェアを持つ製品を多数保有しています。

2025年3月期のセグメント別の純利益は以下の通りです。①金属資源:2854億円②エネルギー:1735億円③機械・インフラ:2329億円④化学品:759億円⑤鉄鋼製品:132億円⑥生活産業:537億円⑦次世代・機能推進:873億円
⑧その他▲216億円
金属資源やエネルギー、機械・インフラ事業の規模が特に大きい事が分かります。
非常に事業内容が多く全てを見ていく事は難しいですから、現在の主力であるこの3事業についてのみ、もう少し詳しく見ていきます。

金属資源セグメントで大規模に取り扱っているのは鉄鉱石であり、その他には銅や原料炭も大きな規模があります。

現在の利益としては圧倒的に大きいのがオーストラリアの鉄鉱石事業となっています。
鉄鉱石相場の影響を特に受けやすく、銅や原料炭相場の影響も受ける事業です。

エネルギーセグメントは、天然ガス・LNGと原油を主に取り扱っており、特に天然ガス・LNGの規模が大きいです。
天然ガス・LNG相場の影響を特に受けやすく、原油相場の影響も一定程度受ける事業です。


③機械・インフラセグメントは、電力や社会インフラを取り扱うプロジェクト本部、自動車や建機などを取り扱うモビリティ第一本部の規模が大きいです。
電力や自動車や建機といった需要に左右されるものの、他の主力の2事業とは違い長期案件が多く比較的安定した業績が期待できる事業です。
とはいえ主力事業を見てみると、資源相場に左右されやすい事業が多く市況による影響を受けやすい企業となっています。
また、大手商社はどういった投資を行っているかも重要です。

2024年3月期時点での事業別の投資の内訳は以下の通りです。①金属資源:18%②エネルギー:20%③機械・インフラ:22%④化学品:12%⑤鉄鋼製品:5%⑥生活産業:17%
⑦次世代・機能推進:11%
投資自体は比較的分散しています。
現在は資源系の事業の利益率が高く、影響を受けやすくなっているという事ですね。

また、国別の投資としては規模が大きい国は以下の通りです。日本:1.9兆円豪州:1.5兆円米国:1.7兆円
ブラジル:1.2兆円
主力である日本市場や、大きな鉄鉱石の鉱山や炭鉱を持つオーストラリア、銅の鉱山を持つ南米なども投資の規模が大きいです。

さらにアメリカにも積極的な投資を行っており、アメリカでは国内完結型の事業を中心に事業を展開しています。
次いで規模が大きいのが輸出型の事業です。
アメリカ市場ではトランプ関税の影響が想定されますが、影響は小さいと考えられる事業構成です。

さて、海外投資の規模が大きく、資源系の利益の規模が大きい事が分かりました。
つまり市況による影響が大きいという事です。
市況変動の影響は以下の通りです。・連結油価(1バレル1ドル):24億円・米国ガス(1mmbtu1ドル):19億円・鉄鉱石(1トン1ドル):31億円・原料炭(1トン1ドル):3億円
・銅(1トン100ドル):5億円
・ドル円:41億円
・豪ドル:21億円
米ドルや豪ドル、原油に米国ガス、鉄鉱石などの影響を特に受けやすくなっています。
こういった相場の変動には注目です。
業績の推移
事業内容が分かった所で続いて業績の推移を見ていきましょう。

2014年3月期~2024年3月期までの純利益の推移を見ていくと2021年3月期までは増減ありつつで3000億円~4000億円ほどで推移しています。
それが2022年3月期には9147億円となり過去最高益を更新し、それ以降は2024年3月期まで1兆円を超えて推移しています。

2022年3月期に業績が大きく伸びた要因は、資源系事業の拡大です。コロナ禍からの経済活動が再開する一方でロシアとウクライナの問題や海運が停滞した影響などもあり資源相場は急騰しました。それに伴って金属資源事業やエネルギー事業が大幅増益となっています。
とはいえ、拡大の要因はそれだけではありません。
2014年3月期と2024年3月期のセグメント別の純利益を比較してみると以下の通りです。


①金属資源:956億円→3351億円②エネルギー:1970億円→2817億円③機械・インフラ:266億円→2487億円④化学品:158億円→392億円⑤鉄鋼製品:181億円→112億円⑥生活産業:192億円→941億円
⑦次世代・機能推進:49億円→873億円
資源相場の高騰によって資源系事業が利益を大きく伸ばした事も影響していますが、機械・インフラ、化学品、生活産業、次世代・機能推進といった資源系以外の製品も取り扱っている事業でも大きな成長を見せています。
資源相場の高騰に加えて事業規模の拡大も影響しているという事ですね。

現在も資源系の事業の規模が大きい事は間違いありませんが、以前は資源系事業が大半を占めており資源相場による影響が非常に大きな企業でしたが、現在は非資源系の事業規模も拡大しています。
以前と比べて安定した業績が期待できるようになったという事が分かります。


さらに、近年の好業績によって投資余力も拡大する中で2024年3月期~2026年3月期までの中計では2.3兆円もの成長投資を計画しています。
これまで投資を進めてきたのは、LNG権益や鉄鉱石、アンモニアなどで、さらにオーストラリアのトラックオークションやインドの金属リサイクル、ベトナムのガス田、鶏やエビといったタンパク質、ヘルスケア事業などへも投資を進めています。
近年の好調によって生まれた投資余力を積極的に再投資しており、さらななる事業規模の拡大が期待されます。

ちなみに、2024年3月期~2026年3月期までの中計では既存事業の強化で700億円、効率化や構造改革で+400億円、新規事業で+600億円で計1700億円の基礎収益力の拡大を進めています。

収益貢献が期待されている新規案件も複数あり、今後も事業規模拡大などで以前と比べても高水準での業績が続く事が期待されます。
という事で現在の三井物産は資源系事業の規模が大きいため、相場変動に業績が左右されやすい企業ではあるものの、事業規模が拡大しており以前と比べて高水準の業績が期待される企業となっています。
直近の業績
続いて直近の2025年3月期の業績をもう少し詳しく見ていきましょう。

売上高:14兆6626億円(+10.0%)純利益:9003億円(▲15.4%)
増収ながらも減益となっています。

とはいえ基礎営業キャッシュフロー(キャッシュを稼ぐ力)は増加しています。
高利益水準も維持していますし、事業規模が拡大し堅調な状況が続いている事が分かります。
とはいえ減益となっていますから、その要因はもう少し詳しく見ていきましょう。

セグメント別の純利益の前期比は以下の通りです。①金属資源:▲497億円②エネルギー:▲1082億円③機械・インフラ:▲158億円④化学品:+367億円⑤鉄鋼製品:+20億円⑥生活産業:▲404億円⑦次世代・機能推進:+335億円⑧その他:▲215億円
ちなみに、その他は退職給付制度の改定による影響で一時要因です。
事業面としては、資源系の事業が特に減益となっています。

資源系の事業が減益となった要因はやはり相場変動の影響もありました。
金属資源では円安の好影響は+160億円ありつつも、市況の悪化で鉄鉱石が▲430億円、原料炭は▲220億円の影響などがあり業績は悪化しています。
一方でエネルギー事業は円安を中心に好影響の方が大きく、市況による影響は+110億円となっていましたが、一方で資産リサイクル(資産の入れ替え)による影響が▲557億円や前期の反動、▲341億円などがあり減益となっています。
大手の商社は多様な分野へ投資を行う事が事業の中心ですから、その資産の入れ替えによって業績が左右されやすいです。
なのでエネルギー事業ではそういった影響が出ていたという事ですね。


とはいえその一方で、比較的大きく増益となっていた化学品事業では資産リサイクルによる影響が+224億円、次世代機能推進では資産リサイクルによる影響が+441億円となっています。

2025年3月期ではキャッシュインは1.63兆円、その内資産リサイクルによって6010億円を回収しています。一方でキャッシュアウトは1.45兆円で自己株の取得による4000億円や配当の2920億円を除いても多くの投資をしており、資産の入れ替えをしている事が分かると思います。
業績はそういった影響を受けやすい企業ですから、その動向には注目です。

そんな中で2026年3月期の通期予想では1303億円ほどの減益を見込んでいます。
資源系事業が市況の悪化によって減益となる事に加えて、資産リサイクルの反動で機械インフラ事業や次世代・機能推進事業が減益になる見込みです。
資産リサイクルでは悪影響が続く事を見込んでいるんですね。
それでも7700億円ほどの純利益を見込んでおり、事業規模の拡大によって以前と比べて高水準の利益は期待できます。
とはいえ資源相場の影響を受けやすい企業です。
トランプ関税によって原油相場は下落を見せ、為替は円高方向に推移しました。それによる悪影響は考えられますが、まだまだトランプ大統領の動き次第で、変化の大きな状況が続く可能性が高いですから相場変動には注目です。
Views: 2