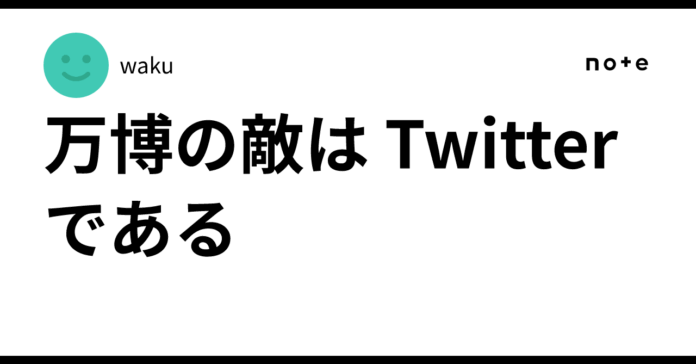🧠 概要:
概要
2025年の大阪・関西万博では、平日と週末の来場者数がほぼ同じ状況が続いている。この現象は、主にSNS(特にTwitter)がもたらす情報の均衡化が原因で、人々が効率的な行動を選択するためと考えられる。運営側は来場者数を増やすために、偶発的な魅力を取り戻す方策を模索しているが、情報の迅速な拡散がその試みを妨げている。
要約(箇条書き)
- 2025年大阪・関西万博は、平日と週末の来場者数がほぼ同じ。
- SNS、特にTwitterが影響を与え、来場者の行動が均衡化されている。
- 情報の共有により、人々は混雑を避けるために最適な行動を選択。
- 過去の万博とは異なり、平日も週末も訪れる人が同じ傾向に。
- 運営側は偶発的なイベントを増やし、特定時間の魅力を高めようとしている。
- 情報の拡散が行動を最適化するため、偶発性を取り戻すのが難しい。
- 「午後入場者に人気パビリオンの予約を保証する」というアイデアが提案されている。
- 既存のシステムに改良を加え、SNSの特性を逆手に取る戦略が重要。

2025年大阪・関西万博が開幕してしばらく経ち、会場の賑わいについての情報も日々アップデートされています。公式発表(※1)によると、ゴールデンウィーク以降の平日の1日あたりの入場者数は、関係者を除いて約11万人程度で推移しているようです。興味深いのは、ユーザーの方々のSNS上の報告を見ていると、この数字が週末でも大きくは変わらない、つまり「平日も週末も人出はそこまで変わらない」という状況が生まれているらしいことです。
かつての万博であれば、週末は家族連れなどでごった返し、平日は比較的落ち着いている、といった傾向が見られたかもしれません。しかし、今回は様相が異なるようです。なぜ、このようなフラットな来場者数になっているのでしょうか?
私は、その大きな要因の一つが「Twitter(現X)」をはじめとするSNSによる情報の均衡化ではないかと考えています。
Twitterがもたらした「情報均衡」と来場者の最適行動
「週末は混みそうだから平日にしよう」 「どうやら土曜日より日曜日の方が若干空いているらしい」 「朝イチで入場して、あの大人気パビリオンをまず押さえるのが鉄則だ」 「午後からの入場だと、もう主要なパビリオンは予約でいっぱいかもしれない…」
こんな会話や投稿を、あなたも目にしたことはないでしょうか?
Twitter上では、リアルタイムで万博の混雑状況、人気パビリオンの待ち時間、効率的な回り方、予約システムの攻略法といった情報が、もの凄いスピードで共有され、拡散されています。まさに「情報の見える化」が極限まで進んだ結果と言えるでしょう。
この「見える化」は、来場を計画している人々にとっては非常に有益です。無駄足を踏みたくない、限られた時間で最大限楽しみたい、という思いは当然です。結果として、人々は情報を元に最適な行動を取ろうとします。「午後から行ってもどうせ何も見られないだろう」と判断し、午前中の予約が取れない日は来場自体を見送る、といった動きです。
実際、午後から出向いても当日予約の枠はないという話も聞きます。これは、多くの人が「午前中から行かなければ意味がない」と判断し、行動をパターン化させている証左ではないでしょうか。
この情報の均衡化と、それに伴う個人の最適行動の積み重ねが、結果として全体の来場者数をある一定のラインで頭打ちにさせ、「平日も週末も変わらない」という一見不思議な状況を生み出しているのではないかと、私は推測しています。
行動経済学の用語を借りれば、これはまさに「確実性効果」と「損失回避」が巧みに組み合わさった状況と言えるかもしれません。午前9時といった早い時間帯の入場枠は、「何としても人気パビリオンを体験したい」という人々にとって「確実に入れる(かもしれない)大きなチャンス」として過大に評価されがちです。一方で、午後からの入場枠に対しては、「わざわざ行って、何も見られなかったら時間もお金も損だ」という損失への恐怖が、どうしても先に立ってしまいます。ここへさらに、Twitter上で見られる「朝イチ攻略法」や「午後は絶望的」といった情報が一種の同調圧力のように作用すると、多くの人の行動は午前中の特定時間帯へと一極集中してしまいます。そして、その争奪戦に敗れたり、そもそもその時間帯に動けない人々は、万博への来場自体を諦めてしまう…という流れです。運営側としても、安全確保の観点から無闇に入場定員を増やすわけにもいかず、結果として「行列が延びないのに来場者も増えない」という、なんとも奇妙な静止状態が現れるのです。
かつて情報が不均衡だった時代には存在したであろう、「よく分からないけど、とりあえず行ってみようか」「午後からふらっと立ち寄ってみようか」といった偶発的な来場。それが、Twitterと高度な予約システムによって、ある意味で「駆逐」されてしまったのかもしれません。
万博運営側のジレンマ:偶発性をどう取り戻すか
おそらく、万博の運営側もこの状況は認識しているはずです。だからこそ、会場内でサプライズ的な小規模イベントを増やしたり、特定の時間帯でのみ体験できるコンテンツを用意したりと、情報の「非対称性」を生み出すことで、午後の時間帯からの来場を促そうという動きも見え隠れします。
しかし、ここにもジレンマがあります。そうした偶発的なイベントや限定コンテンツも、効果的に集客するためには「周知」が必要です。しかし、大々的に周知すれば、またすぐにTwitterで情報が拡散・分析され、最適化行動の対象となり、結局は情報の均衡化へと収斂してしまうのです。まさにイタチごっこです。
では、この自己実現的なループを断ち切るには、どうすれば良いのでしょうか。情報の流れを無理に遅くしたり、止めたりすることは現実的ではありません。むしろ、午後や夕方以降の時間帯にも、「これなら確実にお得だ」「これなら損はしない」と来場者が感じられる魅力的な選択肢を戦略的に配置することが先決だと考えます。たとえTwitterで最適解が瞬時に共有されたとしても、その「最適解」が一つでなければ、人々の行動は自然と分散していくはずです。しかし、残念ながら現在の万博の仕組みは、主要な体験価値やその確実性が早朝の時間帯に極端に集中してしまっており、午後には「運が良ければ何か見られるかも」という、一種の“運試し”のような要素しか残されていないように見受けられます。これでは、多くの人にとって心理的な壁が高く立ちはだかってしまうのも無理はありません。
この膠着状態を打破し、頭打ちになっている来場者数をさらに上積みするには、どうすれば良いのでしょうか。
私は、「午後からの入場者に、人気パビリオンの予約枠を最低ひとつ保証する」というインセンティブを付与することを提案したいと思います。
もちろん、「どのパビリオンでもOK」というのは難しいでしょう。しかし、例えば対象パビリオンをいくつか設定し、午後入場者はその中から1つを選んで予約できる、といった形であればどうでしょうか。「午後から行っても、最低1つは目玉を見られる」という安心感は、これまで二の足を踏んでいた層の背中を押し、新たな来場を喚起する力になるかもしれません。
「動いているものを壊すな」と、その先へ
今回の万博の予約システムは、時に繋がりにくさが指摘されることもありますが、これだけの巨大イベントで、膨大なアクセスを捌きながら、大きな破綻なく稼働し続けている点は、もっと評価されてしかるべきだと感じています。日々、多くのエンジニアの方々が尽力されていることでしょう。
だからこそ、「動いているものを壊すな(Don’t fix what ain’t broken.)」という保守的な判断が強く働くであろうことも、想像に難くありません。大規模なシステム改修はリスクも伴います。
しかし、今回提案した「午後入場者向けの予約枠保証」のようなアイデアが、必ずしもシステム全体を根底から作り直すものではなく、既存のシステムに「アドオン」する形で実現できるのであれば、検討の余地は十分にあるのではないでしょうか。
Twitterという強力な情報プラットフォームは、もはや現代社会のインフラです。それを「敵」と表現しましたが、それは万博にとってネガティブな存在という意味ではなく、その特性を理解し、共存し、時には逆手に取るような戦略が求められている、ということの裏返しです。
情報の均衡化が進んだこの時代、一個人の本音を言えば、自分が訪れる際は少しでも空いている方がありがたいものです。しかし、来場者数の増加を願う運営側の立場を鑑みれば、やはり新たな賑わいを創出し、より多くの人に楽しんでもらうことが重要でしょう。この提案が、そうした万博側の願いの一助として、少しでも届けばと願っています。
(※1) ここで言及している情報は、大阪・関西万博公式サイト 2025年5月19日発表のニュース「万博会場への入場にかかる一日あたりの入場者数について(5月19日現在)」を参考にしています。実際の数値や状況は変動する可能性があります。
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250519-01/
Views: 0