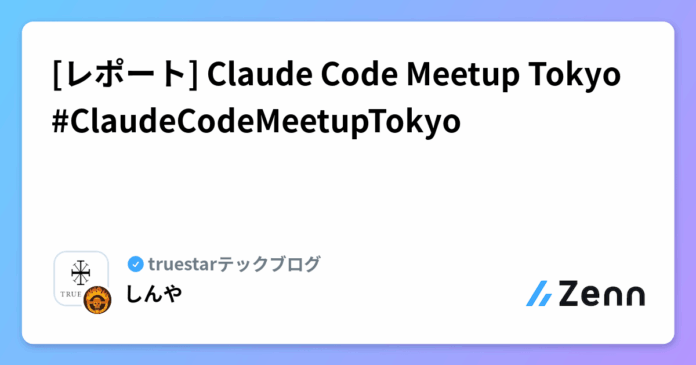2025年10月17日(金)、Claude Codeに関するイベント『Claude Code Meetup Tokyo』がオフライン(株式会社メルカリ@六本木)、オンライン(YouTube Live)のハイブリッド形式で開催されていました。
現地参加:
オンライン視聴:
個人的にも業務でClaude Codeを使うようになっており、直近最新のClaude Codeに関する情報を収集したい!という思いもあったので当日はオンライン視聴で参戦しました。当エントリでは視聴レポートとして内容をまとめたいと思います。
※イベント当日のX投稿も合わせてまとめています。記事内容と合わせてご覧頂けますと幸いです。
イベント概要
イベントページに記載のイベント概要は以下の通り。
セッションレポート
ここからはセッション3つ、LTが計6つ発表されていました。時系列通りに内容を紹介していきます。
[セッション#1]Claude Codeを駆使した初めてのiOSアプリ開発
- 登壇者:Oikon氏
- 登壇資料
- 自己紹介
- グローバルハッカソン Shipatonについて
- 9月までモバイルアプリ開発経験が一切ないバックエンドエンジニアだった。グローバルハッカソン「Shipatton」(RevenueCat主催、賞金総額35万ドル)に参加
- AIによる開発が高く評価され、ベストバイブスアワード3位に入賞。開発期間は9月6日の開始から24日のサブミットまで約3週間。
- メインの開発ツールはClaude Code
- Claude CodeをiOSアプリ開発でどのように使ったか
-
開発においては「Claude is the force, Claude Code is the harness」(Claudeは馬、Claude Codeは手綱)という意識を持った
- 性能の低下がモデル(馬)ではなく、操作系(手綱)であるClaude Codeのアップデートによるものかもしれないと捉えることが重要
-
開発環境には、学習時間が不要でCLIツール(XCRUNやXcode Buildなど)との相性が良いことから、XcodeではなくVSCodeを採用
- VSCodeのID連携により、簡易なコード解析の恩恵も受けることが出来た
-
学習にもClaude Codeの機能を活用
- コードの実装だけでなく、説明やインサイトを提供する
/output-styleのラーニングモードを並行して使用。タスク毎にInsightを考えてくれて、todo(human)で実装箇所の演習題材をくれる
- コードの実装だけでなく、説明やインサイトを提供する
-
コンテキスト管理とサブエージェントの活用
- コンテキスト管理では、冗長にならないようプロジェクト構造や必要なスクリプトのみを記述した「コンパクト派」を志向し、クリア機能を重視
- コンテキストの汚染を防ぐため、サブエージェントを積極的に活用
- サブエージェントには役割を与え、Validatorはリードオンリー設定で並列実行
- サブエージェントの使用は、メインエージェントのコンテキストをクリーンに保つために非常に重要
- コンテキスト管理では、冗長にならないようプロジェクト構造や必要なスクリプトのみを記述した「コンパクト派」を志向し、クリア機能を重視
-
タスク管理には、SDD(Spec-Driven Development)の作法を踏襲し、チェックボックス付きドキュメントを採用

- これによりタスクの調整や、他のAIツールへの引き継ぎが容易に
-
自動フィードバックループとレビュープロセス
- ビルドやテストは、XcodeのUIではなくスクリプト(CLI)をClaude Codeに実行させることで、そのログを直接フィードバックできる自動修正サイクルを構築
- これにより、問題の修正までAIに任せ、ユーザーは最終結果だけを確認することが出来た
- レビュープロセスにおいては、実装者とレビューアが同一のAIになることを避けるため、Claude Codeの
/reviewや/security reviewに加え、Codex CLIやCode Rabbit CLIを並列使用
- ビルドやテストは、XcodeのUIではなくスクリプト(CLI)をClaude Codeに実行させることで、そのログを直接フィードバックできる自動修正サイクルを構築
-
移動時間や休憩時間などでも開発できるよう、GitHub ActionsやXcode Cloud、Codex Cloudを組み合わせ、スマートフォン単体での開発ワークフローも構築
-
開発に費やしたClaude Codeの利用料は、9月6日から24日までで約700ドル
-
- 結論
- Claude Codeは未経験者でも短期間でiOSアプリをリリースできる強力なツールであり、ユースケースや自身の慣れに合ったAIツールを選ぶことが、能力を拡張する鍵
[セッション#2]Claude codeの進化とccusage、そしてこれから
-
登壇者:ryoppippi氏
-
登壇資料:
-
自己紹介
- 英国のStackOne社でAIエンジニアを務めている
- ccusageの作者
- ジョークツールとしての開発
- ccusageは、Claude CodeのMax Planで「こんなに得している」とニヤニヤするためのCLIツールとして、ジョーク目的で作成された
- 機能
- デイリー、マンスリー、ウィークリーでのトークン使用量を可視化
- Claude Codeのセッションがリセットされる5時間のインターバルをグラフで確認できる「ccusage blocks –live」などの機能を提供
- 反響
- 公開から約5ヶ月で8.5KのGitHubスター、NPMで50万ダウンロードを達成するなど、世界中で大きな話題に
- Anthropic社の対応とコミュニティへの影響
- 作成の発端はミロ(@ml0_1337)さんのX投稿から。これでCLIを作ったら面白いのでは?と触発されて1時間程でプロトタイプ完了
- ccusageが拡散された直後の2025年6月、Claude Codeのログからコスト情報(cost_usd)が削除
- すぐにトークン使用量からコストを再計算するアップデートを行い、この迅速な対応が海外での人気に火をつけた
- ccusageの盛り上がりは、Claude CodeのDX(開発者体験)向上にも影響を与える形に
- Anthropic社はその後、公式に/usageスラッシュコマンドをClaude Code 2.0で追加、リアルタイムでのトークン使用量表示を開始
- 界隈への多大なる影響(ccusageがもたらしたもの)
- ccusageはトークン使用量を可視化することで、Multi-Context Processing (MCP) やコンテキストウィンドウ管理、サブエージェントなどの概念に関する議論を促進し、Vibe Codingの技術的基盤の普及に貢献
- 特に、コードの情報をLLMに効率的に渡すSerenaのようなツールが、CC Usageの結果を引用してトークン削減効果を検証するなど、コミュニティ内での具体的な議論の土台となった
- 君たちはどう生きるか
- Agentの社会実装を担う我々はClaude Codeと戯れる事でLLMの実装を深めた。知見をCoding Agent以外の領域で応用して欲しい
- Thanks to…
- この場を借りて御礼を申し上げたい。
- NakamuraTakumi(@nyatinte)さん:Raycastのccusageを作ってくれた方。実はccusageというロゴもこの方が作ってくれた方でもある。すごいありがたいです。
- Alex McFadyen(@a_c_m)さん:ccusage blocks –liveを作ってくれた方。あれがRedditとかTwitterでバズって、ccusageが伸びた要因となってくれた。彼にはすごい感謝をしてます。
- Ben Vargas(@ben_vargas)さん:実際のトークンのやつと差分が違うところのデバッグや、色々Claude Codeが仕様変更するたびにいろいろ助言をくれている方。彼は直接会ったことないし、TwitterとTwitter上でしか喋ったことないんですけど、一番信用しているのは彼なので、いつも相談乗ってくれてありがたい。
- この場を借りて御礼を申し上げたい。
[セッション#3]Context Engineering を意識して Claude Code を最大限活用しよう!
- 登壇者:Kuu氏
- 登壇資料
- (公開され次第共有します)
- 自己紹介
- メルカリで”AIエージェントエンジニア”をやっています
- 今日のお話
- コンテキストエンジニアリングを意識したClaude Codeの最大限活用
- コンテキストエンジニアリングの概要と必要性
- コンテキストエンジニアリングとは、AIに与える文脈を設計し、意図通りの出力を引き出す技術
- 基本は不必要な情報を入れないこと、AIのやることを整理すること、そしてLLMの気持ち(動作原理)を理解すること
- コンテキストエンジニアリングは、個人の小規模な開発(CLIツールなど)では必須では無いが、大規模な業務利用(例:巨大なマイクロサービス群の開発や、iOS・Android・Webにまたがる技術調査)においては、情報量がコンテキストに収まりきらなくなるため、精度の高い結果を得るためには不可欠
- コンテキストが肥大化すると、AIが途中の指示を忘れてしまう「lost in the middle problem」と呼ばれる現象が発生するため、情報量を管理する必要がある
- コンテキストエンジニアリングの4つの主要要素とClaude Codeでの実現

- オススメ記事:
- 関係性は人間に当てはめてみると分かりやすい
- Claude Codeでコンテキストエンジニアリングを実現するには
- サブエージェントの活用
- 隔離の実現に重要であり、複雑なタスク(コード調査など)を実行させる際、メインエージェントが子エージェントを呼び出し、さらにその子エージェントが孫エージェントを呼び出して作業させるという、親子孫の階層的な呼び出しが可能
- これにより、メインエージェントのコンテキスト汚染を防ぐ事ができる
- サブエージェントからのレポート内容が詳細すぎると、結果的にコンテキストを消費してしまうという課題も指摘されている
- まとめ
- コンテキストエンジニアリングは人間が既にやっているkと
- Claude Codeを活用するとコンテキストエンジニアリングしやすい
[LT#1]AIと人間の共創開発!OSSで試行錯誤した開発スタイル
- 登壇者:mae616氏
- 登壇資料
- コンテキストエンジニアリングを導入するにあたり、ウォーターフォール的な「ワンパス実装」ではなく、AIと人間が反復確認を行うアジャイル的な開発アプローチをOSSで試行錯誤。
- カスタム指示やコマンドによりペルソナを設定し、人間が方向性の決定や要件把握を、AIが実装の自動化と反復処理を担うという役割分担を実現。
- 結果、開発に対する気軽さや不安の軽減が実感され、既存の開発理論とAIを組み合わせることで持続可能なソフトウェアのあり方を追求することが出来た。
[LT#2]Claude Agent SDK を使ってみよう
- 登壇者:aq氏(aqhayami)
- 登壇資料
- モバイルアプリ開発者としてClaude CodeのCLI作業を自動化し、タスクを順番に消化する「ccrunner」を自作した経験を紹介。
- 従来のClaude Code SDKは「Claude Agent SDK」に名称変更され、コーディング専用から、Anthropic社がリモート操作や動画作成にも利用するような汎用的なAIエージェント作成ツールへと進化。
- 新SDKでは、プリセット(例: claude_code)を用いたシステムプロンプトの設定や、TypeScriptなどで定義できるカスタムMCP機能が導入され、Bashコマンド実行やAPI通信など自由度の高いエージェント構築が可能になった。
[LT#3]3年ぶりにコードを書いた元CTOがClaude Codeと30分でMVPを作った話
- 登壇者:MaikoKojima氏
- 登壇資料
- 経営層となって約3年間コードから離れていたが、Claude Codeをペアコーディングとして活用し、AIエージェント開発者向けサービス(MVP)をわずか30分で作成。
- Claude Codeは、最新のフレームワーク選定やテストケースの作成などを担い、開発者の役割がコードの実装から、AIの提案に対する判断や方向性の決定へと変化したことを実感。
- AIペアコーディングは、キャリアの変化などで最先端の技術動向を追えていないエンジニアでも、プロダクト作りにいつでも復帰できる持続可能な技術。
[LT#4]テスト生成で気づいた、Claude Codeとのベストな役割分担
- 登壇者:いちご氏
- 登壇資料
- フロントエンドのテスト生成をAIに「テスト書いて」という簡潔な指示で行ったところ、一見網羅的なコードが返ってきたが、実際には正常系(ハッピーパス)しかテストできていないという問題が発覚。
- コードの分岐をテストできていない不具合に対し、人間が泥臭く手動で修正を加えるか、あるいはカスタムスラッシュコマンドを整備してAIの能力のギャップを埋めることが現状のエンジニアの役割。
- 将来的に簡単な指示でテストが生成される世界を目指すものの、現在はAIが書いたテストをそのまま信用せず、人間の判断やカスタムコマンドによる役割分担が必要。
[LT#5]Subagents 再入門 ~cc-sdd Subagents版の実装で学んだこと~
- 登壇者:Gota氏
- 登壇資料
- Claude Codeのサブエージェントは、メインの会話とは独立した独自のコンテキストウィンドウを使用するため、メインエージェントの会話履歴は全く引き継がれず、両方のエージェントの入出力を設計することが重要。
- サブエージェントに委任すべきタスクは、メインエージェントのコンテキストを汚染させたくないタスク(エラーログ解析、リサーチ系など)や、並列で行いたい検索タスクであり、特にリード系(読み込み)タスクでの利用がスムーズ。
- サブエージェントの自律的な動作を確保するためには、設定するサブエージェントを最小限に抑え、ディスクリプションを明確に設定すること、また巨大なコンテキスト(1万トークンなど)はファイルとして委任することを推奨。
[LT#6]複数のGemini CLIが同時開発する狂気 – Jujutsuが実現するAIエージェント協調の新世界
- 登壇者:
- 登壇資料
- Claude Code CLIを複数同時に走らせる際に生じるGitコンフリクトの問題提起から始まり、その解決策として、Gitの代替または共存ツールであるJujutsuを紹介。
- Jujutsuはコンフリクトをデータとして保存し、複数のワークスペース間で状態を共有する機能を提供することで、バックエンドとフロントエンドのような同時開発が可能。
- Jujutsuに対応したGUIツール「Emdash」が紹介され、Claude CodeやCodexなどのCLIコードエージェントを、それぞれ異なるGit Worktreeで同時に走らせるデモを実演。
クロージング
イベント本編終了後はAnthropic Communityから開催を祝してのメッセージ動画が流れ、また生成AI関連のイベントの告知各種が行われていました。何かめっちゃイベントの数が多かった…
まとめ
という訳で『Claude Code Meetup Tokyo』の視聴レポートでした。内容1つ1つがとても聴き応えがあり、十分過ぎるくらい個人的には収穫があった内容だったと思います。キーワード的にも今後の参考になるものが沢山拾えたので、さらなるインプット&アウトプットを重ねて行こうと思います。
Views: 0