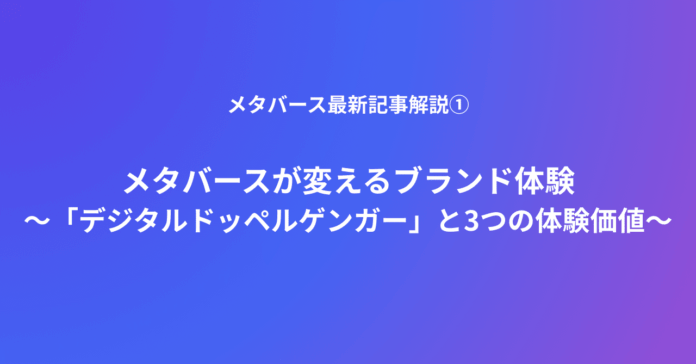🧠 概要:
概要
若宮和男氏が発表した記事「メタバースが変えるブランド体験」では、メタバースの進化が企業と消費者との関係をどのように変えるか、特に「デジタルドッペルゲンガー」という概念に焦点を当てて解説しています。メタバースでの3Dアバターの重要性、またそれらがブランドエンゲージメントに及ぼす影響が述べられています。
要約の箇条書き
- メタバースの影響:RobloxやZEPETOなどが消費者とブランドの関係を変革中。
- デジタル・ドッペルゲンガー:アバターが自己の分身として機能し、物理的体験に近いエンゲージメントを提供。
- ユーザー体験:VRだけでなく、スマホやPCでの非VRプラットフォームでも高いエンゲージメントを確認。
- ブランドへの影響:メタバース体験が物理世界での購買行動に及ぼす影響が実証されている。
- 体験価値の要素:
- 楽しさ(Enjoyment)
- リラクゼーション(Relaxation)
- 評判・名声(Reputation)
- 日常性の重要性:メタバースがリラックスできる居場所としての側面を強調。
- ブランド戦略の提言:ブランドは「楽しさ」だけでなく、「リラックス」できる体験やソーシャルな期待に応える必要がある。
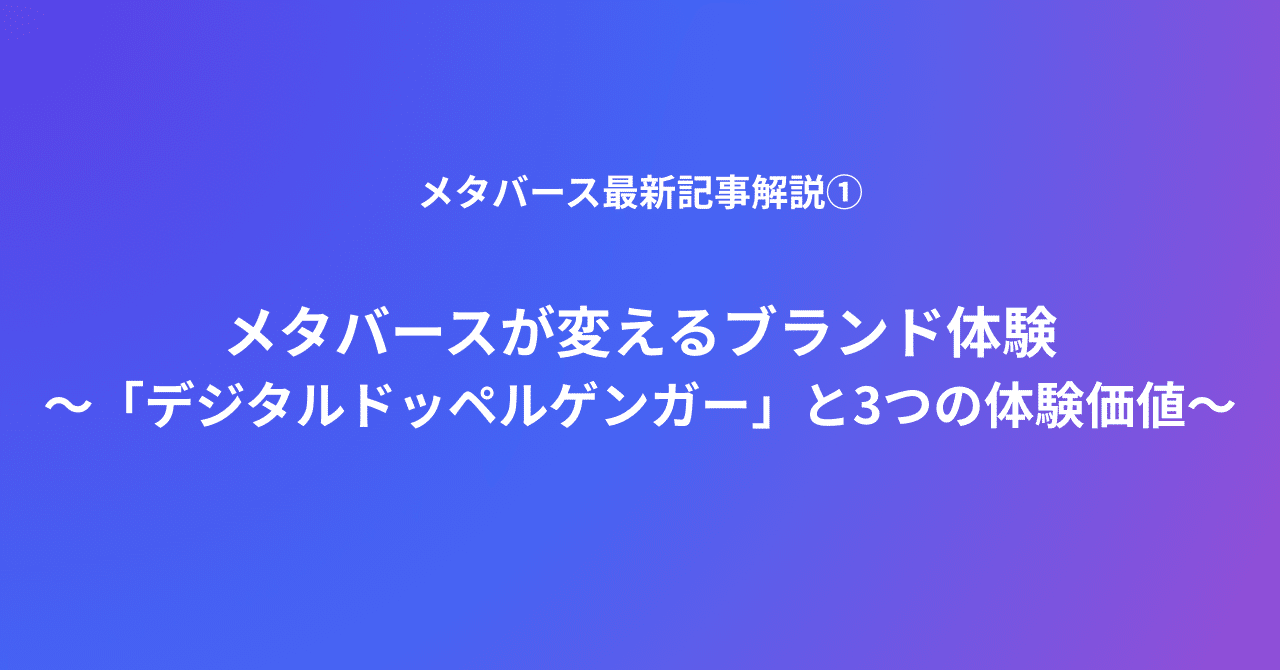
お疲れさまです。メタバースクリエイターズ若宮です。
これからメタバースに関する海外記事などを時々ご紹介していこうと思うのですが、今日は「メタバースによるブランド体験」に関する記事をご紹介しつつ、僕なりの視点で解説してみたいと思います。
企業のマーケやブランド担当の方でメタバースに興味がある方はぜひ!
メタバースがブランド体験を変える?
Robloxなどのメタバースが消費者とブランドの関係を変えつつある、という調査
Metaverse platforms, like Roblox and ZEPETO, are redefining how brands connect with consumers, blurring the lines between physical and digital identitieshttps://t.co/wTWllJT9uH
— waka00/若宮和男(メタバースクリエイターズ代表/uni’que代表/アート思考/新規事業) (@waka_uq) May 8, 2025
こちらも同じ調査を元に書かれた英文の記事ですが、Google翻訳でもとても読みやすく読めるのでおすすめです。(便利な時代)
これらの記事は、サリー大学が発表した「Digital Doppelgänger: Navigating Consumer–Brand Engagement in the Metaverse(デジタルドッペルゲンガー:メタバースにおけるブランドとの関係性)」という論文を元にしています。
「デジタル・ドッペルゲンガー」
論文のタイトルにもなっているキーワードが「デジタル・ドッペルゲンガー」という言葉。
「ドッペルゲンガー」とは自分そっくりの分身のことで、出会ってしまうと死ぬとか、オカルト的な話題でもよく聞く言葉です。
ドッペルゲンガー(独: Doppelgänger)とは、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種で、「自己像幻視」とも呼ばれる現象である[1][2]。自分とそっくりの姿をした分身[1]。第2の自我、生霊の類[3]。同じ人物が同時に別の場所(複数の場合もある)に姿を現す現象を指すこともある(第三者が目撃するのも含む)[2][4]。超常現象事典などでは超常現象のひとつとして扱われる[5][2]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドッペルゲンガー
「デジタル・ドッペルゲンガー」はもちろんオカルトや超常現象ではなく、「アバター」のことを指します。
また「ドッペルゲンガー」とは異なり、見た目がそっくりというのが必須要件ではありません。見た目は全く違ってもメタバース空間の中で「自分の分身のように感じられる存在」ということがポイントです。
論文ではVRやAR/XRなどの技術が進歩する中で、3Dの「デジタル・ドッペルゲンガー」は従来の2Dアバターとはブランド体験において一線を画す、と指摘されています。
Unlike simple 2D avatars, digital doppelgängers are 3D representations that allow users to engage in various activities, interact with brands, and experience emotions similar to those in the physical world.
https://phys.org/news/2025-05-metaverse-consumer-engagement.html
VRやMRなどでのアバター体験は一人称視点で没入感が圧倒的に高く、従来の2Dアバターとは体験として全く違う、というのはイメージしやすいと思います。
ただ、僕が注目したのは、この調査がVRユーザーではなく、RobloxやZEPETOといったスマホやPCでの利用がメインの非VRプラットフォームのユーザーに対して行われたものだ、ということです。
3Dモデルではあっても、スマホやPCの画面に映るアバターという意味では、従来の2Dアバターとそこまで違わない気もします。しかし、こうしたメタバースのユースにおいてもエンゲージメントが高くなる、というのは興味深いです。
僕はいつもメタバースにおいてVRは強力なエンハンス要素だけれども必須ではなく、「メタバース=VRではない」と強調しています。VRでの体験が濃いことはもちろんですが、VRでなくともメタバース的な体験は成り立つことをこの調査は示しています。
VRかどうかよりも、3Dアバターでメタバース空間を自由に動き回りメタバース内のアイテムや他のユーザーと交流できる、インタラクティブ性と行動の主体性こそがアバターに対する「デジタル・ドッペルゲンガー」感覚を生み、「物理世界と同様の体験をもたらす」と言えるでしょう。
メタバース体験は物理世界の購買に影響する
バーチャル美少女ねむさんとMiraさんによる「ソーシャルVRライフスタイル調査」では、メタバースでの体験が物理経済にどれくらい影響を与えるか、という調査がありました。

なんと約4割の人がメタバースでの体験をきっかけに物理現実でも商品を買った、と回答しています。
この影響は特にVRChatユーザーで大きく、またアジア、特に日本が高いのも興味ふかいところです。
メタバースクリエイターズでも、最近サントリーの新商品、クラフトボス世界のティーという商品でメタバースコラボを行いました。
商品の3DモデルをVRChat用に配布しフォトコンテストを開催したのですが、フォトコンは200以上の応募、キャンペーン関連の投稿は合計約2,000に、
VRChatterによる「踊ってみた」動画は10万回以上視聴されるなど、大きな反響がありました。
特に印象的だったのは「買ってきた!」という投稿が散見されたことです。
メタバースがブランド体験に影響することがまさに実証されたと言えるでしょう。
「VR」とサービス名につくVRChatでさえ、必ずしもVRからの利用とは限りません。スマホやPCからの体験でも、アバターを自ら自由に動かせて他者やモノに触れたりイベントに参加したりできる。「自分自身の行動」と感じられることが分身=「デジタルドッペルゲンガー」感覚へとつながり、それは物理世界へも影響するのです。
体験価値を構成する三つの要素
この論文でもう一つ注目すべきは、メタバースでの体験価値を構成する3つの要素について分析されていること。
それは「楽しさ(Enjoyment)」「リラクゼーション(Relaxation)」「評判・名声(Reputation)」の三つです。
「楽しさ」は一番わかりやすいでしょう。メタバースでは友達と遊んだり、ゲーム的な要素もありますから、「楽しい」というのは第一に挙げられる体験価値です。二番目には「リラックス」、現実では得られない安心感や癒しをバーチャル空間で感じられる、と言われていて、アバターによる心理的安全性もここに関わってくるでしょう。そして「名声」や評判。メタバース内での活動やアバターのかわいさで目立ったり、評価されたりすることで得られる達成感です。
この三つが合わさることで、より強い没入感が得られ、ブランド・エンゲージメントを高める、とされています。
僕が注目したのは、「楽しさ」に加え「リラックス」という価値がブランドとコンシューマーの関係性において大事だと指摘されていること。これが重要だと思うのは「リラックス」は「メタバースの日常性」につながっていると思うからです。
「日常性」がこれからのメタバースには重要、と僕はいつも強調しています。メタバースやVRでは「驚きのある体験」が目指される事が多いのですが、それだとどうしても「非日常」の域を出ません。
「驚き」以上に、リラックスしてすごせる「居場所」になる、ということが重要だということです。
VRChatterはもちろんVFesやVketなど、イベントで驚きや感動の体験も好きですが、ある程度沼ったVRChatterはもう少し「いつメン」的な友達と集まるクローズドな場所をもっていて、リラックスして過ごせる「もうひとつの居場所」になっているケースが多いと思います。
そしてメタバースでのブランドエンゲージメントにおいて「レピュテーション(評判)」が挙げられていることは、メタバースは本質的にはソーシャルメディアである、ということを端的に示しています。
人類がメタバースで過ごす時間はこれからますます増えてくるでしょう。すると物理世界ではなくメタバースでの友達が増えます。今や「ソーシャル」のメインがオフラインよりもオンラインになっているように、メタバースへとソーシャルの重心が移ってくる。
ソーシャルの中心がメタバースになれば、ファッションなどの「ブランド」(それは多くの場合「セルフブランディング」のための所有欲でもあるので)はソーシャルなreputationのためのツールになってくるわけです。
アバターで生き生きと動き回り、他者とコミュニケーションできる。メタバースはそういう「ソーシャル」のメディアであり、ユーザー同士だけではなく世界やそこにあるさまざまなモノとインタラクションできます。
その中で「「デジタル・ドッペルゲンガー」感覚が芽生え、物理世界と同様の体験の強度を持ち、物理世界の経済にも影響を与えていく。
すでにナイキやGucciなどのファッションブランド、アーティストがメタバースを活用していますが、これから「デジタル・ドッペルゲンガー」性を活用し、コンシューマーと深い関係を結ぼうとするブランドはますます増えていくでしょう。
そしてブランドがメタバースの住民とより深くつながるためには、「楽しさ」だけではなく、「リラックス」できる居場所づくりを意識すること、そしてソーシャルな「名声」欲求をくすぐるような体験価値を設計することが重要でしょう。
https://platform.twitter.com/widgets.js
続きをみる
Views: 0