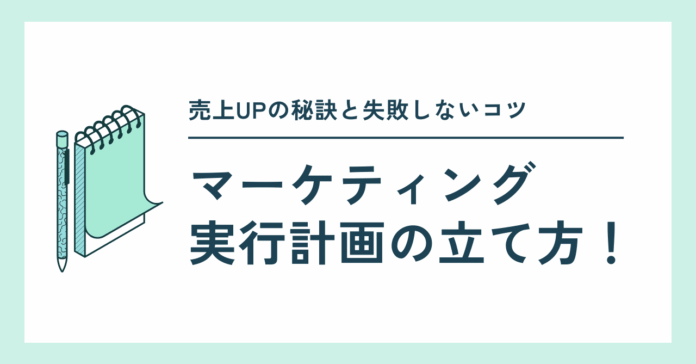🧠 概要:
概要
この記事は、マーケティング実行計画の作り方を詳細に解説し、売上向上のための具体的なステップや注意点を紹介しています。計画は単なる道筋を示す道具ではなく、ビジネスの成長を実現するための「宝の地図」として重要であると語っています。
要約
-
マーケティング実行計画とは:
- 優れたアイデアには具体的な実行計画が不可欠。
- 実施フェーズが特に重要。
-
ステップ1: 目標設定:
- 資金や資源を把握し、具体的な目標を設定。
- 予測損益計算書(PL)を作成し、収益見込みを立てる。
-
戦略シナリオ:
- 短期目標と中長期目標のバランスを考慮。
- 目標の根拠をデータに基づいて明確にする。
-
ステップ2: アクションプラン作成:
- 4P(製品、価格、流通、プロモーション)を使い具体的なアクションを定義。
- 「誰が、何を、いつまでに、どうやって」を明確にする。
-
コスト計画とROI:
- 各作戦のコストを見積もり、投資収益率を確認。
-
社内体制:
- 目標をチームごとに細分化し、役割を明確にする。
-
ステップ3: モニタリングと修正:
- 定期的な評価(PDCAサイクル)で進捗をチェック。
- KPIを設定し、数字で測定することで計画の修正を行う。
-
成功のための心構え:
- 計画は生きたものであり、柔軟に見直し・改善が必要。
- 失敗を恐れず、そこから学ぶことが重要。
- 結論:
- 計画の成功には継続的な見直しと改善が不可欠。
- チームが一つの目標に向かって進むための文化を育成することが大切。
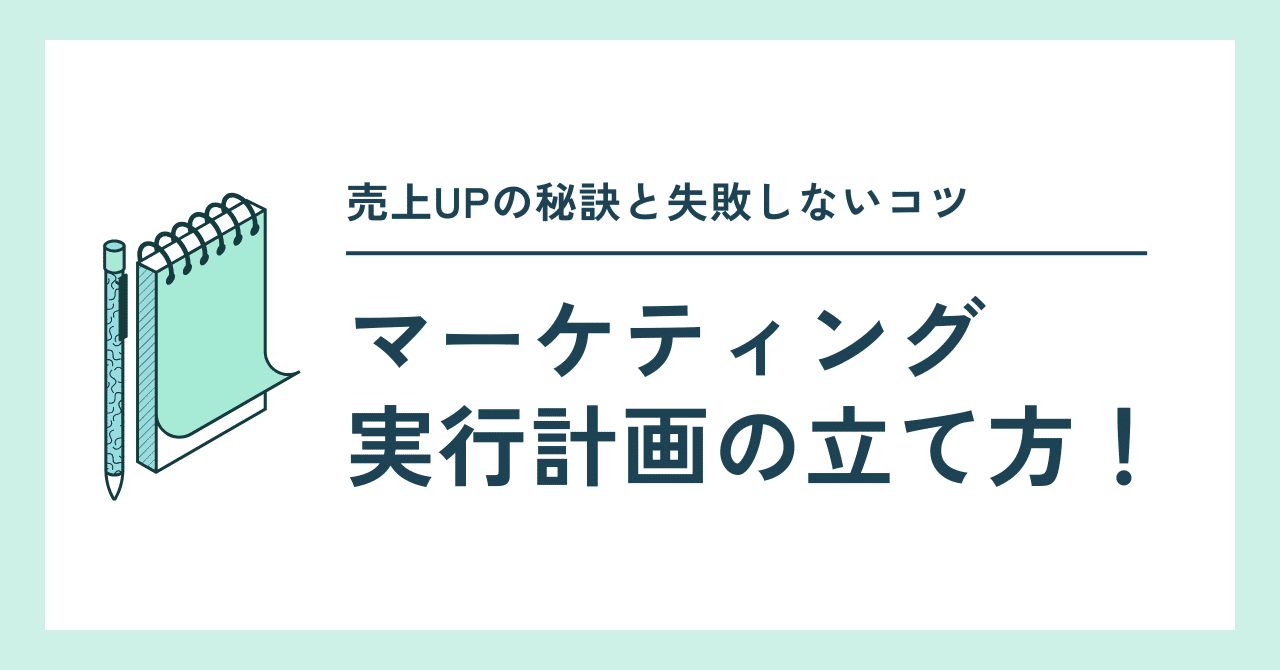
「マーケティングって何から始めればいいの?」
「計画を立てても、いつも途中で挫折しちゃう…」
そんな悩みを抱えていませんか?
この記事を読めば、まるで冒険の地図を手に入れるように、マーケティング実行計画の具体的な作り方がわかり、あなたのビジネスを成功へ導くヒントが見つかります!
この記事では、マーケティングの実行計画を立てるための具体的なステップを、たとえ話や具体例を交えながら、とことん分かりやすく解説します。
もう「計画倒れ」なんて言わせません!
この記事を読み終える頃には、あなたも自信を持って実行計画を立てられるようになっているはずです。
要約ラジオ
なぜマーケティング「実行計画」が宝の地図なの?
素晴らしいアイデアも、具体的な「実行計画」という名の「宝の地図」がなければ、ただの夢物語で終わってしまいます。この地図があれば、どこへ向かい(戦略)、どう進むのか(戦術)が一目瞭然!
ビジネスという大海原を航海するための、超重要なアイテムなんです。
マーケティング活動は、大きく分けて「市場調査」「戦略設計」「実施」「評価」の4ステップ。実行計画は、この中の「実施」フェーズの心臓部。
戦略で描いた「お宝のありか(目標)」へたどり着くための具体的な道のり(行動レベルの計画)を示してくれます。
そして大事なのは、この地図は一度作ったら終わりじゃないってこと。海の状況(市場)は常に変わるし、冒険の途中(計画実行中)で新しい発見や困難(課題)も見つかります。
だから、実行計画はビジネスの成長に合わせて柔軟に見直し、改良していく「生きている地図」として活用しましょう。
ステップ1:冒険の準備!予測と目標設定でお宝の場所を特定せよ
さあ、冒険の始まりです!
でも、いきなり船を出すのは危険。
まずは、どれくらいの食料(資金)が必要で、どこにお宝(目標)があるのかをしっかり把握しましょう。
「お金の計算は大事だよ!」数値なき計画は絵に描いた餅
マーケティング計画で一番大事なのは、お金の計算、つまり数値的な裏付けです。これがない計画は、まるで中身のない宝箱。
事業計画書を作ることで、頭の中のモヤモヤしたアイデアがスッキリ整理され、具体的な行動ステップや必要な仲間(資金、人材、時間など)が見えてきます。
たとえば、豪華客船の設計図(マーケティング戦略)があっても、建造費(予算)がなければ船は作れませんよね?
それと同じです。
「未来の家計簿」予測損益計算書(PL)を作ろう!
冒険に必要な食料(資金)を見積もるために、「予測損益計算書(PL)」という未来の家計簿を作りましょう。これは、将来どれくらい儲かって(売上)、どれくらいお金が出ていくか(費用)、そして最終的にどれくらい手元に残るか(利益)を予測するものです。
これを作れば、「いくらで」「何個売れば」「いつまでに達成できるか」といった具体的な目標が見えてきます。
予測損益計算書のポイントを説明しますね。
-
売上高:お店で商品が売れた総額。例えば、駄菓子屋さんでうまい棒が100本売れたら、「10円×100本=1000円」が売上高です。
-
売上原価:売れた商品を作るのに直接かかったお金。うまい棒の材料費とかですね。
-
売上総利益(粗利益):売上高から売上原価を引いたもの。これがお店の基本的な儲けです。
-
販売費及び一般管理費(販管費):お店の家賃やアルバイトのお給料、電気代など、商品を売るためや会社を運営するためにかかるお金です。
-
営業利益:売上総利益から販管費を引いたもの。本業でどれだけ稼いだかを示す、超重要な数字です。
予測損益計算書を作る手順は、ざっくりこんな感じ。
-
過去のデータや市場の様子、これからの作戦を考えて、未来の売上を予測します。
-
かかる費用を、売上が増えると一緒増える「変動費(材料費とか)」と、売上に関係なくかかる「固定費(家賃とか)」に分けます。
-
予測した売上から、変動費と固定費を引いて、利益を計算します。
お店の経営計画を立てるのは、お小遣い帳をつけるのや、修学旅行の計画を立てるのと似ています。まず収入(お小遣い/売上)を見積もり、何にどれくらい使うか(お菓子代/費用)を計画し、最後にいくら残るか(貯金/利益)を考える。
流れは同じですね!
特に、毎月定額を支払うサービス(例えば、ゲームのサブスクや動画見放題サービス)の場合、新しいお客さんと続けてくれるお客さんの数を分けて考え、どれくらいの人が途中でやめちゃいそうか(解約率)も計算に入れるのがポイントです。
「冒険ルートは一つじゃない!」戦略シナリオと目標のバランス
予測損益計算書ができたら、それをもとにいくつかの「冒険ルート(戦略シナリオ)」を考えます。
「ガンガンいこうぜ!(積極拡大ルート)」とか「いのちだいじに(堅実成長ルート)」とかですね。
ここで大切なのが、短い期間の目標(短期目標)と、長い期間の目標(中長期目標)のバランス。
例えば、「1年以内に海賊船の数を2倍にする!(短期目標)」と「5年後には七つの海を制覇する!(中長期目標)」が、ちゃんとかみ合っているか確認しましょう。
例えば、1年で急成長したいなら、最初にたくさん宣伝費(大砲の弾)を使う必要があるかもしれません。その結果、最初のうちは赤字になるかも。でも、じっくりブランドを育てたいなら、宣伝費は抑えめにして、船の性能アップ(製品開発)や船員満足度アップ(顧客満足度)に力を入れるかもしれません。
どっちのルートを選ぶかで、お金の使い方が全然変わってきます。
KGI(最終ゴール)とKPI(中間ゴール)を設定して、時間ごとに整理すると分かりやすいですよ。KGIは「5年以内に伝説の秘宝を見つける!」、KPIは「1年目:古代地図の解読を終える」
「2年目:最初の試練の島をクリアする」みたいな感じです。
どのルートを選ぶかは、船長(経営者)の度胸(リスク許容度)や持っている武器(リソース)によって変わります。
資金が少ない小さな船なら安全なルートを、大きな船なら大胆なルートを選ぶかもしれませんね。
「なぜその宝を目指すの?」目標設定の根拠と非現実的な夢のワナ
マーケティングの目標を立てるときは、「なぜその宝を目指すのか?」という根拠をはっきりさせることが超重要です。
過去の冒険の記録(販売実績)や、他の船の動き(競合の動向)といったデータに基づいて説明できるようにしましょう。
目標設定には「SMARTの法則」という便利な呪文があります。目標が次の5つの条件を満たしているかチェックしましょう。
-
S (Specific):具体的か?(誰が見ても同じようにわかる?)
-
M (Measurable):測れるか?(達成度を数字で表せる?)
-
A (Achievable):達成できるか?(頑張れば届く範囲?)
-
R (Relevant):関連してるか?(船全体の目的と合ってる?)
-
T (Time-bound):期限はあるか?(いつまでにやるの?)
例えば、「2024年の終わりまでに、宝の地図の解読率を去年の1.5倍にする!」みたいな目標は、SMARTで良い例です。
逆に、根拠のない非現実的な目標は、船員(チームメンバー)のやる気を奪ってしまいます。「どうせ無理だ…」となれば、冒険は失敗です。
もし船長が、前回の冒険の成果を無視して「次の冒険では、いきなり3倍の宝を持ち帰るぞ!」なんて無茶な目標を立てたら、船員たちはどう思うでしょう?きっと「そんなの無理だよ…」とがっかりして、船の中の雰囲気も悪くなってしまいますよね 。
無理な目標は、無駄な大砲(広告費の無駄遣い)や、積みすぎた荷物(過剰在庫)にも繋がりかねません。
目標の立て方次第で、チームの雰囲気や行動の質が大きく変わります。
コニカミノルタジャパン株式会社は、明確な目標をチームで共有し、たった3人だったチームを16人に増やし、5年間で売上見込みを25.6%もアップさせました。適切な目標は、チームを強くする魔法なのです。
ステップ2:いざ出航!具体的なアクションプランで宝島へ進め!
冒険の準備が整ったら、いよいよ出航です!ここでは、マーケティングの武器「4P」を使いこなし、
「誰が」「何を」「いつまでに」「どうやって」、そして「どれくらいのお金で」宝島(目標)へ向かうのかを具体的に決めます。
マーケティングの四種の神器「4P」を使いこなせ!
マーケティングミックス、通称「4P」は、お客さんに最高の価値を届けるための4つの基本的な武器です。
Product(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通・チャネル)、Promotion(販促・プロモーション) の頭文字Pをとったもの。
これらをうまく組み合わせるのがポイント!
-
Product(製品・サービス):何を売るか?
-
これが4Pの心臓部!お客さんが「欲しい!」と思う魅力的な製品やサービスを作ることが大切。
機能だけでなく、見た目やブランドイメージ、アフターサービスも重要です。 -
ユニクロは「シンプルで質の良い服を、いつも新しい感じで提供する」ことを製品戦略の核にしています。スターバックスは、コーヒーだけでなく、「家でも職場でもない、くつろげる第3の場所」という体験も売っています。
-
-
Price(価格):いくらで売るか?
-
値段設定は、売上や利益に直接影響する超重要ポイント。
作るのにかかったお金、ライバルのお店の値段、お客さんが「これなら払ってもいい」と思う金額、そして自分たちが欲しい利益などを考えて決めます。 -
カゴメの野菜ジュース「毎日飲む野菜」は、他のジュースより少し高いけど、健康を気にする大人にはちょうど良い値段。定期購入で割引もあって、続けやすい工夫も。値段の決め方には、「原価+利益」で決める方法や、お客さんが感じる価値で決める方法、ライバルの値段を参考にする方法などがあります。
-
-
Place(流通・チャネル):どこで売るか?
-
製品やサービスを、お客さんが買いやすい場所や方法で届けるためのルート選びです。
お店で売る、ネットで売る、誰かに売ってもらうなど、色々あります。 -
H&Mは、世界中の安い工場で作った服を、効率よく船で運んで、世界中のお店に届けています。カゴメの「毎日飲む野菜」は、あえて通販だけで売ることで、特別な感じを出しています。いまはネット販売も超重要!自分のサイトで売ったり、Amazonや楽天に出店したり、SNSで売ったりもできます。
-
-
Promotion(販促・プロモーション):どうやって知らせ、買ってもらうか?
-
製品やサービスの存在をお客さんに知らせ、魅力を伝え、買いたい気持ちにさせるための活動全部です。
広告、割引、イベント、営業マンの直接販売などがあります。 -
RIZAP(ライザップ)は、衝撃的なビフォーアフターを見せるCMで、一気に有名になりました。任天堂の「スーパーマリオラン」は、SNSで情報を広めたり、人気ユーチューバーに宣伝してもらったりしました。宣伝するときは、お客さんがよく見るメディアを選び、メッセージが心に響くように工夫するのが大切。ハロウィンみたいなイベントに乗っかるのもアリ。
例えば、LINE広告なら、1回クリックされると24円くらいかかる、みたいな具体的なお金の感覚も持っておきましょう。
-
4Pを考えるときは、それぞれの武器がバラバラにならないように、全体で一つの強いメッセージをお客さんに届けることが重要です。
アクションプランの呪文:「誰が」「何を」「いつまでに」「どうやって」
4Pの各作戦を具体的に実行するためには、「誰が(担当者)」「何を(やること)」「いつまでに(締め切り)」「どうやって(方法)」という4つのWと1つのHをはっきりさせることが絶対必要です。
演劇の舞台を成功させるのを想像してみてください。演出家(誰が)が中心になって、台本準備や役者選び、舞台セットのデザイン(何を)を、公演日(いつまでに)から逆算して計画します。
そして、役者の演技指導や舞台装置の組み立て(どうやって)を進めます。マーケティングもこれと一緒!
実際の計画表では、市場調査、製品戦略、価格戦略、流通戦略、プロモーションといった項目ごとに、詳しい内容、担当者、締め切り、そして成果を測るためのKPI(中間目標)などを書くのが一般的です。
例えば、新しいゲームを作るなら、リーダー、デザイナー、プログラマーがいて、それぞれどれくらい時間がかかるか、一人あたりいくらかかるか、を計算して、開発費全体を見積もります。
「どうやって」の部分は、作戦が成功するかどうかの分かれ道。どんなに良い製品(Product)も、買いにくい場所(Place)でしか売っていなかったり、魅力が伝わらない宣伝(Promotion)しかしなかったりしたら、売れません。
4つの武器がうまく連携し、お互いに良い影響を与え合う(相乗効果)ためには、それぞれのやり方や使う道具、チームの能力、そして武器同士の連携を細かく決めておくことが大切です。
コスト計画:「いくら使える?」「いくら必要?」
各作戦を実行するには、もちろんお金(コスト)がかかります。これらを正確に見積もり、最初に作った「未来の家計簿(予測損益計算書)」の予算内に収まるように調整することが重要です。
ここで役立つのが「ROI(投資収益率)」という考え方。これは、使ったお金に対してどれだけ儲かったかを示す数字で、「(儲け ÷ 使ったお金)× 100%」で計算します。
ROIを意識することで、どの作戦がお金を生み出しやすいかを見極められます。
例えば、作戦Aに100万円使って150万円儲かったら、ROIは150%。作戦Bに100万円使って80万円しか儲からなかったら、ROIは80%。
この場合、作戦Aの方が効率が良いとわかります。
広告費の予算の決め方には、売上目標の何パーセント(例えば5%)を広告費にする方法や、目標とするお客さん候補の数に必要な一人あたりの獲得費用を掛けて計算する方法などがあります。
赤字にならない範囲で予算を組むことも大切です。
コスト計画は、一度決めたら終わりじゃありません。
作戦の成果を見ながら、柔軟に見直しましょう。
社内体制:「みんなで目指せ、お宝ゲット!」目標を細かく分けよう
会社全体の大きな目標(お宝ゲット!)を達成するためには、その目標を各チーム(営業チーム、開発チーム、広報チームなど)の具体的な小さな目標やKPI(中間ゴール)にまで落とし込む(ブレークダウンする)必要があります。
そうすることで、各チームが自分の役割をしっかり理解し、みんなで力を合わせて目標に向かえます。
例えば、会社全体のKGIが「年間売上を去年の1.2倍にする!」だったら、営業チームのKPIは「新しいお客さんとの契約を毎月20件増やす!」、マーケティングチームのKPIは「ホームページからのお問い合わせを毎月100件にする!」みたいに、各チームが追いかける具体的な数字を決めます。
ある会社では、マーケティングチームが生み出す「質の高い見込み客の数」を一番大事なKPIにしたら、営業チームとの連携がスムーズになり、契約につながる確率が上がったそうです。
さらに、KPIを達成するための具体的な行動目標として、「KDI(重要行動指標)」を設定するのも効果的。
例えば、マーケティングチームのKPIが「ホームページのアクセス数を月30%増やす」なら、KDIは「週に2本、役立つブログ記事を書く」「月に1回、オンラインセミナーを開く」などです。
色々なチームが関わる難しい課題(例えば、製品を早くお客さんに届けるとか、会社全体でお客さんをもっと満足させるとか)に取り組むときは、各チームから代表者を集めた「特別チーム(タスクフォース)」を作るのも良い方法です。特別チームをうまく運営するには、まず解決したいテーマをはっきりさせ、次に各チームからやる気のあるメンバーを選びます。
そして、会議の頻度(例えば月1回)や、いつまでに何をやるか、どうやって話し合うか、といったルールを決めて、進み具合を管理します。
チームごとのKPIがバラバラにならず、会社全体の大きな目標達成に繋がるように設計することが、めちゃくちゃ重要です。
ステップ3:冒険の記録と進路変更!モニタリングと軌道修正
アクションプランができたら、いよいよ実行!
そして、計画通りに進んでいるか、こまめにチェック(モニタリング)して、必要なら進路を変える(軌道修正)ことが大切です。
「見張り台」を設置せよ!モニタリングの仕組み作り
作戦を実行したら、その状況を定期的にチェックして評価するための「見張り台(モニタリングの仕組み)」を準備することが絶対必要です。
モニタリングとは、計画と実際の進み具合のズレを早めに見つけて、目標達成のために必要な調整をするための一連の活動のこと。
車の運転を想像してみてください。目的地に向かって運転中、ドライバーはスピードメーターやガソリンメーター(これらがモニタリング指標)を常に見て、状況に応じてアクセルを調整したり、給油したり、時には道を変えたり(これらが軌道修正)しますよね。
マーケティングも同じです。
会社全体のルール作り(内部統制システム)でも、仕事の状況をずっと見守り、記録することが大事なステップとされています。
冒険日誌「PDCAサイクル」をつけよう!
マーケティング活動の進捗管理と改善に超役立つのが「PDCAサイクル」。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4ステップを繰り返すことで、どんどん賢く、強くなっていく方法です。
-
Plan(計画):まず、何を達成したいか(目標)をはっきりさせ、そのための具体的な作戦を立てます。
-
Do(実行):立てた作戦を実行します。何をやったか、どんな結果が出たかを記録するのがポイント。
-
Check(評価):実行した結果を、計画の時の目標やKPI(中間ゴール)と比べて評価します。うまくいったこと、いかなかったこと、その原因を、データに基づいて分析します。
-
Action(改善):評価で見つかった課題や改善点に対して、具体的な対策を考え、次の計画に活かします。成功はもっと伸ばし、失敗は繰り返さないようにします。
このPDCAサイクルをグルグル回し続けることで、マーケティング活動はどんどん良くなっていきます。
例えば、新しいネット広告を出してみたけど(Plan)、思ったよりクリックされなかった(Do&Check)。
そこで、広告の文章やデザインを変えてみたら(Action)、クリック率がすごく上がった!みたいな感じです。
PDCAサイクルで特に大事なのは「Check(評価)」。
ここでどれだけ深く、客観的に現状を分析できるかが、次の「Action(改善)」の質を決めます。
「宝の目印」KPIを設定し、数字で測ろう!
マーケティング活動の進み具合を客観的に見て、PDCAサイクルをうまく回すためには、大事な指標を決めて、できるだけ「数字」にすることが絶対必要です。
この数字にされた指標が、KPI(重要業績評価指標)。KPIは、最終ゴールであるKGI(重要目標達成指標)への道のりを示す「目印」みたいなものです。
例えば、売上目標なら「売上金額」や「売れた数」がKPI。利益目標なら「利益率」や「利益額」。市場シェア目標なら「市場での割合」や「その変化」をKPIにします。
ネットショップなら、「ホームページに来た人の数」や「来た人のうち買ってくれた人の割合(CVR)」、「一人のお客さんを獲得するのにかかったお金(CPA)」などが代表的なKPIです。
KPIを決める一般的なステップは、まず最終ゴール(KGI)を決め、次にKGI達成の鍵となるポイント(KSF)を洗い出し、その達成度を測るためのKPIを設定し、さらにKPI達成のための具体的な作戦を立てて、実行・測定・改善を繰り返す、という流れです。
「お客さんの満足度アップ」や「ブランドイメージ向上」みたいに、直接数字にしにくい目標もあるかもしれません。でも、工夫次第でKPIにできます。
-
「お客さんの満足度アップ」:定期的にお客さんにアンケートをして、満足度点数(例えば5段階評価の平均点)をKPIにする。
-
「ブランドイメージ向上」:ブランドを知っている人の割合や、SNSで良い口コミの数をKPIにする。マーケティングの成果は、売上だけでなく、こういう目に見えない価値も大事。
-
「接客の質アップ」:お店の評価点や、リピートしてくれるお客さんの割合をKPIにする。
KPIは、決めるだけでなく、チームみんなでその意味と大切さを共有することが重要です。
進捗チェックと進路変更:計画とのズレはすぐ直す!
決めたKPIは、定期的に達成度を確認し、計画と実際の間にズレがないか常にチェックすることが大切です。
この進捗管理で、計画通りに進んでいないところを早めに見つけ、原因を分析して、適切な進路変更(軌道修正)をすることが、目標達成の確率を上げるカギです。
例えば、新しいお菓子の販売計画で、最初の1ヶ月の目標販売個数を1000個と設定したとします。でも、発売から2週間で200個しか売れていなかったら(計画と大きなズレ!)、すぐ原因を調べる必要があります。原因は、ライバルのお菓子が同じ時期に出た、季節の読み違い、宣伝が届いていない、値段が高すぎた、など色々考えられます。
原因がわかったら、例えば、期間限定の割引をする、追加で宣伝する、売る場所を変える、といった対策をすぐに行うことが求められます。
市場の状況やライバルの動きは常に変わるので、最初に立てた計画がいつまでも正しいとは限りません。変化のサインをいち早くキャッチして、柔軟に作戦を修正していく力が、今のマーケティングには絶対必要です。チェックの頻度も、状況に合わせて変えるのが賢いやり方。
例えば、新しい作戦を始めたばかりの頃は、問題点を早く見つけるために毎週チェックし、作戦が安定してきたら毎月や3ヶ月ごとなど、だんだん頻度を下げていく、といった感じです。
おわりに:実行計画という名の「宝の地図」を成功へ導くために
マーケティングの実行計画は、作って終わりじゃありません。
それを確実に実行し、期待するお宝(成果)を手に入れるためには、いくつかの大事な心構えと、続ける努力が必要です。
「計画倒れ」のワナを避けろ!
せっかく作った宝の地図も、いくつかのワナにはまると、途中で使えなくなってしまいます(計画倒れ)。そうならないために、気をつけたいポイントはこちら。
-
高すぎる目標は禁物: 現実を見ずに、達成不可能な目標を立てると、最初からやる気がなくなります。
-
具体的な行動計画がないのはダメ: 「何を」「いつまでに」「誰が」「どうやって」が曖昧だと、誰も動けません。
-
行き当たりばったりは危険: 準備不足で始めたり、その場しのぎの対応を繰り返したりしていては、計画通りに進みません。
-
記録と評価を忘れずに: やったことや結果をちゃんと記録しないと、後で正しく評価できず、改善にも繋がりません。
-
的外れな改善策は無意味: 評価結果を無視して、昔のやり方や思いつきで改善しても、問題は解決しません。
-
無理なスケジュールは破綻のもと: 仲間の能力や予期せぬトラブルを考えずに、ギチギチのスケジュールを組むと、計画は途中でダメになりやすいです。計画には少し「ゆとり」を持たせましょう。
過去の冒険には、残念ながら失敗に終わったものもたくさんあります。
これらの失敗から学ぶことは非常に多いです。
例えば、レストランチェーン「いきなり!ステーキ」のアメリカ進出は、現地の食文化(立ち食いに馴染みがない)やステーキに対する価値観(日常食より特別なご馳走)の理解が足りず苦戦しました。ZOZOTOWNの「ZOZOSUIT」は、家で体型を測れる画期的なアイデアでしたが、測る手間やアプリの不具合、スーツが届くまでの時間などが、お客さんの期待に応えられませんでした。コンビニのドーナツ販売も、コーヒーほどの人気は出ず、ドーナツ専門店との違いも出しにくかったようです。ユニクロが昔やった野菜の通販「SKIP」も、服のノウハウがそのまま野菜には通用せず、撤退しました。
ジュースの「トロピカーナ」がパッケージをガラッと変えたら、お客さんがいつもの商品だと気づきにくくなり、すぐに元のデザインに戻した、なんてこともありました。
これらの話は、事前の市場調査、お客さんの理解、そして現実的な作戦と実行計画がいかに大事かを教えてくれます。
マーケティングでの失敗は、ただの残念な結果じゃありません。未来の成功のための貴重な「手がかり」として活用する視点が大切です。計画がうまくいかなかったら、その原因を徹底的に分析し、そこから学んだことを次の計画に活かすことで、チーム全体が賢くなり、より良いマーケティング活動に繋がります。SKIPの野菜通販の経験は、後に別のブランド「GU」の立て直しに役立ったと言われていますし、ZOZOSUITで集めたたくさんの体型データは、新しい技術開発の基礎になったそうです。
失敗を恐れずに挑戦し、結果から学び、改善を繰り返す。これこそが、変化の激しい市場で生き残るためのカギです。
「常に最新版に更新!」継続的な見直しと改善の文化を
マーケティングの実行計画は、一度作ったら終わりではありません。市場の流行、ライバルの動き、そして何よりお客さんの気持ちは常に変わっています。
だから、作った計画も定期的に見直し、今の状況に合わせて柔軟に改善していくことが、マーケティングを成功させ、その成果を持続させるための秘訣です。
マーケティング計画の運用は、庭の手入れに似ています。一度きれいにした庭も、放っておくと雑草だらけになり、花も枯れてしまいます。
美しい庭(成功したマーケティング)を保つためには、定期的に水をやり、雑草を取り、肥料を与える(計画を見直し、改善する)といった継続的な手入れが絶対に必要なのです。
この「継続的な見直しと改善」をチームの文化にするためには、メンバーからの意見を積極的に集め、それを真剣に受け止め、改善点を見つけ出す努力が求められます。そのためには、チームの中に「何を言っても大丈夫」「失敗しても責められない」「新しいアイデアをどんどん出せる」
といった、オープンで建設的な雰囲気を作ることが超重要です。
マーケティングの実行計画は、単なる作業指示書ではなく、チームが同じ目標に向かって進むための羅針盤であり、変化に対応しながら成長していくための学習ツールでもあります。
この記事が、あなたの冒険を成功に導くための一助となれば幸いです!
Views: 0