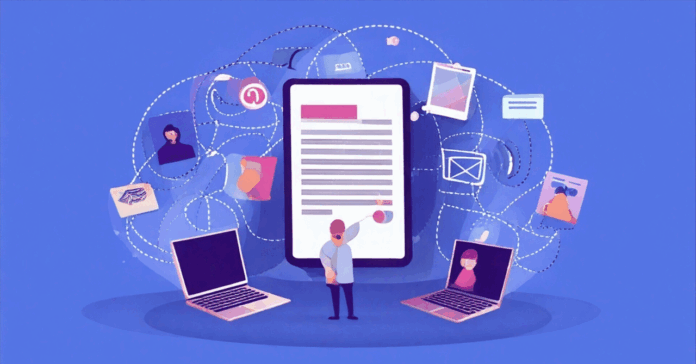🧠 概要:
概要
この記事は、IBMが独自に構築した「Market Intelligence(MI)」という職能に焦点を当て、これがどのように経営判断やマーケティング戦略を支えるのかを解説しています。MIは他社に比べて独立した組織として位置づけられ、データに基づく意思決定の文化を根付かせる重要な役割を果たしています。さらに、他の企業におけるMI組織の導入状況や、BtoBマーケティングにおける示唆を考察しています。
要約
-
IBMのMarket Intelligence (MI):
- 2000年代初頭に導入され、独立したマーケティングの専門職能
- 経営判断を「事実」で支持する役割を持つ
-
他社との違い:
- MIは通常、マーケティングの一部業務として扱われるが、IBMは独立した専門組織として制度化
- 世界的にもMIを専任組織としている企業は少数派
-
MIの機能と組織文化:
- 「数字で語る文化」が米国の企業文化に浸透しており、MIは経営の核となる情報源
- ファクトに基づく意思決定が根付いていない企業では、MIチームの効果が薄れる
-
メリット・デメリット:
- MI組織の導入によって、意思決定の質が向上する一方で、分析が目的化し現場で活用されないリスクも存在
- 短期的な成果を求めすぎると、組織の本質的な変革が妨げられる
-
グローバルな動向:
- SAPやP&Gなどの企業ではMIが重要な役割を果たしているが、成功例は限られている
- 経営が事実を基にした意思決定を行うことが重要
-
日本のBtoBマーケティングへの提言:
- 勘や前例を排し、事実と数字に基づく思考方法を採るべき
- ファクト筋トレを通じ、マーケティングの効果を高める必要がある
- 結論:
- IBMのMIは、事実に基づく判断力の象徴であり、日本企業もこれを導入することで変化に対応できるようになるべきである。
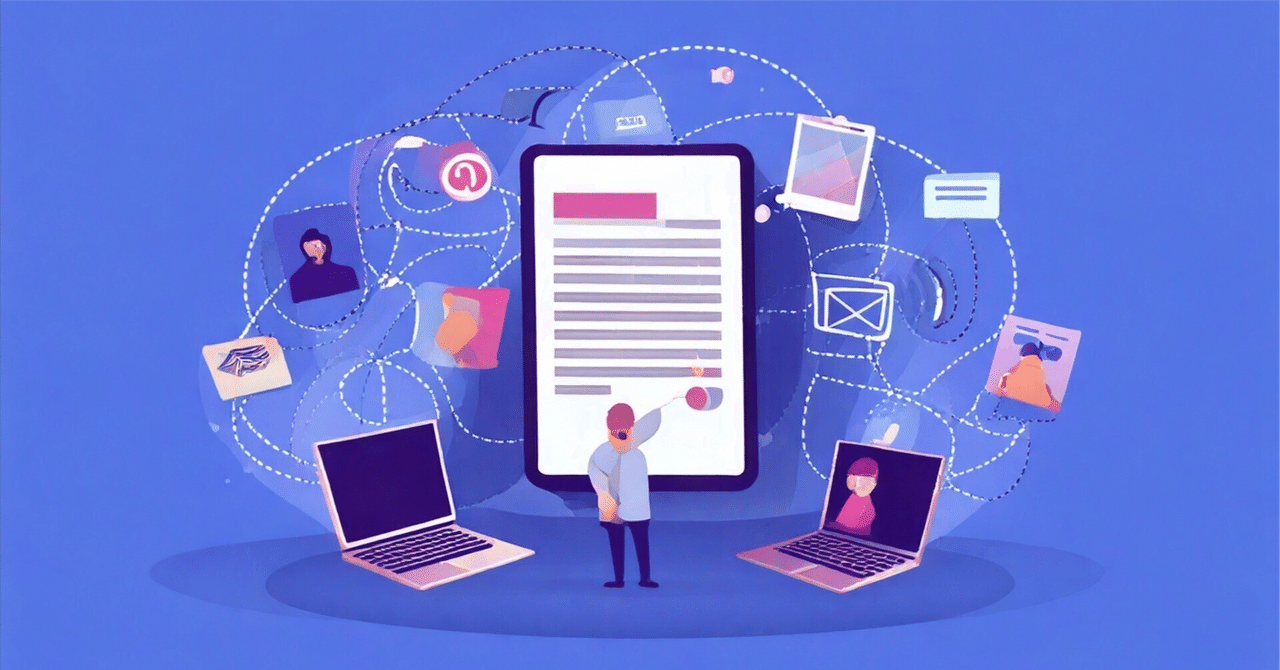
前回の記事では、IBMが2000年代初頭にどのようにしてグローバル規模で体系的なマーケティング組織を構築したのか、その全体像を解説しました。
今回の続編では、その中でもIBM独自とも言える、他社にはなかなか見られないMarket Intelligence(MI)という職能・組織にフォーカスします。
世界の多くの企業では、市場調査や競合分析はマーケティング部門の一部業務に過ぎません。しかしIBMは、Market Intelligenceを独立した専門職能・キャリアパスとして制度化し、マーケティングの中枢に据えていた点が非常にユニークでした。なぜIBMはこのような組織を持ち、どのように経営判断や現場の実行力を支えていたのか。そして、なぜ他の欧米大手や日本企業で同じ形が普及しなかったのか。今回はこのテーマを掘り下げ、日本のBtoBマーケティングにとっての示唆を考えます。
IBMのMarket Intelligence (MI)とは何か
IBMが2000年代初頭に導入したマーケティングディシプリン。その中でも「Market Intelligence(MI)」という職能は、単なる市場調査やデータ分析係とはまったく違う役割を担っていました。
MIの最大の仕事は、「どの市場に進出すべきか」「競合とどう差別化するか」「どんなプロダクトをいつ投入すべきか」といった経営やマーケティングの意思決定を、徹底的に「事実」で支えることです。たとえば米国市場で新たな競合が急成長しはじめたとき、MIチームは机上のデータだけでなく、現場に足を運んでユーザーやパートナーの声を直接ヒアリング。トレンドや業界の噂話だけで意思決定するのではなく、「どんな顧客が、どんな理由で新興ベンダーに流れているのか」を数字で明らかにし、そのファクトをもとに経営判断に本物の根拠を提供していました。
そのアウトプットは単なるレポートや統計ではありません。「この仮説はどの事実に基づいているのか」「なぜ今、この分野に投資すべきなのか」といった経営陣への「問い直し」を内包した、組織全体の思考をファクトベースに鍛える「筋トレコーチ」のような存在だったのです。
MIは世界の常識ではない〜IBMが例外だった
ここで押さえておきたいのは、IBMのようにマーケティング部門の中でMarket Intelligenceを独立した職能・キャリアパスとして明確化し、制度的に運用している企業は、実は世界的にもかなりの少数派だという事実です。
欧米の多くのBtoB企業でも、「市場調査」「競合分析」「リサーチ」自体はマーケティング職能の一部として存在しますが、IBMのように専任組織としてMIを位置づけるケースは少数派です。多くは「マーケティング部内の一機能」あるいは「経営企画や戦略部と兼任」だったりします。SAPやP&Gなど一部のグローバル大手を除けば、「Market Intelligence=独立した専門職能」が普及しているわけではありません。言い換えれば、事実に基づくマーケティング判断の重要性は理解されているものの、MIを専任組織化して企業文化まで落とし込めている例は、今も昔も数えるほどしかないのです。
MIが機能する組織と、その成否を分けるもの
なぜIBMでMIがこれほど強い影響力を持ちえたのか。それは一言でいえば「数字で語る文化」が徹底されていたからです。会議で何かを提案すると必ず「その根拠となるデータは?」「実際に現場でそれが起きている証拠は?」と問われます。たとえば、ある年の新製品戦略会議で、開発側が「この機能が業界標準になるはず」と推した際も、MIは「実際の顧客アンケートでは、その機能は要望の上位に全く入っていません」「競合が強い理由はむしろ別のサポート体制にあります」と事実を突きつけ、プロジェクト自体が方向転換したこともありました。
このように、「思い込み」や「横並び主義」ではなく、「現場と数字」で物事を決める。それが企業文化として根付いていると、MIは単なる情報屋ではなく、経営の頭脳として機能します。
逆に言えば、数字やファクトに基づく意思決定の風土が無い組織に、どれだけ優れたMIチームを導入しても、形だけで終わってしまうのです。よくある失敗例として、「毎月レポートだけは出すが、誰も見ない」「現場や経営が最終的には勘と経験で決めてしまう」という幽霊部門化が挙げられます。ファクト筋トレの道場破り状態ですね。
他社で導入した場合のメリット・デメリット〜B2Bマーケター現場から
MI型組織がうまくワークすると、意思決定の質が飛躍的に向上します。私が支援したグローバルIT企業では、新規市場参入の可否判断や大規模プロダクト投資の際、必ずMIチームが現場ヒアリングと定量分析を重ねて「本当に勝てる場所/勝てない場所」を見極めていました。その結果、傷が浅いうちに撤退できる場面も多く、マーケターとしても「数字と現場の感覚をすり合わせる」理想的な連携が生まれていました。

一方、デメリットや失敗パターンも枚挙にいとまがありません。よくあるのは、「分析が目的化し、現場で活用されないこと」。ある大手メーカーでは、MI部門が「月次競合レポート」をひたすら量産。しかし経営陣は「参考程度」に目を通すだけで、実際の施策や戦略に反映されませんでした。結局「お飾り部署」と化し、数年後には吸収・消滅というパターンです。
さらに、短期成果を求めすぎることも危険です。MIは即効性より組織の思考の質を中長期で鍛える役割ですが、「半年で売上を上げろ」とプレッシャーをかけすぎると、本質的な変革は起こりません。逆に「資料作成係」として使い倒されれば、優秀な人材ほど辞めてしまいます。
グローバル動向と成功・失敗事例
世界に目を向けると、SAPやP&Gのようなグローバル大手B2B企業では、Market IntelligenceやConsumer & Market Knowledgeといった専任部門が当たり前のように存在します。
SAPでは、MI部門が製品開発から営業支援、買収判断にまで深く関与しており、経営会議でも「MIの分析レポート」が共通言語として扱われます。単なる「事務方」ではなく、組織戦略の羅針盤そのものです。
P&GもCMK(Consumer & Market Knowledge)という組織を通じて、ユーザーや市場のファクトを軸に全社戦略を回しており、B2BでもB2Cでも「分析=現場のアクション」につなげるモデルを徹底しています。

ただし、こうしたモデルはあくまで「例外的な成功事例」であることにも注意が必要です。欧州の某IT企業では、MI部門が「データは出すが経営判断には使われない」状態に陥り、数年で組織縮小。どちらも、「経営が本気でファクトを意思決定の武器にする覚悟があるかどうか」が成否を分けているのです。
日本BtoBマーケティングへの提言〜ファクト筋トレから始めよう
日本のBtoB企業は今こそ、「勘や前例」から「事実と数字で考える」カルチャーへ脱皮すべき時です。そのための第一歩は、どんな小さな会議や施策でも「なぜそうするのか、根拠となる数字や事実は何か」を問い直し、ファクト筋トレを地道に繰り返すことに尽きます。
現場の勘や経験も、もちろん重要です。けれど、それを「データで裏打ちし、時に間違いにも気づける」組織でなければ、真の競争力は生まれません。分析職能(MI)を単なる裏方で終わらせず、経営や現場と対等な立場で議論し、意思決定に必ず結びつける仕組みをつくること。そして経営陣自身が「この判断の根拠は?」と問い続ける姿勢を見せることが、ファクト筋トレ組織への近道です。

おわりに
筋肉質な思考で未来を変える
IBMのMarket Intelligenceは、思い込みや空気から自由になり、事実に立脚した判断力を全社に根付かせた象徴的な存在です。BtoBマーケティングの本質は、「現場感覚」と「ファクト」の絶妙なバランスにあります。今こそ、日本の企業もファクト筋トレで意思決定の筋肉を鍛え、変化の時代をしなやかに生き抜く準備を始めてはいかがでしょうか。
Views: 2