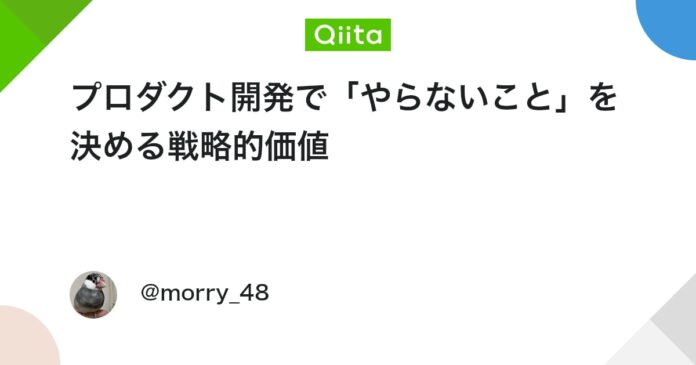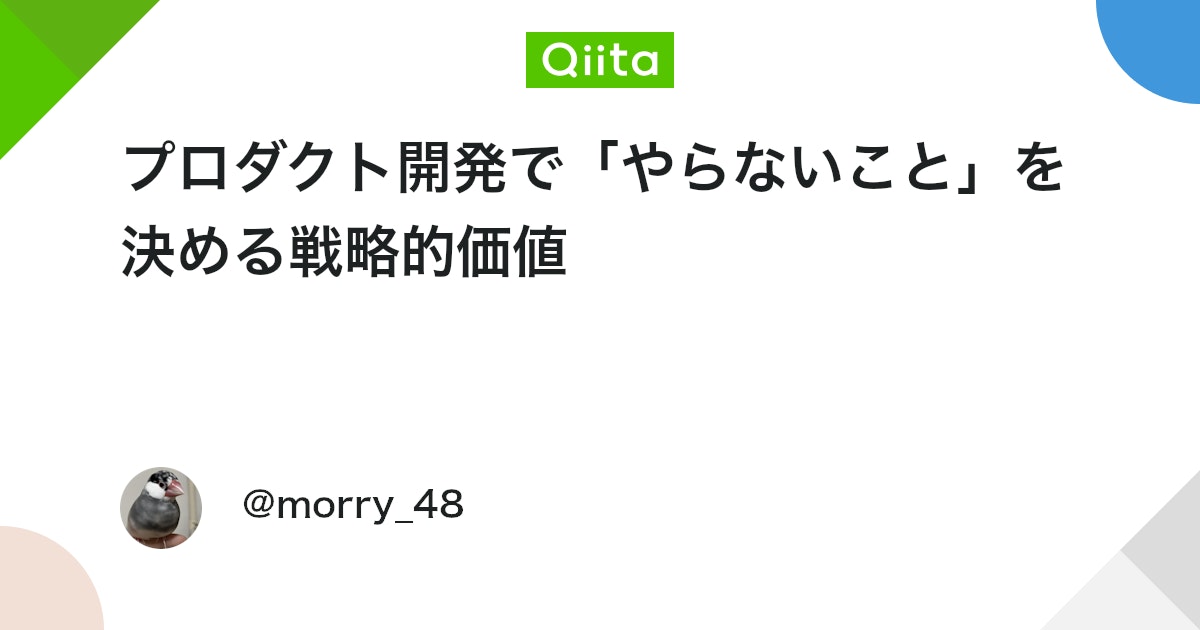
どうも。鳩胸になりたい文鳥です。
プロダト開発していると、「あれもこれも機能を追加したい」ってなりがちですわね。
たまに機能を増やすことが本当にプロダクトの競争力に繋がるのか?みたいなことを考えることがあります。
今回は、あえて機能を絞ることで競争優位性を築く戦略についても考えてみたいと思います。
機能を増やすことのメリットはわかりやすいと思うので書かないですが、機能を増やすことを否定しているわけではないので悪しからず。
包丁で考えるプロダクト戦略
「ものを切るためのツール」として包丁をリリースしたとします。
営業先の病院で「メスのような精密さが欲しい」というフィードバックをもらい、工務店では「ノコギリのような力強さが欲しい」という要望をもらったとしましょう。
このときに、「潜在顧客の全ての用途に応えよう!」と考えて、先端にノコギリの要素を、根本にメスの要素を組み込んだマルチ包丁を作ったとして、需要は果たしてあるだろうか。
包丁でこんなことする人はいませんが、プロダクト開発だとこういうことは結構起きてるとおもうんですよね。
十徳ナイフの市場規模
「じゃあ十徳ナイフを作ろう!」ってなったところで、十徳ナイフの市場が包丁よりも小さいのは想像できるでしょう。
十徳ナイフにする開発コストを「よく切れる包丁」にするためのコストに割いていた方が成功する可能性が高いかも知れないですよね。
多くのユーザーのニーズに答えるために機能を増やしたつもりでも、「質の悪い十徳ナイフ」では誰にも相手にされないのは確かでしょう。
器用になんでもできるというのは、実はどれも微妙ということになってるかも知れないです。
市場で選ばれる製品の条件
以下のうち、どれが一番売れると思いますか?(本数・売上の観点)
- 世界一切れ味の良い高級包丁
- そこそこ切れるコスパのいい包丁
- 世界一質のいい高級十徳ナイフ
- そこそこ切れるコスパのいい十徳ナイフ
私は「そこそこ切れるコスパのいい包丁」が一番売れると思います。
市場で選ばれるかどうかは品質と値段のバランスが重要で、品質を最高レベルにしている製品は大体主力製品にはなりません。Macの最上位モデルよりもMacBook Airの方が売れるし、市場でのインパクトも強いのと同じですね。
総合フィットネスジムの苦戦
フィットネスカオスマップによると、日本のフィットネス人口は増えているにも関わらず、総合フィットネスジムの会員数は横ばいか微減だそうです。
一方で、会員数を伸ばしているジムを見てみると:
エニタイム:
- 中級者以上に人気の本格的なマシンを揃える
- ウェイトトレーニングに特化(スタジオやプールなし)
チョコザップ:
- 初心者に特化
- 圧倒的な安さ
サブ的機能削減による競争力創出
ここで重要なのは、総合フィットネスジムは機能的にはエニタイムやチョコザップの機能を内包しているということです。でも、新興のファストジム系はコアバリューにフォーカスして原価を抑える(維持費の高いプールやスタジオを置かない)ことで競争力を生み出しているんです。
最近都内で店舗数が増えているFIT PLACE24は、エニタイムのようなジム設備を持ちながらエニタイムよりも安い価格を実現しています。その理由はシャワーがないこと。
シャワーを持つことで工事費や保健所の申請など手のかかることが多くなりますが、ファストジムの利用者でシャワーを使う人は少ないというデータがあるので、思い切ってそのシャワー設備を削った分を利用者に料金として還元しているそうです。
戦略的な「やらないこと」の決定
もしエニタイムが施設見学の要望をもとに「うちにもプールが欲しいというお客さんはいる」ということでプールを持つ意思決定をしていたら今ほど大きくならなかったでしょうし、フィットプレイスがシャワーを持ってしまったら今の価格でサービスを提供することはできないでしょう。
「このユーザーは我々のターゲットではない」ということを戦略的に明確にできているからこそ競争力を持っているのです。
格安航空しかり、格安SIM然り、格安ジム然りですが、先発サービスのコアバリューを維持したまま周辺の維持コストがかかる部分をそぎ落として、価格還元することは大きな競争力を持つこともあるのです。
それはハードを伴う施設やサービスであってウェブサービスは機能が豊富な方がいいに決まってるだろと思う人もいるかも知れません。
でも、ウェブサービスでも同じような問題は起きるんです。その代表例がEvernoteの5%問題です。
多機能化が招いたかもしれない迷走
2012年に企業評価額10億ドルと評価されたEvernoteは、メモ、データストック、リマインダー、共同作業など非常に多機能なノートアプリでした。しかし、その多機能さが逆に足を引っ張ることになったそうです。
当時のCEOであったPhil Libin氏は、ユーザーから「私はEvernoteを長年使用してきて、とても愛しています。でも、私は最近になってEvernoteで出来ることのほんの5%しか使っていなかったことに気付いたんです」と言われたことを明かしています。
使ったことある人はわかるかも知れないですが、確かにいろんな機能はあるがどれもちょっと痒いところに手が届かないプロダクトという印象が私もあります。
5%問題の本質
Libin氏自身もこの問題を理解しており、「問題は、この5%がユーザーによって異なることです。もし、すべてのユーザーが同じ5%の機能を使用している場合、他の95%の機能をカットしてしまえば開発にかかる多くの資金を大幅にカットできます」と語っています。
結局抜本的な解決には至らず、技術的負債の問題なども重なり、2015年にLibin氏はCEOを辞職、職員の18%をカットすることになりました。
今ではNotionに地位を奪われた企業という印象
機能開発の見えにくいたコスト
システムに置き換えて考えたときも同じことが言えます。機能を開発するときに、田舎の限界集落に高速道路を整備するような施策になっていないか考える必要があります。
中途半端に使われている機能を持つことは:
- ライブラリ導入・廃止時の制約
- バージョンアップの障害
- 継続的な維持コスト
- ユーザーの学習コスト増加
- サポートコストの増大
Webサービスの市場が成熟しつつある今、機能の開発工数だけでなく、企画時に運用負荷やインフラコストまで考えないと勝てない世界線になっています。
エンジニアが事業戦略を理解する必要性
以前の記事でも書きましたが、経営者や企画者は運用コストを正確に測れないことが多いです。そういう意味でも、エンジニアが事業理解してバランスの良い提案・ソリューションを提供できることが今後大事になってくるのではないかと思います。ずっと前からそうやという声が聞こえてくる気はしますが
AIによって開発速度は上がるが機能開発によってユーザーの混乱を招いたりオペレーターコストを増やすかもしれないです。
AI自体をプロダクトに組み込む開発なんかは特に顕著で、割とすぐに思いつくし「80%大丈夫そう!」まではすぐいきます。でも製品レベルに持っていくには、APIの利用料なども含めて利益が残る状態でないとビジネスとして成り立ちません。
戦略的な機能削減の価値
- コスト削減による価格競争力:不要な機能を削ることで運用コストを下げ、価格優位性を築く
- ターゲットの明確化:「誰のためのプロダクトか」を明確にすることで、コアユーザーの満足度を最大化
- 開発リソースの集中:限られたリソースをコア機能の改善に集中投下
- ユーザビリティの向上:機能を絞ることで、ユーザーが迷わずに使える直感的なプロダクトを実現
- オペレーションの簡素化
エンジニアの役割
- 機能追加の技術的コストと運用負荷を正確に見積もる
- 事業戦略を理解した上で、技術的な制約や可能性を伝える
- 「作れるから作る」ではなく「作るべきかどうか」を判断する
最後に
「安易に全部やる」と決定を下すのは一番簡単です。というかこれは何も決めてないに等しいです。
でも競争力を持つためには優先順位・やらないことを決めて、それが事業全体で共通認識として持てていることが強いんだろうなと思います。
ハードウェアを伴う施設でもウェブサービスでも、根本的には同じだと思います。自分たちの存在価値はなんなのかを常に問い続けてフィードバックをもとにサービスを改善し続けることが大切だと思います。
以上
Views: 0