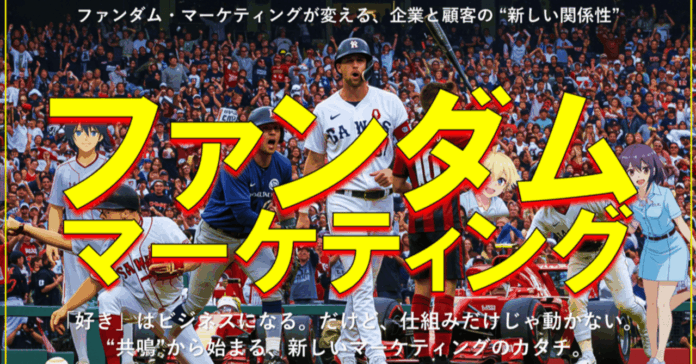🧠 概要:
概要
「ファンダムマーケティング」は、消費者の心を「愛される」形でつかむ新しいマーケティングアプローチを提唱しています。この考え方は「共鳴」や「共感」を基盤にし、単なる物販や広告から脱却して、ファンとの深い関係性を築くことが重視されています。本書では、その基本概念や方法論、注意点を解説しています。
要約(箇条書き)
-
ファンダムマーケティングの理念:
- 「好き」をビジネスに変える新しい方法論。
- 共感や誇りがマーケティングの核となる。
-
現代の消費者の変化:
- 企業の売りたいものよりも、「共感できるか」で判断。
- 「愛され続ける」ことが重要。
-
ファンダムの定義:
- 熱狂的で持続的な支持の集合体。
- 参加意識が強く、文化や価値観を共有。
-
ファンダムマーケティングの基本モデル:
- 認識、関与、行動変換を三つのポイントに設定。
- 共感の設計: ストーリーや価値観を届ける。
- 関与の強化: ファンを参加させる仕掛け作り。
- 行動の転換: 感情を購買や拡散に変える。
- 認識、関与、行動変換を三つのポイントに設定。
-
ファンダムの現実:
- 万能ではなく、トラブルやリスクも存在。
- ファンダムは細分化され、一枚岩ではない。
-
ファンダムを育てるための覚悟:
- ガイドラインや長期的なビジョンが必要。
- 短期的な利益追求よりも共創関係の構築が重要。
- 経営資産としてのファンダム:
- 強力な顧客基盤として活用し、愛され続けるブランド価値を高める。
- ファンダムマーケティングは企業の戦略的な軸となる。
本書では、実際の成功事例や失敗事例も紹介されており、ファンダムマーケティングの実用性と重要性を強調しています。
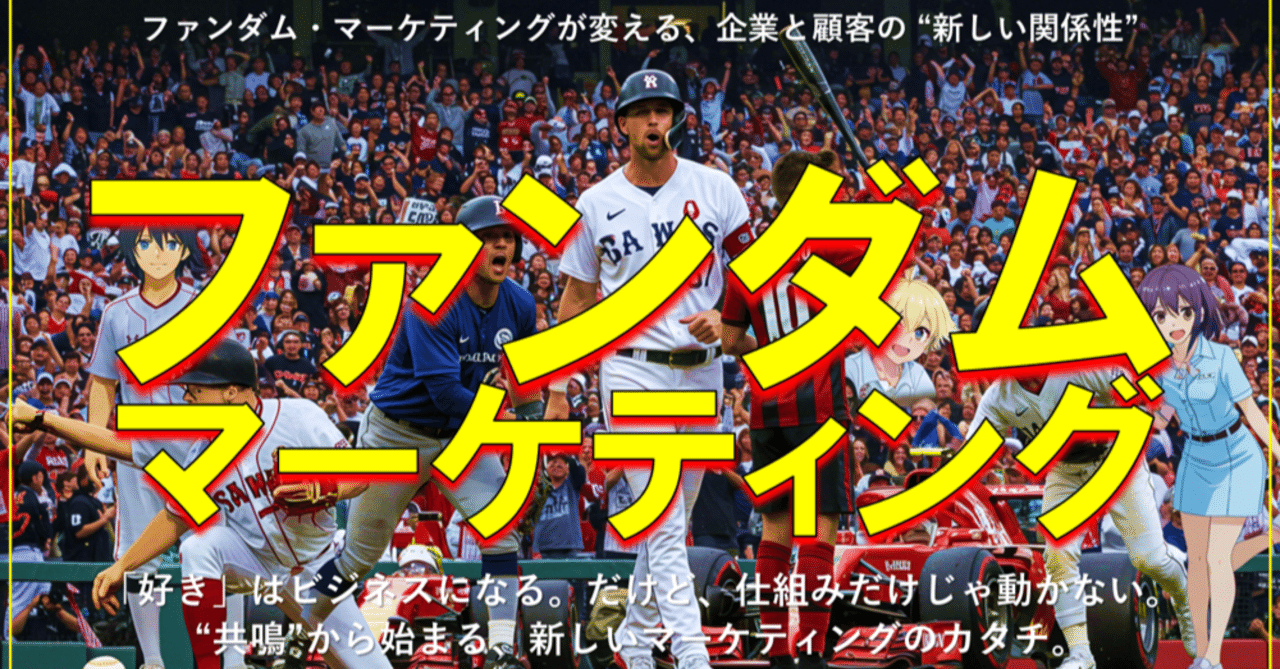
「好き」はビジネスになる。だけど、仕組みだけじゃ動かない。
“共鳴”から始まる、新しいマーケティングのカタチ。
プロローグ:
「熱量」が、数字を超えるとき─マーケティングの次なる挑戦へマーケティングに「答え」がありそうだった時代は、もう終わりつつあります。広告を出せば商品が売れる、キャンペーンを打てば人が集まる。そんな「計算可能な反応」は、もはや過去の話。今、私たちが向き合っているのは、「好き」や「共感」や「誇り」。言葉にならない熱量に突き動かされて、ファンたちは動き、支え合い、拡張し続けています。この書は、そんな“ファンダム”の力を、マーケティングの文脈で活かそうとするあなたのためのものです。ファンダムマーケティングは、簡単ではありません。手間も、時間もかかるし、数字に現れるまでには忍耐がいります。社内の理解も得にくく、他部署との調整も多いでしょう。そして何より、上司や役員が「短期の成果」しか見ていないと、進まなくなることだってある。でも、あなたが本気でこの“ファンダム”の力に可能性を感じているなら、それは間違っていません。
なぜなら、“ファンダム”は企業の“本質”に触れる唯一の領域だからです。
企業が誰のために、なぜ存在するのか。その答えが、ファンとの対話の中に隠れています。本書が、あなたの背中を押す“設計図”であり、
あなたの挑戦を支える“味方”であることを、願っています。
第1章:ファンダムマーケティングとは何か?
~「売れる」より「愛される」が勝つ時代に~
1-1. 「推されるブランド(企業/商品/サービス)」こそが選ばれる情報も商品もサービスも、今の時代は溢れかえっています。似たような製品、同じような価格帯、類似したコンセプト。かつては品質の差、スペックの違い、広告の規模が勝敗を分けましたが、今やそうした“合理性”だけでは、人の心を動かせなくなってきました。
現代の消費者は、もはや“便利だから”“価格が安いから”と「買う理由」を探しているのではなく、**「共感できるかどうか」「好きと言えるかどうか」**で判断しています。
企業が売りたいものではなく、「自分が応援したいもの」や「自分の価値観を表現できるもの」にこそ人は惹かれる。
つまり、今の時代のマーケティングが目指すべきは「売れ続ける」ではなく「愛され続ける」にはどうしたらいいか、へと変わりつつあるということです。
そして、その答えのカギを握るのが「ファンダムマーケティング」なのです。
1-2. ファンダムとは「熱狂」と「共創」の経済圏
「ファンダム(fandom)」とは、「ファン(fan)」と「王国(kingdom)」を組み合わせた言葉。
単なる“好き”を超えた、熱狂的で持続的な支持の集合体を指します。
集合体といっても、単なる集合体でもなく、もっと深く、もっと濃く、もっと感情的なつながりがある…。
それはまるで、一つの国や文化圏のような存在なのです。
構成要素 具体例 世界観 物語、キャラクター、チーム、理念行動様式 推し活、SNS拡散、課金、グッズ購入など言語 スラング、特有のハッシュタグ、内輪ネタ
儀式 ライブ参戦、配信視聴、現地巡礼、ガチャ回し
そして、こうしたファンダムに共通するのは、
“自分も一員である”という参加意識です。
▶ 図解:ファンダム構造モデル[中核層] … コアな熱狂ファン(定期的に課金・イベント参加)↓↑[準コア層] … 習慣的ファン(SNSで拡散、ライト課金)↓↑[周辺層] … 一般ファン・潜在層(関心はあるが未アクション)
ファンダムマーケティングではこの中核層に近い層ほどLTV(顧客生涯価値)が高いのが特徴
企業がマーケティングで意識すべきなのは、この中核〜準コア層をどうつかまえ、熱量を維持しながら拡散や収益につなげていくのか、という点です。
1-3. ファンダムマーケティングの基本モデルファンダムマーケティングは、ファンの熱量を最大化し、その熱量を売上・プロモーション・ブランド価値に変えていく仕組みです。
以下の基本3つのポイントを意識することで、ファンダムの力を引き出すことができます。
① 共感の設計(ストーリーと価値観を届ける)消費者は、ブランド(企業/商品/サービス)の人格や価値観に共感して動きます。ロジックではなくストーリーで伝えることが、第一の入口です。ただ、モノやサービスを紹介するのではなく、“価値観”や“ストーリー”に共感してもらう。
(例)「このチームを応援することが、地元の活性化につながる。」
② 関与の強化(参加させる・語らせる)ファンが関われる仕掛け(投票、SNS参加型キャンペーン、二次創作など)を作ることで、愛着と参加意識を育てる。ファンが“自分も物語の一部”として関われる場をつくる。
(例)ファンが投降した応援イラストを公式が紹介する
③ 行動の転換(感情を、購買・拡散に変える)熱量の高まったファンに、行動への橋渡しをする設計。
購入だけでなく、シェアやイベント参加などのアクションへと誘導する。
1-4. 「光」だけではないファンダムの現実ここまで聞くと、「ファンダムってすごい!魔法の杖かも?」と思うかもしれません。でも、実際はそう簡単ではありません。
ファンダムは“万能ではない”。
むしろ、扱いを間違えると企業にとって大きなリスクにもなり得ます。
例えば、以下のような課題があります。
-
ファンダムは細分化されており、”一枚岩ではない”
-
極めて繊細で、裏切りに敏感
-
熱量の高さゆえに、企業活動に強い監視・干渉が入る
-
一見盛り上がっていても、マネタイズできないことがある
つまり、ファンダムは“熱量”という強力なエンジンを持つ反面、「制御不能」にもなり得るという両側面があるのです。
1-5. ファンダムは無数の支流であるかつてのマス市場は「大河」のように、みんなが同じ流れに乗っていました。
しかし、今のファンダムは、「無数の細い支流」の集まりです。
特性 説明高度に細分化 マニアックな趣味・価値観ごとのクラスターが存在専門性が高い 一般人にはわかりづらい“文脈”や“文化”がある
大きさ≠収益性 規模が大きくても、マネタイズできるとは限らない
・大規模なファンダムでも「コンテンツは好きだが、課金しない。」層が中心の場合、売上にはつながらない
・一方で、小規模でも「命を削ってでも推す」熱狂層がいれば、収益は大きい
「熱狂の質」こそが、ファンダムの価値を決めているのです。
1-6. ファンダム活用は“覚悟と設計”が試される
ファンダムを活用したい企業が陥りやすいのが、「単に、人気IPを使えばうまくいくだろう」という誤解です。
しかし実際には、以下のような現実が待っています。
-
IP活用にはライセンス料や監修コストがかかる
-
短期的に見てしまうと、利益が出にくい(初期投資が大きい)
-
企業とファンダムの文化がミスマッチだと炎上リスクがある
つまり、ファンダムマーケティングには **「目先の売上より、長期的な共創関係をどう築くか」**という設計思想が必要不可欠なのです。
1-7. まとめ:「ファンダム」は“育てる経営資産”であるファンダムは、企業にとって新しい「顧客基盤」であり、それ自体が企業のブランド価値を押し上げる力を持っています。ただし、それは“買える”ものではなく、“築く”ものです。
本質は、**「熱狂を理解し、共感を生む関係をどうデザインするか」**にあります。
「ファン」という資産をいかに育て、いかに味方につけるか。ファンダムマーケティングとは、ただのトレンドではなく、
**企業がこれから生き残っていくための“戦略の軸”**となる存在なのです。
次章では、実際にファンダムがどのようにビジネスを動かし、どんな成功と失敗があるのか、国内外の事例を紐解いていきます。
Views: 0