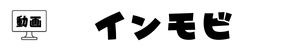🧠 概要:
概要
この記事では、AIを用いた画像生成と短編小説執筆の実験として、「ファスナーアニマル」というテーマが紹介されています。このテーマは、不条理で哲学的な発想から生まれたもので、動物たちの背中にファスナーがついているユニークなアイデアが展開されています。また、AIによる生成物を通じて、作品を楽しむための体験が強調されています。
要約
- ChatGPT-4.1の一般公開についての記述。
- AIのコーディング以外の用途として、画像生成と短編小説の試みを紹介。
- 「ファスナーアニマル」というテーマは、動物の背中にファスナーがついているという発想から生まれた。
- 技術的な比較ではなく、純粋に作品を楽しむためにAIを利用。
- 短編小説「ファスナーの森」では、動物たちがファスナーを持つ謎の森が描かれ、主人公はその森での不思議な体験をする。
- 物語の終わりで、主人公は自分の背中にもファスナーがあるのではないかと疑念を抱く。

今日、ChatGPT-4.1のAPI版ではないバージョンが一般公開されました。
本来はコーディング用途が推奨されていますが、せっかくなので“お試し”として、画像生成や短編小説の執筆に使ってみました。
今回ご紹介する「ファスナーアニマル」というテーマは、
動物たちの背中にファスナーがついている――という、ちょっと不条理で哲学的な発想から生まれたものです。
ベンチマークや技術的な比較が目的ではなく、純粋に作品を楽しむために利用しています。
↑この文章がChatGPT-4.1作。
マンガ

画像
以下は生成そのまま。


WEBアプリ
以下も生成そのまま。

小説
以下も生成そのまま。
ファスナーの森
土曜の午後、僕は近所の公園の裏手にある小さな森へと迷い込んだ。何度も来ているはずなのに、今日はなぜか見知らぬ獣道が現れていた。淡い光が降り注ぐその道を進むうちに、足元の落ち葉の感触も、木々のささやきも、普段とは少し違うものに思えた。
しばらく歩くと、開けた場所に出た。そこには猫、犬、狐、クマ、ペンギン……見慣れたようでどこか異質な動物たちが、まるで円を描くように背中を向けて座っていた。彼らの背中には、共通して大きな銀色のファスナーがまっすぐ縦に走っている。猫はふわふわの縞模様、犬はベージュの短毛、狐は炎のような赤茶色、クマはずっしりした茶色、ペンギンはつややかな黒白。だが、どの背中にも違和感があった。
僕は声をかけた。「こんにちは。君たち、どうしてそんなふうに並んでるの?」
猫が振り向きそうに見えたが、結局誰も顔を見せなかった。ただ静かに、柔らかく、森の空気だけが揺れた。動物たちは何も答えない。ただ、そこに在ることを許されているような、不思議な安心感と、ほんの少しの不安が入り混じる。
僕はぐるりと円の外側を回ってみた。どの動物もじっと前を向き、背中のファスナーはしっかりと閉じている。「これは着ぐるみなのかな、それとも……?」好奇心がざわめく。
そのとき、森の奥からどこか懐かしい声が聞こえた。 ――ファスナーは、開けてはいけないよ。
振り返っても、誰の姿も見えなかった。警告のようなその声が、胸の奥にひっかかる。だが、それでも僕の手は、猫のファスナーにそっと伸びていた。
ファスナーの金具に触れた瞬間、ぞくりと背筋が震えた。なぜか「開けてはいけない」と分かっていたのに、指が勝手に動いてしまう。カチリ、と小さな音がして、ファスナーがわずかに開いた。
途端に、眩しい光が溢れ出す。白とも金ともつかないその輝きに、僕は目を覆った。だが、まぶしさの向こうに、なにか“みてはいけないもの”が、こちらをじっと見返している――そんな確信と、得体の知れない罪悪感が、僕を圧倒した。
気がつくと、僕はベッドの上で目を覚ましていた。カーテンの隙間から夕陽が射し込み、鳥の声が遠くで聞こえる。心臓がまだドクドクと早鐘を打っている。夢だったのだろうか。それとも……。
だが、あの森の光景も、背中のファスナーも、手の感触も、あまりにも生々しい。夢で片付けるには、身体に残る違和感が大きすぎた。胸の奥には、開けてしまったことへの強い罪悪感が残っている。
不安に駆られた僕は、ふと鏡の前に立った。自分の背中をねじるようにして見ようとするが、うまく見えない。もしかして、自分の背中にも……?そんな妄想が頭をよぎる。
「お母さん、ちょっと……僕の背中、ファスナーとか、なんか変なのついてない?」
母は、台所から顔を出してきた。僕の突然の問いに少し驚いた様子で、近づいて背中をのぞく。そして、ほんの少し、ためらうように間を置いた。
「……あるわけないでしょ。なに言ってるの、もう」
母の声はいつもより静かだった。その言葉にほっとして、「そうだよな」と僕は笑った。 だが、ふと気になって振り向いたとき、母の手は僕の背中のあたりに伸びていた。まるで、そこにあるはずのファスナーを、静かに開けようとするかのように。
僕は、思わず身を引いた。母の手は、空中で宙ぶらりんになったまま、少し寂しそうに震えていた。
そして今も、ときどき鏡を見るたび、自分の背中に――本当は何が隠されているのか、考えずにはいられない。
Views: 0