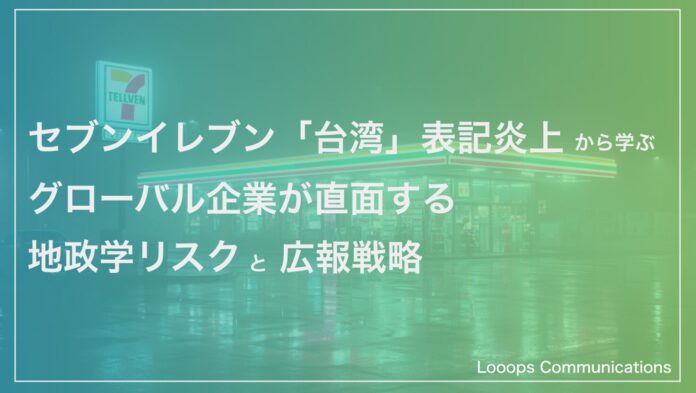2025年7月、大手コンビニエンスストアチェーンであるセブン&アイ・ホールディングス(以下、セブン&アイHD)の公式SNS投稿が「中国(台湾)」という表記を巡り、大きな炎上を招きました。この問題は、グローバルにビジネスを展開する企業が直面しやすい「地政学的な陥穽(かんせい)」であり、企業がブランドイメージや顧客からの信頼を維持するために、どのような広報戦略とリスク管理が必要かを浮き彫りにしています。
今回の事例は、広報担当者や炎上リスク管理に携わる方々にとって、貴重な教訓となるでしょう。
セブン-イレブンの「中国(台湾)」表記に批判 セブン&アイHDが謝罪 | TBS NEWS DIG
概要:事実の時系列整理
今回の炎上は、以下の時系列で展開しました。
- 2025年7月11日: セブン&アイHDは「セブン‐イレブンの日」に合わせ、公式X(旧Twitter)アカウントで「世界のセブン‐イレブンのユニフォーム」を紹介する画像を投稿しました。
- 問題の表記: この投稿において、台湾のユニフォームが「中国(台湾)」と表記されていたことが問題となりました。他の中国の地域は「中国(広東)」「中国(広州)」「中国(香港)」と表記されていました。一方で、「アメリカ合衆国」と「ハワイ」はそれぞれ別のユニフォームとして紹介されていました。
- 炎上発生: 投稿直後から、台湾の人々や台湾に寄り添う日本人ユーザーから「台湾は中国の一部ではない」「配慮に欠ける」といった批判が殺到しました。中には「不買運動」を呼びかける投稿も見られました。
- 2025年7月12日: セブン&アイHDは批判を受け、公式Xで謝罪文を発表し、問題の投稿を削除しました。しかし、この謝罪では事態が沈静化せず、むしろ「火に油を注ぐ」結果となりました。
- 2025年7月13日以降: 在日台湾人団体「美麗島人会」が正式な抗議文を提出し、謝罪文に「台湾」の表現が含まれていないことや、過去に「台湾フェア」などで「台湾」の名称を使用していたこととの矛盾を指摘しました。神戸市会議員の上畠寛弘氏も、企業の対応を「極めて無礼」「最低の広報対応」と強く非難しました。
セブンイレブンさんの台湾に対する見解はこちら https://t.co/n4G8JmHPJO pic.twitter.com/vU5qDFGMUM
— 台湾史.jp (@Formosanhistory) July 11, 2025
リスク兆候:炎上前後の兆候をどう検知できたか
今回の炎上において、直接的な炎上前の兆候が明記されているわけではありませんが、複数のソースから内部リスクの可能性が示唆されています。
社内での表記の常用
SNS上の指摘によると、今回の投稿だけでなく、セブン&アイグループ内で「中国(台湾)」という分類が常用されていた可能性があります。実際に、同社が公表している事業説明資料「コーポレートアウトライン2023年度版」にもこの表記が確認されています。これは、SNS担当部署だけでなく、全社的・全グループ的に特定の表記が使用されていたことを示唆しており、「氷山の一角」であった可能性が高いです。
事前のチェック体制の不備
識者は、各国の情勢や政治的な内容を含むチェックリストの共有、および日本国内のウェブ担当者と中国・台湾・香港等の担当者間の連携が不足していた可能性を指摘しています。もしこれらの連携とチェックが適切に行われていれば、投稿前のリスクを予見できたかもしれません。
炎上原因:ユーザーの怒りのポイント
今回の炎上の主な原因は、「中国(台湾)」という表記が、台湾の主権やアイデンティティに関わる非常にデリケートな問題に触れたことにあります。
台湾側の視点
- 台湾は1949年以降、実質的に独立した国家として独自の政治体制、選挙制度、軍隊、パスポートなどを有しています。
- そのため、「中国の一部」として表記されることは、自らのアイデンティティや主権の否定と受け止められ、強い反発を招きました。
- 台湾の人々からは「セブンイレブンは私たちの存在を否定しているのか」「中国向けの忖度が過ぎる」「もう利用しない」といった声が上がりました。
日本国内の批判
- 台湾に寄り添う日本人ユーザーからも批判が寄せられました。特に、アメリカのハワイは「アメリカ(ハワイ)」と表記されず個別に扱われているのに、台湾が「中国(台湾)」とされたことへの矛盾が指摘されました。
- また、セブン-イレブンが過去に「台湾ラーメン」や「台湾スイーツ」などの商品で「台湾」という名称を商業的に積極的に利用していたにもかかわらず、今回の件で「中国(台湾)」と表記したことへの批判もありました。
中国側の視点と謝罪への不満
- 一方で、中国政府は「一つの中国」原則を掲げ、台湾を自国の一部と主張しています。この立場からすれば、「中国(台湾)」という表記は「当然のこと」と見なされます。
- そのため、セブン&アイHDの謝罪に対しては、中国側の一部ユーザーから「なぜ謝る必要があるのか?」「中国に配慮した企業が、圧力に屈した」といった不満の声も上がりました。
企業の対応:実施内容と反応
セブン&アイHDは炎上を受けて、迅速にXの投稿を削除し、謝罪文を発表しました。
謝罪文の概要
謝罪文は「配慮に欠けるものであった」「ご不快な思いをされたすべての皆様に心よりお詫び申し上げます」「この度の反省を踏まえ、今後はよりいっそうの配慮のもと投稿を行ってまいります」といった抽象的な表現で構成されていました。具体的な国や地域名には言及せず、問題となった表記が何であったかや、その根拠については触れられませんでした。
【当社の公式SNS投稿に関するお詫び】
当社の公式SNSアカウントにおいて本年7月11日に投稿いたしました「世界のセブン‐イレブンのユニフォーム」の画像に記載された一部の国・地域の名称における表記につきまして、多くのご意見をいただいております。…
— セブン&アイ・ホールディングス【公式】 (@7andi_jp_pr) July 12, 2025
謝罪への反応
この謝罪文は、結果として「火に油を注ぐ」状態となりました。以下のような批判が集まりました:
- 「配慮」の問題ではなく「誤表記」だったのではないか、という指摘
- 「修正版を再ポストしないのか」という疑問の声
- 謝罪文が「具体性に欠ける」点への厳しい批判
- 投稿のどの部分が問題で、誰に対して配慮が足りなかったのかが明示されていない
- 問題の本質に向き合っていない印象を与えた
「ご不快な思いをされたすべての皆様」という表現は、国際問題において対象を曖昧にし、客観的な評価を避けているように見えました。政治的・歴史的に触れづらい問題では、対象を切り分けて寄り添う内容にするべきだったとの指摘があります。
また、「どういった意図で『中国(台湾)』の表現を用いたのか」という原因の説明がないため、消費者からの納得感が得られませんでした。これにより、「ただ形式上の謝罪を行っただけだ」「誠意がない」と見なされ、謝罪がむしろイメージダウンにつながりました。
SNSの反応:感情のトーンや拡散ルート
セブン&アイHDの投稿は、SNSを中心に瞬く間に拡散され、特に台湾と日本のユーザーから強い感情的な反応を引き起こしました。
感情のトーン
- 台湾の反応: 多くの市民が「怒り」と「失望」を表明し、「長年日本ブランドを信頼していたのに裏切られた」「二度と買わない」といった不買運動を呼びかける声も上がりました。
- 日本の反応: 台湾に共感する日本人ユーザーからは、「失礼すぎる」「気持ち悪い」といった否定的な意見が見られました。
- 中国の反応: 一方、中国本土のネットユーザーからは「当然の表記」「国際標準」とする意見が主流でしたが、謝罪文発表後は「なぜ謝罪するのか」という不満も一部で見られました。
拡散ルート
問題の投稿は、セブン&アイHDの公式Xから発信され、その後、台湾のネットユーザーや日本のSNS(Threadsなど)を通じて広範囲に拡散されました。台湾メディアもこの問題を大きく報じました。
教訓:他社が学ぶべきポイント+未然防止策
今回のセブン-イレブン炎上から、グローバル企業が学ぶべき重要な教訓と未然防止策は以下の通りです。
地政学的リスクの深い理解と認識
地名や国名の表記は、単なる言葉の問題ではなく、その地域のアイデンティティや主権に直結する非常にセンシティブな問題であることを深く認識する必要があります。特に中国・台湾問題のように、政治的に「正解のない」グレーゾーンでは、表現の一つひとつに細心の注意が求められます。
社内における情報共有と連携体制の強化
- 各国・地域の政治情勢や歴史的背景をリサーチし、これらを反映した国際感覚のある編集チェック体制を社内に設けることが不可欠です。
- 日本国内の広報・ウェブ担当者と、中国・台湾・香港など現地に駐在する担当者やリーガル部門との密な連携と情報共有を徹底すべきです。
- 現地では当然とされる表現が、他の地域で問題になるケースがあるため、グローバル基準とローカル事情をすり合わせた「折衷表現」を検討する必要があります。
トップ主導の明確なポリシー策定
表記の統一や、どのような表現を用いるかというグローバルポリシーは、経営トップの判断によって明確に規定されるべきです。後手後手の対応は、さらなる批判を招くため、トップからの明確な社内向けメッセージが重要となります。
謝罪の際の具体性と透明性
- 謝罪文は、「誰に対して、何を、どのような理由で謝罪しているか」を具体的に明示することが重要です。抽象的な表現は、問題の本質に向き合っていないと見なされ、かえって不信感を招きます。
- 消費者が知りたい「なぜその表現を用いたのか」という理由も、可能な範囲で伝えることで納得感を得られます。
企業文化と国民性の誤認防止
グローバルに活動する日本企業は、その言動が「日本人の国民性の表れ」と誤解される可能性があることを肝に銘じる必要があります。一連の対応が、その国の態度と見なされかねないという自覚を持つべきです。
「触れない」という選択肢も検討
政治的に敏感なテーマにおいては、あえて国名を出さずに「地域ごとの特徴」や「文化の違い」に焦点を当てることで、安全かつ内容豊かなコミュニケーションが可能になる場合があります。例えば、日本の航空会社が中国政府の指示に対し「東アジア」という表現で「お茶を濁した」事例もあります。
類似事例との比較
今回のセブン-イレブンと同様に、台湾の表記を巡って炎上した事例は少なくありません。
主要な類似事例
- 航空会社(2018年): 中国政府は各国の航空会社に台湾の記述を「Taiwan, China」に変更するよう指示しました。日本の航空会社は、台湾と中国、韓国をまとめて「東アジア」と表現することで、戦略的に曖昧な対応を取り、大きな制裁や不買運動を避けました。
- 良品計画: 「原産国:台湾」と表記した商品に対し、上海当局から罰金を課されました。同社はすぐに修正し、中国政府の姿勢に沿ったコメントを出しました。
- アシックス: ECサイトの国選択ドロップダウンで「香港」「台湾」を中国と別の独立した国として明記したことで、中国のネットユーザーから大きな非難を受けました。
業界横断的な課題
これらの事例は、国際ビジネスにおいて地名や国名の表記がどれほど政治的な影響力を持つかを示しており、企業はどちらの顧客も大切にするために「高度な曖昧戦略」や「二枚舌戦略」を取らざるを得ない現状を浮き彫りにしています。
まとめ:行動につなげる振り返り
今回のセブン-イレブンの炎上は、グローバル企業が直面する地政学的問題の複雑さを改めて認識させるものです。収益と利益を最大化するためには、時に「正しさ」を一旦脇に置き、双方の顧客を大切にする「高度な曖昧戦略」や「二枚舌戦略」が必要となることもあります。しかし、それは同時に「裏切り者」と指をさされるリスクや、世論からの不信感を招くコストを伴います。
炎上リスク担当者が今後活かすべき点
- 「たかが表記」ではなく「されど表記」: 小さな表現一つが、企業の信用を揺るがす重大な問題に発展し得ることを忘れてはなりません。
- トップダウンでの明確なポリシー策定と部門間の連携強化: グローバル展開における表記ルールを明確にし、関連部署間での徹底した情報共有とチェック体制を構築することこそが、未然防止の鍵です。
- 透明性のある説明と誠実な対応: 万が一炎上が発生した際には、「なぜその表現を用いたのか」「今後どう見直すのか」を具体的に説明し、問題の本質に向き合う姿勢を示すことが、信頼回復への第一歩となります。
- 「全員から賛同されないが、この路線で行こう」という決断: 政治的に複雑な問題においては、すべてのステークホルダーを完全に満足させることは困難です。企業としては、リスクと収益を考慮し、時には批判を受けることを覚悟した上での、明確な判断と姿勢が求められるでしょう。
今回の事例は、グローバル化が進む現代社会において、企業が「どのような価値観を持ち、誰に対して敬意を示しているか」が厳しく問われる時代に入ったことを示しています。
The post セブンイレブン「台湾」表記炎上から学ぶ:グローバル企業が直面する地政学リスクと広報戦略 first appeared on in the looop | Looops communications.
https://platform.twitter.com/widgets.js
続きをみる
🧠 編集部の感想:
今回のセブンイレブンの「台湾」表記炎上は、地政学的な sensitivities を無視した結果だと思います。企業はグローバルな視点を持ち、国や地域のアイデンティティを尊重するべきです。また、透明性のある謝罪と具体的な表現が信頼の回復に重要だと実感しました。
Views: 0