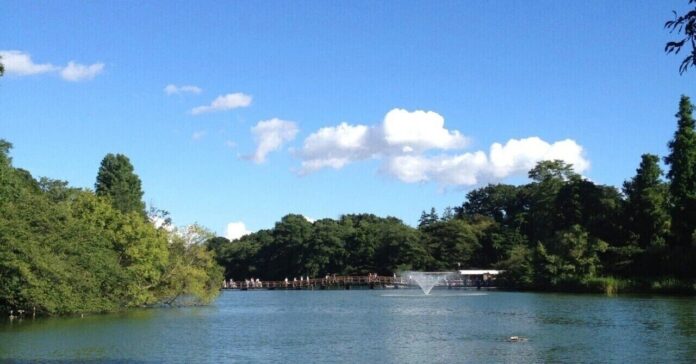🧠 概要:
概要
「グレイナーの企業成長モデル」は、企業が成長する過程で直面する「危機」に焦点を当てた理論で、多段階の成長ステージが存在することを説明しています。著者は、自身の経験をもとに、各フェーズの特性や課題、そして成長に求められる要素を掘り下げています。成長は必ずしも直線的ではなく、危機を乗り越えることが重要であるとされています。
要約(箇条書き)
- 企業成長の非直線性: 成長には必ず危機が訪れ、その背景を理解する重要性。
- グレイナーの企業成長モデル: 企業成長の課題を地図として示すフレームワーク。
- 成長フェーズと危機:
- リーダーシップの危機: 創業者の限界と組織化の必要性。
- 自律性の危機: 階層化により現場の自由が奪われる。
- 統合の危機: 分権化による全体のバラバラ化。
- 官僚制の危機: 制度の重さがスピードを落とす。
- 内部成長限界の危機: 内部資源の限界と外部との連携が必要。
- アイデンティティの危機: 外部連携で文化や価値観が揺らぐ。
- 企業成長の旅: 単なる拡大ではなく、危機を乗り越える経験の連続。
- 成長の地図: 現在地を理解し、次に起こることを予測することで、過渡期を乗り越える助けとなる。

企業は成長する。だが、その成長は決して直線ではない。ある時期まではうまくいっていたことが、突然うまくいかなくなる。新しい部署を作ったはずなのに、逆に混乱が起きる。現場から「もう限界です」と声が上がる。あるいは、社内に妙な停滞感が漂い、「これ以上どうすればいいんだ?」と経営陣が悩む──。
私はこれまで、青果市場、食品、製薬、IT、ファンド傘下の中小企業と、異なるフェーズの会社でマーケティング・人事・DX・広報などを担ってきました。数百人規模から数千人規模まで、経営の最前線と現場をつなぎながら、事業拡大に取り組んできました。
そんな私が企業変化の「地図」として強く共感してきたフレームワークがあります。それが、グレイナーの企業成長モデル(Greiner’s Growth Model)です。
この理論は、企業の成長は段階的であり、そのたびに必ず「危機(クライシス)」が訪れることを前提としています。成長を目指すなら、この“成長の地形図”を知らずに経営するのは、地図なしで登山するようなものです。
本稿では、このモデルの各フェーズと、それに対応する危機、そして私が体験してきた企業のリアルを重ねながら、「成長とは何か?」を掘り下げていきます。
第1フェーズ:創業と「リーダーシップの危機」
企業は、創業者の情熱と行動力によって始まります。決断も実行もスピーディーで、トップダウンで動くことが効率的です。朝令暮改も許され、個人のカリスマが企業を引っ張っていきます。
しかし、成長していくにつれて、創業者一人では限界がくる。業務が属人的で属人依存が強まり、社員が何をしているのか見えにくくなります。ここで訪れるのが、「リーダーシップの危機」です。
このフェーズを脱するには、仕組み化と組織化が必要です。しかし、ここで創業者が手放せないと、会社は“成長疲労”を起こします。
第2フェーズ:指令による成長と「自律性の危機」
創業者がマネジメントを任せ、組織が階層化され、管理職が登場します。制度やルールが整備され、会社らしくなっていくフェーズです。
この段階では、「ちゃんと回す」ためのプロセスが整えられますが、やがてその制度が現場の自律性を奪っていきます。現場は「指示待ち」になり、自由に動けなくなる。これが「自律性の危機」です。
ある企業で「管理職の離職」が相次いでいた原因です。理由は、「管理職になっても裁量がない」「意思決定はすべて役員会で決まる」とのことでした。会社は成長し、ルールも整っているはずなのに、現場の声はむしろ「前の方がよかった」と嘆いていたのです。
成長とは矛盾を孕んでいます。だからこそ、管理と現場力のバランスをどう取るかが、このフェーズの肝です。
第3フェーズ:権限移譲による成長と「統合の危機」
この段階では、各部門に大きな裁量が与えられます。「現場主導」「部門別採算」「意思決定のスピード」が重視され、組織は分権化していきます。
しかし、その自由さゆえに、会社全体がバラバラになるという危機が訪れます。これが「統合の危機」です。
このフェーズでは、全社視点を持つ「調整屋」的な人材が重要です。分権化を維持しながら、「バラバラにならない組織文化」をどう作るかが問われます。
第4フェーズ:調整による成長と「官僚制の危機」
分権と統合のバランスを取るために、「調整機能」や「横串プロジェクト」が導入されます。経営企画、ブランド戦略、情報システムなど、全社を横断する動きが出てきます。
しかし、ここで起こるのが「官僚制の危機」です。つまり、制度が重くなり、スピードが出なくなるのです。
このフェーズでは、「調整疲れ」「制度疲れ」に陥らないよう、現場との距離感を取り戻すことが求められます。
第5フェーズ:協働による成長と「内部成長限界の危機」
ここでは、トップダウンでもなく、制度依存でもない、「チーム型組織」や「自己管理型組織」へと移行していきます。理念や価値観を共有し、自律と協働の文化で動いていく段階です。
しかし、ここで企業は別の壁にぶつかります。それが「内部成長限界の危機」です。社内リソースだけでは、新たな飛躍ができなくなるのです。
この段階で必要なのは、外部との連携や、イノベーションの導入です。しかし、組織文化が成熟しているがゆえに、新しい血が入りにくい。理念との整合性ばかりが重視され、「過去の成功体験」に縛られがちになります。
この段階では、「外からの刺激をどう受け入れるか」が焦点となります。
第6フェーズ:外部連携による成長と「アイデンティティの危機」
グレイナーが後年に追加したフェーズであり、外部との連携──M&A、アライアンス、新市場参入などを通じて成長を図る段階です。
しかし、外部との連携が進むと、自社の文化や価値観が揺らぎ始めます。「自分たちは何者なのか?」というアイデンティティの危機が訪れます。
私が関わったファンド傘下の企業では、「元の企業文化が失われた」との声が現場から上がりました。売上は伸びている、けれど、社員の帰属意識が薄れ、「この会社がどこに行くのかわからない」と語る人が増えていったのです。
このフェーズにおいて大切なのは、変化を受け入れながらも、「守るべき軸」を見失わないことです。
「ここまで読んでくださったあなたと、本当にご一緒できたらと願っています」
無料相談受付中です
もし、あなたの会社が
「がんばっているのに成果が出ない」
「どこに手をつけていいか分からない」
そんな状態にあるなら、
まずは“構造の見える化”から始めてみませんか?
初回相談は無料です。お気軽にどうぞ!
ご相談はこちらから
https://.com/seitasuzuki/message
取材・セミナー・講演のご依頼も随時受け付けております。
感想・共感・ご意見をぜひコメント欄へ
このテーマに関心がある方は、フォローやスキを押していただけると励みになります。
おわりに─成長とは、危機を繰り返すことでしか手に入らない
企業の成長とは、単なる拡大ではなく、「危機を乗り越える旅」の連続です。
人が成長するように、企業もまた痛みを伴いながら進化していきます。
グレイナーのモデルは、その旅路に地図を与えてくれます。地図があれば、現在地がわかり、次に起きることを予測できる。
それだけで、手詰まりに見えた状況が「過渡期」に変わるのです。
Views: 0