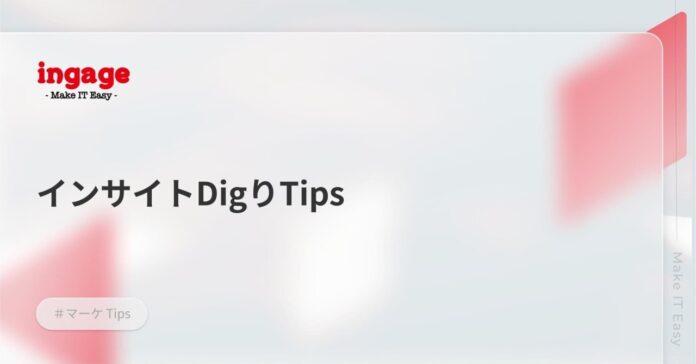🧠 概要:
概要
この記事では、企業のインサイトを深掘りする方法について述べています。特に、マーケティングにおける「インサイト」の重要性や、その定義、仮説との関係性、インサイトを見つけるための具体的な手法について説明しています。また、良いインサイトを見つけるために必要な心構えやアプローチ方法も提供しています。
要約
- インサイトの定義: 表面から見えない内部にある本質的な動機や真実。
- インサイトとニーズ: 表面的なニーズを超え、本質的な「なぜ」や「本当の気持ち」を探ることが重要。
- インサイトは仮説の元: インサイトは、まだ確証のない「見立て」であり、仮説はそれを検証可能にするものである。
- 良いインサイトを見つけるためのポイント:
- 定量データの収集: Webを活用し、様々なデータをセグメント化して分析。
- 定性データの収集: インタビューや観察を通じて人々の生の声を探る。
- 生成AIの活用: 新たな視点を得るためにAIツールを活用するアイデア。
- 心構え: 一度見つけたインサイトに固執せず、常に疑問を持ち続けることが多様なインサイト発掘には不可欠。
- プロセスの繰り返し: インサイトから仮説を立て、検証し、新たなインサイトを探る流れが重要。
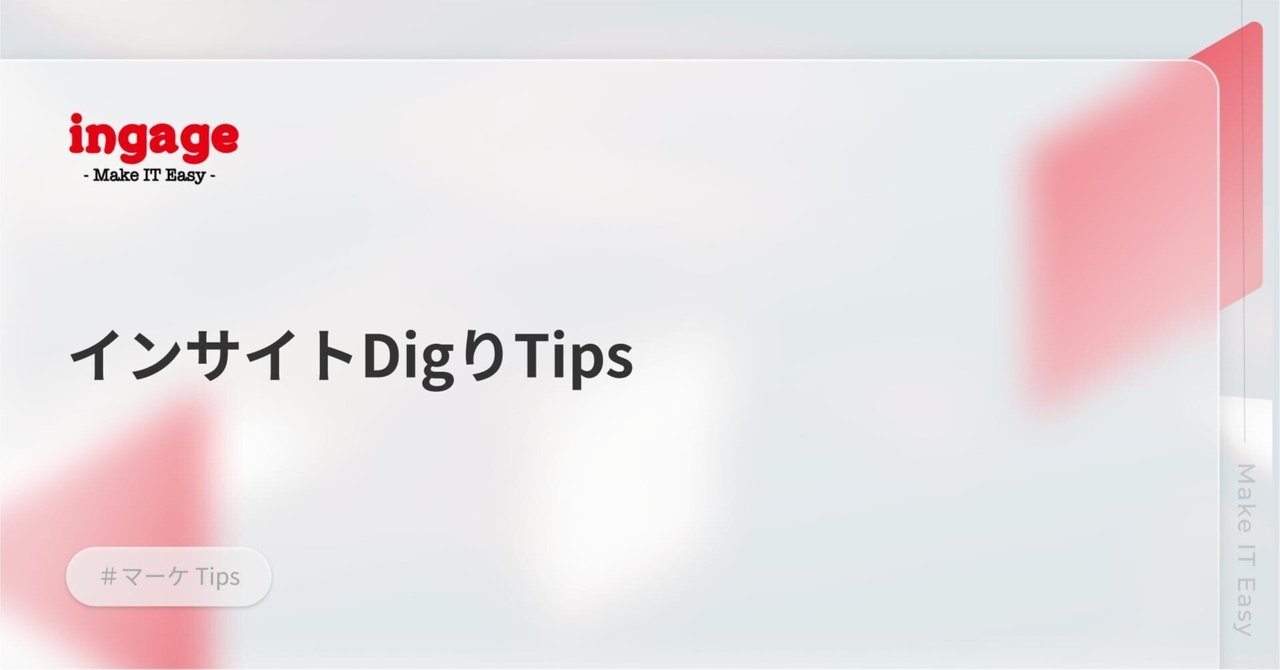
弊社では社内勉強会をやっており、そこでとりあげたのですが折角なので一部をに展開しようと思います。
なお、弊社ではRe:lationというツールを提供しておりお客様の声の集約と対応にお使いいただけるのでメタ的にインサイトを掘っていくのに使えるツールだったりします。
そもそもインサイトを「掘り下げる」とは、どういうことか?
マーケをやっていると概念を表す単語、特にカタカナ言葉が多用される傾向があります。まぁ意思疎通とジャーゴンによる仲間意識が捗るんですが、にしてもとっつきにくいっすよね。
インサイト is …
今回はそのひとつである「インサイト」について取り上げます。まず、インサイトという言葉の成り立ちから見てみましょう。
インサイト = IN-SIGHT = IN(中にある)- SIGHT(見えるもの)。つまり、文字通り、表面からは見えない、内側にあるもの、ってことなんですよね。
概念的に表すなら第1階層:表面(言動)第2階層:ニーズ第3階層:インサイト
かなぁと思います。
よく、「あなたのインサイトは浅い」とか、「もっと深く掘り下げてほしい」なんて言われたりしますよね。それはつまり、表面的な「ニーズ」だけを見ているのではなく、その奥にある「なぜ、そうしたいんだろう?」「本当の気持ちはどこにあるんだろう?」といった、もっと本質的な部分に迫ることが求められている、ということなのだと思います。
私たちは日頃、様々な「ほしい」や「こうしたい」といったニーズに囲まれています。でも、その表面的な欲求のさらに奥には、もっと複雑な、あるいは環境や情報によって形作られた無意識的な動機や、自分自身ですら気づいていないような本心があるのかもしれません。インサイトを探ることは、そうした表面の下に隠された「何か」を見つけ出す作業と言えるでしょう。
なんかこれも相当言及されつくしてて五劫の擦切れになってる気がしますけど「顧客が欲しいのはドリルではなく、穴を空けること」の話ですね。
インサイトは「仮説の元ネタ」である、という視点
このように深掘りしたインサイトは結局妄想でしかありません。そこで導入したいのは「インサイトは仮説の元ネタである」という考え方です。
「仮説」=検証可能な暫定的な説明や予測
つまり、インサイトとして私たちが発見するのは、「もしかしたら、こういうことなのではないか?」という、現時点ではまだ確証のない、しかし検証する価値のある「見立て」なんですね。そしてこの見立てを集め、検証可能になったものがいわゆる「仮説」といえます。
一般にインサイト → 仮説という順に思考を進めますが、これはインサイトありき、という前提に基づいています。つまりインサイトがないと仮説なんて成立せんのでは?という立場です。
「インサイトとしてAがある。Aが合っているなら、①/②/③となるはず」のようにインサイトは単なる思いつきではなく、その奥にある本質的な理解に基づいているからこそ、そこから導かれる予測や具体的なアクション(①、②、③)が、より確からしく、検証するに足るものになるのです。つまり、インサイトは、その後の戦略や施策の強力な根拠となるポテンシャルを秘めている、ということです。
「良いインサイト」はどうすれば見つけられるのか?
さて、ここが一番難しいところですよね。「どうすれば、その表面の下にある、強い仮説の元となる『インサイト』を見つけられるのか?」
個人的にはある意味で非常にシンプル、というか、現実的に やるか
→絶対やるか
の世界かと思っています。じゃあ、「ひたすらやる」ために、具体的に何をすればいいのでしょうか?個人的なTipsも含め書いていきます。
インサイトをひたすらやるためのTips
定量データの収集
これは、まさにWebの世界が得意とするところです。多様なデータを統合し、そこからインサイトの種を見つけ出そう、というマーケターとして求められる基本的な所作です。
単に全体の数字を見るだけでなく、属性、業界、業種、さらには特定の行動などでデータを細かく「セグメントカット」して見ていく。なぜかというと数字の裏に隠された、特定のグループだけに見られる傾向や、意外な行動パターンの中に、インサイトのヒントが隠されていることがあるからです。Webだと結構この辺のログ解析とかは得意ですからね。(データ突合で辛い思いをしますよね、分かります。)
定性データの収集
他方、定量化できないデータもありますよね。主に数字だけでは見えない、人の生の声や行動に触れる方法です。
インタビューで対象者に直接、深く話を聞く。なぜそう思ったのか? 何に困っているのか? どんな時に嬉しいのか? といった、感情や背景を探ります。展示会などもおススメです。試行回数多めに生の声を聴くことができます。
ほかにも行動観察調査で、対象者が実際にどのように行動しているのかをじっと観察する。インタビューで語られることと、実際の行動が違う場合も多く、そのズレの中に重要なインサイトがあったりします。
手軽にソーシャルリスニングで、SNSやブログなどのインターネット上の声を収集・分析する。ここは、人々の本音や、まだ表に出ていないニーズ、あるいは特定の話題に対する熱狂や不満が溢れている宝庫です。いわゆる口コミやVoC 活用とかもこの文脈ですね。
インサイトの発掘にも使えるかもしれない生成AI活用Tips
突然ですが、マツコの知らない世界ってご存じですか?
あの番組、熱度を持った人をひたすらマツコ(敬称略)が受け入れる構図になっていてめっちゃスキなんですよね。今回の話でいうとインサイトの深堀りをマツコさんがやってくれているわけです。
あんまりインサイトの深堀り、うまくいってないな~みたいな方は仮想マツコ・デラックス(敬称略)を召喚し、インサイトの深堀を手伝ってもらうのもおススメです。一例としてのプロンプトを置いておきます。
※使い方:XXを知りたいトピックに書き換えるといい感じの番組台本が出来上がります。
添付のコンセプト、番組構成、番組の強み、視聴者インサイトを守りマツコとXXの世界、という架空の番組台本を作ってください。#コアコンセプト:ニッチなテーマや趣味を深掘りし、視聴者に新しい発見や驚きを提供。マツコの鋭いコメントとユーモアが、ゲストの熱量を増幅し、テーマを身近に感じさせる。#番組構成:導入:テーマとゲストの紹介。マツコがテーマへの初歩的な反応を示し、視聴者の興味を引く。プレゼン:ゲストがテーマの魅力やディープな知識を披露。実物、映像、体験などを交えて具体的に伝える。対話:マツコが質問や突っ込みを入れ、ゲストの情熱や個性を引き出す。時に感動や共感も生まれる。まとめ:マツコがテーマの新たな魅力や気づきを総括。視聴者に「試してみたい」と思わせる。#番組の強み:マツコの存在感:彼女のリアクションとトークスキルが、専門性の高い話を一般視聴者に親しみやすく変換。ゲストの熱量:マニアックな知識や情熱が視聴者の好奇心を刺激。テーマの多様性:日常の身近なものからマニアックなものまで幅広く取り上げ、視聴者の興味を継続的に喚起。#視聴者インサイト:「知らない世界を知りたい」「新しい趣味や興味を見つけたい」という好奇心。「専門家の熱量やこだわりに触れたい」という共感欲求。
「マツコのリアクションで自分と同じ目線で楽しみたい」という親近感。
自作プロンプト
インサイトを見つける旅で忘れてはいけないこと
最後にインサイト探しの旅において、非常に大切だと感じた心構えについてです。それは、自分が一旦見つけたインサイトに「固執しない」ことかと思います。
私に限らず人間は一度「これだ!」と思うと、そのアイデアにしがみつき、それが正しいことを証明しようとしがちです(確証バイアス)。しかし、より深く、より本質的なインサイトを見つけるためには、自分の見立てに常に疑問符をつけ、「これは本当に正しいのか?」「もっと奥があるんじゃないか?」と、謙虚な姿勢でインサイトを掘り下げ続ける必要があります。
自分が最初に発見したものが、実は表面的なニーズの一部だった、あるいは解釈が間違っていた、という可能性を常に頭の片隅に置いておくことが、真のインサイトにたどり着くための鍵となるのかと思います。
インサイト探しを「ひたすらやる」旅へ
インサイトは、表面的なニーズのさらに奥にある、内側で見える本質的な動機や真実です。
それは単なる事実ではなく、検証可能な「仮説」という形で見出されます。インサイトから導かれる仮説は、その後のアクションの強力な根拠となります。良いインサイトを見つける道のりは決して簡単ではありませんが、「ひたすらやる」ことでしかたどり着けません。
その「ひたすらやる」ための具体的な方法としては、定量・定性の両面から多様なデータを集め、対象に強い「興味を持って」質問し、時には生成AIのような新しいツールも活用しながら、様々な角度から掘り下げていくことが有効です。
そして何より大切なのは、自分が見つけたインサイトに固執せず、「もっと奥があるはず」「これは違うかもしれない」という謙虚な気持ちを持ち続けることです。
インサイト探しの旅は、見つけて終わりではありません。見つけたインサイトを元に強い仮説を立て、検証し、その結果からまた新しいインサイトを探しに行く…この繰り返しこそが、インサイトを真に使いこなし、より深い理解へたどり着くプロセスなのだと感じています。
皆さんのインサイト探しの旅が、少しでも実り多きものになることを願っています。そして、もしよろしければ、皆さんがインサイト探しで工夫していることや、感じている難しさなども教えていただけたら嬉しいです!
Views: 2