🧠 概要:
概要
本記事では、転職活動における「軸」を持つことの重要性について述べています。著者は転職経験を通じて、自分の軸を持つことで転職活動が大きく変わったことに焦点を当て、具体的な方法やプロセスを紹介しています。特に、自己の価値観や働き方を明確に言語化することが、キャリア選択における重要なポイントであると強調しています。
要約
-
転職の軸の必要性:
- 軸があることで、自分に合った企業を選べる。
- 軸がないと、選択基準が曖昧になりミスマッチが起こりやすい。
-
転職活動における軸の効果:
- 自分の言葉で考えを語れるようになり、一貫性が生まれる。
- 軸があると、冷静に企業を選ぶ判断ができる。
-
自分の軸を見つける方法:
- 5年後の自分を想像し、逆算する。
- 過去の経験を振り返り、楽しかったことや辛かったことを分析する。
- 現在の違和感を洗い出し、自分の価値観を明確にする。
-
自分の軸を言語化する3つのステップ:
- 過去を振り返り、経験を分析する。
- 現在の違和感を明確にする。
- 未来を具体的に思い描く。
-
実際の変化:
- 軸を持つことで応募企業数が減ったが、選考通過率が上がった。
- 軸があることで、入社後の目標が明確になり、やりがいを感じやすくなる。
-
成長のための継続的な見直し:
- 軸は一度決めたら終わりではなく、時と共に変化するもの。
- 今の自分の状況に応じて軸を持つことが重要。
- 自分のキャリアを創るのは自分自身:
- 軸を持って行動することで、キャリアを効果的に築いていく重要性を訴える。
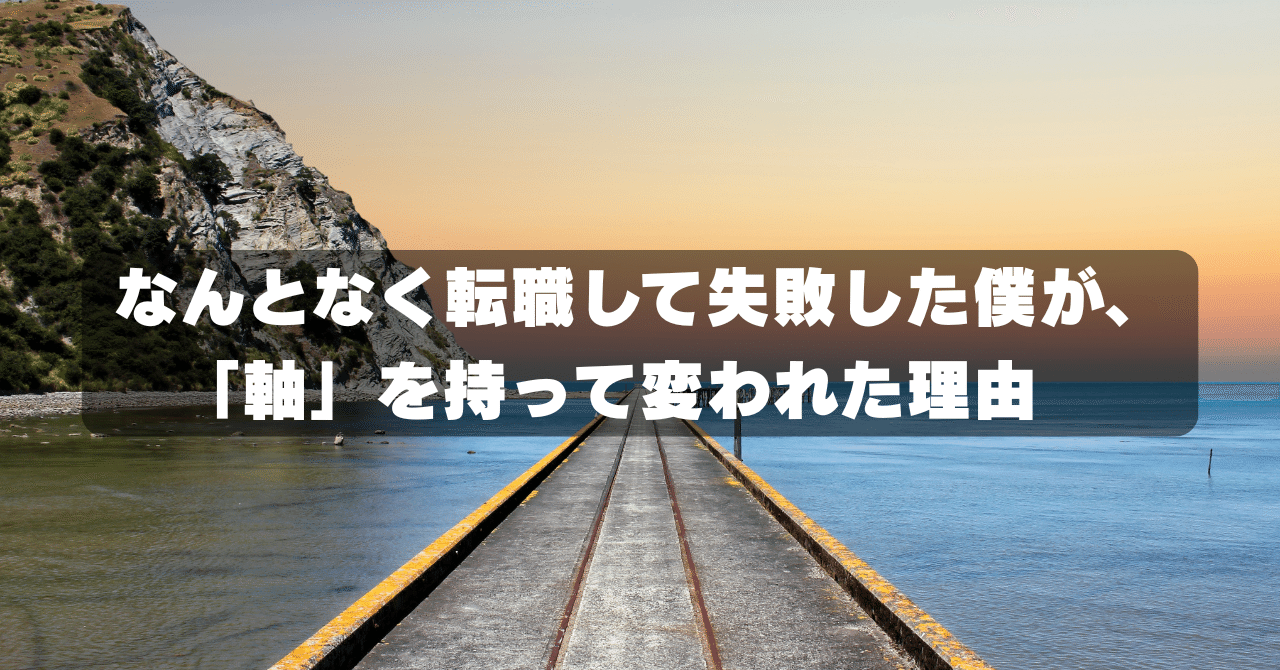
そんなふうに、転職活動がモヤモヤして進まない人は少なくありません。
かつての僕も、まさにそうでした。
求人票を眺めては、「なんとなく条件が良さそう」という理由だけで応募して、転職後に「思っていたのと違う…」とまた悩む。
気づけば、キャリアの舵を「自分」ではなく「環境」に握られているような感覚。
でも、そんな状況を抜け出す鍵がひとつだけあります。
それが、「自分の転職軸を持つこと」です。
この記事では、
-
なぜ転職に軸が必要なのか
-
軸がないとどうなるのか
-
どうすれば自分の軸を見つけられるのか
を、僕自身の経験を交えながらお伝えします。
もし今、「なんとなく求人を見て、なんとなく不安になっている」なら、この記事がきっと、あなたのキャリアを前に進めるヒントになるはずです。
転職に「軸」があるかどうかで、すべてが変わる
転職活動において、最初にやるべきことは「求人を探すこと」ではありません。
真っ先に取り組むべきなのは、自分の軸を定めることです。
軸というのは、自分が「何をやりたいか」「どうありたいか」といった自分なりの判断基準のこと。
この軸があるかないかで、転職活動の質も、選ぶ企業も、面接の伝え方も、大きく変わってきます。
軸を持っていると、求人に対して「これは自分に合っているかどうか?」を明確に判断できます。
逆に軸がないと、「なんとなく条件が良さそう」「とりあえず受けてみよう」といった曖昧な基準で動いてしまい、結果的にミスマッチが起きやすくなります。
面接でも同じです。軸がある人は、自分の考えや志向を自分の言葉で語ることができるので、面接官にも「この人はブレないな」と伝わりやすい。
企業選びから面接まで、すべてに一貫性が生まれるのが軸を持つ最大のメリットです。
さらに言えば、転職の軸は人生の軸にもつながります。
仕事は、1日8時間・週5日・年間約2,000時間もの時間を使う行為です。
だからこそ、自分が「どんな働き方をしたいのか」「どんな価値観を大切にしたいのか」を言語化することは、人生全体の方向性を定めることとほぼ同じだと言っても過言ではありません。
そして不思議なことに、人間の脳は目標を定めると、それに関する情報を無意識のうちに集め始める性質があります。
例えば「5年後にこうなりたい」と決めるだけで、それに必要な情報・人・チャンスが自然と目に入ってくるようになります。
だからこそ、軸を定めることは「動き出す前の準備」ではなく、「動き出すための起爆剤」なんです。
軸がなかった頃の僕は、選ぶ力がなかった
「軸がないとどうなるか?」
これは、僕自身の過去がすべてを物語っています。
正直に言うと、僕は昔から「自分はどうしたいか」を真剣に考えてこなかったのです。
大学受験のときでさえ、理系の中で一番偏差値が高いから——という理由だけで数学科を選びました。
特別数学が好きだったわけでも、将来なりたい姿があったわけでもない。
ただ、「そこそこ頭がいい自分ならこの辺かな」と、完全に他人目線の選び方でした。
就活も同じです。
当時の僕は子どもの頃から病弱で、よく病院に通っていました。
だからこそ、仕事のイメージといえば、医療系くらいしか浮かんでこなかったんです。
「何か専門的なことがしたい」「人の役に立ちたい」みたいな漠然とした憧れもありましたが、実際には医療職としての資格も経験もなかったので、応募条件を満たす求人はほとんどなし。
結果的に、「医療にちょっと近そう」という理由で、ドラッグストアに就職しました。
完全に「それっぽさ」だけで決めた選択。
でも、やりたいこともなく、働く意義も感じられない。
そんな仕事に熱意を持てるはずもなく、日々モヤモヤを抱えながら働き続けました。
初めての転職でも、その傾向は変わりませんでした。
「エンジニアってこれから需要あるらしい」
「なんとなく、手に職がついてよさそう」
そんなふんわりとした印象だけでIT業界を選び、C言語を使ったレガシーなシステムの開発をしている企業に転職しました。
技術のトレンドにも乗っておらず、会社のビジネスモデルもいまひとつ将来性が見えない。
業務で得られるスキルも限定的で、どこかに潰しがきくわけでもない。
それでも「転職できたし、まぁいいか」と思っていた自分がいました。
でも、当然うまくいきません。
働けば働くほど、自分が何をしたいのか、どこに向かっているのかがわからなくなっていく。
転職したのに、「前と同じような悩み」にぶつかる日々が続きました。
今になって思えば、それはすべて「軸がなかった」から。
自分がどう生きたいのか、どんな働き方をしたいのかを考えず、その場その場で「それっぽい選択」を繰り返していただけだったんです。
「どうありたいか」から逆算する、そして現実からも目をそらさない
では、どうすれば「自分の軸」は見つかるのでしょうか。
大切なのは、まず「自分はどうありたいか」を言語化することです。
転職軸というと、「年収を上げたい」「モダンな技術を使いたい」「リモートで働きたい」
など、条件面ばかりに意識が向きがちです。
もちろんそれも大事な要素ですが、もっと根本にあるのは、「自分がどんな働き方をしたいのか」「何に時間を使いたいのか」
という「あり方」の部分です。
この軸を見つけるときに、特におすすめなのが「5年後、どうなっていたいか?」という問いから逆算する方法です。
例えば——
-
どんなチームで働いていたい?
-
何を任されていたい?
-
どんな生活リズムで過ごしていたい?
-
どんな技術を身につけていたい?
-
どんな言葉で評価されていたい?
こういった問いに答えていくことで、「自分にとって何が大事なのか」が見えてきます。
その上で、「じゃあその未来に向かうには、今どんな経験を積む必要があるか?」と逆算して考える。
これが自分の軸を明確にする最初のステップです。
ただし、逆算思考だけでは不十分です。
なぜなら、人生もキャリアも行動してみないとわからないことのほうが多いから。
だからこそ必要なのが順算思考です。
これは、今の自分の現在地を起点として、
を少しずつ試してみる考え方です。
逆算=ゴールから今を考える
順算=今からできることを考える
どちらかだけに偏るのではなく、両方の視点を行き来しながら、自分なりの軸を育てていく。
これが、無理なくブレずにキャリアを築くための現実的なアプローチです。
自分の軸を言語化する3つのステップ
「ありたい姿」や「働き方の理想」を言語化するのは、簡単そうで意外と難しいものです。
何から手をつければいいかわからない、という人も多いのではないでしょうか。
ここでは、僕自身が実践してきた「自分の軸を言語化するための3ステップ」を紹介します。
紙とペン、またはスマホのメモアプリなどを使って、ぜひ一緒にやってみてください。
ステップ1:過去を振り返る
まずは、これまでの経験を振り返ってみましょう。
ポイントは、「楽しかった経験」と「つらかった経験」の両方を掘り下げることです。
-
どんなときにやりがいを感じた?
-
逆に、どんなときに「もう嫌だ」と思った?
-
成果を出せたとき、自分はどんな働き方をしていた?
そこには、自分が大切にしたい価値観や、得意な働き方のヒントが隠れています。
感情が動いた出来事には、必ず自分らしさが表れているからです。
ステップ2:今の違和感を言語化する
次に、現在の仕事や働き方について、「なんとなく違和感がある部分」を洗い出してみましょう。
-
何がしんどい?
-
どんな場面でストレスを感じる?
-
どんな価値観と合わないと感じている?
モヤモヤの正体を言葉にすることで、「これはやりたくない」「これは避けたい」というネガティブな軸が見えてきます。
これもまた、転職先を選ぶ上での大切な判断材料になります。
ステップ3:未来を描く
最後に、「5年後、どうなっていたいか?」を具体的に思い描きます。
-
どんなチームで働いていたい?
-
どんな技術を使っていたい?
-
どんな評価をされていたい?
-
仕事以外の時間は、どんなふうに過ごしていたい?
ここでは、「今の延長線上」だけで考えなくてOKです。
「本当はこうなりたい」という理想を素直に描くことが大切です。
この3ステップを通して出てきた言葉や感情の中に、自分の軸のヒントがたくさん眠っています。
はじめはぼんやりしていてもかまいません。
少しずつ書き出しながら、「自分はどう働きたいのか」「どうありたいのか」を明確にしていきましょう。
軸を持って動くと、転職活動はこう変わる
ここまで読んで、「軸を持つことの大切さ」は少しずつ伝わってきたかもしれません。
でも実際のところ、軸があることで転職活動はどう変わるのか?
僕自身の実感も交えながら、軸を持ったからこそ得られた変化について紹介します。
まず、応募する企業の数はぐっと減りました。
でもその代わり、選考の通過率は明らかに上がったんです。
理由はシンプルで、自分の考えを自分の言葉で語れるようになったから。
面接では、企業に合わせたテンプレ的な受け答えではなく、「自分はこうありたい」「だから御社に惹かれている」
といった芯のある話ができるようになりました。
その一貫性が、結果的に信頼感につながっていたのだと思います。
また、内定が出たときの自分の反応もまったく変わりました。
以前の僕は、「せっかくもらえたから」と、焦って飛びついてしまうことが多かったんです。
でも、軸があることで「この会社は自分の理想に合っているか?」と冷静に判断できるようになりました。
企業に選ばれる側であると同時に、自分も企業を選ぶ側である。
その意識が芽生えたことで、内定がゴールではなく、あくまでスタートラインだと思えるようになったんです。
複数の企業から内定をもらったときにも、軸があると判断に迷いません。
年収や働き方といった条件面だけで比べるのではなく、「自分が目指す方向に近いのはどちらか?」という基準で選べるので、ミスマッチも起きにくくなりました。
そして何より、転職後の働き方にも大きな影響がありました。
軸があったからこそ、「この職場で何を目指すか」が最初からはっきりしていて、入社後に迷うことが少なかったんです。
自分がどう成長したいか、どんなポジションを目指したいかが明確だったことで、行動にも一貫性が生まれました。
その結果、チーム内での信頼も早く得られ、やりがいを感じながら働くことができました。
転職活動は、「どう選ぶか」だけでなく、「選んだ先でどう動けるか」までが勝負です。
そのすべてにおいて、軸を持つことが確かな道しるべになってくれました。
あなたの「軸」は、あなたにしかつくれない
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
転職活動における「軸」の大切さが、少しでも伝わっていたら嬉しいです。
僕自身、軸のないまま就職や転職を繰り返してきた過去があります。
なんとなく良さそうな選択肢に飛びつき、そのたびに違和感を抱えながら働き続けていました。
でも、「自分はどうありたいのか?」という問いに向き合い、言語化し、軸を持って動くようになってから、キャリアの景色が一気に変わったんです。
軸があると、企業選びにブレがなくなります。
面接でも、自分の言葉で語れるようになります。
そして転職後も、「この場所でどう成長していくか」がはっきりするので、やりがいを持って働けるようになります。
もちろん、軸は一度決めたら一生変わらないものではありません。
年齢やライフステージ、経験を重ねる中で少しずつ変わっていって当然です。
でも、だからこそ「今の自分にとっての軸」を持っておくことが、前に進む力になります。
最初はぼんやりしていても構いません。
「5年後どうなっていたいか?」という問いから始めてみるだけでも、きっと見えるものが変わってきます。
大事なのは、完璧な答えを出すことではなく、自分の言葉で考えて、自分なりに行動していくことです。
あなたのキャリアをつくるのは、あなた自身です。
その一歩を踏み出すきっかけとして、この記事が少しでも役に立てたなら、こんなに嬉しいことはありません。
Views: 1



