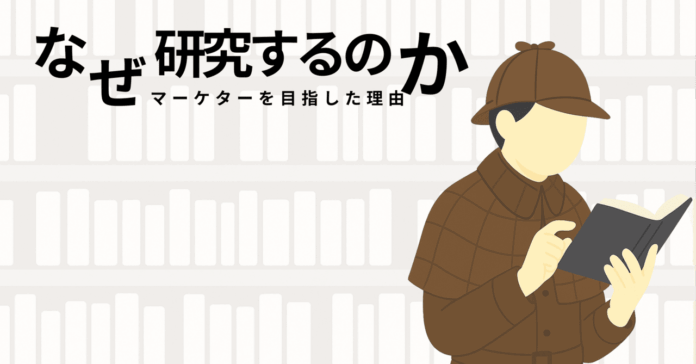🧠 概要:
この記事は、主婦ライターが年間33万人のPV(ページビュー)を達成した理由について述べています。著者は、SEOや成果主義に依存せず、感性や人間らしさを重視したアプローチが重要であると主張しています。
### 概要
– 成功した主婦ライターの事例を通じて、数値だけではなく感情や人間的なつながりを重んじるべきだと提案。
– 数字の背後にいる「誰か」の感情を想像することで、読者との関係を築くアプローチを強調。
### 要約の箇条書き
– 多くの主婦ライターが記事作成に取り組んでいる現状を紹介。
– SEOや成果主義に依存する危険性について警鐘を鳴らす。
– 主婦ライターの運営するメディアは、年間33万PVを達成し、ほとんどが検索から得たもの。
– 150本の記事で30倍以上の読者を集めた理由は、心のこもった文章が要因。
– メディア「香LIG」は、記録よりも観察と育成を目的としている。
– SEOに依存せず、感情を大事にした文章作成が成功のカギであると主張。
– 数字の分析だけでなく、読者の感情を理解することが本質的な価値を持つ。
– 読者に伝える「体験」や「気持ち」の大切さを強調し、量産されたコンテンツへの懸念を表明。
– メディア運営の目的は「売る」ことではなく、「満たす」ことと述べる。
– 読者との関係を築くためには、感性と人間らしさを大切にすることが不可欠。
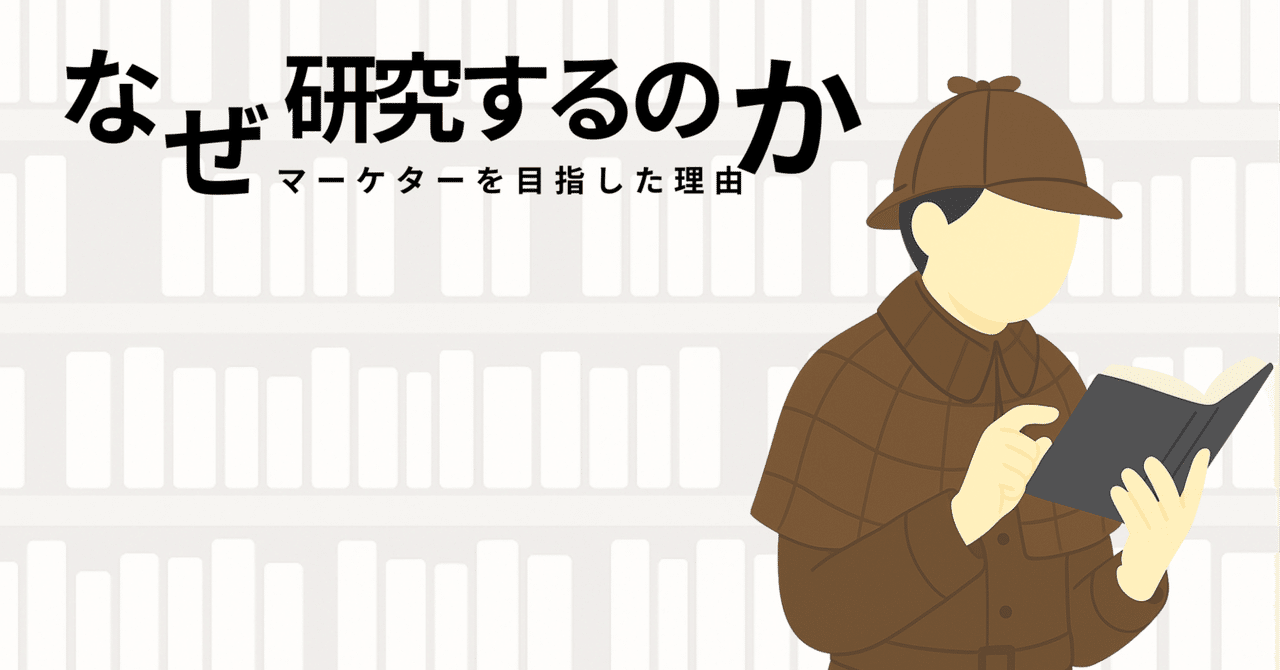
いわゆる“成功法則”とされる情報に、あなたの感性が、少しずつ削がれていってはいませんか?
文章に心が乗らないまま、今日も何本もの記事を納品していませんか?
そんな現実に、私たちは静かな危機感を抱いています。
私たちのメディアは、年間33万人に読まれています。99%がSEOと言われる検索から読まれています。
記事数は、およそ150本。


実はこの数字、オウンドメディアの世界では、ちょっとした“異常値”なのです。
というのも、150記事といえば、一般的にはせいぜい年間1万PV前後が相場らしい。運営会社の多くは、そこからじわじわと数年かけて成長していきます。
 グーグル先生の回答
グーグル先生の回答
けれど私たちは、1万どころか、その30倍以上の読者を1年で集めた。
そして、これは広告に多額の費用をかけた結果でも、炎上を狙った派手なバズでもありません。
一体なぜ、これほどの成果が出たのか?
その理由は、記事を書いたのが「一人の主婦」だったからこそ、かもしれません。私自身、その昔メディアを育て売った経験がありますが、おそらく達成できてないと思いました。
なぜ、私たちはメディアを運営しているのか?

マーケティング会社として活動する私たちが、自社で香りに特化したメディア「香LIG(かおりぐ)」を立ち上げました。
「自社メディア」と聞くと、多くの人が「集客目的」「広告収益」「ブランド認知」といった、いわゆるビジネス的な理由を思い浮かべるかもしれません。
でも、私たちがこのメディアを運営する目的は、そこにはありません。
香LIGは、お金儲けのためのメディアではなく、観察と育成のための“実験場”のような存在です。
私たちは、マーケティングという仕事を通じて、「どうすれば人に届くのか」「なぜ、この商品は選ばれたのか」という人の行動の“なぜ”を、もっと深く知りたかった。
ツールの数字やアンケートの結果では捉えきれない、“リアルな感情の流れ”を観察したかった。
そのために、私たちはあえて自分たちでメディアを持ち、運営を続けています。
彼女の名前は、オノリカ。ガチの香りオタクであり、日常の中にある小さな違和感に敏感で、言葉を拾う感性に長けた女性です。
そして何より、「数字よりも人の気持ちを見てきた」人でした。
SEOの教科書をなぞったわけでも、情報をかき集めて並べたわけでもない。
ただひたすら、「この香りが誰かの心に届くといいな」と思いながら、言葉を選び続けた結果でした。
数字の正しさではなく、「体温のある記事」が、人の手元に届いた。
それだけのことなのかもしれません。
その始まりは、ただ1本の香水記事でした。SEOツールも、上位表示のマニュアルも使っていません。
あったのは、
「この香りは、どんな気分の人に届くのか?」という問いと、
「この香りを手にした誰かが、ちょっと幸せになるといいな」という願い
だけでした。
データが先にある時代です。
ツールが先に語り、数字が評価され、効率が“成果”とされる時代です。
でも、だからこそ私たちは伝えたい。
感性は、捨てるべき“非効率”ではなく、
“誰かの心を震わせる唯一の手がかり”です。
あなたの文章には、もともと「体温」があったはずです。
読者の背中をそっと押す、あの小さな言葉の余白があったはずです。
それを思い出すきっかけになればと思い、この記事を書きました。
最初の「うれしさ」は、数字じゃなかった。

私たちの最初の経験は、バーバリーのペアフレグランスでした。読者数は、まだ1000人にも届かない小さなメディア。
静かで、手探りで、たしかに誰かに届いているのかも分からない、そんな時期でした。
そんなある日。
画面の通知に「購入」の文字が灯りました。
購入されたのは、香水だけじゃなかった。
一緒に、旅行プランも選ばれていたのです。
私たちは思わず、顔を見合わせました。

「……このユーザーさん、どんな気分だったんだろうね」「香水をつけて旅行……なんてオシャレなんだろう」「香水をつけて旅行なって経験ありますか?」
「いやー、経験したことないなー….食にしか興味が出ないんですよね」
一瞬、オフィスの空気がふわっと変わりました。
机の上にあった資料や画面よりも、頭の中に浮かんだその人の旅の景色のほうが、ずっと鮮やかに思えた。
その時、私たちは確かに思ったのです。
「もしかしたら、あの人の“いい時間”を、少しだけ後押しできたのかもしれない」
利益なんて、ほとんどありませんでした。
でも、数字では測れない喜びが、そこにはありました。
誰かの目に映った香り。誰かの思い出に溶け込んだ体験。
まだ始まったばかりの私たちのメディアに、初めて“人の気配”が宿った瞬間でした。
私たちが届けたのは、「商品」か、「体験」か?
あのとき、私たちが本当に届けたのは、“バーバリー”というブランドの香水だったのでしょうか?
あるいは、旅の荷物にそっと忍ばせたくなるような、心を整える香りだったのかもしれない。
その人の「楽しい旅を、もっと素敵にするきっかけ」だったのかもしれない。
オウンドメディアというのは、気を抜けばすぐに、
“情報”や“商品”を並べるだけの場所になってしまいます。
PVを稼ぐための記事、キーワードに沿った構成、売れる流れ。どれも間違ってはいません。でも、あの日の私たちは、
画面の向こうにいる“ひとりの感情”を、静かに想像していたのです。
「いいな、この香りと旅の組み合わせ」
「なんだか、その人の物語にちょっとだけ触れた気がする」
——そのとき感じた、あの“あたたかい手触り”。
それこそが、私たちが本当に届けたかったものだったのかもしれません。
商品ではなく、気持ちの高まり。
文章ではなく、思い出を彩る装置。
私たちはきっと、「売る」ではなく「満たす」ことを願っていたのだと思います。
答えがあるようで、どこか薄い世界

今、ネット上には無数の情報サイトが溢れています。「人気10選」「コスパ最強」「この機能がすごい」
——そんな言葉たちが、まるで判を押したように並んでいます。
もちろん、それ自体が悪いわけではありません。必要な情報を、必要な人に届けること。
それは、立派な価値です。
でも、なぜでしょう。
どれも“似ている”という感覚が、心に引っかかるのです。
見た目は違っても、どこかで“コピー”されたような空気をまとっている。読んでも読んでも、何も残らない。
ふと閉じたとき、自分が何を得たのか分からなくなる。
その原因はきっと、「こうすれば成果が出る」「この順番で書けば売れる」
——そんな“成功法則”が、広まりすぎたから。
あらかじめ用意された「答え」がある世界では、
人は考えなくても、手を動かせてしまう。
「早く」「無駄なく」「効率よく」
その美徳がもてはやされるうちに、
感情や揺らぎ、人間らしさは、いつの間にか後ろに置き去りにされたのかもしれません。
人は「道具」か、それとも「協力者」か。

私たちはマーケティング会社として、日々さまざまな人と関わりながら仕事を進めています。
ライター、デザイナー、ディレクター、時にはお店のスタッフやお客様まで。
そんな中で、ふと感じることがあります。
「人を道具のように扱う人」が、確かに存在しているという事実です。
自分ができないから頼むのではなく、
自分がやりたくないから、やらせる。
「やらせよう」「書かせよう」
「作らせよう」
——そんな“命令形の言葉”が、会話の中にひっそりと混ざっているとき、
私はどこか冷たいものを感じてしまいます。
たしかに、効率化や標準化は、ビジネスにおいて重要です。
再現性のある手法、分かりやすいマニュアル、それらはチームを支える道具として役立ちます。
でも。
手足が増えても、「考え方」は増えない。
協力者の数が増えても、「脳」は増えない。
そこにあるのは、ただの「実行力の分散」に過ぎません。
中には、「自分の方が上だから」「報酬を払っているから」
という理由で、人を安く買い叩こうとする人もいます。
いわゆる「主語が自分」というやつです。
「違い」がなくなっていく世界で、書き手が感じる“寒さ”

同じ構成。同じ言葉遣い。同じようなタイトル。
違うはずのメディアなのに、どこかで見たことのある記事が、今日も量産されていく。
それを作っている側の“書き手自身”も、
本当はもう気づいているのだと思います。
「これ、昨日書いたものとほとんど同じじゃないか」「違うテーマだけど、言ってることは結局いつも同じだな」
「これって、誰かの心に届いてるんだろうか?」
そんな小さな“違和感”が、積もっていく。でも、締切は来るし、報酬は変わらない。
思考を止め、手を動かすしかない。
「意味があるのか?」と問いながら、誰かの検索意図に寄せる日々。
やがて、書き手の目は、読者ではなくGoogleを向くようになります。
「このキーワード、もう検索ボリューム減ってきたかも」「競合は10選って書いてるから、うちは15選にしよう」
「アルゴリズム、また変わった?どう対応すれば…」
——そうして、
記事は「伝えるもの」ではなく、「戦う武器」になっていく。
それは、書く人を疲弊させるループの始まりです。
AIに怯え、アルゴリズムに振り回され、自分の文章がどこに向かっているのか分からなくなる。“どう生き抜くか”という問いだけが先走り、
「なぜ書くのか」は、だんだん遠ざかっていく。
その結果、生み出されるコンテンツは、
どこかに“冷たさ”をまとってしまうのです。
言葉は整っている。情報も正確。
でも、読み終えたあとに残るのは、温度ではなく“空白”。
読者の心に何かを灯すのではなく、
“用を済ませる”だけの存在になってしまう。
そして、何よりその冷たさに、一番先に気づいているのは——
書いている“あなた自身”なのではないでしょうか。
数字の先に、”誰か”がいる。

数字が伸びることは、確かにうれしい。
月間PV、クリック率、購入数、滞在時間——
画面に並ぶそれらの数値は、努力の証であり、安心材料でもある。
でも、どんなに数字が積み上がっても、
私たちはいつも問い続けています。
「その先に、“誰か”がいたことを、ちゃんと想像できているだろうか?」
たとえば——
何かを“買いたい”と思ったその人は、
どんな未来を叶えようとしていたのか?
検索バーに言葉を打ち込んだその人は、
どんな気持ちで、どんな迷いを抱えていたのか?
記事を最後まで読んでくれたその人は、
何にうなずき、どの言葉に、そっと救われたのか?
数字は、教えてくれません。
それが“誰の時間”だったのかを。
だからこそ、想像するしかない。想像することでしか、私たちはその人に近づけない。
だからこそ、私たちはそこに力を注ぎます。
目に見えるものだけを信じるのではなく、
見えない感情を、見ようとする努力をやめない。
数字の向こうに、確かに“誰かがいた”。それを忘れずにコンテンツをつくることが、
私たちがこの仕事を続ける理由です。
私たちはマーケティング会社として一つの答えを持っています。
それは
認知率が高いからと言って、売上が上がるわけではない。
なぜなら、顧客に「好き」と思ってもらえない限り、認知の壁は来ないから。
です。
面白いことに、人は「知られていれば買ってもらえる」と考える傾向があります。確かに一定数買ってもらえますが、思っている以上に低い傾向があります。
読者が、答えを持っている。

これからの検索は、どうなっていくのでしょうか。
いまの検索結果は、どこか“戦い”のようです。10選と書けば、次は15選。他より多く、他より早く、他より網羅的に。
アルゴリズムに好かれるための情報が、次々と押し出されていく。
でも——
その中に、本当に読者がほしかったものはあるのでしょうか?
誰の言葉かわからない「おすすめ」に、どこかで見たような文章。安心はあっても、ときめきがない。
正確だけれど、どこか無味無臭。
読者は、それを「正しい」と受け入れながら、
どこかで、「物足りなさ」も感じている気がします。
私たちは、思うのです。
本当に求めているものは、検索される“前”の感情の中にある。
キーワードには映らない、曖昧で、混じり合った気持ち。「なんとなく知りたい」「誰かに代弁してほしい」
「自分のことが、少しわかるような何かを探している」
その“揺れ”を見つけて、言葉にすること。
それが、これからのメディアにできることなのかもしれません。
そして——その「何が響くか」の答えは、私たちが決めるものではなく、
読者自身が、静かに選び取っていくものだと信じています。
だからこそ、私たちはこれからも、
読者のまなざしで世界を見て、言葉を紡いでいく。
届けるのではなく、寄り添うように。言い当てるのではなく、
気づくきっかけとして。
そうして生まれた言葉だけが、
きっと、誰かの心にちゃんと届くと、私たちは信じています。
最後に――「ライターとして活躍する主婦の皆様」へ。
はじめにお伝えしたかった言葉を、最後にもう一度届けさせてください。
いま、たくさんの主婦の方がライターとして活躍されています。家事や育児と両立しながら、毎日のように言葉を紡ぎ、
多くの人に情報を届けるという、大きな仕事を担っています。
でも、きっとあなたは、もう気づいているはずです。
どれだけ構成が整っていても、どれだけテンプレに忠実でも、
“自分の感性が乗っていない文章”が、誰かの心に深く届くことはないということを。
アルゴリズムやSEOに沿って書くことも大切。でも、そればかりを追いかけていると、
あなたの中に本来あったはずの“あたたかさ”が、少しずつ削がれてしまう。
このメディアで記事を書いてきたオノリカという女性も、最初は特別なスキルがあったわけではありません。
ただ、「なんでこれが売れるんだろう?」「どんな気持ちで買うんだろう?」と、ひとつひとつの動きに純粋な疑問と好奇心を持ち続けた人でした。
そして今、彼女の書いた記事は年間33万人に読まれ、
言葉が、香りと共に人の記憶の中に溶けていっています。
だからどうか、思い出してほしいのです。
あなたが書き始めたあの頃の、“誰かを思う気持ち”を。
効率や収益の前にあった、“伝えたい”という感情を。
言葉には、力があります。でもそれは、誰かの構成に沿った時ではなく、
あなたの中にある願いや祈りが、にじみ出たときにこそ、宿る力です。
あなたの言葉で、世界は変えられる。
そのことを、どうか忘れないでください。
量産の海に、あなただけの“視点”を投げ込んでください。
それは、誰も気づかなかった“青”を滲ませるはじまりです。
ブルーオーシャンは、“人が気づいていない感情”の中にあると信じています。
そして私たちもまた、数字ではなく「誰か」に届く言葉を、これからも探し続けていきます。
Views: 0