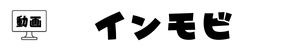🧠 あらすじと概要:
あらすじ
映画『ミゼリコルディア』(Misericordia)は、フランス南西部の村を舞台にした物語。主人公のジェレミーは、かつて働いていたパン屋の葬儀に出席するため、トゥールーズから帰郷します。店主の未亡人マルティーヌに家に泊めてもらうことになり、当初は一泊の予定が、周囲の影響で滞在が延びていきます。村では人間関係が密接で、噂話が飛び交う中、ジェレミーは村人たちとの関係に緊張感を抱くことになります。
ある日、ジェレミーはヴァンサンと口論になり、激しい喧嘩の末に致命的な事態を引き起こします。その後、ヴァンサンの失踪事件が発生し、村人たちから疑いの目を向けられることに。物語は閉鎖的な村の中でのサスペンスとユーモアが交錯し、ジェレミーの奮闘が描かれます。
記事の要約
『ミゼリコルディア』は、閉鎖的な村で生じる事件と、主人公ジェレミーのコミカルな苦悩を描いた作品です。観客は、ジェレミーの真顔でのボケや、彼の緊張感を感じる目力に笑みをこぼしながら緊迫した状況を楽しむことができます。映画は、ユーモアを通じて人間の欲望や複雑な人間関係を描写し、タイトルの「慈悲」が持つ意味を問いかけます。これは、監督アラン・ギロティによる登場人物たちへの一種の慈悲であるとも解釈できるのです。

フランスで23万人を動員する大ヒットとなった、アラン・ギロティ監督の最新作。タイトルの『ミゼリコルディア(Misericordia)』は”慈悲”を意味する。
※ネタバレを含みます
舞台はフランス南西部。石造りの家が並ぶ田舎の村は、おとぎ話のような印象を与える。映画の冒頭は秋の空気を感じさせる広大な丘の中を車で走っていく一人称視点の映像。しかし秋のすがすがしさを感じるのはここだけで、全編を通して霧のかかった薄暗い雰囲気が続く。
主人公のジェレミーはかつて働いていたパン屋の店主の葬儀に出席するためにトゥールーズからこの村に帰郷する。未亡人となった店主の妻マルティーヌはジェレミーを家に泊めてあげることにした。はじめは一泊の予定だったが、周囲に流されるまま滞在が延期され、次第に村人との関係に不穏な空気が漂い始める。
毎日のように顔を合わせ、日々の小さな出来事がすぐに噂として広まっていく村社会。昨日どこにいたとか、何をしていたとかが、いつの間にか知れ渡っている。人間関係が希薄な都会生活を快適だと感じている私には、とても重苦しいものとして映る。村の住人は時間を持て余しているためか、噂話を仕入れては、その断片的な情報を頼りに夜な夜な想像を膨らませる。
ある日ジェレミーはヴァンサン(パン屋の息子)に車で拾われ、マルティーヌやワルター(村人)への感情をめぐって口論になる。粗野なヴァンサンとのもつれは、山の中で殴り合いのけんかに発展。頭に血が上ったジェレミーは、ヴァンサンを棒で殴り倒し、後頭部に大きな石を振り落とす。その一撃で絶命したヴァンサンを、ジェレミーは一晩かけて掘った穴に埋めるのである。
こうして村ではヴァンサンの失踪事件が起こったと騒ぎになる。事件の夜、家にいなかったジェレミーは、マルティーヌをはじめとする村人たちに疑いの目を向けられる。
あらすじを振り返ると、閉鎖的な村を舞台にした薄暗いサスペンスにしか思えないが、実際の描写は抑えの利いたユーモアであふれている。あまりにも真顔でボケるものだから、本気なのかと思ってしまう、そんなタイプのコメディ。
嘘を語るときのジェレミーの目力が面白い。事件当日のことを説明するたびに、おびえたような目で村人たちの顔色を伺う。そんな顔したらばれてしまうよと、見ているこちらに笑みがこぼれる。緊張感が漏れ出ているにもかかわらず、筋は通っているだろうと堂々と振舞おうとするジェレミーが、真相を知っているこちらからすると滑稽に見える。
死体を埋めた地面からは季節外れのキノコがはえ、村人に怪しまれるのを心配したジェレミーは定期的にそのキノコを摘みに山に出かける。ある日、回収したキノコを見られ、食卓にそのキノコがたっぷり入ったオムレツが並ぶ。「死体から生えたキノコ…」と無言で皿を見つめた後、怪しまれてはいけないと一気に口に詰めこみ、ワインで流し込むシーンはまさにコント。
ジェレミーをかばうことにした神父は、彼が事件当日自分と一緒にいたのだと主張するため、ジェレミーと裸でベットに入っているところを警官に見せつける。ベッドからまじめな顔で全裸のまま立ち上がるシーンは、この映画の中で最もユーモラスだった。
この映画が、フランスでヒットしていることに驚く。日本人の目からすると明らかにマイナーな部類に入る奇妙な作品である。日本でブラックユーモアはあまり注目されないけれど、ヨーロッパではこのセンスが一般に浸透しているのだろうか。確かにヨーロッパの民話などには人間の欲望や世界の残酷さを滑稽に描いたものが多い印象がある。
登場する人物たちは、それぞれ欲望の現れ方が違う。露骨な性描写はないが、この映画の中でいう欲望とは性欲のことである。ジェレミーは普段は理性的にふるまっているものの、ふとした瞬間に抑えていた欲望があらわになる。マルティーヌは決して表には出さないが、自分の欲望が満たされるよう、遠回しに手を打つ。ヴァンサンは欲望をそのまま粗野な形で表出させる。神父は何も後ろめたくはないというように真っすぐな姿勢で欲望を伝える。ワルターは自分の欲望をうまく自覚できないでいる。形は違えど、それぞれがもつ流動的な欲望によって人間関係が複雑に絡んでいく。
人間の欲望はあらゆる形に変化する。世の中は欲望で回っているといっても良い。生まれた欲望は満たされて消えるばかりでなく、様々な形に変化し、時に歪なものとして現れる。気になる人に振り向いてもらいたいという気持ちが屈折して、奇行に走った痛々しい記憶がよみがえる。
タイトルにもなっている”慈悲”っていったい何なのだろう。わかるようでわからない言葉。辞書的な説明では、苦痛に対する憐みあるいは罪に対する赦し。キリスト教に詳しくないからあまりピンとこないけれど、人間のきれいではない部分を肯定することだと言い換えられるかもしれない。殺人、性欲、嫉妬など重苦しいものをテーマにしつつ、それらを軽快なユーモアに昇華させる。これはアラン・ギロティ監督による歪な登場人物たちに対する慈悲だったのだろうか。
Views: 0