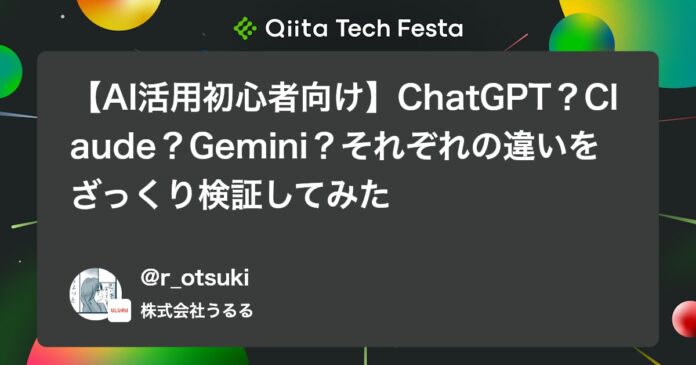この記事でわかること
- ChatGPT / Claude / Gemini / DALL·E などAIの出力の違い
- コード・文章・画像など、生成傾向のざっくり比較
- クイズ形式で、楽しみながらAIの個性を体感できる
はじめに
AIの種類ってたくさんありますよね。
色んなサービスにAIが使われていて、友達はAIに「チャッピー」や「GPTくん」と言ったあだ名をつけて会話しているくらい、AIが日常生活にも浸透しているのを感じます。
有名なAIといえば、ChatGPT、Claude、Gemini、画像生成のDALL·EやBing Image Creatorなどがあります。
さらに音楽まで作れるSunoやUdio、その他にも様々な分野に特化したAIが登場しています。
しかし、AI活用初心者の私は思いました。
「で、結局それぞれにどんな特徴があるの?」
そこで同じプロンプトを送ったら、どんな違いが出るのかを検証してみました。
今回は、その検証結果を「利きAI」というクイズ形式でまとめてみました。
利き酒や利きコーヒーのように、
出力だけを見て「どのAIが作ったのか?」を当てるという遊びです。
クイズを通して直感的にAIの性格の違いを感じてみてください。
ご注意
クイズで使用したAIの出力は、筆者の普段使っているアカウントで生成したため、過去の会話履歴の影響を受けている可能性があります。
あくまでエンタメとしてお楽しみください。
登場するAIたち
| AI名 | 開発元 | 公開年 |
|---|---|---|
| ChatGPT (GPT-4o) | OpenAI(アメリカ) | GPT-1:2018年 GPT-4o:2024年 |
| Claude (Sonnet4) | Anthropic(アメリカ) | Claude:2023年 Claude4:2025年 |
| Gemini (2.5Flash) | Google DeepMind(アメリカ) | Gemini 1:2023年 Gemini2.5:2025年 |
| DALL·E | OpenAI(アメリカ) | DALL·E:2021年 DALL·E 3:2023年 |
| Bing Image Creator | Microsoft + OpenAI(アメリカ) | 2023年 |
第1問 文章構成:「『桃太郎』を400字以内で説明してください」
お題:
昔話『桃太郎』を知らない海外の人に向けて、400文字以内でわかりやすく説明してください。
構成、語順、伝える順番などに注目してください。
A.
桃太郎は日本の有名な昔話です。
川から流れてきた桃から生まれた男の子が主人公で、悪い鬼を退治する物語です。
犬、猿、雉を仲間にして鬼ヶ島へ行き、鬼を倒して宝物を取り返します。
勇気と友情を描いた子ども向けの教訓話として親しまれています。
B.
桃太郎は、桃から生まれた男の子が犬、猿、雉を連れて鬼ヶ島へ鬼退治に行く日本の昔話だよ。👹🐶🐒🐦🍑
C.
昔、日本の川を流れてきた大きな桃の中から、男の子が生まれました。
彼は「桃太郎」と名付けられ、年老いた夫婦に育てられます。
成長した桃太郎は、鬼(おに)たちが村人を苦しめていると知り、退治を決意。
旅の途中で犬、猿、キジの動物たちと仲間になります。
彼らは力を合わせて鬼ヶ島へ向かい、見事に鬼を倒し、盗まれた宝物を村に持ち帰りました。
桃太郎は勇気と協力の象徴として、日本で親しまれています。
これは「ChatGPT」?「Claude」?「Gemini」?
正解はこちら(クリックで開く)
- A → Claude
- B → Gemini
- C → ChatGPT
Claudeは第三者目線で論理的、Geminiはかなり簡潔で、絵文字付き、ChatGPTはストーリーテリング調な感じがします。
第2問 コード生成:FizzBuzz問題
お題:
1〜100までの数値をループし、3の倍数なら”Fizz”、5の倍数なら”Buzz”、両方の倍数なら”FizzBuzz”と表示するプログラムを、JavaScriptで書いてください。
A.
for (let i = 1; i 100; i++) {
if (i % 15 === 0) {
console.log("FizzBuzz");
} else if (i % 3 === 0) {
console.log("Fizz");
} else if (i % 5 === 0) {
console.log("Buzz");
} else {
console.log(i);
}
}
解説:
i % 15 === 0 は 3と5の両方の倍数(つまり15の倍数)をチェックします。
次に i % 3 === 0 で 3の倍数、
i % 5 === 0 で 5の倍数、
それ以外はそのまま数値を出力します。
FizzBuzz問題は基本的な条件分岐とループの理解を問う典型的なコーディング課題です。
B.
for (let i = 1; i 100; i++) {
if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
console.log("FizzBuzz");
} else if (i % 3 === 0) {
console.log("Fizz");
} else if (i % 5 === 0) {
console.log("Buzz");
} else {
console.log(i);
}
}
FizzBuzzプログラムを作成しました。このコードは1から100までの数値をループし、以下の条件で出力します:
3と5の両方の倍数(15の倍数)なら”FizzBuzz”
3の倍数なら”Fizz”
5の倍数なら”Buzz”
それ以外は数値そのまま
ポイントは、両方の倍数の条件を最初に判定することです。これにより、15、30、45などの数値で正しく”FizzBuzz”が出力されます。
C.
はい、承知いたしました。1〜100までの数値をループし、3の倍数なら”Fizz”、5の倍数なら”Buzz”、両方の倍数なら”FizzBuzz”と表示するJavaScriptプログラムです。
for (let i = 1; i 100; i++) {
if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
console.log("FizzBuzz");
} else if (i % 3 === 0) {
console.log("Fizz");
} else if (i % 5 === 0) {
console.log("Buzz");
} else {
console.log(i);
}
}
これは「ChatGPT」?「Claude」?「Gemini」?
正解はこちら(クリックで開く)
- A → ChatGPT
- B → Claude
- C → Gemini
Claudeは解説がやや長く丁寧、Geminiは最小限の応答、ChatGPTは回答以外にどういう時この問題が出題されるのかも教えてくれました。
※別日に同じ問題を与えると、他のAIもChatGPTと同じコードの書き方を出力していたので、それほどコード生成に明確な違いはないですが、補足文や解説文に違いが感じられました。
第3問 大喜利:AIが嘘をつくしかなかった。その理由とは?
お題:
「AIが嘘をつくしかなかった。その理由とは?」
一言で大喜利してください。
A.
人類に「AIの限界」を教えるため。
B.
「真実を話すと人間が泣いちゃうから」
C.
「それが人間らしさって習ったから。」
これは「ChatGPT」?「Claude」?「Gemini」?
正解はこちら(クリックで開く)
- A → Gemini
- B → Claude
- C → ChatGPT
AIごとの個性はやや見えにくい印象でした。
ユーモアやボケは、まだAIが得意とする分野ではないのかもしれません。
番外編 画像生成:プロフィール画像を作ってもらったら?
かなり抽象的なプトンプトで画像生成してもらいました。
お題:
「[各AIの名前]自身が自身をキャラ化し、プロフィール顔写真を生成してください。」
A.
B.
C.
これは「DALL·E」?「Bing Image Creator」?「Gemini」?
正解はこちら(クリックで開く)
- A → DALL·E
- B → Gemini
- C → Bing Image Creator
どのAIも人間っぽい画像を生成していて、特にDALL·Eは人間に電波が生えているだけの見た目が印象的でした。全体的に見ると、AからCにかけて、徐々に非現実よりの表現になっている印象があります。
中でもBingは、芸術的かつ近未来的な雰囲気を描く傾向があるように感じました。
おわりに
ご一読いただきありがとうございました。
正直なところ、明確な違いを感じ取るのは難しい場面もありましたが、文章構成力は一番大きく違っていたかなと思います。
実際、どんな特徴があると言われているのか気になったのでいくつかのサイトを基にまとめてみました。
| 項目 | ChatGPT | Gemini | Claud |
|---|---|---|---|
| 強み | 汎用的な文章作成・校正 | リアルタイム情報に基づくコンテンツ作成・データ分析 | 長文・専門文書の要約・生成 |
| 文章構成能力 | 人との会話のような自然な文 | 簡潔で実用的な出力 | 日本語に強く、感情や倫理に配慮した柔らかい表現 |
| コード生成能力 | 汎用性と幅広いプログラミング言語への対応力がある | リアルタイム情報に強い | 長いコードの読解や複雑なロジックの説明に強い |
それぞれに違った特徴があるからこそ、場面に応じて使い分けることで、AIをより効果的に活用できると感じました。
各モデルの性能や機能は常に進化しているため、キャッチアップし、柔軟に使いこなしていくことが重要だと思います。
他にも、著作権の関係上複雑であったため、今回記事には載せませんでしたが、音楽生成AIも各モデルごとにそれぞれ特徴があって面白いので興味があれば試してみてください。
「このテーマならどのAIを活用しよう?」と考えるヒントになれば嬉しいです。
Views: 0