「おすすめに乗らないのはどうして?」
「再生回数が安定せず、伸び悩んでいるのはなぜ?」
「投稿頻度を増やしても成果が出ないのはアルゴリズムの影響?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
YouTubeは世界最大級の動画プラットフォームであり、その成長を左右する仕組みがアルゴリズムです。
動画の評価は、単純な再生回数だけでは決まりません。仕組みを理解せずに投稿を続けても、チャンネルが伸び悩む可能性があります。
そこで今回は、2025年のYouTubeアルゴリズムについて、最新の傾向や仕組みをはじめ、リセットされる条件・嫌われる理由まで徹底解説します。
さらに、チャンネルを伸ばすための指標や具体的な最適化方法も紹介するので、ぜひ運用改善に役立ててください。

YouTubeアルゴリズムとは
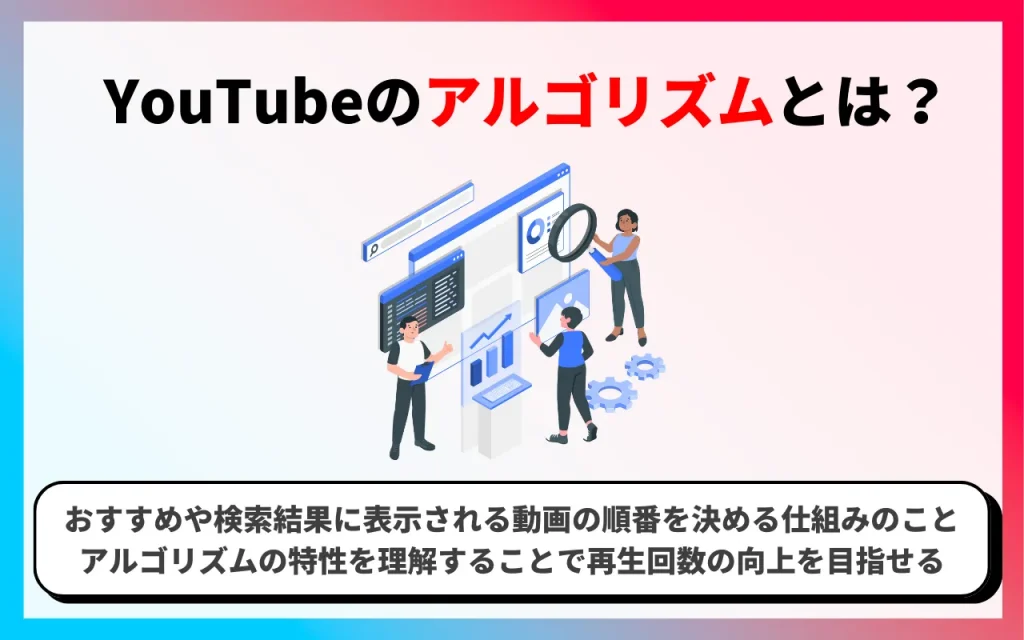
YouTubeのアルゴリズムとは、視聴者一人ひとりに最適な動画を表示するための仕組みです。
クリック率・再生時間・視聴維持率・エンゲージメントなどのデータをもとに、ホーム画面やおすすめ欄に並ぶ動画が決定されます。
たとえば、視聴維持率が高ければ「最後まで見たい動画」と判断され、より多くの人に表示されて、逆に離脱が早い動画は露出が減ります。
つまりアルゴリズムを理解すれば、チャンネル運営の方向性を調整しやすくなり、再生回数や登録者増加にもつなげられるのです。
YouTubeのアルゴリズム|最新の傾向を解説

YouTubeのアルゴリズムは日々アップデートされ、視聴者に最適な動画を届ける精度が高まっています。
近年は「どの動画を誰に表示するか」という基準が変化し、チャンネル運営にも大きな影響を与えているのが特徴です。
2025年最新のYouTubeアルゴリズムの主な傾向は、次のとおりです。
| 特徴 | 概要 |
| ショート動画の 優先度上昇 |
短尺コンテンツは視聴時間の高さが評価され、おすすめ表示されやすい状況が続いている |
| クリック数から 視聴満足へシフト |
単純な再生数よりも、最後まで見られたか・満足度が高いかが重視される |
| 多様性と パーソナライズの強化 |
同ジャンルに限らず、関連する異ジャンルの動画も表示されるなど、 レコメンドの幅が広がっている |
| トレンド表示の刷新 | 従来の「急上昇」ページは終了し、AIによるパーソナライズ型のチャートや Exploreページへ移行している |

YouTubeアルゴリズムの仕組み|おすすめ表示との関係

YouTube公式クリエイターLiaisonのRene Ritchie氏は「人は動画の細部よりも“どう感じたか”を覚えている」と指摘しています。
つまり、視聴者がどんな要素に共感しているかを把握することが重要です。
アルゴリズムはそうした視聴者の反応を取り込み、「どの動画をどの場所でおすすめするか」を決定します。
ここでは、主なおすすめ表示先とアルゴリズムの関係・仕組みについて5つにわけて解説します。
- おすすめ動画
- 関連動画
- ショート動画
- ホーム画面
- 急上昇動画
1. YouTubeアルゴリズム【おすすめ動画】
長尺動画のおすすめ表示は、YouTube側が一方的に動画を押し出す仕組みではなく、視聴者一人ひとりの行動によって決まります。
主な判断基準は以下のとおりです。
- 動画を再生したか、スキップしたか
- いいねやシェアといったアクション
- 視聴後の満足度
中でも重視されるのは視聴者の「満足度」です。
アンケートなどを通じて「視聴者が動画をどう感じたか」まで評価されます。
2. YouTubeアルゴリズム【関連動画】
関連動画は、視聴中の動画の横や再生後に表示される「次に見たくなる動画」を提案する仕組みです。
ここで表示される内容は、今見ている動画のテーマに加え、各ユーザーの視聴履歴によってパーソナライズされます。
関連動画の表示に重要なアルゴリズムのポイントは、次のとおりです。
- 視聴中の動画のテーマとの関連性
- 各ユーザーの視聴履歴や関心度
- 他のユーザーが一緒に見ている動画
- フィルターボタンによる切り替え
さらに最近では、関連動画欄にフィルターボタンが追加され、視聴者は「このチャンネルの動画」「関連トピック」「最近アップロードされた動画」など、気分に合わせて選べます。
3. YouTubeアルゴリズム【ショート動画】
ショート動画は長尺動画とは異なる仕組みでおすすめ表示が行われますが、共通する目的は「視聴者満足度を高めること」です。
長尺動画では、視聴者がタイトルやサムネイルを見て再生を選びます。
一方でショートはモバイル中心のスワイプ式フィードで、流れてきた動画を「見るか・スキップするか」で判断します。
ショートのアルゴリズムで、特に評価される要素は以下のとおりです。
- 平均視聴時間や視聴完了率
- いいね・コメント・シェアなどエンゲージメント
- スワイプせずに見続けた割合
短時間で強い印象を与える動画ほど、拡散されやすい傾向があります。
4. YouTubeアルゴリズム【ホーム画面】
ホーム画面はYouTubeを開いたときに最初に表示される場所で、一人ひとりの視聴者に応じてパーソナライズされた動画が並びます。
ホーム画面のアルゴリズムは次の要素で構成されます。
- 登録チャンネルの新着動画
- 最新の投稿や話題性のあるコンテンツ
- 視聴動画のパターンが似たユーザーが見ている動画
- 動画のパフォーマンス
- 個々が視聴した動画・検索の履歴をもとにした関心度

5. YouTubeアルゴリズム【急上昇動画】
急上昇動画は個人の視聴履歴に依存せず、その国で注目を集めている動画やショートを一覧で表示します。
リストは15分ごとに更新され、リアルタイムの人気を反映するのが特徴です。
選定の主な基準は次のとおりです。
- 動画の再生回数
- 再生数が伸びるスピード(温度)
- 外部サイトからの流入の有無
- 動画の公開からの経過時間
- 同じチャンネル内での相対的なパフォーマンス
また、過度な暴力表現や不適切な内容を含む動画は自動的に除外されるため、健全な範囲で話題性を持つ動画のみが表示される仕組みです。
YouTube投稿頻度とアルゴリズムの関係

YouTubeでは投稿頻度そのものよりも、視聴者にとって喜ばれるコンテンツかどうかが重視されます。
毎日投稿すれば露出の機会は増えますが、質が落ちればアルゴリズム評価や視聴者の信頼を損なうリスクが高まりやすいです。
逆に投稿間隔が空いても、内容が濃く視聴者にとって価値がある動画なら、安定してアルゴリズムに評価されます。
重要なのは「数をこなすこと」ではなく、質と継続性のバランスです。
無理のない範囲で定期的に配信を続け、視聴者の期待に応える動画を積み重ねることが、アルゴリズムにポジティブな影響を与え、長いスパンでのチャンネル成長につながります。
YouTubeアルゴリズムがリセットされる条件は?
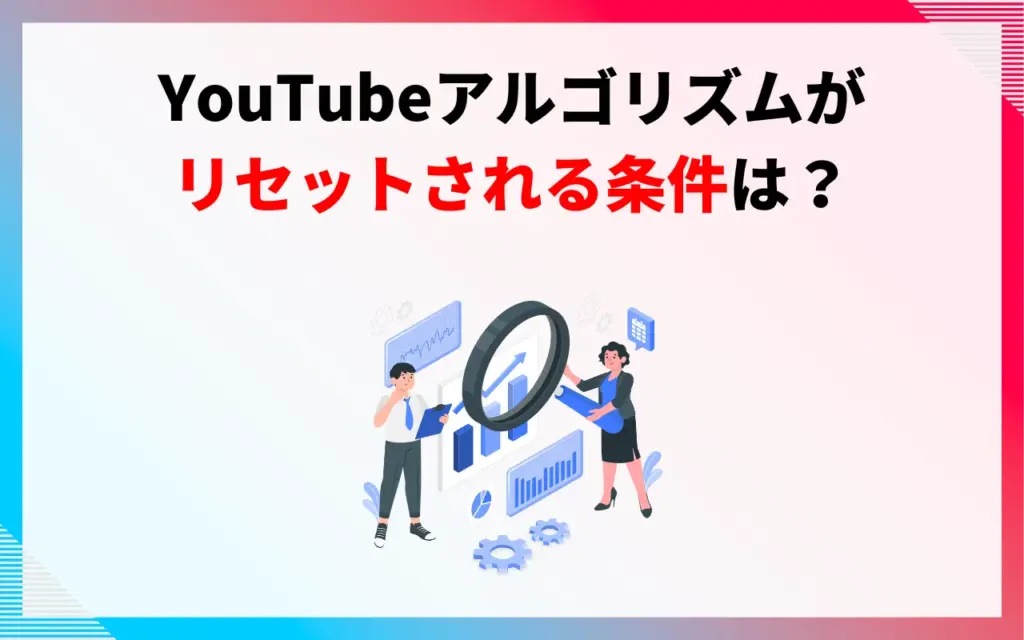
アルゴリズムの「リセット」とは、YouTubeが公式に定義している仕組みではありません。
ただし、クリエイターの間では チャンネルや動画がアルゴリズム上一時的に評価されなくなる現象を指す表現としてよく使われています。
アルゴリズムのリセットが発生しやすいとされるケースは、次のとおりです。
| ケース | 概要 |
| 長期休止 | 数週間〜数カ月投稿を止めると、 評価が初期化されたかのように見え、再評価に時間がかかる |
| 投稿内容や 頻度の急激な変更 |
ジャンル転換や投稿内容の大きな変更で、 過去に築いた信頼や評価が活かされにくくなる |
| 視聴維持率や エンゲージメントの大幅低下 |
再生時間や高評価・コメントが急減すると、 アルゴリズム評価が下がるリスクがある |
| ガイドライン違反による制限 | ポリシー違反により動画が制限されると、 視聴減少が「リセット」と感じられる要因になる |
YouTubeアルゴリズム攻略で重視すべき8つの指標
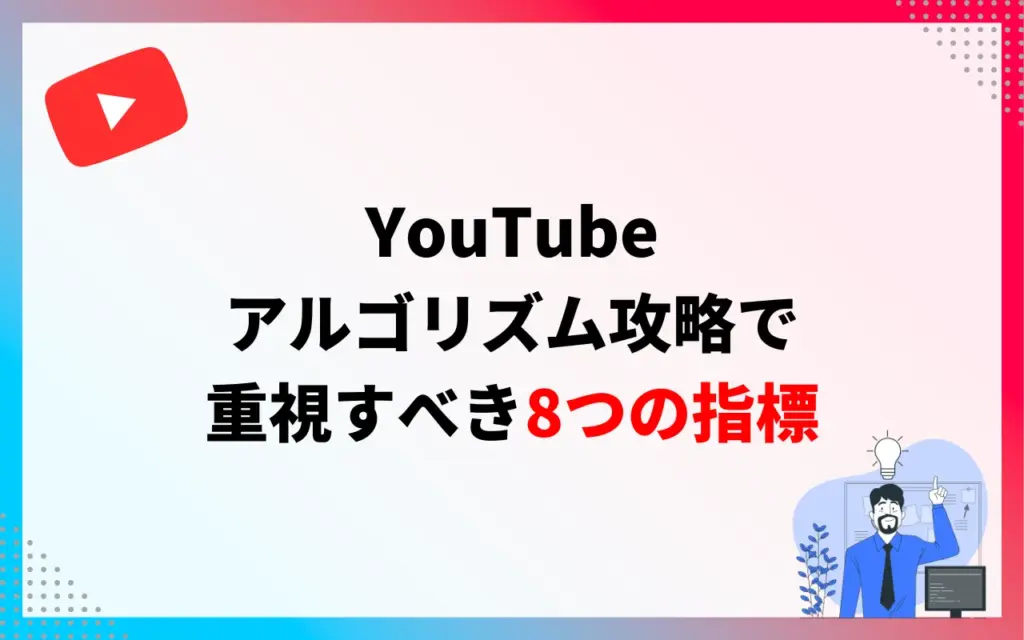
YouTubeの評価は単なる再生数だけでなく、多面的な指標に基づいています。
ここでは、チャンネル成長に欠かせない下記の重要な要素を8つ解説します。
- 動画の尺
- エンゲージメント
- 総再生時間
- クリック率
- 高評価数
- 視聴履歴・関連性
- 平均視聴時間
- キーワード
1. 動画の尺
動画の長さはアルゴリズムに影響を与える重要な要素です。
短すぎれば視聴時間が稼げず、長すぎれば離脱が増えるため、最適な長さを意識することが視聴維持率の改善につながります。
目的やジャンルに合わせて尺を調整すると、安定した評価を得やすいでしょう。
たとえば、基礎知識の解説やハウツー動画なら3~10分、エンタメ系のショート動画なら3分以内が目安です。
2. エンゲージメント
アルゴリズムは「視聴者がどれだけ関わったか」を重視します。
コメントやシェア、チャンネル登録といった行動は、動画の質を示す重要なシグナルです。
視聴者の反応を引き出すには、動画内で質問を投げかけたり、投票機能を使うのが効果的です。
例えば「次に見たいテーマは?」「役に立った部分は?」と問いかけると自然に反応が生まれ、アルゴリズム評価の向上につながります。
3. 総再生時間
総再生時間はYouTubeが重視する指標の一つで、長く視聴されるほど価値のある動画だと判断されます。
これを伸ばすには、シリーズ化や再生リストで複数動画をまとめる方法が有効です。
またエンドカードを設置し、関連動画へ誘導するのも効果的です。
視聴の流れを設計することで、自然と再生時間が積み上がり、アルゴリズムに好影響を与えます。
4. クリック率
クリック率は、動画が視聴されるかどうかを左右する最初の関門です。
内容が優れていてもクリックされなければ再生数は伸びません。
改善にはサムネイルとタイトルの工夫がポイントです。
たとえば、数字を取り入れる、ビフォーアフターを並べる、強い対比表現を使うと直感的に内容が伝わります。

5. 高評価数
高評価は「この動画が気に入られている」と示す明確なアルゴリズムの指標です。
増やす工夫としては、動画の最後で自然にアクションをお願いすることが効果的です。
たとえば「役に立ったら高評価をお願いします」や「続編が見たい方はいいねで教えてください」と伝えると視聴者が行動しやすいでしょう。
6. 視聴履歴・関連性
アルゴリズムは視聴者の履歴や興味とマッチするコンテンツを優先的に表示します。
つまり、過去の行動に基づき「次に見たい可能性が高い動画」が選ばれる仕組みです。
関連性を高めるには、説明欄やタグでテーマを整理する、関連動画から導線を設けるなどの工夫が有効といえます。

7. 平均視聴時間
平均視聴時間は「どこまで見てもらえたか」を示す重要な指標です。
途中離脱は、YouTubeアルゴリズムの評価が下がる原因になり得ます。
対策としては、冒頭のつかみの強化や結論の先出しなどの工夫が効果的です。
テンポの良い構成にすると最後まで見てもらいやすくなり、アルゴリズムにも好まれます。
視聴者を飽きさせない工夫を施すことが大切です。
8. キーワード
検索や関連動画に表示されるには、適切なキーワード設定が欠かせません。
タイトルや説明欄、タグに自然に盛り込むことで発見される確率が上がります。
特に「初心者向け」「2025年版」といった具体的な言葉を加えると、検索意図と合致しやすく効果的です。

YouTubeアルゴリズムに嫌われる理由と回避策
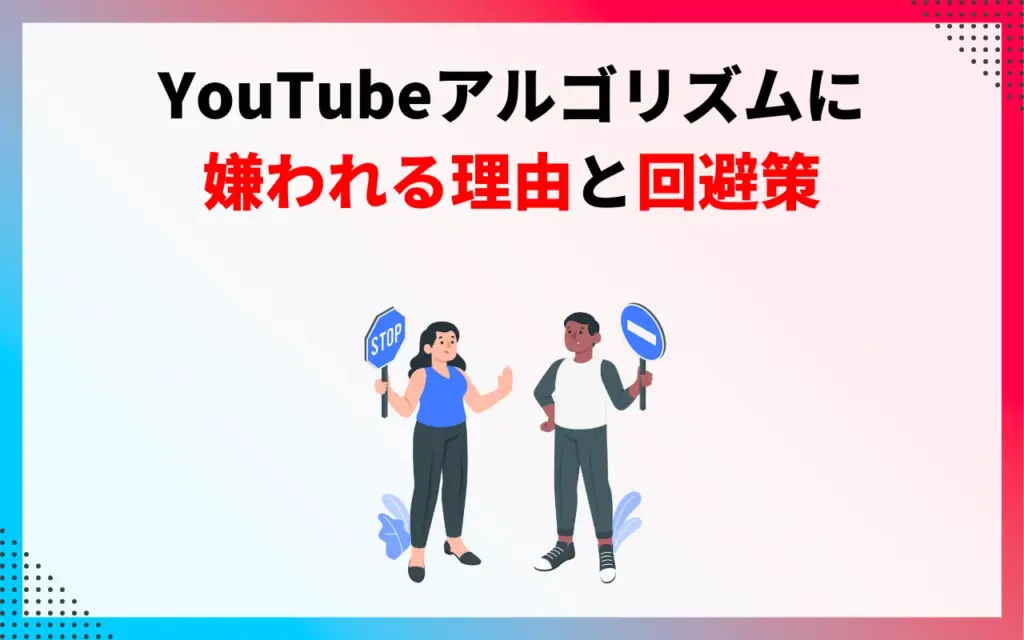
YouTubeでは、視聴者に不満を与える動画はアルゴリズム評価が下がります。
ここではアルゴリズムに嫌われる代表的な3つの理由と、それを避ける方法を解説します。
- 極端に低い視聴維持率
- クリックベイトや釣りサムネ
- スパム的なタグ・説明欄の使い方
1. 極端に低い視聴維持率
視聴維持率が著しく低いと、動画が魅力的でないと判断され、おすすめ表示回数が減少しやすいです。
冒頭部分で視聴者に「続きを見たい」と思わなければ、すぐに離脱されてしまいます。
改善には、冒頭のつかみでハイライトを見せたり、口頭で期待を持たせる説明をしたりといった対策が有効です。
2. クリックベイトや釣りサムネ
誇張したサムネイルや誤解を招くタイトルは、一時的にクリック率を高めても視聴者の離脱を招き、逆効果です。
視聴者の期待を裏切る動画は信頼を失い、アルゴリズムにも嫌われやすいといえます。
解決法としては、内容に即したタイトルを付け、誠実なビジュアルを使うよう心がけましょう。
3. スパム的なタグ・説明欄の使い方
無関係なキーワードや過剰なタグを説明欄に詰め込むと、スパムとみなされ評価が下がります。
視聴者の検索意図と一致しない内容は避けるべきです。
改善法としては、動画のテーマと直結するタグを使い、説明欄で要点を簡潔にまとめるとよいでしょう。
YouTubeアルゴリズムを最適化してチャンネルを伸ばす方法
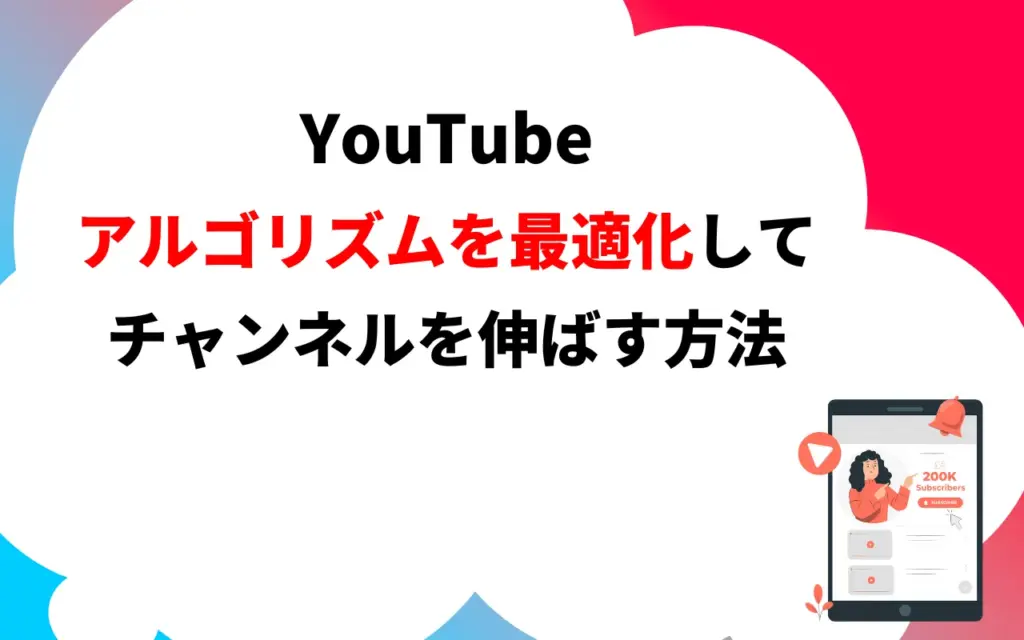
YouTubeで成果を出すには、アルゴリズムに沿った工夫が欠かせません。
ここでは以下の7つの最適化方法を解説します。
- 視聴維持率を高める構成と編集
- 魅力的なサムネイルとタイトルの作成
- 視聴者の興味に沿ったテーマを投稿する
- エンゲージメントを促す仕掛けを作る
- ショート動画も活用する
- 再生リストでテーマごとに分類する
- 分析データを活用して改善を繰り返す
これらを実践することで、動画がおすすめ表示される機会が増え、チャンネル成長を加速させられます。
1. 視聴維持率を高める構成と編集
視聴維持率が高い動画は、YouTubeから「良質」と判断され、おすすめ表示される可能性が高まります。
そのためには冒頭で結論を提示し、不要な部分を省き、テンポを意識した編集を心がけることが重要です。
改善の具体例は以下の通りです。
- 最初に見どころを提示する
- 冗長な説明をカットする
- 視覚的効果を活用する

2. 魅力的なサムネイルとタイトルの作成
クリック率は再生数を左右する重要な指標です。
サムネイルやタイトルが視聴者の興味を引けなければ、内容が良くても見てもらえません。
そこで第一印象を強化する工夫が必要です。
改善の具体例は以下の通りです。
- タイトルに数字を入れる(例:おすすめ5選)
- ビフォーアフターを並べる
- 感情に響く言葉を入れる
クリックしたくなる仕掛けを整えることで、再生数を大きく伸ばせます。
3. 視聴者の興味に沿ったテーマを投稿する
YouTubeは視聴履歴をもとに関連性の高い動画を表示します。
ターゲットの興味を捉えたテーマを投稿することで、アルゴリズムにもよい影響をもたらします。
工夫の具体例は以下の通りです。
- トレンドや話題を取り入れる
- 視聴者アンケートでテーマを決める
- 競合動画からヒントを得る
視聴者の関心と合致したテーマほど、視聴維持率やエンゲージメントが高まります。
4. エンゲージメントを促す仕掛けを作る
コメントや高評価、シェアなどのエンゲージメントは、アルゴリズムからの評価を高める重要な要素です。
自然に参加したくなる仕組みを作ることが大切です。
仕掛けの具体例は以下の通りです。
- 動画内で質問を投げかける
- エンドカードで次の行動を促す
- 投票機能やスタンプを活用する

5. ショート動画も活用する
ショート動画は新規視聴者の獲得に有効で、アルゴリズム上の表示機会が増えやすい形式です。
短尺ならではの特性を活かし、認知拡大のきっかけにしましょう。
活用法の具体例は以下の通りです。
- 長尺動画の要点を切り抜く
- トレンド音源に合わせて作る
- トレンドネタを取り扱う
ショートと長尺を併用すると、幅広い層にリーチできます。
6. 再生リストでテーマごとに分類する
再生リストを使うと視聴者が複数動画を続けて見やすくなり、総再生時間を伸ばせます。
整理次第で、アルゴリズムにも好影響を与えられます。
工夫の具体例は以下の通りです。
- テーマやシリーズごとに分類する
- 視聴順序を意識して並べる
- 関連動画をまとめて導線を作る
視聴者が迷わず次に進める仕組みを作れば、離脱防止と評価向上につながります。
7. 分析データを活用して改善を繰り返す
YouTube Studioの分析データは、チャンネル運営の改善点を明確にする羅針盤です。
数値をもとに課題を把握し、改善を重ねることが評価の安定化につながります。
注目すべき項目は以下の通りです。
- クリック率で興味の度合いを測る
- 視聴維持率で離脱ポイントを把握する
- エンゲージメント率で関心度を確認する

YouTubeアルゴリズムに関するよくある質問(FAQ)
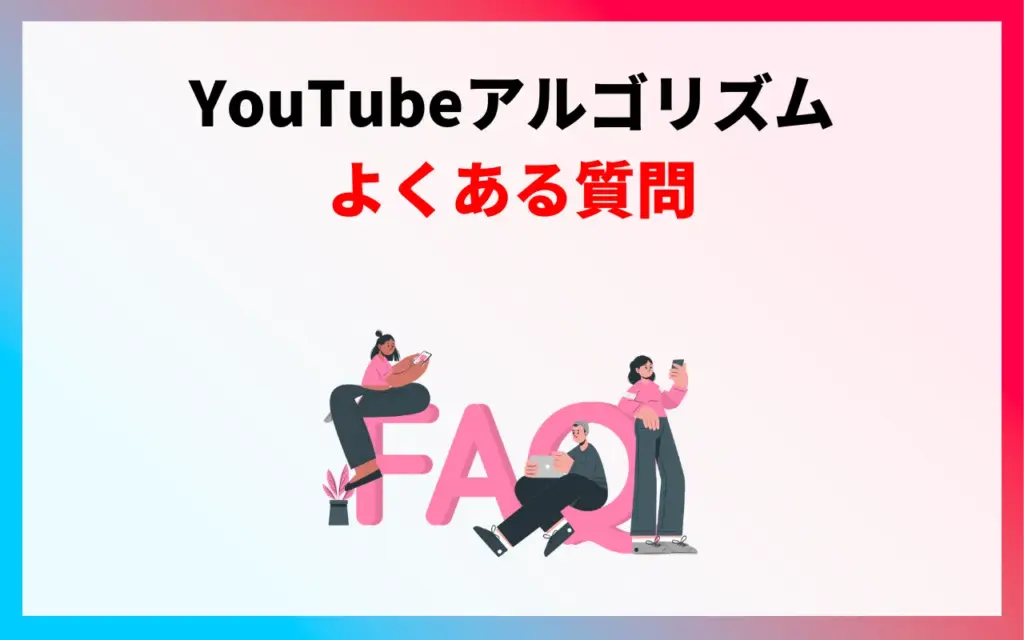
アルゴリズムは公開されていない部分も多く、正しく捉えるのが容易ではない分野です。
ここでは、よくある疑問を簡潔に解説します。
Q.1 サムネイルの文字はアルゴリズム評価に影響しますか?
サムネイル内の文字そのものはアルゴリズムに直接影響しませんが、クリック率を上げる効果があります。
その結果、再生数や視聴者との接触機会が増え、アルゴリズム評価にも間接的に良い影響を与えます。
Q.2 広告を多く入れるとアルゴリズム評価に影響しますか?
広告の本数自体は評価に影響しません。
しかし、視聴維持率を下げるような配置や頻度だと、結果的にアルゴリズムからの評価が下がるリスクがあります。
Q.3 プレミア公開はおすすめ表示に有利ですか?
プレミア公開そのものが優遇されるわけではありませんが、チャット参加や同時視聴による初期のエンゲージメントが高くなると、その反応がアルゴリズムに好影響を与える可能性があります。
Q.4 古い動画はアルゴリズムで不利になりますか?
古い動画が自動で不利になることはありません。
ただし、削除するとチャンネル全体の過去データも影響を受けるため、表示や推薦に悪影響を及ぼす場合があります。
Q.5 外部SNSからの流入は評価されますか?
外部からの流入はアルゴリズムにプラスの影響を与えます。
特に公開初期に視聴やエンゲージメントが増えると、YouTubeがその動画を価値あるものと認識しやすくなるでしょう。
まとめ
YouTubeアルゴリズムの仕組みや最新の傾向、評価指標や最適化の方法などを解説しました。
今回の内容をまとめると、以下のとおりです。
- アルゴリズムは視聴者の行動や満足度を重視して表示を決定する
- ショート動画やパーソナライズの強化などが最新の傾向
- 投稿頻度や視聴維持率などは評価に直結する重要な指標
- 不適切なサムネや低いエンゲージメントはアルゴリズムから嫌われる原因に
- データ分析や再生リスト活用などでチャンネル成長を加速させる
アルゴリズムの理解と運用の工夫を両立させ、YouTubeの成果につなげていきましょう。
YouTubeの運用事例
最後に、株式会社pamxyが実際に行ったYouTubeアカウントの運用事例をご紹介します。
- ナイツ塙の自由時間
- 腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】
ナイツ塙の自由時間

ナイツ塙氏のチャンネルでは「自由時間」の名前の通り幅広い企画を行っています。
弊社では、チャンネル運用・ディレクション・撮影・データ分析までを一貫して提供。
テレビやラジオなど、従来メディアの枠にとらわれず、自由気ままなコンテンツ制作や芸能人コラボ企画を展開しています。
M-1の裏側を語った動画は公開1日で20万回を超える再生数を叩き出し、YouTube急上昇動画7位にランクインしました。
腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】

山内義弘様からはチャンネル登録者3500名の段階でご相談をいただきました。
実際に自社でYouTube運用をしてきた累計登録者数200万人超えのノウハウをもとに、独自の世界観を企画してあらたに「セルフ整体」動画を配信いたしました。
チャンネル設計・構成制作・動画編集・実配信まで一通りご支援の結果、運用開始一ヶ月でチャンネル登録者10万人を達成しました。
中でも肩甲骨はがしの動画は、590万回超の視聴回数を誇る現在でも人気の動画です。
【先着10社/月】無料相談受付中 ︎
︎
株式会社pamxyのYouTube運用代行

累計登録者200万人超え自社チャンネルで培った、売上につながるYouTube運営のノウハウを存分に活用したYouTube運用代行サービスです。
下記のようなお悩みがある場合はお気軽にご相談ください。
- YouTubeを始めたいが、自社内にノウハウやリソースがない
- ただ再生数を稼ぐのではなく、自社の売上につながる運用をしたい
- 視聴者とより濃密な関係を構築したい
ぜひお気軽に下記フォームよりお申し込みください。
まずは無料WEB会議にて、YouTube活用のメリットや同業界の成功事例についてお伝えします。
window.hsFormsOnReady = window.hsFormsOnReady || [];
window.hsFormsOnReady.push(()=>{
hbspt.forms.create({
portalId: 8538486,
formId: “fb7ec51a-d237-42a1-a161-626957a76d55”,
target: “#hbspt-form-1758549261000-5007278436”,
region: “”,
})});
The post 【2025年最新版】YouTubeアルゴリズムの仕組みを解説! first appeared on マーケドリブン.
Copyright © 2025 マーケドリブン All Rights Reserved.
Views: 6

 ︎
︎