🧠 概要:
概要
この記事では伊藤ハム米久ホールディングス(2296)の株について分析が行われており、同社が高配当株として注目されている理由や財務状況、経済環境の影響を探っています。特に、連続増配と高利回りが強調されつつも、原材料高や利益率の低下リスクにも言及されています。
要約の箇条書き
- 企業概要: 伊藤ハム米久は食肉加工品の大手企業、時価総額約2,844億円、配当利回りは6.46%。
- 経済動向: トランプ関税による影響は限定的だが、輸入原材料価格上昇が懸念される。
- 直近決算: 2025年の決算は増収も減益、EPSは230.87円、2026年は年間320円の配当予定。
- 配当の推移: 配当利回りは右肩上がりで、2026年は記念配当を含む高水準。
- 株価状況: 現在の株価は4,950円、配当利回りは6.46%、安全圏として4,500円割れでの購入を推奨。
- 同業他社比較: 伊藤ハム米久は同業の日本ハム、丸大食品と比較して高利回りが特徴だが、利益率が低い。
- 財務評価: 自己資本比率61%、安定したキャッシュフローも示されるが、配当急増による流動性リスクあり。
- 総合評価: 総合評価は★★★☆☆(3.4)、配当は魅力だが特別配当後の水準に注意。
- まとめ: 利益率改善シナリオが望まれるが、株価4,500円以下での投資を推奨し、過度な集中投資は回避するべき。
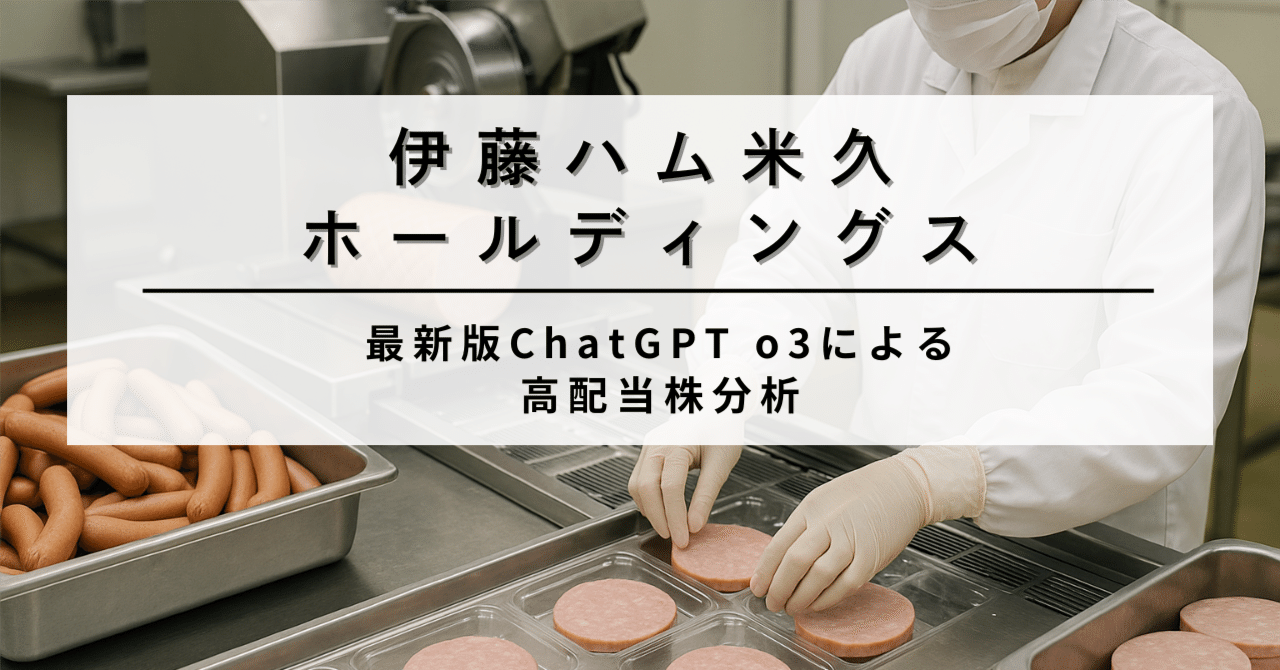
本記事は 「ChatGPT o3モデル(有償版向け限定で2025年4月リリース)」 による自動生成レポートです。読者のみなさまは必ず一次情報をご確認ください。特にグラフはAIの制約上、表示崩れが起こる場合があります。
作成日:2025年5月25日
目次
-
企業概要
-
直近の経済動向(トランプ関税など)の影響
-
直近決算のポイント
-
一株あたりの純利益(EPS)の推移
-
配当利回りの推移
-
一株あたり配当金の推移
-
配当性向の推移
-
株価チャートと足元の評価
-
同業他社との比較
-
財務状況の評価
-
総合評価
-
まとめ
1. 企業概要
伊藤ハム米久ホールディングス(以下、伊藤ハム米久)はハム・ソーセージをはじめとする食肉加工品の最大手グループの一角です。現在の時価総額は約2,844億円、予想PERは16.05倍で同業平均(食料品セクター:17~20倍)よりやや割安です。配当利回りは6.46% と4%を大きく上回り、連続増配も6期目に突入しました。国内でのブランド力に支えられる一方、海外シフトで利益率向上を図っています。ハム、ソーセージなど「嗜好品寄りの必需財」を主力に持つため景気変動にも比較的強い点が特徴です。
2. 直近の経済動向(トランプ関税など)の影響
4月上旬に発表された「相互関税」政策(いわゆる トランプ関税)では、日本産農水産物に平均24%の追加関税が課される可能性が浮上しています。食品輸入商社は輸出タイミングの見直しや価格交渉を急ぎ、国内メーカーも米国向けアイテムの組成変更を検討するなど、業界全体が様子見状態です。伊藤ハム米久は北米拠点を保有せず、米州向け売上比率は約3%にとどまるため直接打撃は限定的ですが、輸入原材料(豚肉・牛肉)価格の上振れリスク が懸念されます。企業側は「為替ヘッジと値上げで吸収可」とのスタンスを示していますが、短期的なコスト圧力は無視できません。 ジェトロ futokoro.san-yu.co.jp
3. 直近決算のポイント
2025年3月期(通期)決算は、売上高9,887.7億円(前年比+3.5%)と増収ながら、原材料高を吸収し切れず営業利益195.8億円(同▲12.4%)・純利益131.0億円(同▲15.8%)と減益。EPSは230.87円 に低下しました。一方、2026年3月期は記念配当を含む年間320円を計画し、増収増益シナリオを提示しています。 IR BANK Yahoo!ファイナンス
一株あたりの純利益(EPS)の推移
図1 一株あたりの純利益(EPS)の推移
伊藤ハム米久のEPSは2019年に一旦179円まで落ち込みましたが、2021年に343円へ急回復。その後は物流費や飼料価格の高止まりで前年比マイナスが続き、2025年には230円台へ再び減速しています。2026年は統合10周年記念関連の一時費用が消える見込みで、会社計画は308円へ+33%の反発。ただし飼料・電力コストの不透明感を踏まえると、保守的に見たほうが安全と言えるでしょう。
配当利回りの推移
 図2 配当利回りの推移
図2 配当利回りの推移
配当利回りは2017年の1.6%から右肩上がりに上昇し、足元では3.4~3.6% を維持してきました。さらに記念配当込みの2026年計画ベースでは6.46% と高水準です。株価が過度に上昇しなければ6%超えが続く可能性がありますが、特別配当要素が剥落する2027年以降は平常時水準(3.5%前後)へ戻る点には留意が必要です。高配当を安定的に享受するには「利回り5%台後半以上での逆張り」が望ましい戦略でしょう。
一株あたり配当金の推移
 図3 一株あたり配当金の推移
図3 一株あたり配当金の推移
配当金は2017~2020年の85円据え置き期間を経て、2021年以降は連続増配に転じました。特に2025年145円 → 2026年320円 という大幅増配は記念配当170円を含む特殊要因です。普通配当ベースでは年間150円程度がコアレンジであり、これでも配当性向45~50%と同社方針(DOE3%+累進)には沿っています。したがって、2027年以降は正常化しても減配リスクは相対的に小さい と考えます。
配当性向の推移
 図4 配当性向の推移
図4 配当性向の推移
配当性向は2019年に47%、2020年に44%と高止まりしましたが、2021年には31%まで改善。その後再び上昇し2025年には62.8% と過去最高水準です。記念配当を含める2026年も60%超が想定されます。累進配当方針を掲げる一方、DOE3%を上回る水準までは無理をしない堅実な資本政策と見てよいでしょう。
8. 株価チャートと足元の評価
5月23日時点の株価は4,950円。予想配当320円を利回り換算すると6.46%、普通配当150円ベースでも3.0%台半ばです。短期的な記念配当プレミアムが株価に織り込まれる可能性が高く、初心者が追随買いする場合は4,500円割れ(利回り7%以上)を待つ のが安全圏と判断します。
9. 同業他社との比較
主要同業の日本ハム(2282、利回り2.4%)、丸大食品(2288、2.5%)と比べると、伊藤ハム米久の配当利回りと累進姿勢は突出しています。営業利益率では日本ハム4%、丸大2%に対し、伊藤ハム米久は2%前後とまだ低水準。利益率改善余地が残る一方で原価高の影響を受けやすい脆弱さも抱える ため、高利回りはある種のリスクプレミアムと見るのが妥当です。 IR BANK
10. 財務状況の評価
自己資本比率は約61%、有利子負債比率は20.8%と保守的。キャッシュフローは営業CFの8~9割を設備投資・配当に回しており、フリーCFはプラス圏を維持。ただし記念配当で配当支払いが110億円→320億円規模に急増すると、手元流動性が目減りするリスクはあるため、追加的な借入や社債発行に備えた枠は確認しておきたいところです。
11. 総合評価

総合評価:★★★☆☆(3.4)
高利回りが魅力だが、記念配当後の水準に注意。初心者は株価が下落し通常利回り5%台を確保できる局面での買い下がりを推奨。
12. まとめ
伊藤ハム米久ホールディングスは、国内ハム・ソーセージ市場で高いブランド力を誇り、連続増配と記念配当で利回り6%超を提示しています。もっとも営業利益率は同業比で低めであり、原材料高が長期化すると利益水準が揺らぐリスクは否定できません。特別配当剥落後の平常利回りは3~4%レンジと想定されるため、配当狙いなら株価4,500円以下での仕込み が安全域です。将来の利益率改善シナリオが実現すれば、累進配当と合わせて長期複利が期待できますが、初心者は過度な資金集中を避け、分散投資の一角として検討することを強く推奨します。
この記事は特定の銘柄の売買を推奨するものではございません。投資は自己責任でお願いいたします。
Views: 2

