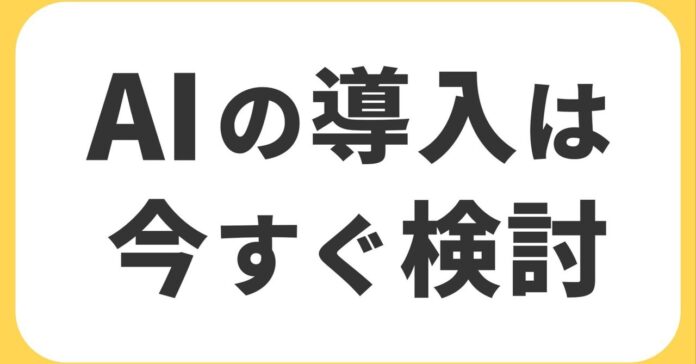🧠 概要:
この記事は、相談支援専門員がAIを活用する重要性について語り、新しい技術を早めに取り入れることで得られる価値を強調しています。AIが一般的になる前に、どのように業務に取り入れていくべきかを考えています。
### 概要
– AIが急速に進化している現状を踏まえ、相談支援専門員におけるAI導入の必要性を説いています。
– 特にAIによって生まれる“空いた時間”を、どのように人間にしかできない価値ある活動に使うかがポイントです。
### 要約の箇条書き
– AIの進化が目覚ましく、近い将来職場における当たり前の存在になる。
– 「いつかAIを使えるようになるから」とのんびり構えるのは危険。
– AIは事務作業の効率化をもたらし、その時間を利用者との関係構築に注ぐことができる。
– 空いた時間を使って心のこもったコミュニケーションや細やかな対応が可能になる。
– AIを業務に積極的に取り入れる早さが、サービスの質を大きく左右する。
– AIの活用は、障害福祉業界でも「本当の価値」を提供するための重要なステップである。
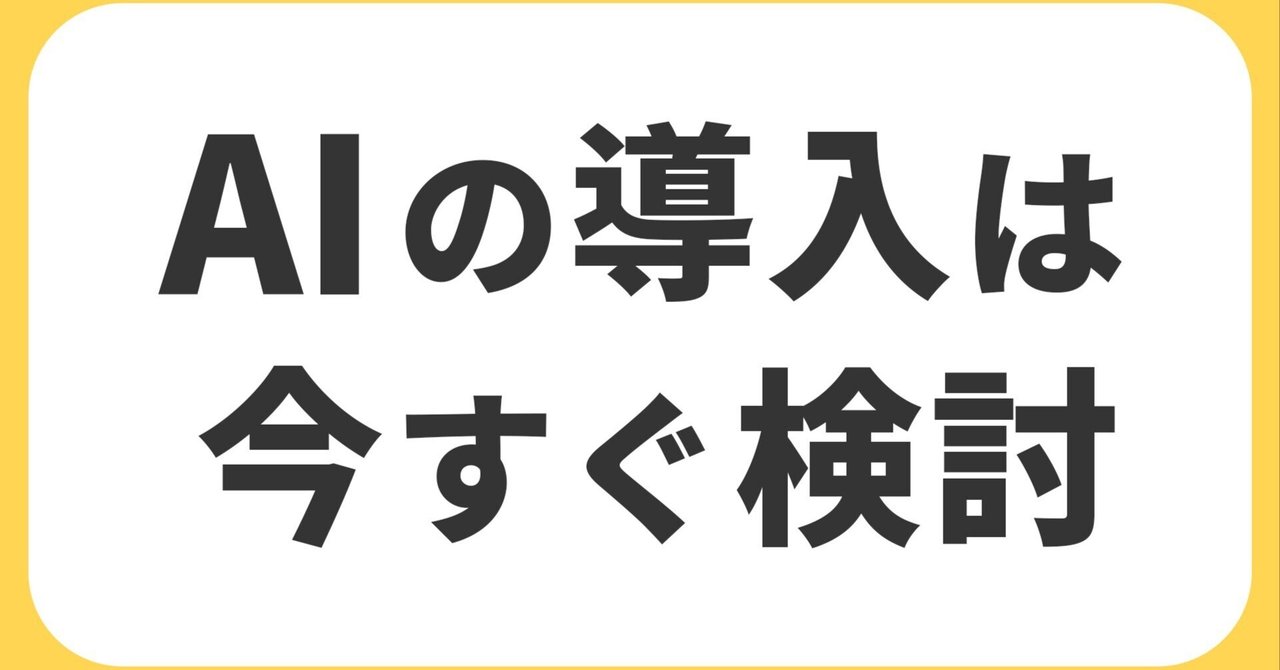
そうなると、中にはこう思う人もいるかもしれません。
「どうせAIがみんなに行き渡って、誰でも簡単に使えるようになるんでしょ?だったら、その時になってから取り入れればいいんじゃないの?」って。
その気持ち、すごくよく分かります。新しい技術って、覚えるのもちょっと面倒だったりしますしね。
それに、今やってる仕事だけでも手一杯で新しいことになんて手が回らないって方も多いんじゃないでしょうか。
それに、「AIが入ってきたら今の仕事がなくなっちゃうかも…」なんて聞くと、ちょっと不安になったりするのも無理ないことだと思います。
でも、ちょっと考えてほしいんです。本当にAIが当たり前になるときまで、今の働き方のまま待っていていいんでしょうか。
僕が思うに、AIが当たり前になる時代に大事なことって「うまくAIを使えるようになる」とか「仕事が楽にできるようになる」とか、そういう話じゃなくなってくると思うんです。
AIで「時間が生まれる」ってどういうこと?
じゃあ、何が大事なの?っていうと、僕が注目しているのは「AIによって生まれた“空いた時間”をどう使うのか?」っていう視点なんです。
例えば、今まで毎日2時間かけていた書類作成があったとします。
それが、AIを活用することでなんと30分で終わっちゃった!みたいな。
こうなると「いきなり1時間半も時間が浮いちゃった!さて、どうしよう?」ってなりますよね。
今、AIに積極的に触れている人たちって、実はこういう「自分の手が空く」っていう体験を、結構してるんですよね。
だから、そういう人たちにとっては、単に「作業を時間内に終わらせること」とか「書類をきっちり作ること」っていう作業そのものには、もうあんまり価値を感じなくなってきてるんです。
だって、それはAIがかなりの部分を手伝ってくれるから。
「空いた時間」でできる、人にしかできないことって?
じゃあ、そのAIが生み出してくれた「空いた時間」で、僕たちは何ができるようになるんでしょうか。
ここが、すっごく大事なポイントだと思うんです。
例えば、相談支援専門員さんを始めとして、障害福祉に関わる方だったら、こんなことができるようになるかもしれません。
まずは、利用者さんから相談の連絡が来た時に、すぐにお返事ができる。「あとで確認して連絡しますね」とついついなってしまいがちなことだけど、その場で悩みを聞いてあげられる。時間に追われなくなることで、いつでも余裕を持った対応ができるようになる。
些細なことですけど、感じる安心感は全然違うと思います。
利用者さんと電話しているときも「作らなきゃいけない書類残ってるし、時間が伸びたら残業しないといけなくなるかな……」なんてよぎってしまうと、どこか急いで切り上げちゃう気持ちがあったかもしれません。
でも、相手の方が「うん、しっかり話せて満足したな」って思えるまで、じっくり耳を傾けられるようになる。
アセスメントやモニタリングの時も、議事録の作成はAIがしてくれるので、パソコンでカタカタとメモしながら話す必要がなくなるかもしれません。
パソコンは横に置いておいて、ちゃんと利用者さんの目を見て、表情を感じながらお話を進められる。
ふとした時に「あ、そういえば〇〇さん新しい施設行ってから少し経つから、ちょっと連絡してみようかな」って、気軽に声をかけられるようになる。
こういう細やかな気遣いの支援って、忙しいとつい後回しになりがちですけど、すごく大切ですよね。
こういうのって、どれもAIが直接やってくれるわけじゃないんです。
でも、AIが時間を作ってくれるからこそ、もっとこういう「温かい配慮」や「心のこもったコミュニケーション」に時間を使えるようになる。
これこそが、AIが当たり前になった時代に、僕たち人間が提供できる「本当の価値」になっていくんじゃないかなって、僕は考えています。
利用者さんが本当に求めているのって、完璧な書類よりも、親身になって話を聞いてくれる支援者の存在だったりしますもんね。
「いつか」じゃなくて「今」考える理由
ここまでのお話でなんとなくイメージが付いたかと思います。
「どうせAIがみんな使えるようになるんでしょ?その時でいいや」ってのんびり構えているのと、「今のうちからAIに触れてみて、時間を作る練習をしておこう。そして、その時間で自分にしかできないことって何だろう?」って考え始めるのとでは、数年後、支援の仕方一つとっても、たぶん雲泥の差が生まれてると思うんです。
毎日、書類作成や事務作業、会議の議事録を作るのに追われているAさんと。
そういう作業はAIに上手に手伝ってもらいながら、利用者さんが本当に必要としているサポートにたっぷり時間をかけているBさん。
どちらの支援者さんが、利用者さんにとってより心強い存在かは、きっと言うまでもないですよね。
まだ世の中全体が、「完全にAIに仕事任せてます!」っていう状態ではないです。
だからこそ、「今」、AIを自分の仕事に取り入れて、業務のやり方を見直してみるっていうのは、次の時代でも「本当に価値のある支援を利用者さんに届け続ける」ために、すごく意味のある一歩になるんじゃないでしょうか。
「もうちょっと落ち着いてから考えようかな…」なんて思っているうちに、AIが当たり前になる時代って、案外あっという間に来ちゃうかもしれません。
というわけで、AIを先に先に取り入れて準備しておくことは、障害福祉業界でも結構大事な動きになるんじゃないかな、というお話でした。
実は僕自身、計画相談支援事業所・就労支援事業所向けに業務効率化のお手伝い・AIを活用したシステムのご提案をする仕事をしております!
もし、この記事を読んでみて、「うちの事業所でも、書類仕事とか、もっとAIで減らせる部分があるのかな?」と少しでもご興味持っていただけたら、お気軽に僕のTwitterのDMにメッセージください!
まずは情報交換からでも大丈夫ですので、ぜひ一度、お話できたら嬉しいです!
ここまで読んでくださったみなさん、ありがとうございました!
そして今回も追加記事を書いてみました。
この先は、じゃあそのAIによって「作られた時間」を使って、僕たちはどういう風に自分の価値を高めていけるのか?AIとどうやって「協力」していくのか?という部分に、 もう少しだけ突っ込んだお話をしています。
この記事をTwitterでシェアしていただけると続きも無料で読むことができますので、ぜひよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
Views: 0