🧠 概要:
概要
田窪哲旨氏は、演劇が「むずかしい」とされる理由を考察し、他の芸術形式と比較しながら、教育や情報の提供が不十分であることを指摘しています。演劇が観客にとって理解しにくいものであるのは、学校教育や体験の機会が限られていることに起因し、結果として選択肢が制限され、初めて観る人が感じるハードルが高くなると述べています。
要約の箇条書き
-
演劇が「むずかしい」とされる背景:
- 他の芸術に比べ、演劇が難解であるとされる傾向が強い。
-
教育の欠如:
- 演劇は学校教育で扱われる機会が少ないため、基礎知識が不足している。
-
体験の少なさ:
- 演劇を観る機会が限られており、多くの人が初めて演劇に触れる際に戸惑う。
-
情報の不十分さ:
- 演劇に関する事前情報が少なく、自分に合った作品を見つけにくい。
-
地域差:
- 特に東京以外では演劇の選択肢が少なく、アクセスが難しい。
-
マーケティングの課題:
- 演劇の市場原理に基づくマーケティング戦略が難しく、観客にとっての選択肢が狭まる。
-
「当たりはずれ」の多さ:
- 演劇は、他の芸術と比べて「当たりはずれ」が多いと感じる人が多いが、観劇経験を重ねることで良い作品と出会える可能性がある。
- 失敗を楽しむ精神:
- 演劇の観賞を通じて失敗を恐れず、多くの作品に触れることを促進することが重要。
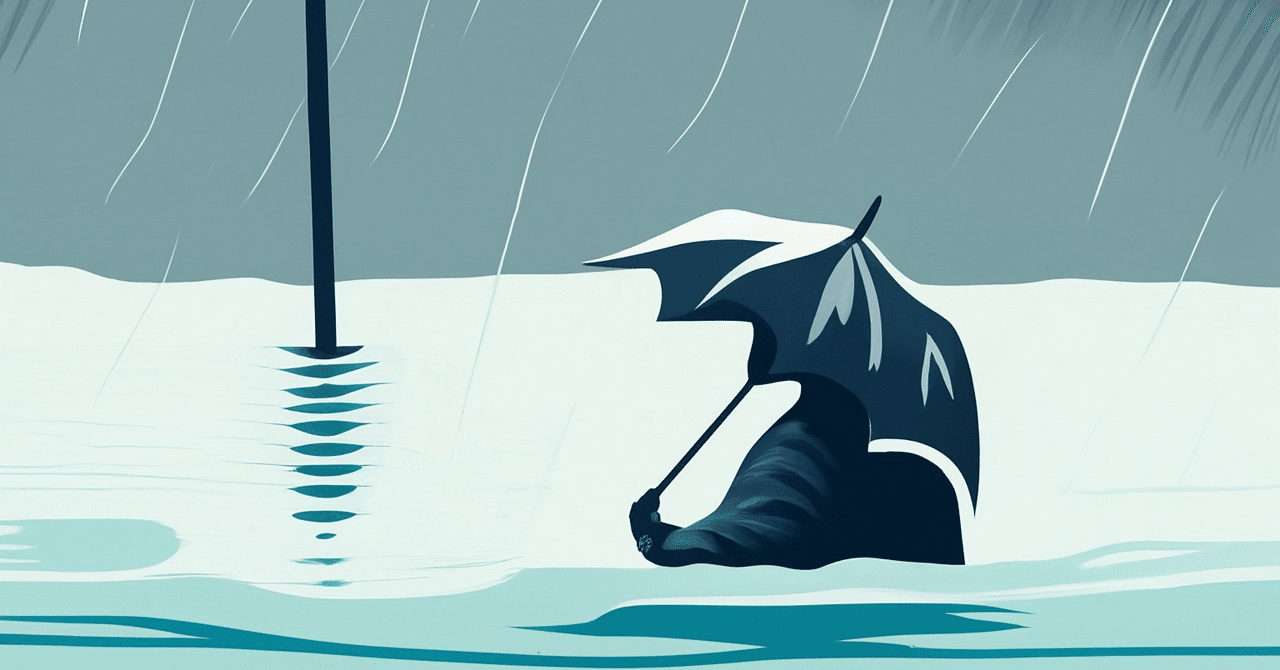
「演劇はむずかしいから(私は興味がない)」という言葉をよく聞いてきました。また、それとは逆に、観劇後の感想などで、「今回の舞台はわかりやすくてよかった」といった言葉もよく聞いてきました。 そのたびに、そういうことを言う、言いたくなる方々の気持ちも理解しつつ、それでも「むずかしいって何?」「わかりやすいって何?」という反問というか、煩悶を抱えてきました(笑)。 どうして演劇は「むずかしい」とか「わかりやすい」という物差しでその良し悪しが判断されることが多いのでしょう。 一方、おなじ芸術でも、「小説はむずかしいから」「映画はむずかしいから」「音楽は…」「美術は…」という言葉は、演劇に比べるとあまり聞かないような気がします。でも、小説にも、映画にも、音楽にも、美術にも、その人にとってむずかしい作品、逆にわかりやすい作品があるはずです。 では、「むずかしい」といわせてしまう演劇と、文学や音楽、美術や映像など、他の芸術ジャンルとのちがいは何なのか、考えてみたいと思います。
① 学校の授業で習っていないから、演劇に慣れていない。
小説や詩、随筆などの文学は国語の授業で習います。音楽の授業でも、指導要領でクラシック音楽だけでなく、日本の伝統音楽やポピュラーミュージック、世界の民族音楽に触れてみたり、自分たちで演奏したり合唱したりといった体験ができることになっています。美術の授業では、絵画や彫刻、工芸、伝統美術、デザインなどの鑑賞・創作活動を体験します。そしてそのための時間が、少ないながら1年を通して確保されています。 しかし小中学校に通年の演劇の授業はありません。 そのため、子どもたちが学校で演劇を体験できるのは、芸術鑑賞会や体験授業になってきます。しかし文化庁の調査(令和5年度 文化芸術による子供育成推進事業に関する調査研究 報告書)によると、令和5年度に芸術の鑑賞または体験機会をもった小中学校の割合は63.5%。そのうち演劇分野(音楽劇や児童劇、ミュージカル、歌舞伎・能・狂言・人形浄瑠璃等の伝統芸能含む)が占めるのは39.6%。このデータをかけあわせると、令和5年度、学校で演劇等に1回でもふれることができたのは、約25%の子どもたちだけということです。 多くの人々が子ども時代に学校で習っていない、鑑賞・体験機会がないわけですから、いきなり演劇に出会ってもその接し方、楽しみ方がよくわからない、というのは仕方ないと思います。
② 学校の授業で習っていないから、他の芸術ではもっている基礎知識がない。
クラシック音楽に興味のない人でも、世界的な作曲家の名前を何人かあげることができると思います。ベートーベン、シューベルト、モーツァルト、バッハ、ショパン、チャイコフスキー、ドビュッシー…。私が通っていた中学校の音楽室には、彼らの肖像画が飾ってあったのをおぼろげに覚えています(たぶん髪型のめずらしさが印象に残っているのでしょう)。そして彼らの代表曲を音楽室で聴いた記憶があります。 音楽室といえば、もうひとつ覚えているのが、音楽の先生が、冨田勲さんのシンセサイザー音楽を聴かせてくれたことです。これまで音楽室ではクラシック音楽を聴き、合唱曲や当時のフォークソングを歌ったりしていたのが、まったく未知の、でも私にとっては衝撃的な音楽、こんな音楽もあるのか、と中学生の私が目を開かされた体験で、今もその時の衝撃は思い出せます。 話は戻りますが、では世界的な劇作家の名前を何人あげることができるでしょう。クラシック音楽に興味のない人があげられるであろう作曲家の人数と、演劇に興味のない人があげられる劇作家の数はどちらが多いでしょうか? 明らかなデータはありませんが、私は劇作家の方が少ないと思います。なぜなら学校の授業で、音楽のように演劇を習っていないからです。 ウィリアム・シェイクスピア、サミュエル・ベケット、ニール・サイモン。活躍した時代も国も異なりますが、いずれも世界的な劇作家です。 例えば「初めて演劇を観るんだけど、この3人の作品の中だったらどれがいい?」ときかれたとします。その人の志向や趣味を全く知らない場合、そして私と同年代の人だった場合、私はニール・サイモンを勧めると思います。シェイクスピアも作品や出演者によってはアリだと思いますが、おそらくベケットは勧めません。 でもこの3人のうち、私が自分の演劇体験のなかでいちばん衝撃を受けたのは実はベケットなのですが。 小説には様々なジャンルがあります。推理小説、恋愛小説、歴史小説、SF小説…。 推理小説の中だけでも様々にジャンル分けされます。江戸時代を舞台にした「捕り物帖」から現代の国内外を舞台にした警察小説、シャーロック・ホームズや明智小五郎が活躍する探偵小説、社会問題に深く切り込むものから恋愛を題材にしたものなどなど。 書店やネットで購入したり、図書館で借りたりするとき、読者はその本がどのような内容の本なのか、把握したうえで手にします。歴史小説を読みたかったのにSF小説だった、ということはあまりないかと思います。それは、その小説がどんな小説なのか、文庫本なら裏表紙に書いてありますし、amazonの紹介文にも詳しく書いてあります。口コミもあります。それ以前に、どんなジャンルの小説があって、今、自分がどんな小説を読みたいのかを、読者本人がわかっているからです。そして書店や図書館、amazonには膨大な選択肢があります。 演劇には、どんなジャンルの演劇があって、今、自分がどんな演劇を観たいのか、そしてどんな作品を選んで観ることができるのか、最初はわかりにくいと思います。わからないままに自分の趣味じゃないもの、気軽に楽しみたいのに重いテーマを扱ったものなどに出会ってしまい、演劇はわからない、演劇は好きな人だけのもの、演劇は自分とは無縁だ、となってしまうことが多いのではないかと思います。 先ほどのベケットの代表作『ゴドーを待ちながら』は、二人の男がゴドーという人物をただ待っているだけで何も起こらない、起承転結のない作品です。でもそこに人生の不安感や人間の存在、神の存在について考えさせられる、不条理演劇といわれるジャンルの世界的代表作です。 しかし、有名な作品、評価されている作品だからといって、気楽に楽しむつもりで初めて劇場へ行って出会った作品が、この『ゴドーを待ちながら』だとしたら、「演劇はわからない」「演劇は好きな人だけのもの」と言われても仕方ないと思います。
③ 選択肢が少ない。特に東京以外では。
「CoRich舞台芸術!」という、全国で開催される演劇やミュージカルの口コミやチケット情報を掲載しているサイトがあります。このサイトで、原稿執筆日時(2025年3月29日土曜日)に、当日上演される公演数を都道府県別に数えてみたのが以下の順位です(その日に公演があるかないかを数えています。なので1日2回上演するものも1公演として数えています)。1位72公演:東京都 2位17公演:大阪府 3位6公演:京都府・兵庫県 5位5公演:神奈川県・福岡県 7位4公演:愛知県 8位2公演:北海道・長野県・香川県 11位1公演:宮城県・千葉県・福井県・三重県・沖縄県 まずことわっておきたいのが、2025年3月29日(土)という1年のうちのある週末の1日を切り取ったデータであること。そして当然、「CoRich舞台芸術!」には日本で行われているすべての演劇公演が網羅されているわけではないということです。 しかしながら、このサイトへの登録は無料であり、『ハリー・ポッター』から数十人しか入らない小さな空間で催される公演まで等しくフォローされていること、週末の土曜日なので、ロングランが難しい週末だけ実施される小規模な公演や、地方の文化会館等で実施される公演も、平日よりは含まれてくるのではないか、ということを考えると、ある程度の傾向は読み取れるのではないかと思います。 このデータから読み取れるのは、東京の、または東京の劇場へ行ける近隣地域の人が、この土曜日に演劇を観たいがどの作品にしよう、と考えた時に、最低でも72の選択肢があるのに対し、大阪では4分の1以下、他の地域ではそれよりももっと少なくなってしまう、ということです。 日本の人口は2024年10月現在では、約1億2千万人。東京都の人口はその11%強、約1千4百万人です。しかし、上のデータでは、全国で半分以上の公演が東京都内で行われているのです。(この、演劇はじめ文化芸術の東京一極集中については別に述べます) 居住地にかかわらず、小説なら書店やオンラインで、映画ならシネマコンプレックス(複数のスクリーンをもつ映画館)などで、好みの作品を選ぶことができます(実は映画も、人口あたりのスクリーン数では、都道府県間に大きな差があります)。 ですが、演劇には選択肢が圧倒的に少ないのです、東京や大都市圏以外では。 好きなものを選べない、ということは、生活の中で演劇を楽しむということを根付かせることは困難である、ということになってしまいます。 つまり「演劇はむずかしい」と多くの人にいわせてしまうのは、日本の教育のなかで演劇が他の芸術のように明確にしっかりと位置付けられておらず、そのために演劇に関する基礎的な知識を子ども時代に得られていないこと、そして自分に合う、自分が観たい演劇作品についての情報も、出会う機会も、他の芸術に比べて限られていることが、大きな原因ではないか、と考えられます。 そして、「演劇はむずかしい」と感じている多くの人が、自分が共感出来て楽しめた作品に出会えた時、その反動から「この作品はわかりやすくてよかった」という感想の表現になるのではないかと思います。
マーケティングの4P~演劇の場合
ちょっと寄り道になってしまいますが、ここで視点を変えてみたいと思います。 4Pというマーケティング用語をきいたことはあるでしょうか。マーケティング戦略を検討していくうえで重要な、以下の4つの要素のことです。
①Product(製品)
顧客に提供する製品やサービスの特性、品質、デザイン、ブランドなど。ターゲットとする市場のニーズに応じた製品開発が重要とされます。
②Price(価格)
製品やサービスの価格設定。需要や競合の状況、採算性を考慮して、適正な価格設定を行います。
③Place(流通)
製品を顧客に届けるための販売場所や流通経路。届けたい対象に確実に届く流通手段を検討します。
④Promotion(販売促進)
製品やサービスの認知を広め、購買意欲を刺激するため、どのようなプロモーション活動を行うか検討します。 何度も例にだして恐縮ですが、執筆段階でロングラン中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』を、この4Pのフレームに当てはめてみます。
①Product(製品)
「ハリー・ポッター」という世界的に強力なブランドを題材とした作品であり、演劇鑑賞という枠を越えて、ディズニーランドやUSJと同様に「魔法の世界」をライブで楽しむ体験を、演劇ファンだけでなく幅広い層に提供できます。
②Price(価格)
「ハリー・ポッター」ブランドのプレミアム性があるので、比較的高めの料金設定が可能です。
③Place(流通)
舞台公演なので、映画のように全国一斉公開というわけにはいきません。しかし、劇場外のカフェやショップ、ストリートなども含めて、ハリー・ポッターの世界観にもとづいた唯一無二の劇場エリアを形成することで、わざわざ日本でひとつだけの劇場へ出かけなければならないということをポジティブな行為に変換しています。もちろんチケットは、主催者や各プレイガイドからオンラインで購入できます。加えて観劇前後で、劇場やカフェのグッズがオンラインで全国から購入できます。
④Promotion(販売促進)
原作の知名度、著名な出演者といった力があるので、主催者でもあるTBSをはじめテレビ、ラジオなどのメディアを使った幅広い層への情報発信が可能となります。またSNSによる発信も、ハリー・ポッターが好き、という既存の大きなファンコミュニティへ届けることができます。 ここでは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』を例にとりましたが、海外公演も成功している舞台『千と千尋の神隠し』や、劇団四季によるディズニーミュージカル『アナと雪の女王』なども、それぞれ4Pのフレームにあてはまるマーケティング戦略をとることができる作品です。だからロングランが可能になり、スポンサーも資金を投資できるわけです。 しかし、現代演劇のなかで、そういったダイナミックな戦略がとれる公演はごく一部です。 そもそも、①Product(製品)について、市場ニーズにあわせた作品創作という方向性が、芸術としての演劇になじむものなのかどうか、という前提段階から考えていかなければなりません。
現代演劇のプロモーションについて
この連載の最初に書きましたが、私は以前、関西ローカルの月刊情報誌で、演劇公演情報や、おすすめの公演の取材記事を担当していました。当時は、私が所属していた「エルマガジン」のほか、「プレイガイドジャーナル」、「ぴあ」といった情報誌が、京阪神で行われる演劇公演を網羅的に紹介していました。読者は、そのいずれかを書店で入手したら、いつ、どこで、どんな演劇公演が、いくらで観劇できるのかを俯瞰して知ることができました。しかし、それらの紙媒体も今はありません。今は新聞や一部の専門誌だけが頼りです。 昔話になりますが、かつて、演劇公演の広報のことを「情宣(じょうせん)」と呼んでいました。 チラシをつくる。劇場をまわってそのチラシをたくさんの公演で配布してもらう。行きつけの飲食店をまわってチラシをおいてもらう。新聞社や情報誌の担当にアポイントをとって宣伝にまわる、といったことです。そして知り合いや関係先にチケットを売ってまわる。アンケートに答えてくれたお客に手作業でDMを送る。広く広報するのは紙媒体にお願いして、あとは自分たちの手足を使う、まさに○○してまわる、といった感じでした。 今、多くの劇団、劇場は、相変わらずのチラシによる宣伝とともに、それぞれの戦略のもとでSNSを活用しているかと思います。手間はかかりますが、基本的には無料で利用できるありがたい媒体です。映画などと違って映像情報を出しづらいなか、いろいろな工夫を凝らして発信しています。 しかしながら、SNSの特性上、すでに興味を持ってくれている人には届きやすいですが、なかなか創客にはつながらない、新しい人にリーチできにくい、という側面もあるかと思います。
失敗を楽しむ
そしてもうひとつ、これは蛇足かもしれませんが、また、演劇だけの問題ではないと思うのですが、今、私たちが生きる時代の「余裕のなさ」が、過剰に失敗を恐れさせているのではないか、と思うのです。 例えば、誰かと食事する、その店を新たにさがす、というときに、多くの人がネットで検索し、口コミを読み込んで、失敗しなさそうなお店を検討すると思います。 あるいはデートで意中の人を映画に誘うとします。恋愛映画にするのか、アクション映画にするのか、それともヒューマンドラマにするのか。そしてその映画の評判は? ここでも口コミや評価の星の数を気にします。 会食やデートで絶対に失敗したくないからです。 しかし、演劇ではそういった失敗を避けるための「下調べ」が難しいです。 有名な原作がある演劇や、規模の大きなミュージカルなどでしたら、作品内容のわかる情報、予告映像や十分な数の口コミもあるでしょうが、多くの演劇公演にそれらはありません。チラシのイメージやその文言、キャストや作家・演出家の名前程度と、事前情報は限られています。しかもこちらから探しに行かないと、その情報はなかなか見つかりません。三谷幸喜さんや宮藤官九郎さんなど有名な作・演出家や、テレビ・映画などで見覚えのある俳優が名を連ねていたら、大いに安心材料になるかもしれませんが、そうでないことも多いです。 そういった意味で演劇は、言葉を選ばずにいうと、当たりはずれの多いジャンルだと思います。当たりはずれというのは、作品の質もそうですが、自分に合うかどうか、好みかどうか、が大きいです。 この「当たりはずれが多い」ということに、当然マイナスのイメージを持つ方がほとんどだと思います。しかし、あえて、その当たりはずれを楽しむ、ということを試してもいいのではないか、と考えたりもするのです。 選んだのは自分、そして選んだ作品が自分には合っていなかった。どこが合っていなかったのだろう。こういう内容は自分は楽しめないのだな。でも、あの俳優は素敵だったな。あの劇場の雰囲気だけは好きだな。そういったことが経験になります。 その失敗経験を楽しんで、次は違う選択をしていく。あの劇場でやっている、違う劇団の作品を観てみよう。前とはまったく違う雰囲気のこの作品を観てみよう。あの俳優を少し追いかけてみよう。 もし誰かと一緒に観に行ったのなら、ああ、失敗したね~、ここがもう少しこうだったらよかったのにね、とか、え~、あなたはここがよかったの?私はだめだった!などなど、失敗をネタに笑って話ができると素敵だと思います。その失敗が、その人との思い出になるのですから。 失敗をおそれない「余裕」があったら、思いがけない、あなたの好きな演劇作品に出会えるかもしれません。 私はお酒が好きですが、初めての街で初めての酒場の扉を開けるときのドキドキ感が大好きです。当然失敗したなぁ、と思うときもありますが、隠れた名店を発掘することもあります。一人飲みのときは自分で完結しますが、親しい家族や友人となら、その失敗や成功を一緒に楽しめます。 たしかに仕事や人生の大事な選択で失敗することは避けなければなりません。でも文化や芸術を楽しむにあたっては、失敗でさえも楽しむことができる余裕があれば、素敵な出会いの可能性も大いに広がっていくと思うのです。 演劇の場合も、そうやって失敗や成功を繰り返していくうちに、あなたの一生を変えるような運命的な作品に出会えるときがくるかもしれません。演劇好きの人、そして演劇を仕事にしている人、それぞれにそんな出会いがあったから、その人たちは明日も演劇を観に行くし、演劇を仕事にしようと思ったのだと思います。もちろん私もそのひとりです。 そして、心配はいりません。 何事もそうですが、何度か失敗を経験すると、そのうち鼻が利くようになってきますから。
まとめ
1 音楽、美術などは、学校の教科として、少ないながらも継続的に学習、鑑賞の機会がありますが、演劇については年に1度あるかないかの体験授業や鑑賞会にとどまり、それが実施されている学校も多くはありません。2 そのため、音楽、美術では学校で習うような基礎知識も鑑賞体験も演劇では乏しく、そのために初めて演劇と出会ってもむずかしいと感じてしまうのはしかたないかもしれません。3 音楽や美術、そして映画などと比べて、演劇には事前情報も少なく、東京や大都市圏以外では選択肢も少ないので、自分に合う作品を見つけにくいです。4 ほとんどの演劇公演において、市場原理にのっとったマーケティング戦略をとることは、その規模、そして市場原理と芸術が必ずしもなじまない、という理由から、難しいと思われます。
5 以上の理由から、観客側からみると、他の芸術分野に比べて演劇は、いわゆる「当たりはずれ」が多いかもしれません。しかし、いろいろな出会いを繰り返し、観劇経験を重ねる中で、きっとあなたの心を揺さぶる作品に巡り合えるのではないかと思います。
Views: 2



