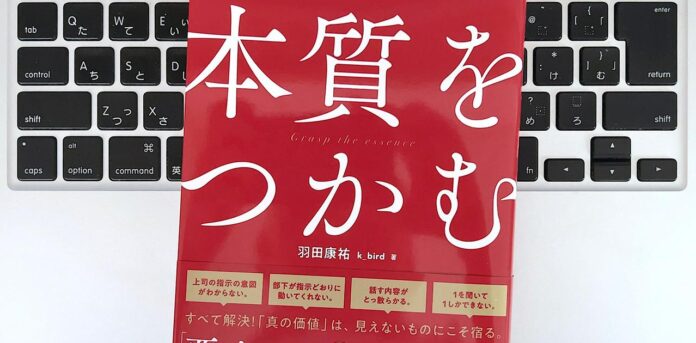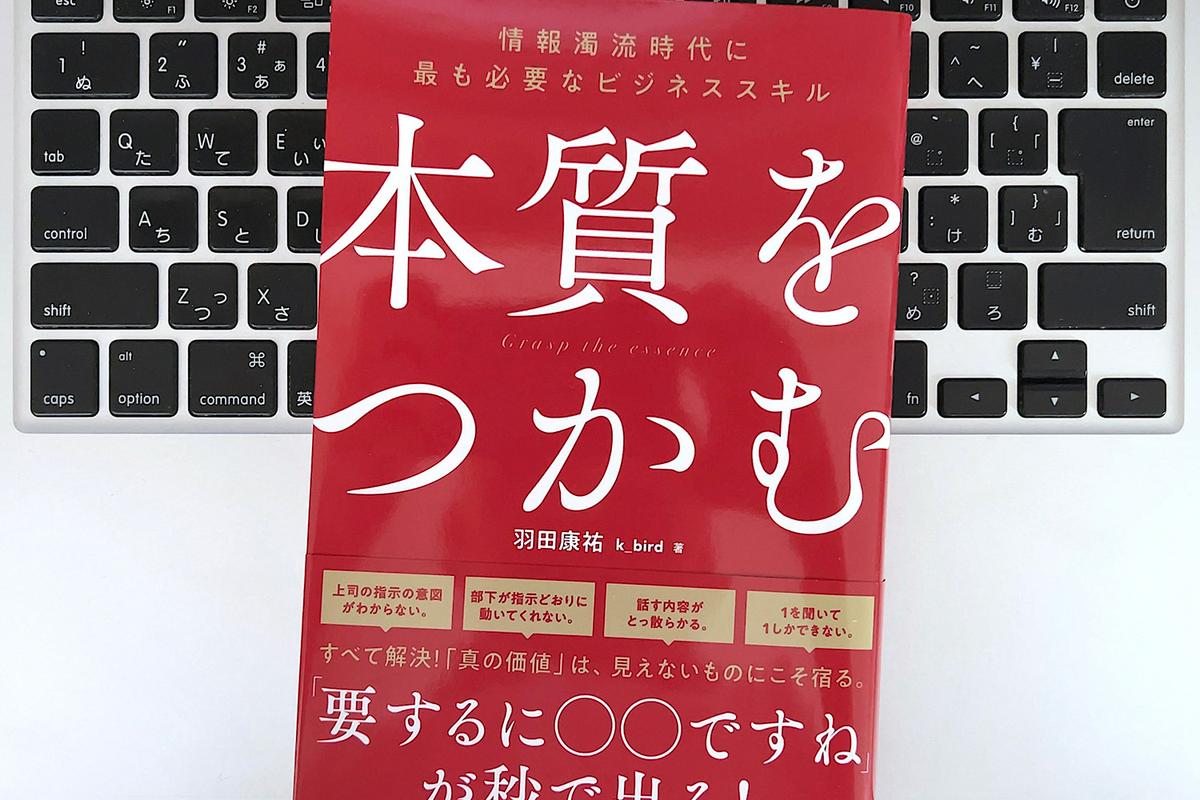
「上司の指示どおりに作業したのに、『思ってたのと違う』と突き返されてしまう」とか、「ていねいに報告したつもりでも、『要はどういうこと?』と聞かれて返答に窮してしまう」などということは、仕事の現場では起こりがち。
『本質をつかむ』(羽田康祐 k_bird 著、フォレスト出版)の著者によれば、それらの原因は「物事の表面にとらわれるあまり、本質を見失っている」ことなのだそうです。
仕事の生産性を上げるうえで、業務スピードを上げることは本質ではない。生産性向上の本質は「やらなくてもよい」ことを見極めて、「やめてしまう」ことにある。なぜなら業務スピードをいくら上げたところで、そもそもその業務自体が必要ないのであれば「スピードを上げること」には意味がないからだ。(「まえがき」より)
それは、さまざまなことにあてはまるでしょう。
・「情報収集」に関しては、事前にその「目的」や「重要な核心」を見極めておかなければ、価値ある示唆を引き出すことはできません。
・「分析」についても、その本質が「誰にもわかりやすくシンプルなもの」であることは明白です。
・「報告書作成」の本質は、相手が知りたいことや必要とする結論を伝えつつ、次に向けた示唆や教訓を組織知に加えていくことであるはず。
・「マネジメント」の本質は、部下が自立して成果を出せるような機会を与え、自主性を育むことです。
他にもいろいろ考えられますが、つまりは「本質を見抜く力」が乏しく、「本質の価値」を理解していないと、ビジネスのあらゆる局面で的外れな言動を繰り返してしまうことになるわけです。
そこで本書において著者は、本質を見抜く力を磨くための具体的なアプローチを紹介しているのです。
きょうは第一章「本質を見抜く力とは何か?」内の「本質が持っている5つの特性とは」に注目してみたいと思います。「本質」は曖昧な概念であるからこそ、「本質が持つさまざまな特性」を理解する必要があるというのです。
本質の特性1:根本性(物事の確信部分)
「本質」には、根本性が備わっていなければならないそう。
ここでいう根本性とは、ものごとを成り立たせるもっとも重要な核心部分のこと。表面的な特徴や一時的な変化に左右されるのではなく、「それがなければ成り立たない」「意義を持たない」という性質のものだということです。
たとえば、自動車について考えてみよう。自動車は「移動手段としての機能」がなければ、それはもはや自動車とは呼べない。
エンジン性能やデザイン、快適性といった要素は重要ではあっても、それらは移動手段としての本質を支える周辺的な要素に過ぎない。
根本となる「走る」機能がなければ、どんなに他の機能や外観が優れていても自動車としての存在意義を失う。(26ページより)
ここからもわかるように、本質を見抜くためには、ものごとの表面に惑わされることなく、核心部分を探り当てる力が必要であるわけです。(26ページより)
本質の特性2:必要性(ニーズに応える価値)
「本質」に備わっていなければならない必要性とは、相手がそれを求め、価値を感じ、なくては困ると感じる要素のこと。
たとえば、製品の機能を例に挙げてみよう。
どれだけ豊富な機能を搭載していても、顧客にとってその機能が「役立つ」「必要だ」と感じられなければ、豊富な機能は本質的な価値があるとはいえない。
逆にシンプルな機能であっても、顧客の課題を解決し「これがなければ困る」と思われる機能であれば、本質的な価値を持つといえる。(27ページより)
相手にとっても必要不可欠な存在となるために重要なのは、相手の状況や課題を深く理解し、本当に求められる価値を見抜くこと。相手からの必要性を伴ったものこそが、本質を成り立たせるということです。(27ページより)
本質の特性3:シンプル性(複雑さの奥にある原則)
シンプルであるとは、複雑さのなかから余計な枝葉を取り除いたあとの、純粋で簡潔な状態。
たとえ表面的には複雑に見えても、その根底にはシンプルな原則が存在するもので、その原則こそが本質であるというわけです。
たとえば、プロジェクトについて考えてみよう。
どのようなプロジェクトでも、成功の本質は「チームが共通の目標に向かって効果的に協力すること」にある。
このシンプルな原理は、大きなプロジェクトであれ、小さなプロジェクトであれ、あるいはテーマが異なるプロジェクトであっても共通する。(28ページより)
人は、複雑なものごとのなかにある核心をとらえ、シンプルな形で表現できるとき、正しい方向性を見出せるのだといいます。(28ページより)
本質の特性4:普遍性(時代を超えて通用する法則)
「本質」には、普遍性が備わっていなければならないもの。普遍性とは、特定の時間や場所、状況に縛られず、多くの場面や分野で通用する性質のことです。
ビジネスの本質とは、技術の進化やトレンドの変化にかかわらず「顧客に価値を提供し、問題を解決することで対価を得る」ことだ。
このような普遍的な視点を持つことで、可視化依存社会の中で、揺るがない指針を得ることができる。(29ページより)
本質に携わる普遍性は、抽象化することでその応用範囲を広げられるそう。個別事例にとどまらず、裏側にある共通の原理や力学を導き出し、応用可能な法則として整理すれば、汎用性の高い学びを手に入れられるわけです。(29ページより)
本質の特性5:全体規定性(全体を貫く中心軸)
全体規定性とは、本質が全体の働きを決定づける力だ。
たとえば、企業におけるミッションやパーパス(存在意義)について考えてみよう。明確なミッションやパーパスは、組織全体のカルチャーや行動指針、さらには意思決定の基準にまで影響を及ぼす。(30〜31ページより)
本質が明確であれば、全体がその本質を中心に規定され、整合性を持った取り組みが展開できるようになるのです。(30ページより)
本質を見抜く力は、「3日で身につく〇〇」などのビジネスハックとは異なり、日々の習慣によって少しずつ鍛えられていく筋トレのようなものだと著者は述べています。そこで本書を活用し、本質を見抜くための基礎体力をつけておきたいところです。
>>Kindle unlimited、500万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
Source: フォレスト出版
Views: 2