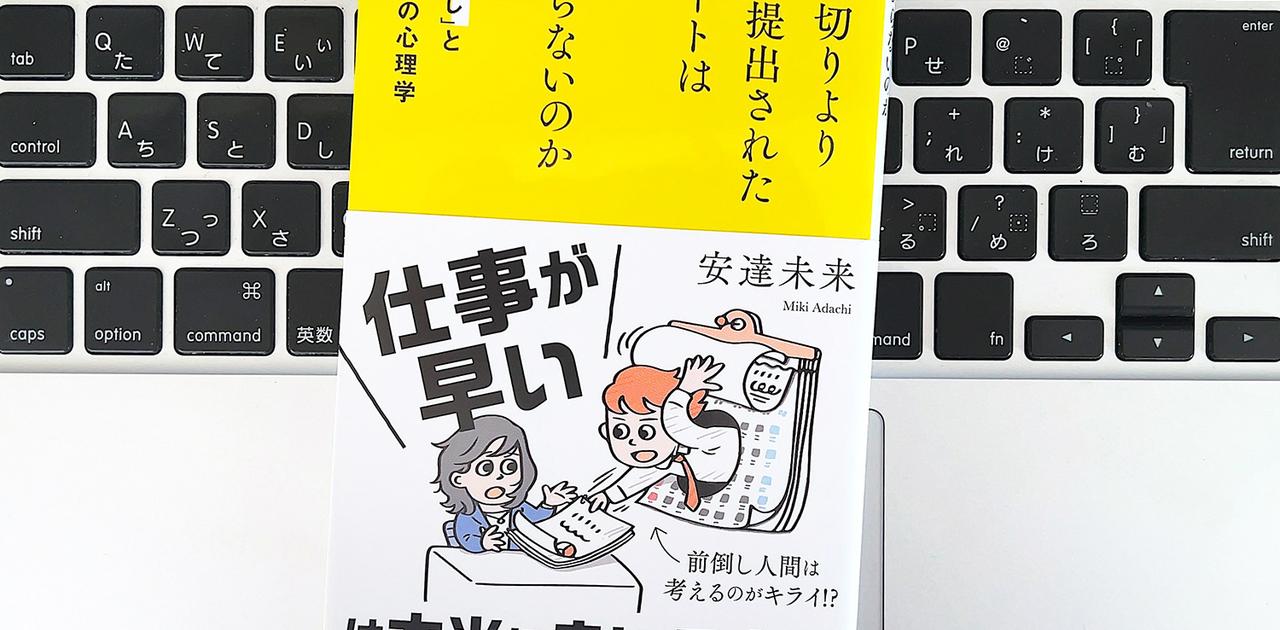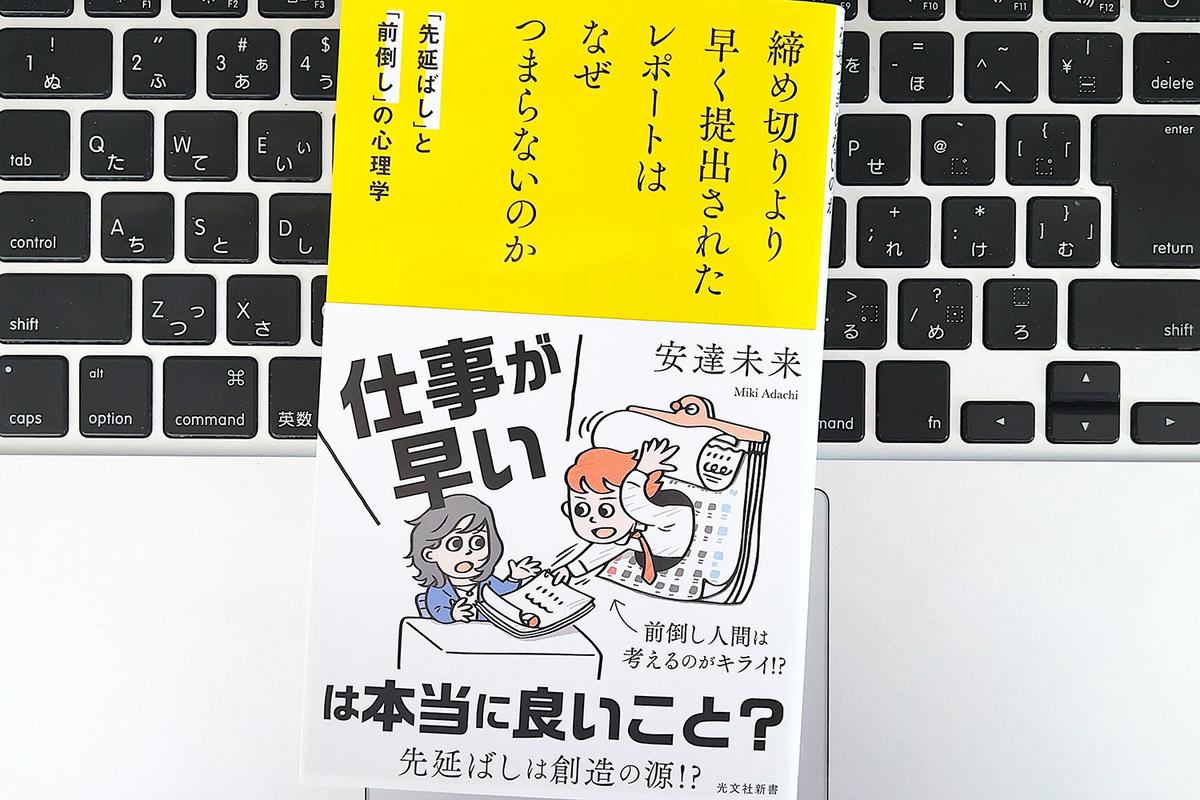
「先延ばし」ということばには、あまりよいイメージがないかもしれません。やらなければならないことを後回しにするとか、否定的な印象がついてまわるからです。一方、「前倒し」には「やらなければならないことに早めに取りかかる」というように、堅実で計画的に感じさせるものがあります。
しかし、『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』(安達未来 著、光文社新書)の著者によると、この2つは単に「望ましい――望ましくない」という尺度で捉えられる概念ではないようです。先延ばしと前倒しは必ずしも反対の意味をもつわけではなく、実際はより複雑だというのです。
そして、そうした考え方が本書の内容につながります。
本書では、タスクマネジメントの観点から先延ばしと前倒しを捉え、それぞれの特徴や長所および短所を、セルフコントロールという言葉を切り口に解説していきます。
そして、なぜ先延ばしや前倒しが生じるのかというメカニズムや、先延ばししやすい人、前倒ししやすい人の特徴などを、これまでの研究や日常生活での例をもとにわかりやすく説明していきます。(「はじめに」より)
著者は社会心理学、教育心理学を専門とする研究者。所属している大阪電気通信大学では、青年心理学、教育心理学などの授業を担当しているのだそうです。基本的なアプローチは、「身近な現象に対する“なぜ”にもとづき、問題の原因を多様な観点から考えていくこと」。それを軸としながらさまざまな調査や研究を行っているというのです。
そして本書においては、先延ばしや前倒しに関する研究は、これまでどのような研究が行われてきたかを概観しているわけです。きょうはそのなかから、2章「先延ばしは本当に悪いのか?」に焦点を当ててみたいと思います。
先延ばしが創造性を高める
タスクを後回しにしているように見えたとしても、計画的で意味のある先延ばしはさまざまなプラスの効果をもたらすことがあるそうです。
たとえばそれは、YouTubeやSNS、Netflixなどのサブスク動画を視聴したり閲覧したりすることにもあてはまるのだとか。
アメリカで行われた調査では、オフィスで働く人たちが1日あたり平均およそ77分間を、本来やるべき仕事とは関係のないYouTube動画の視聴に費やしていることが示されているというのです。
イエール大学のシンらは、参加者の大学生に、起業のための提案書を作成してもらうという実験を行いました。提案書の作成中、画面にはその課題に関連しないYouTube動画のリンクが表示されていました。
参加者は1本の動画が視聴できる低条件、4本の動画が視聴できる中条件、8本の動画が視聴できる高条件の3つの条件に分けられ、どのグループも動画を視聴できる状態で、提案書を作成しました。(86ページより)
その後、完成した提案書の内容がどれくらい創造的かを評価した結果、4本の動画を視聴できる状態で作成された中条件の人の提案書が、もっとも創造的だったという結果が得られたというのです。つまり、先延ばしが少なかったり、過度に先延ばししたりするよりも、「適度な先延ばし」が効果的であることがわかったわけです。
たしかに、仕事や課題が煮詰まった際には、たとえ先延ばしをしている場合ではなかったとしても、意図的にタスクを中断することは効果的である場合があります。気分転換やリフレッシュでき、新たな考えを思いついたり、逆にはかどったりすることがあるからです。
つまり「時間がないのだから、先延ばしをする余裕はない」というときでも、一時的に後回しにしてみることはタスクマネジメントのひとつであると解釈できるのです。(85ページより)
先延ばし研究からのパラダイムシフト
だとすれば、先延ばしという考え方自体を見なおす必要があるとも解釈できます。重要なのは、「いかに効率的にタスクをマネジメントすればよいのか」を考えること。それこそが、著者が長らく興味や関心を寄せてきたテーマであり、本書で扱う「先延ばし」と「前倒し」の研究をはじめた経緯につながっていくのだそうです。
そして興味深いのは、学生に課すレポートについての著者の実感です。
著者が所属する大学で用いられている学習管理システムでは、その学生がいつ課題にとりかかったか、作業にどれくらいの時間をかけたか、最終的にいつ課題を提出したかなどがすべて記録され、確認できるのだそうです。そんななかで提出されるレポートをチェックしていくと、「提出日がやたらと早いな」と思うケースに出合うことがあるというのです。
もちろん、期限を破って提出する先延ばし行為に比べると、高評価以外のなにものでもありませんし、早めの提出を労いたいとも思います。ただし、あまりに早い時期に提出されたレポートは、質がよくないことが多いのです。「さっさと終わらせた感」がヒシヒシと伝わってくる内容です。(88〜89ページより)
“先延ばしをしない”ことをよしとする風潮は、この社会に間違いなく存在しています。ビジネスシーンにあてはめるなら、「仕事が早くて助かる」と上司に評価してもらえることなどがそれにあたるでしょう。
けれども、本当によいことばかりなのだろうかと著者は疑問を投げかけています。早めにことを進めることに異論はないけれど、だからといってあまりにさっさと終わらせることが必ずしもよいとはいい切れない気がすると。
学生は多くの授業を履修していて、それぞれにレポートや課題をかかえています。課題によって難易度やかかる時間も違いますし、好き嫌いや関心の度合いも違います。
それらにどのような順序でとりかかるかは、まさにタスクマネジメントに関わる問題といえるでしょう。
そして、これは学生のレポートに限らず、社会人にとっても身近なテーマです。(90ページより)
たしかにそのとおりではないでしょうか? 働き方への意識や関心が高まる現代社会において、誰もが心身ともに健康な生活を送るためには無視できないことがあるはず。先延ばしの是正や改善だけではなく、効率的にタスクを進めていくための適切な方法を視野に入れることが重要なのです。
仕事の早さで評価が決まるような状況においては気づきにくいことかもしれませんが、これは現代社会においてとても重要な視点ではないかと感じます。(87ページより)
研究の紹介のみならず、著者自身が経験した日常生活での気づきやエピソードも交えられているため、気負いことなく読み進められるはず。先延ばしや前倒しについての悩みを抱えている方には、きっと役立ってくれるでしょう。
>>Kindle unlimited、500万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
Source: 光文社
Views: 0