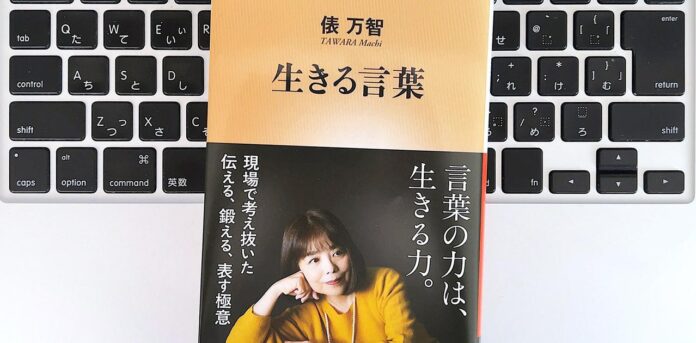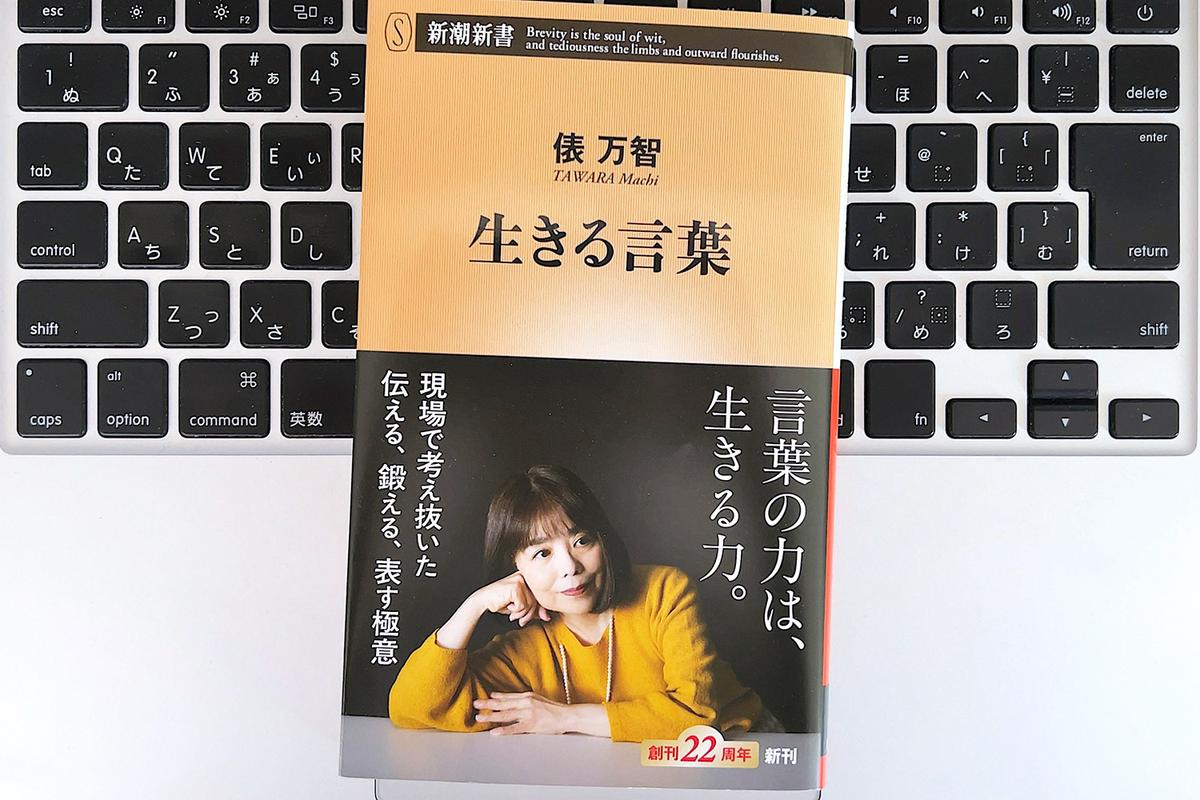
写真や動画が手軽に撮れて発信できるだけに、いま私たちが生きているのは“ビジュアルの時代”であるという認識のほうが強いのかもしれません。しかしコミュニケーションに関しては、ことばの比重が増している――。
『生きる言葉』(俵 万智 著、新潮新書)の著者はこう語っています。
共感できる方は多いのではないでしょうか。ビジュアルが重視されがちであるとはいっても、“ことば”がコミュニケーションにとっての大前提であることは間違いないからです。
「個人の言葉の背景を理解してもらえる環境」ではないところで、多くのコミュニケーションをしていかねばならないのが現代社会だ。
家族や友人、恋人同士などはこの限りではないけれど、行動範囲がグンと広がり、ネットでのやり取りが日常になっている今、背景抜きの言葉をつかいこなす力は、非常に重要だ。それは、生きる力と言ってもいい。(「はじめに」より)
だからこそ、「普通の人が普通に使う書きことばとしての日本語の、足腰を鍛える」ことがいっそう重要になってきたというのです。
だとすれば、「具体的にどのようなトレーニングが有効なのか」「“生きることば”を発するためにはなにが大切なのか」などを知りたいところです。
そこで著者は本書において、現代のことばに関するさまざまなトピックスを考察しているわけです。きょうはそのなかから、5「言い切りは優しくないのか」に注目してみたいと思います。
なんでもハラスメント
2024年の春に、「マルハラ」ということばがメディアを賑わせました。「マル」とは句点のことで、「マルハラスメント」を略してマルハラ。中高年がLINEなどのSNSで送信する際、文末に句点をつけることが若者からすると威圧的に感じられるということです。
もちろん、ことばとして違和感を覚えずにはいられないという方がいらっしゃったとしても、決して不思議ではありません(私自身も、その部類に入ります)。しかし、“好きか嫌いか”“肯定か否定か”ということとは別に重要なポイントがあるのも事実。
著者が指摘しているように、これはハラスメントというより“シンプルな誤解”だという可能性があるわけです。
若者が、LINEでの会話に句点があることに違和感を抱くのは、それが限りなく話し言葉に近いと思っているからだろう。
だから「マル」がついていると、あえて付けたように感じてしまう。
たとえば日常会話で「わかった」ではなく「わかった、以上!」と言われたような感じではないだろうか。
後者には「もうわかったから、このことにいつまでも拘泥するな」的なニュアンスが漂う。(108〜109ページより)
しかし中高年世代にとっては、LINEといえども画面に文字が表示される以上、あくまでそれは「書きことば」。だとすれば、文末には句点を打つのが当然だと考えてしまうということなのでしょう。
とはいえ若者たちも、いっさい句点を使わないわけではありません。たとえば学校のレポートは会社内のメールなどでは文末にマルを入れているはずで、つまりは「そこがどういう場なのか」についての認識の違いだということ。
普段着であいさつしに来たつもりが、年上の人がスーツ姿で現れたら、居心地が悪いし、なんだか自分の服装をとがめられたような気持になる。
無言の圧力……それがハラスメントと感じられるのではないだろうか。(109ページより)
そう考えれば、少なくとも違和感は減らすことができるのかもしれません。(108ページより)
マルで終わる日本語
マルハラの少し前に、「おばさん構文」というものが話題になったこともありました。
長文で、必要以上に絵文字や句読点が多いというもの。つまりはここでも、句点がマイナスのイメージで捉えられているわけです。
そこで著者はふと、自身の短歌を思い出したのだとか。それは、「日本語って、〇(マル)で終わるんだな、それってなんだか素敵なことだな」と感じて詠んだ一首。「世の中的には分の悪い句点だが、こういう見方もできるのでは?」と思い、X(旧Twitter)に投稿したのだそうです。
句点を打つのも、おばさん構文と聞いて…この一首をそっと置いておきますね〜
優しさにひとつ気がつく ×でなく〇で必ず終わる日本語
(110ページより)
マルハラの話題と時期が重なり、この投稿には10万を超える「いいね」がついたそう。新聞各紙でもマルハラの話題にからめて取り上げられ、反響の大きさに驚いたのだといいます。
このことについて、「マルをつけたい」「句点があるほうが落ち着く」「そんなつもりのマルじゃない」と感じる人が多かったのかもしれないと著者は分析しています。
だとすればそれは、モヤモヤを抱えていたところに、「マルで終わるって日本語の優しさでは?」という一首のメッセージが届いたということを意味するのでしょう。
ちなみに、ここまで拡散されると、もちろん思いがけないリプライも付く。
多かったのは「×で終わる言語があるんですかね」というもの。
いちおう反論というか補足をしておくと、「×でなく」とは、「今から句点の〇を、〇×の〇と見立てますよ」という伏線としての表現である。(110ページより)
補足が必要とされることにはモヤモヤしてしまう部分もありますが、誤解や疑問を生んでしまうこともまた、ことばが持つ特徴のひとつなのかもしれません。(110ページより)
著者のフィールドである現代短歌や和歌のみならず、子ども時代のことば、芝居のことば、日本語ラップや小説、AIなどを通じ、ことばのあり方を広い視野で考察した一冊。
便利な時代であるからこそ、本書を通じ、原点ともいえることばの力を再認識してみてはいかがでしょうか。
>>Kindle unlimited、500万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
Source: 新潮新書
Views: 0