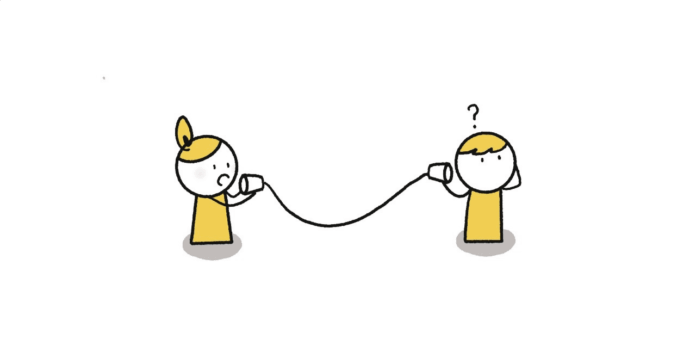🧠 概要:
概要
この記事では、薬に対してアレルギーを感じたり、避けたいと思う自然療法派の人々に向けたコミュニケーション方法について説明しています。薬を使うことへの抵抗感や罪悪感を和らげるための実体験の活用や心理学的アプローチが重要視されています。
要約(箇条書き)
- 自然療法を好む人々が薬を使うことに対する罪悪感や抵抗感について触れる。
- 著者は実体験を通じて、西洋薬と漢方の併用が効果的であったことを紹介。
- 心理学のリアクタンス理論を用い、選択肢の自由を尊重する重要性を強調。
- 「納得」を生む会話のスタイル(説得ではなく体験談の共有)が効果的。
- 中医学のバランスを用い、西洋薬、漢方、波動療法の共存を説明。
- 専門家の役割は「正解」を提示することではなく、安心して選べる状態を作ること。
- 実践の鍵は、共感・知的納得・心理的安心を提供するフレーズを使うこと。
- 経験や知識を受け取りやすい形で伝えることが意義深い。
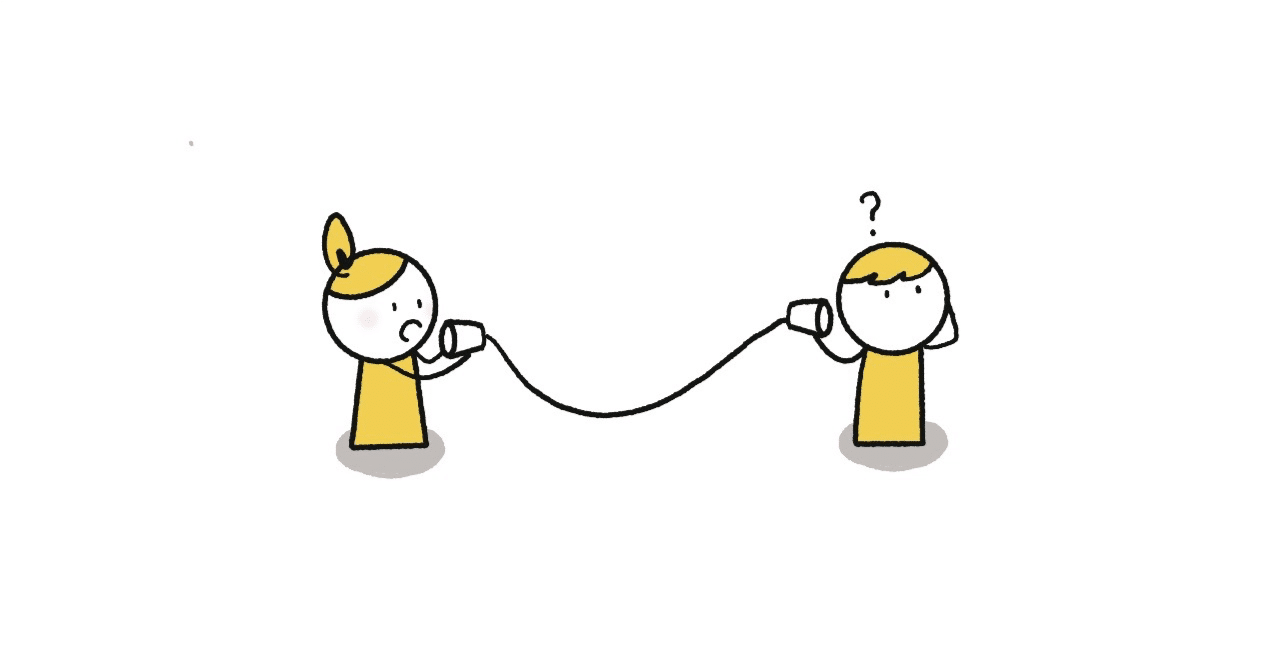
「薬は使いたくないけど、咳がつらいんです」
そんな声を、健康意識の高いお客さまからよく耳にしませんか?
「自然療法を選んでいるのに、薬を使うって“負け”なのかな…」
そんなふうに、罪悪感すら感じている方も。
でも実はその迷いにこそ、伝え方のチャンスがあります。
実体験こそ“橋渡し”になる
私は最近、ひどい風邪を引きました。
声が出ない、咳が止まらない。中医学的に言えば「肺の潤い不足」、いわゆる“肺陰虚”状態。
いつものように漢方で乗り切ろうと思ったのですが、今回はそれだけでは回復が追いつかない…。
そこで私は、西洋薬の去痰薬と、潤いを補う漢方(麦門冬湯)を併用しました。
すると、1日で呼吸がラクに。声も出てきて、咳もおさまりました。
この「併用」には、西洋医学・中医学両方の理屈があります。西洋薬は「排出を促すスイッチ」、漢方は「潤いの材料を与える」。
つまり、機能と資源の両輪で回復をサポートするという発想です。
「薬=悪」と思わせない伝え方
ここで活用したいのが、心理学のリアクタンス理論です。人は「選ばされる」状況に抵抗を感じます。
「薬はNGです」と言われると、それが理屈として正しくても、反発が生まれるのです。
だからこそ、
「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」という言い回しは有効です。これは**NLPの“肯定的フレーミング”**でもあります。
「使っていい理由」を与えることで、お客さまは“選んでいい自由”を取り戻せるのです。
自分の“体験”で納得を誘う
伝え方で意識したいのは、**「説得」ではなく「納得」**をつくること。
今回のように「実体験として、私は併用して回復できた」という言葉は、最強の説得力になります。
行動経済学でも、「人は論理よりもストーリーに動かされる」と言われます。
小難しい理屈より、「自分ごとに感じられる体験談」が一番刺さるんです。
バイオレゾナンスの“補助線”を引く
私は同時に、波動療法で喉周辺の周波数の乱れを整えるセッションも行いました。
この“トリプルアプローチ”で、よりスムーズに改善を実感できたのです。
ここでも重要なのは、“波動療法が効く”と断言することではありません。
「乱れた状態に“気づき”、整える」という補助線を引いてあげること。
それだけで「やってみようかな」と思う心理的ハードルはぐっと下がります。
中医学の「バランス」の視点を借りる
中医学は、バランスを重んじる医学です。
この視点を「選択肢の共存」の根拠として使いましょう。
「西洋薬だけでは整えきれない“潤い”を、漢方が支える」「波動療法は、全体の微調整を助ける」
このようにそれぞれの立ち位置を明確に言語化することで、納得を生みやすくなります。
まとめ:専門家の“言葉”が、選択肢の扉を開く
専門家である私たちの役割は、「これが正解です」と決めることではなく、
「いくつかの選択肢を“安心して選べる状態”を作ること」です。
そのためには、
-
実体験を語る(=共感と納得)
-
なぜ効いたのかを“両方の視点”から説明する(=知的納得)
-
相手の自由を尊重するフレーズを使う(=心理的安心)
という伝え方が、鍵になります。
そしてこれは、“売り込む”ことではありません。
あなたの経験や知識を、「受け取りやすい形」で届ける技術です。
あなたのその一言が、
“自然療法しか選べない”と悩む誰かの視野を広げ、体を助けることになるかもしれません。
【伝え方Tips】「伝えたいこと」を“届く形”に変換できるのは、あなただけです。
その力を、もっと軽やかに楽しんで使っていきましょう。
読んでくださってありがとうございました!あなたの知識や経験を「伝える」ことは多くの人たちの幸せに繋がる。
共に、「健康が当たり前になる世界」作っていきましょう(^з^)-☆
Views: 2