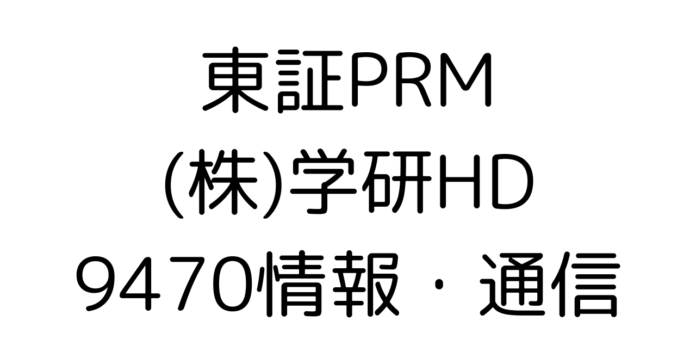🧠 概要:
概要
この記事は、株式会社学研ホールディングス(学研HD)の最新の決算報告を基に、同社の成長戦略や投資魅力を詳細に分析しています。教育と医療福祉の二つのビジネスセグメントを持つ学研HDは、少子高齢化やデジタル化などの社会的変化に適応しながら、M&Aを通じて事業拡大を目指しています。記事では、最近の業績、財務状況、そして競合状況についても触れ、投資の観点からの示唆を提供します。
要約(箇条書き)
-
企業の歴史と理念
- 株式会社学研ホールディングスは1946年創業の教育・医療福祉グループ。
- 「すべての人が心ゆたかに生きる」を理念に、多様な教育サービスと高齢者福祉事業を展開。
-
事業構造
- 教育分野と医療福祉分野が主要な事業セグメント。
- 教育分野では出版、塾、学校向け事業などが多岐にわたる。
- 医療福祉分野では高齢者向け住宅や子育て支援事業に注力。
-
M&A戦略
- 教育分野での桐原書店の子会社化や、ベトナム企業の連結子会社化を進めている。
- 医療福祉分野でもM&Aを通じて事業規模の拡大を図る。
-
業績の動向
- 2025年3月期中間期の売上高は前年同期比5.7%増。
- 営業利益と経常利益は減少、純利益は36.8%増加した。
- 教育分野は増益を達成したが、医療福祉分野はコスト増に悩む。
-
財務健康度
- 自己資本比率は36.7%に低下、流動性は維持されています。
- M&Aによる負債の増加が見られるが、全体的な財務状況は堅調。
- 未来の展望
- デジタル化や社会の変革により、新たな成長機会を追求する姿勢が強調される。
- コストコントロールと収益改善が今後の課題。
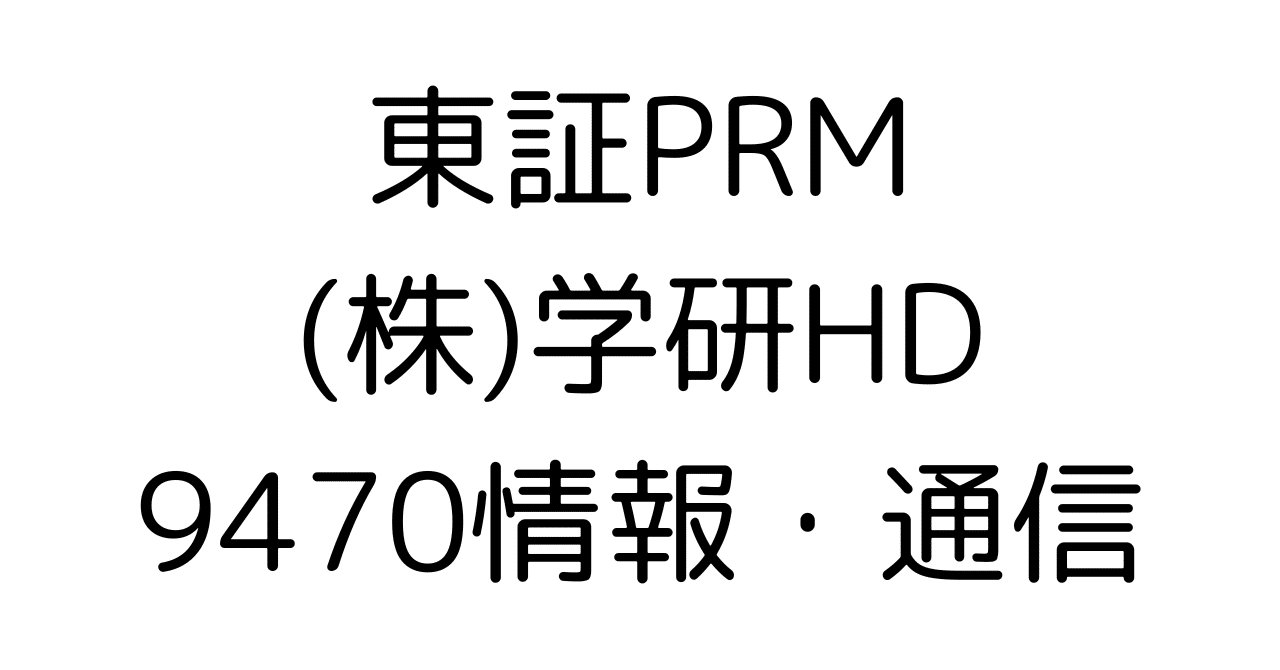
株式会社学研ホールディングスは、日本を代表する総合教育・医療福祉グループです。その歴史は古く、戦後の復興期である1946年に「学習研究社」として創業し、以来、日本の教育の発展と共に歩んできました。「すべての人が心ゆたかに生きることを願い今日の感動・満足・希望と明日の夢・成長・貢献を追及します」というグループ理念のもと、教育分野では出版、教室・塾、園・学校向け事業などを展開し、医療福祉分野では高齢者福祉施設や子育て支援事業などを手がけています。
本稿では、2025年5月9日に開示された2025年3月期中間期の半期報告書を基に、学研HDの直近の業績、財務状況、事業戦略を詳細に分析します。さらに、外部環境の変化や競合の動向も踏まえ、同社の成長ドライバーや潜在的なリスク要因を多角的に考察します。最終的には、これらの分析を通じて、投資対象としての学研HDの「投資妙味」を評価し、読者の皆様に具体的な示唆を提供することを目指します。
少子高齢化、デジタル化の急速な進展、働き方の多様化など、日本社会は大きな変革期にあります。このような環境下で、学研HDがどのように事業を変革し、持続的な成長を達成しようとしているのか。その戦略と実行力に注目が集まります。
2. 企業概要とビジネスモデル
学研グループの成り立ちと理念
学研グループのルーツは、終戦直後の1946年に創業された学習研究社に遡ります。創業者の古岡秀人氏は、「戦後の日本の復興は教育をおいてほかにない」という強い信念のもと、教育雑誌の出版から事業をスタートさせました。以来、学研グループは教育を核としながら、時代のニーズに合わせて事業領域を拡大してきました。
グループ理念として掲げる「すべての人が心ゆたかに生きることを願い今日の感動・満足・希望と明日の夢・成長・貢献を追及します」は、創業以来の精神を現代に受け継ぎ、事業活動の根幹となっています。この理念に基づき、学研グループは、人々の学びや成長、そして心豊かな生活を支援するための多様なサービスを提供し続けることを目指しています。
事業ポートフォリオ概観
学研HDの事業は、大きく「教育分野」と「医療福祉分野」の二つのセグメントに大別され、これに「その他」事業が加わる形で構成されています。
教育分野:多様な学びの機会を提供
教育分野は、学研グループの祖業であり、現在も中核をなす事業領域です。その内容は多岐にわたります。
-
出版コンテンツ事業: 学習参考書、児童書、一般書、雑誌などの出版を手がけています。長年にわたり培ってきた編集力とブランド力は、この事業の大きな強みです。「ニューコース」シリーズや「ハイレベル徹底問題集」といった学習参考書は、多くの学生に利用されてきました。また、近年ではデジタル教材の開発・提供にも注力しています。
-
教室・塾事業: 「学研教室」をはじめとする学習教室や進学塾を全国に展開しています。幼児から高校生までを対象に、それぞれの学力や目標に合わせた指導を提供しています。特に「学研教室」は、地域に根差したきめ細かい指導で高い評価を得ています。また、首都圏を中心に進学塾「市進学院」などを運営する株式会社市進ホールディングスを持分法適用関連会社としています(本報告書では、市進ホールディングスの伸長が教室・塾事業の増収に寄与したと言及されています。)。オンライン指導の導入も進めています。
-
園・学校事業: 幼稚園・保育園・こども園向けの教材や遊具の提供、運営コンサルティング、小学校・中学校・高等学校向けの教科書や教材の供給、ICT教育支援サービスなどを行っています。2024年1月には、教科書や学習参考書を手掛ける株式会社桐原書店を子会社化し、この分野での事業基盤を強化しています(本報告書では、桐原書店のグループインが教育分野の増収に寄与したと記載されています。)。
-
その他教育サービス: 語学教育、社会人向け教育(リカレント教育)、オンライン英会話サービス「Kimini」(本報告書ではKiminiの受講者数増加が寄与したと言及)など、幅広い層に向けた教育サービスを提供しています。
この分野では、少子化という構造的な課題に直面しつつも、個別最適化された学びへのニーズの高まり、デジタル技術の活用、リカレント教育市場の拡大といった機会を捉えようとしています。
医療福祉分野:高齢社会を支えるサービス
医療福祉分野は、日本の急速な高齢化とそれに伴う社会ニーズの変化に対応するため、学研グループが戦略的に強化している事業領域です。
-
高齢者福祉事業: サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)「ココファン」シリーズの運営を主力としています。入居者の自立支援を重視した質の高いサービス提供を目指しており、全国に施設展開を進めています。本報告書によれば、新規開設は堅調に推移し、高水準の入居率を維持しているものの、水道光熱費や食材費の高騰が収益を圧迫している状況がうかがえます。
-
認知症グループホーム事業: 認知症高齢者を対象としたグループホームの運営も行っています。家庭的な環境の中で、専門的なケアを提供しています。こちらも建築費上昇などにより新規出店が難しい環境にあるものの、拠点数は拡大しており、高い入居率を維持しています。
-
子育て支援事業: 保育園や学童保育施設の運営を通じて、子育て世帯を支援しています。待機児童問題の解消や、多様な働き方を支えるインフラとしての役割を担っています。この事業は、保育園の定員充足率の高水準維持や学童・児童発達支援施設の安定運営により増収増益を達成しており、堅調な様子です。
この分野は、高齢者人口の増加や介護ニーズの多様化を背景に市場拡大が期待される一方で、介護人材の確保・育成、介護報酬改定の影響、運営コストの上昇といった課題にも直面しています。学研HDは、M&Aも活用しながら事業規模の拡大とサービス品質の向上を図っています。
近年のM&A戦略と事業再編
学研HDは、既存事業の強化と新規領域への進出を目的として、M&Aを積極的に活用しています。
教育分野では、前述の通り、2024年1月に教科書出版の桐原書店を子会社化しました。これにより、園・学校事業におけるコンテンツ力と販売網の強化を図っています。さらに、本報告書では、2024年10月30日(みなし取得日:2024年12月31日)に、ベトナムで教科書・教材出版等を手がけるDTP Education Solutions JSCを追加取得し、連結子会社化したことが特筆されています。 これは、東南アジア市場への本格的な展開に向けた重要な布石と位置づけられます。
医療福祉分野においても、サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの運営会社を対象としたM&Aを継続的に実施し、施設数の拡大とエリア展開を加速させています。
これらのM&Aは、事業規模の拡大によるスケールメリットの追求、新たな成長エンジンの獲得、既存事業とのシナジー創出を狙ったものと考えられます。一方で、のれんの計上額も増加傾向にあり、買収後のPMI(Post Merger Integration:経営統合プロセス)の巧拙や、のれん償却・減損リスクの管理が重要性を増しています。
(サマリー)学研HDは、教育と医療福祉を二本柱とする複合企業です。教育分野では出版から教室運営、学校向けサービスまで幅広く展開し、医療福祉分野では高齢者施設運営や子育て支援に注力しています。近年はM&Aを積極的に活用し、事業規模の拡大とグローバル展開の足がかりを築いています。
3. 直近業績と財務分析
本章では、2025年5月9日に提出された2025年3月期中間期の半期報告書に基づき、学研HDの直近の業績動向と財務状況を詳細に分析します。
全社業績ハイライト(2025年3月期中間期)
対象となる中間連結会計期間は、2024年10月1日から2025年3月31日までの6ヶ月間です。
売上高・利益の動向
-
売上高: 98,841百万円(前年同期比5.7%増)
-
営業利益: 4,541百万円(前年同期比11.7%減)
-
経常利益: 4,212百万円(前年同期比18.3%減)
-
親会社株主に帰属する中間純利益: 2,424百万円(前年同期比36.8%増)
売上高は、教育分野における桐原書店のグループインや学習参考書の販売増、医療福祉分野における施設数増加などにより、前年同期比で5.7%の増収を達成しました。
一方、営業利益は前年同期比11.7%減、経常利益は同18.3%減と、増収減益の決算となりました。営業利益の減少要因としては、医療福祉分野における水道光熱費や食材費等の高騰が主因とされています。 教育分野では増益を確保したものの、医療福祉分野の減益が全体を押し下げた形です。経常利益は、営業利益の減少に加えて、持分法投資損益の悪化も影響しました。
親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期比36.8%増と大幅な増益を達成しました。これは、前年第1四半期に計上した株式売却損がなくなったことに加え、DTP Education Solutions JSCの連結子会社化に伴う段階取得差益(480百万円)を特別利益として計上したことが大きく寄与しています。
キャッシュ・フローの状況
-
営業活動によるキャッシュ・フロー(営業CF): 1,249百万円の収入(前年同期は1,597百万円の収入)
-
投資活動によるキャッシュ・フロー(投資CF): 2,846百万円の収入(前年同期は3,864百万円の収入)
-
財務活動によるキャッシュ・フロー(財務CF): 166百万円の支出(前年同期は2,481百万円の支出)
-
現金及び現金同等物の中間期末残高: 22,676百万円(前中間連結会計期間の期首残高22,049百万円から626百万円増加)
営業CFは、税金等調整前中間純利益4,390百万円の計上などプラス要因があったものの、売上債権の増加(6,812百万円)などが影響し、前年同期比で収入額が減少しました。
投資CFは、有形及び無形固定資産の売却による収入(4,146百万円)が大きく、前年同期に引き続き収入超過となりました。これは主に、保有不動産の売却などが含まれているものと推察されます。一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出(1,365百万円)や、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(1,969百万円、DTP Education Solutions JSCの段階取得に関連する清算処理等が含まれる可能性)なども発生しています。
財務CFは、短期借入金の純増(4,522百万円)や社債の発行による収入(6,957百万円)があった一方で、長期借入金の返済による支出(3,674百万円)、社債の償還による支出(6,000百万円)、自己株式の取得による支出(1,006百万円)などがあり、全体としては支出超過幅が前年同期から大幅に縮小しました。
結果として、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間連結会計期間の期首から3,908百万円増加したと記載がありますが、ページ冒頭の「現金及び現金同等物の中間期末残高」の差額(22,676百万円 – 22,049百万円 = 626百万円)とは整合性が取れません。これは、おそらく期首残高の定義(前中間連結会計期間の期首残高と前連結会計年度末残高の差異)によるものと考えられます。財務諸表上の現金及び現金同等物の期末残高(22,676百万円)は、前連結会計年度末の残高(20,385百万円に現金及び現金同等物に係る換算差額等を調整した18,768百万円)からは3,908百万円の増加となっており、こちらが実質的なキャッシュの増加額を示していると解釈できます。
セグメント別業績分析
教育分野:市況と収益性
-
売上高: 49,639百万円(前年同期比3.0%増)
-
セグメント利益(営業利益): 4,074百万円(前年同期比10.8%増)
教育分野は増収増益を達成しました。
主な事業別の状況は以下の通りです。
-
教室・塾事業: 売上高 27,256百万円(前年同期比0.1%増)、営業利益 1,638百万円(同8.6%増)。 塾事業では、首都圏を中心とした市進ホールディングスの伸長が寄与し増収。教室事業は減収となったものの、幼児会員数は増加しており顧客基盤は拡大しています。コスト効率の改善や不採算教室への対応が奏功し増益となりました。
-
出版コンテンツ事業: 売上高 13,574百万円(前年同期比4.0%増)、営業利益 1,578百万円(同26.8%増)。 高校学参書、語学書、実用書でヒット作が生まれ、返品率も改善。看護師向けeラーニングやオンライン英会話「Kimini」の受講者増も寄与し増収。返品率改善やコスト効率向上に加え、デジタルコンテンツ事業の拡大が増益に繋がりました。
-
園・学校事業: 売上高 8,808百万円(前年同期比11.7%増)、営業利益 1,063百万円(同6.5%減)。 幼児事業は幼稚園・保育所数および園児数の減少で減収が続くものの、学校事業では桐原書店のグループインが寄与し増収。営業利益面では、幼児教育事業は経費削減で黒字転換しましたが、学校事業において小学校向け教科書改訂に伴い伸長した前年度からの利益減少を桐原書店の寄与で一定程度補ったものの、全体では減益となりました。
教育分野全体としては、学習参考書の好調や桐原書店の連結効果が売上を牽引し、教室・塾事業や出版コンテンツ事業における収益性改善が利益を押し上げました。
医療福祉分野:成長と課題
-
売上高: 46,329百万円(前年同期比9.9%増)
-
セグメント利益(営業利益): 1,310百万円(前年同期比37.8%減)
医療福祉分野は増収ながら大幅な減益となりました。
主な事業別の状況は以下の通りです。
-
高齢者住宅事業: 売上高 22,385百万円(前年同期比11.6%増)、営業利益 599百万円(同45.2%減)。 引き続き高水準の入居率を維持し、新規開設も堅調で増収。しかし、水道光熱費、食材費、消耗品費などの高騰が大きく影響し大幅な減益となりました。2025年3月からの価格改定や業務効率化によるコスト削減で下半期の利益回復を見込んでいます。
-
認知症グループホーム事業: 売上高 19,937百万円(前年同期比6.9%増)、営業利益 918百万円(同23.9%減)。 建築費上昇で新規出店が難しい中、承継案件含め新規開設を行い拠点数拡大。既存入居率も97%超と高水準を維持し増収。こちらも水道光熱費や食材費等の高騰の影響で減益。2025年2月からの価格改定やコスト削減で下半期の利益回復を目指しています。
-
子育て支援事業: 売上高 4,006百万円(前年同期比16.6%増)、営業利益 113百万円(同36.0%増)。 首都圏中心に学童および児童発達支援施設の新規開設を進め、保育園の定員充足率も高水準を維持し増収。園児数の増加に加え、運営効率化施策の推進により増益となりました。
医療福祉分野では、高齢者向け施設における光熱費や食材費といった運営コストの急上昇が利益を大きく圧迫しています。施設数の増加や高い入居率により売上は伸びていますが、コスト増を吸収しきれていない状況です。価格改定の効果が下期以降にどの程度現れるかが注目されます。子育て支援事業は堅調に推移しています。
その他事業
-
売上高: 2,872百万円(前年同期比9.7%減)
-
セグメント利益(営業利益): 253百万円(前年同期比10.4%減)
その他事業には、グローバル事業などが含まれます。東南アジア、中国市場のポテンシャルを踏まえた継続投資を進めているものの、新興国向けODAや民間企業の海外進出支援事業での受注減により減収。人員強化や投資活動に関連した支出増で減益となりました。
本報告書には、このセグメントにDTP Education Solutions JSCの連結子会社化に伴うのれんの増加額(3,252百万円)が記載されており、今後のグローバル展開の核となることが期待されます。
財務健全性チェック
財政状態計算書の分析
2025年3月31日現在の中間連結貸借対照表の主な項目は以下の通りです。
-
資産合計: 141,882百万円(前連結会計年度末比 11,167百万円増)
-
流動資産: 76,609百万円(同 13,496百万円増)
-
現金及び預金: 24,375百万円(同 3,989百万円増)
-
受取手形及び売掛金: 30,355百万円(同 7,199百万円増)
-
-
固定資産: 65,272百万円(同 2,329百万円減)
-
有形固定資産: 15,879百万円(同 4,073百万円減、純額)
-
無形固定資産: 17,119百万円(同 3,804百万円増、のれん12,733百万円を含む)
-
投資その他の資産: 32,273百万円(同 2,061百万円減)
-
-
-
負債合計: 85,023百万円(前連結会計年度末比 7,961百万円増)
-
流動負債: 48,169百万円(同 4,981百万円増)
-
支払手形及び買掛金: 9,848百万円(同 3,224百万円増)
-
短期借入金: 8,969百万円(同 4,522百万円増)
-
-
固定負債: 36,854百万円(同 2,980百万円増)
-
長期借入金: 17,655百万円(同 3,989百万円減)
-
社債: 7,000百万円(同 7,000百万円増)
-
-
-
純資産合計: 56,858百万円(前連結会計年度末比 3,205百万円増)
-
株主資本: 48,655百万円(同 307百万円増)
-
自己資本(純資産合計から新株予約権と非支配株主持分を除いたものと仮定): 約52,074百万円(計算値)
-
自己資本比率(※2): 36.7%(前連結会計年度末 39.4%)
-
総資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加により増加しました。無形固定資産はDTP社の連結に伴うのれん増などで増加しましたが、有形固定資産は減価償却や売却により減少しています。負債は、短期借入金の増加や社債の新規発行が主な増加要因です。長期借入金は返済が進み減少しています。
純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上(2,424百万円)などにより増加しました。
主要財務指標の評価
-
自己資本比率: 36.7%(前連結会計年度末 39.4%から2.7ポイント低下)
一般的に30%以上が一つの目安とされますが、M&A等による総資産の増加や有利子負債の増加が影響し、やや低下しました。引き続き注視が必要です。 -
D/Eレシオ(※3 有利子負債÷自己資本): 0.79倍(前連結会計年度末 0.75倍から0.04ポイント上昇)
有利子負債(借入金+社債+リース債務)は41,046百万円と、自己資本(純資産から新株予約権と非支配株主持分を控除したものを近似的に使用)と比較してやや高めの水準にありますが、許容範囲内と考えられます。今後の金利動向や収益性改善によるキャッシュフロー創出力が重要になります。 -
流動比率(流動資産÷流動負債): 159.0%(76,609百万円 ÷ 48,169百万円)
短期的な支払い能力を示す指標で、100%を上回っていれば安全性が高いとされます。学研HDは十分な水準を維持しています。 -
固定比率(固定資産÷自己資本): 125.3%(65,272百万円 ÷ 52,074百万円(計算値))
自己資本でどの程度固定資産を賄えているかを示す指標で、100%以下が望ましいとされます。100%を超えており、固定資産投資の一部を借入金等で賄っている状況です。
全体として、財務健全性は一定の水準を保っているものの、M&Aや設備投資に伴う有利子負債の増加傾向が見られ、自己資本比率がやや低下している点は留意が必要です。今後の収益力強化による財務体質の改善が期待されます。
収益構造とコスト分析
営業利益段階での増収減益の背景には、売上原価と販売費及び一般管理費(販管費)の動向が影響しています。
-
売上原価: 71,850百万円(前年同期は67,011百万円)
売上原価率は72.7%(前年同期は71.7%)と1.0ポイント上昇しています。これは主に医療福祉分野における食材費等の高騰が影響していると考えられます。 -
販売費及び一般管理費: 22,449百万円(前年同期は21,353百万円)
販管費は前年同期比で増加しています。報告書に記載されている主な費目を見ると、従業員給与手当(4,598百万円、前年同期4,274百万円)や賃借料(1,831百万円、同1,762百万円)などが増加しています。 これは事業拡大に伴う人員増強や拠点増、インフレ影響などが考えられます。
利益率の観点では、
-
売上総利益率: 27.3%(前年同期は28.3%)と1.0ポイント低下。
-
営業利益率: 4.6%(前年同期は5.5%)と0.9ポイント低下。
売上原価率の上昇が売上総利益率を圧迫し、販管費の増加も相まって営業利益率の低下につながっています。特に医療福祉分野でのコストコントロールと、教育分野での高付加価値化による利益率改善が今後の課題と言えるでしょう。
株主還元の方針
本報告書には、2025年3月期の中間配当に関する記載があります。2025年5月9日の取締役会において、2025年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり13円00銭の中間配当を行うことを決議しています(支払開始予定日:2025年6月5日)。
また、前連結会計年度(2024年9月期末)の配当金は1株当たり12円50銭でした。 中間配当は0円50銭の増配となります。
学研HDは、安定的な配当を継続することを基本方針としつつ、業績動向や将来の事業展開に必要な内部留保のバランスを考慮して株主還元を行うとしています。今後の業績回復と成長に伴う継続的な増配が期待されます。
(サマリー)学研HDの2025年3月期中間期業績は、増収ながら営業・経常減益となりました。教育分野は堅調だったものの、医療福祉分野でのコスト増が響きました。純利益は段階取得差益により大幅増益。財務面では自己資本比率がやや低下しましたが、流動性は維持されています。コストコントロールと収益性改善が今後の鍵となります。中間配当は増配の予定です。
4. 市場環境と競合ポジショニング
有料部分が全部読み放題になります
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
Views: 0