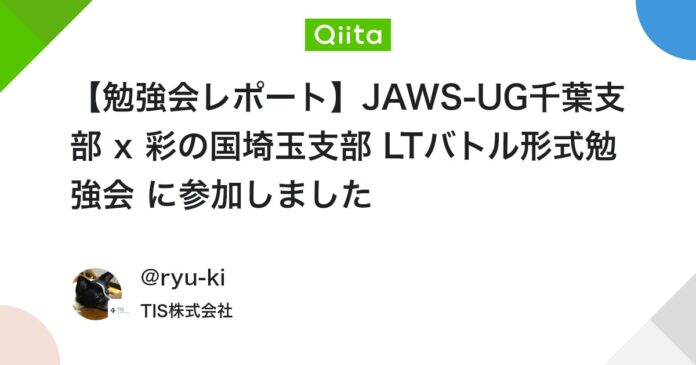はじめに
JAWS-UG千葉支部 x 彩の国埼玉支部 LTバトル形式勉強会 に参加しました。
今回もさまざまな発表があり、勉強になったと感じることがいくつもありました。今回はその振り返りをしたいと思います。
本記事では、発表に対する私の解釈・感想を記載しています。間違いなどありましたらご指摘ください。修正などの対応をいたします。
発表資料のリンクは確認でき次第追記していきたいと思います。
マルチアカウント環境に触れて得た私の知見
実務でのマルチアカウント環境での気づき・学びについてお話しされていました。印象に残ったのは、「価値を下げないこと」を提供するというお話で、AWS Summitの基調講演でも言われていた、価値創造に注力するビルダーを支援するといった話と通じるのではないかと感じました。
また、私は学習もかねて、いわゆる「おひとりさまOrganizations」をしているのでそちらにも今回のお話を活かせればと感じました。
ムダ遣い卒業!FinOpsで始めるAWSコスト最適化の第一歩
コスト最適化の第一歩として、まずは可視化していこうというお話をされていました。コスト最適化は単なるコスト削減でなく、ビジネス価値を最大化することで、組織間で同じ目線になれるようにする努力が必要というお話が印象に残りました。
私自身も最近、部門の検証アカウントのコストの確認をする機会があり、CURなどに手を出し始めていたので興味深く聞かせていただきました。
また、冒頭の渋沢栄一の言葉(常に見直し、最適化を繰り返すことが重要)を、発表の最後にも持ってこられていたのは、発表の構成としてもとても印象に残りました。
Amplify Gen2 で OpenSearch を併用したファセット検索の実現
Amplifyという、AWSでサーバレスなアプリケーションの開発・運用を効率化するフレームワークに、OpenSearchを併用した際の学びについてお話しされていました。
私は今までいくつかWebアプリを作り、AWSにのせて運用していますが、勉強もかねてすべてマネコンやCDKを用いて構築しています。もう少し慣れてきたらAmplifyも試してみたいと感じました。
RAGの構築にも興味があり、OpenSearchのお話も興味深く聞かせていただきました。RAGでも仕組みとしては文書の検索を行っているので、そちらでも何か活かせることがあるのかなと思いながら聞かせていただきました。
また、作業時間は省略するが、学ぶ時間は省略するわけではないという言葉が印象に残っています。これは生成AIなどにも通じると思っており、便利になったものに対して、もともと裏ではどういうことが行われているのかに目を向ける習慣は持っていたいと感じました。
ETLに憧れて無理やりAWS Glueでデータ処理した話
Datadogのアカウント情報をExcelに書き出す作業を自動化したお話をされていました。具体的には、以下の3ステップをStep Functionsで実現されたとのことでした。
- データ取得(Lambda)
- データ加工(Lambda)
- データ変換(Glue)
生成AIの発展によってこのあたりの自動化はどんどんできるようになっているのだなという印象を受けました。ただ、発表では結構な回数AIとのラリーがあったとのことなので、そのあたりのお話も気になりました。
また、Glueで利用するためのデータ加工に苦労されたというお話をされていましたが、どのような点で苦労されたのかも気になりました。
mysqlコマンドを実行したいだけなのに〜AWS Step Functionsと歩んだ脱Jenkinsへの道〜
AWS Step Functionsを用いて、バッチジョブのクラウドシフトを実施したお話をされていました。比較的シンプルな部分はスムーズに移行できたものの、mysqlコマンドの実行に工夫を要したとのことです。
私はまだ経験が浅く、今回のお話を100%理解するのは難しかったですが、さまざまな制約の中で工夫を凝らして自分の実現したいことを実現するというのは、うまくいけばかなり達成感があるのだろうなと感じました。
また、こちらのLambda実装部分でも生成AIを活用されたとのことで、こういった生成AI活用のお話は自分の周りの人に積極的に伝えていきたいなと感じました。
ベスプラに憧れてIAMユーザーを集約した話 -Identity Center × Jump アカウント × CDK で実現するマルチアカウントのアクセス管理-
Identity Centerを用いたマルチアカウントのアクセス管理についてお話しされていました。(私の理解が足りず、ざっくりとした概要説明になり申し訳ございません)
印象に残ったのは、教科書通りの答えをどう緩ませていくかが大事というお話です。これをするためには、まずベストプラクティスへの深い理解が必要で、さらに、そこと実現したいこととのギャップを正しく認識する必要があると感じました。
また、こちらのお話についてQiitaにも記事を投稿されているそうです。ぜひご覧ください。
おわりに
さまざまなテーマがあり、正直すべてのお話を100%理解できたわけではありませんが、発表されている方の熱は直接肌で感じることができたので、やはりオフラインイベントはいいなと思いました。自分もそういった地に足の着いたお話ができるようになりたいなと感じました。モチベーションをたくさんいただけたので、今回参加できてよかったです。社外社内問わずいろいろ頑張っていきたいなと改めて思いました。
ありがとうございました。
Views: 0