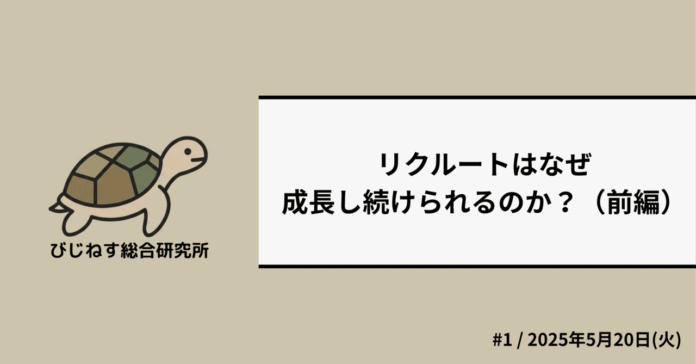🧠 概要:
記事の概要
この記事は、リクルート社の歴史と成長の理由を多角的に分析したものである。著者の神門たかあきが、リクルートのビジネスモデルや経営者の戦略、心理学的経営の手法、そしてM&Aの実績を考察している。リクルートは約4000人の人員削減を発表したが、依然として成長を続ける企業として注目されている。記事は前編であり、26000字を超える内容を2部に分けている。
要約の箇条書き
-
リクルートの歴史と成長: 記事では、リクルートの創業から現在に至るまでの歴史を追い、成長の理由を分析。
-
成長理由の分析:
- 経営者の戦略: 歴代経営者のビジョンと実行力が成長を支えた。
- 心理学的経営: 個の尊重を重視した「心理学的経営」を採用し、社員の内発的な動機付けを促進。
-
ビジネスモデルの独自性: 情報を価値に変える「リボンモデル」で、顧客(求職者や企業)を集め、マッチングを実現。
-
M&A戦略: IndeedやGlassdoorのような企業を買収し、HRテクノロジー事業を強化。
-
業績の好調さ: 売上高は3.4兆円、時価総額は約18兆円に達するなど、ビジネスの幅を広げている。
-
組織文化と人材育成: 社員が自らの可能性を発揮し、自律的に行動できる企業文化を形成している。
- 前編の結論: リクルートは過去の成功体験にとらわれず、自己変革を続け、市場でのリーダーシップを維持している。
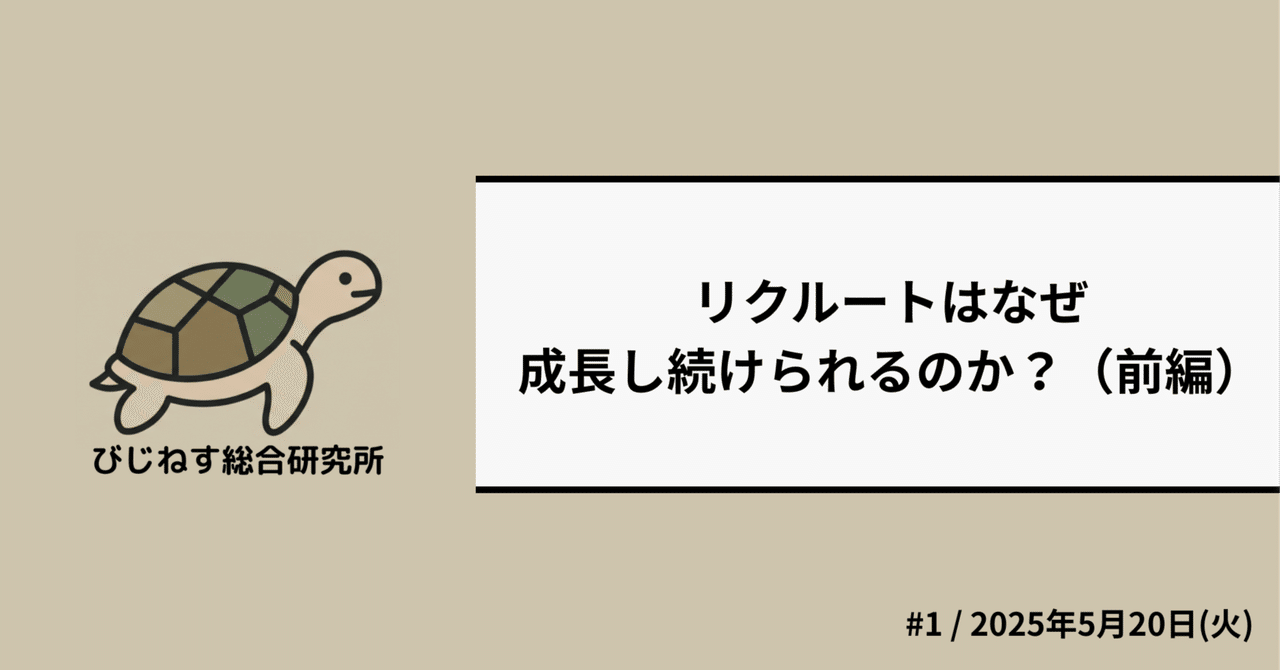
初めまして、神門(カンド)です。
普段は、East VenturesというVCに勤めています。
びず研、記念すべき第1弾は「リクルート」を取り上げます。
気合いを入れすぎて26000字を超えてしまいましたので、前編後編の2部構成でお送りします。
しかしこれを読んだ暁には、リクルートについて他者に説明できる身体になっているはずです。(自信をもって言えます。。。!)
<導入>
直近リクルートは約4000人の人員削減を発表しました。従業員数は約5万人なので、8%の人員削減となります。1/3のコードをAIに書かせると言うのだから、この規模の企業としてはすごいものです。
「リクルートってぶっちゃけ何をしてる会社なの?」
「何で稼いで、何で儲けているの?」
という、素朴な疑問があるかと思います。このでは、そんな素朴な疑問から、今日に至る歴史などを網羅的にまとめました。主に、以下を知ることができます。
【学べること】
・リクルートのこれまでの歴史
・リクルートが成長し続ける理由
:歴代経営者の戦略や組織文化の変遷から解説
・リクルートのM&A手法 :リクルート独自のM&Aルール:IndeedのM&A
<主なポイント>
・個の尊重を重視した「心理学的経営」
・業界のスタンダードを作る市場への早期参入
・過去の成功体験にとらわれず自らを変革し続ける「連続的自己否定」
では、どうぞご覧ください!
その前に、ぜひ私のXをフォローしていただけますと嬉しいですw
◆ びず研(びじねす総合研究所)とは?
詳しくは、こちらをご一読くださいますと幸いです。
<概要>
まずは、リクルートのHPに記載の「数字で見るリクルートグループ」から概要を見ていきましょう。
現在のリクルートID登録者数は世界で8.7千万人も存在しており、これはIndeedも含みます。売上高は3.4兆円、海外売上高比率は53%を超えており、紛れもないグローバルテック企業となっております。2010年代初頭の海外売上高比率が数%だったことを考えると、なんという成長なのか。。。
 引用:https://www.recruit.co.jp/employment/students/service/
引用:https://www.recruit.co.jp/employment/students/service/
時価総額&株価
時価総額を見ていきましょう。
2015年は約2兆円の時価総額でしたが、2024年の12月30日(直近のピーク時)には約18兆円にまで到達しました。この10年間でおよそ9倍になっており、1963年の創業から実に60年と言う長い歴史を迎える企業でありながら、直近の成長は目を見張るものがあります。
 引用:https://irbank.net/6098/cap?mw=2
引用:https://irbank.net/6098/cap?mw=2
業績
この時価総額の成長には多くの要因があると思われますが、やはり1番は業績の好調な伸びでしょう。2012年に、リクルートはHD化し持ち株会社制に移行したため、2012-13年度で売上高が跳ね上がっていることを考慮に入れながら業績を見てみます。
2015年におよそ1.3兆円だった売上高は、2025年3月には3.5兆円になり、10年間で売上高はおよそ2倍、営業利益はおよそ4倍とかなりの工業石であることがわかります。
また1株当たり利益を示すEPSも、2015年には約42円でしたが、2025年には270円と6倍以上になっています。このような好調な数字背景に時価総額が伸びていることがわかります。
 引用:https://irbank.net/E07801/pl
引用:https://irbank.net/E07801/pl 引用:https://irbank.net/E07801/pl
引用:https://irbank.net/E07801/pl 引用:https://irbank.net/E07801/pl
引用:https://irbank.net/E07801/pl
セグメント
この好調な業績は、以下の3事業から生み出されています。
 引用:https://www.recruit.co.jp/company/group/
引用:https://www.recruit.co.jp/company/group/
以下、各セグメントの事業内容などの詳細です。
<HRテクノロジー事業>グローバル展開しているHRテック事業。・グローバルなオンライン求人プラットフォーム「Indeed」・企業の口コミ・評価サイト「Glassdoor」を運営・求職者と企業のマッチングをテクノロジーで効率化し、採用プロセスの自動化などを推進
主なサービス
・Indeed (求人検索、有料求人広告、Indeed Smart Sourcing等)
・Glassdoor (企業情報、企業ブランディング) など
<マッチング&ソリューション事業>日本国内を中心とする、我々の生活に根付いたマッチング事業。
・日本国内を中心に、住宅、美容、旅行、飲食、結婚などのライフイベント領域や日常消費領域におけるマッチングプラットフォーム
・中小企業向けの業務支援SaaS(Airビジネスツールズなど)を提供人材領域
「リクナビ」「リクナビNEXT」「タウンワーク」など
販促領域
住宅: 「SUUMO」美容: 「ホットペッパービューティー」旅行: 「じゃらん」飲食: 「ホットペッパーグルメ」結婚: 「ゼクシィ」
業務・経営支援SaaS: 「Airレジ」「Airペイ」「Airシフト」などAirビジネスツールズ
 引用:https://www.recruit.co.jp/company/group/
引用:https://www.recruit.co.jp/company/group/
<人材派遣事業>実は、売上高の50%以上を占める事業。
・
日本、欧州、米州、豪州などで総合的な人材派遣サービスを提供・各マーケットの特性に応じた「ユニット経営」を推進
主なブランド
株式会社リクルートスタッフィング(日本)、RGF Staffing(旧USG People、欧州)、Staffmark(米国)など。
<売上>
次に、セグメント別売上高を見てみましょう。
2019年から会計基準をアメリカ式に変えたのと同時に、セグメント分けも変更されました。この売上高推移を見ても、人材派遣事業の寄与がとても大きいことがわかります。ホットペーパーやじゃらんなどのto Cの印象が強いですが、実は人材派遣事業会社なんですね。
また、2022年からはHRテクノロジー事業の伸びが顕著なことがわかります。これは、Indeed買収(2012年)、Glassdoor買収(2018年)の効果が出てきていることが要因と考えられます。
 引用:https://www.buffett-code.com/company/6098/financial
引用:https://www.buffett-code.com/company/6098/financial
<利益>
セグメント別利益も見てみましょう。人材派遣事業は売上規模と比較すると、利益への寄与度はそんなに大きくないことがわかります。特筆すべきは、やはりHRテクノロジー事業ですね。2022年以降の利益の伸長が圧倒的です。なぜここまでの急激な上げ幅を記録できたのでしょうか?
 引用:https://www.buffett-code.com/company/6098/financial
引用:https://www.buffett-code.com/company/6098/financial
<利益率>その答えは、セグメント別利益率を見ればわかります。リクルートの3大事業のうち、稼ぎ頭は人材派遣事業ですが人材集約型ビジネスという側面があるため利益率が6%程とそこまで高くありません。しかし、2022年を境にHRテクノロジー事業の利益率が大幅に改善したことが、上記の営業利益の急激な成長に寄与したものと思われます。
 引用:https://www.buffett-code.com/company/6098/financial
引用:https://www.buffett-code.com/company/6098/financial
では、本題に入っていきましょう。
リクルートはなぜ、成長し続けられるのか?
<目次>
<沿革>
リクルートの沿革はこちらです。より詳しく知りたい方は、公式HPおよび「The社史」をご覧ください。
 引用:https://www.recruit.co.jp/employment/students/service/
引用:https://www.recruit.co.jp/employment/students/service/
<歴代経営者>
 筆者作成
筆者作成
リクルートは1963年の創業から2025年に至るまで、リクルート事件やそれを発端としたダイエー傘下入り、巨額有利子負債の返済、インターネット企業への脱皮、グローバルHRテック企業への転換、など多くの出来事がありました。
各経営者にはそれぞれミッションがあったと考えられます。一体、歴代経営者のミッションとはなんだったのか?伝説の起業家、江副氏から見ていきましょう。
【第1章:「情報をカネに変える」ビジネスモデルの開発】
 筆者作成
筆者作成
1. 江副 浩正 (えぞえ ひろまさ) :1960-88年 / 【創業者、組織文化、ビジネスモデルの発明】
 引用:https://www.sbbit.jp/article/cont1/61005
引用:https://www.sbbit.jp/article/cont1/61005
時価総額15兆円起業リクルートは、「起業の天才」と称される、江副 浩正 (えぞえ ひろまさ)氏によって創業されました。
【在任期間】:25年・1963年:株式会社日本リクルートセンター設立・1988年:社長退任
【経歴】
・1936年 愛媛県生まれ・甲南中学校・高等学校を卒業・1960年 東京大学教育学部教育心理学科卒業
:リクルートにおける右腕・大沢武志氏と「心理学的経営」を実践(後で詳述)
◆起業
・1960年(23歳) 「大学新聞広告社」(リクルートの前身)を設立 :大学在学中に東京大学新聞社で広告営業を経験し、その経験を元に起業
◆リクルート時代(1963〜88年)
・1963年(26歳) 株式会社日本リクルートセンターを設立 :代表取締役社長・1988年1月 代表取締役会長に就任
◆リクルート事件(1988年)
・1988年6月 リクルート事件報道 :不動産を扱う子会社リクルートコスモスの未公開株が、政治家に賄賂として譲渡 :同月会長を辞任し相談役に就任・1989年2月 贈賄容疑で逮捕・2003年2月 執行猶予付き有罪判決が確定・2013年 逝去
:同年2月8日、享年76歳
<経営者としての役割>
A. 創業とビジネスモデルの確立
現在のリクルートの根底として、「情報をカネにする」という革新的な発想があります。リクルートの祖業は、江副氏が1962年に創刊した大学生向け就職情報誌「企業への招待」(後のリクルートブック)です。企業から広告料を得て、求職者(学生)に無料で情報を提供するという当時としては画期的なビジネスモデルを確立し、日本の就職活動のあり方を大きく変えました。
江副氏が開発した情報をカネにするビジネスモデルは、「リボンモデル」と言われています。サービスを使うカスタマー(例:就活生)とクライアント(例:企業)を「集めて」、集めた両者にサービスを積極的に使ってもらうよう「動かして」、最後に、カスタマーとクライアントをマッチング(「結ぶ」)させるというモデルです。このビジネスモデルは、リクルートが展開するほぼすべての事業の根底に通ずるものです。
 引用:https://br-campus.jp/articles/report/129
引用:https://br-campus.jp/articles/report/129
B. 事業領域の拡大(多角化戦略)
就職情報に留まらず、人々のライフステージやライフスタイルに関わる様々な領域で情報誌を次々と創刊し、事業を多角化していきました。江副氏がリクルートにおいて影響力をある程度持っていた時期において創刊された雑誌が以下の通りです。
【主な創刊誌】
・「週刊住宅情報」(現 SUUMO、1976年)・「とらばーゆ」(女性のための転職情報、1980年)・「エイビーロード」(海外旅行情報、1984年)・「カーセンサー」(中古車情報、1984年)
・「B-ing」(社会人のための転職情報)
【以下、リクルート事件以降の雑誌】
・「ガテン」(技能職求人情報、1990年)、「ケイコとマナブ」(進学・資格・習い事情報、1990年)
・「じゃらん」(宿泊旅行情報、1990年)
・「ゼクシィ」(結婚情報、1993年)
・ホットペッパー(飲食・美容などのクーポン付きフリーペーパー、2000年)
など
C. 不動産事業への大規模進出
事業多角化の一環として、子会社リクルートコスモス(現コスモスイニシア)を通じて、マンション開発・分譲などの不動産事業に大規模に参入しました。一時はリクルートグループの収益の大きな柱となりましたが、後のリクルート事件の大きなきっかけとなり、その後のダイエー傘下入り、巨額有利子負債の返済という企業にとっては大きな転換点となりました。
D. 独自の企業文化の醸成
① 「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」
この社訓は1968年に制定され、リクルートのバリューズ(大切にする価値観)の根底に流れる最も象徴的な言葉です。社員一人ひとりが現状に満足せず、主体的に新しい価値を創造し、その過程で自己変革を遂げることを奨励するものであり、リクルートの社風を形成する上で決定的な役割を果たしました。この精神は、現在の新規事業提案制度「Ring」など具体的な制度としても結実しています。
②「社員皆経営者主義」
江副氏は「会社は社員みんなのものである」という考えをもっていました。社員一人ひとりが当事者意識を持ち、自律的に仕事に取り組むことを重視し、社内に「プロフィットセンター(PC)」と呼ばれる独立採算の小組織を多数設置し、そのリーダーに大きな権限を委譲しました。これにより、多くの社員が経営経験を積み、社内外で活躍する起業家を多数輩出する「人材輩出企業」としての評価を確立しました。
③ ナンバーワン主義
「2位になることは我々にとっては死」という言葉に象徴されるように、進出する市場においては常にトップを目指すことを強く意識していました。後発であっても既存の良い点は積極的に取り入れ、協調的競争を通じてナンバーワンであり続けることをモットーとしました。この徹底した競争意識が、リクルートの各事業が高い市場シェアを獲得する原動力となりました。2位じゃダメなんですw。
E. 人材育成
① 「採用狂」
江副氏は、採用を経営の最重要課題の一つと位置付けていました。優秀な学生を獲得するためには、取締役会よりも学生の面接を優先することもあったと言われています。また、理工系学生の採用のためにスーパーコンピュータを自社で購入したこともあります。1968年にIBM 1130を日本企業として初めて導入し、テスト事業などで活用し、情報を扱う企業として、最新のIT環境を追求・整備していました。それほど、人の採用を重要視し、お金を出していたということでしょう。当時の日本においてコンピュータを導入するというのは先進的すぎる意思決定です。また、データセンターの設置も構想していたようです。
② 社員のモチベーションと自己成長の促進
「企業は人生の学校である」と考え、社員が仕事を通じて学び、成長することを重視しました。新入社員に対して心構えや仕事への取り組み方を説き自律的な成長を促した、「12の言葉」は有名です。また、「君はどうしたいの?」という問いかけは、社員の当事者意識を引き出すリクルート独特のコミュニケーションとして定着しています。読んでみてください、金言ばかりです。
【12の言葉】
1)君はピカピカの新入社員として注目されている。注目されている間は大きな機会が開かれていると考え、自ら積極的に働きかけよ。時が経ち注目されなくなってから働きかけても、周囲はなかなか振り向いてはくれない。2)学校と企業とは全く別の世界と考え、今日を区切りとし、今まで学んだことはひとまず棚上げし、一から学ぶ姿勢を持て。企業において「失敗は成功の母」という言葉ほど、教訓に満ちた格言はない。1度失敗すれば2度と同じ失敗はしないものだ。失敗を恐れぬ勇気を持て。ブリッ子よりダサイ人間の方がよく伸びる。
3)新入社員は会社にとっては扶養家族である。一日も早くなくてはならぬ人間になって欲しい。会社が君に期待しているのは、我々の共同の目標に対して君が自ら進んで貢献することだ。それも「まあまあ」、「ほどほど」といったレベルではなく、精一杯の貢献である。
4)目標を大きく持て。志が小さければ人間も小さくなる。この会社の社長になるという志を持ってもらえれば嬉しい。そういう人間が多ければ多いほど良い会社になる。社長は勿論女性でもいい。女子社員もこの会社を結婚までの仮の住まいといった考えを持たないで欲しい。ドラッガーいわく「人はその掲げる目標までしか伸びない」。
5)今日すべきことは明日に延ばすな。明日に延ばすことは人に迷惑を掛けるか、機会を逸するかのどちらかである。総ての仕事をその日のうちに片づけ、毎日空身となって眠れ。明日になって何をするのかを考えるのではなく、良い明日とする為に今日何をどこまでやるかが大切なのである。
6)上司・先輩の話を聞くときは鵜呑みにするな。質問を心がけよ。疑問を持ち、議論をし、そして理解出来ればそれは間違いなく実行出来る。会議に列席すれば必ず発言すべし。意見がなければ質問でも良い。会議で一言も発言しない存在感の薄い人間になるな。
7)ビジネスはbusy(忙しい)とness(事)の結合語である。ビジネスマンは忙しい人。永いビジネスマン生活で大切な事は健康管理である。身体の調子が悪ければ気力も萎える。朝10分早く起きて朝食を必ずとること。室内ゲームよりスポーツを。それも汗の出るスポーツを。思いっきり汗を出せばストレスはすべて解消。
8)企業は人生の学校である。あらゆる場面で向上心を失わないでいること。君自身の成長はいかなる場面でも君自身の姿勢と努力の結果である。周囲は君に対して刺激を与えるに過ぎない。至るところに師を見つけよ。論語にも「3人行けば必ず我が師あり」とある。
9)社内だけではなく社外に友を持て。外飯、外酒を心がけよ。同窓会には努めて出席せよ。社内だけしか通用しない人間になるな。良き社員であると同時に良き社会人であることを心がけよ。
10)君は近いうちに気の合わない人間に出くわすだろう。あいつとは気が合わない、あの人はどうも苦手だ、等という心を持つことは自分の居場所を狭くする。誰に対しても「彼も人なり、我も人なり」と、広い心を持って接するように。
11)君はいつか、仕事や人間関係に於いて失望したり落胆することがあるだろう。失望と落胆とは長い人生につきものである。大事なことは、失望を希望に、落胆を奮起に変える、人生に対する前向きの姿勢である。いつもピンチをチャンスに変える努力を重ねれば、君の熟年時代は素晴らしいものになるはずだ。
12)君は隠れた大きな力の持ち主である。まず君自身が持っている隠れた力を自覚することだ。そしてその力をいかに表に出すかである。問題は勇気である。勇気を出せ。いつの場合も引っ込み思案は敵、積極果敢は味方。
引用:https://www.truepm.co.jp/blog/6677/
③ 「心理学的経営」の試み
創業初期には、社員のモチベーションを高めるために「心理学」を経営に取り入れました。これは、カリスマ的なリーダーシップに頼るのではなく、社員の内発的な動機付けによって組織を活性化させようとする考え方であり、後の「社員皆経営者主義」にも繋がる発想と言えます。この心理学的経営を推進したのが、同社の創業メンバーで元専務取締役でありSPIの開発者でもある大沢武志氏です。この心理学的経営については、後ほど詳しく触れます。
まとめると、江副氏の最大の功績は「ビジネスモデルを開発」したこと、そして「組織文化を根付かせた」こと、この2つかと考えられます。リクルートの骨格と血肉を、代表としての25年間で構築したことが、その後の回復・成長の下地となったのでしょう。
2. 位田 尚隆 (いだ なおたか) :1988-97年 / 【経営再建、OPT制度、ゼクシィ・リクナビ】
 引用:https://imagelink.kyodonews.jp/search?product_type=1,2,11&keyword=%E4%BD%8D%E7%94%B0%E5%B0%9A%E9%9A%86&opendetail=9202371
引用:https://imagelink.kyodonews.jp/search?product_type=1,2,11&keyword=%E4%BD%8D%E7%94%B0%E5%B0%9A%E9%9A%86&opendetail=9202371
「起業の天才」江副氏が残した負の遺産をきれいに片付けようと奮闘した男、位田 尚隆 (いだ なおたか)氏です。
【在任期間】:10年・1988年1月~1997年6月
【経歴】
・1937年10月15日 愛知県名古屋市出身・愛知教育大学教育学部、東北大学教育学部卒業・1964年 東北大学大学院修士課程修了
◆日本アイ・ビー・エム:25年
・1964年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社・1976年 同社取締役・1984年 同社専務取締役
◆リクルート:10年
・1988年1月 株式会社リクルート代表取締役社長に就任 :リクルート事件に揺れる同社の江副氏の後任
・1997年6月 代表取締役社長を退任し、取締役相談役に就任
<経営者としての役割>
A. ダイエー傘下での経営再建
位田氏の一番のミッションはやはり、リクルート事件後の立て直しでしょう。創業者・江副氏の逮捕という未曾有の危機の中、生え抜きではない立場として、経営の立て直しと社会からの信頼回復に尽力しました。
また事件の反省を踏まえ、1989年に経営理念を改定。「商業的合理性の追求」を筆頭としていた旧経営三原則を見直し、「新しい価値の創造」「個の尊重」「社会への貢献」を新たな柱としました。
さらに、江副時代に始めたリクルート事件の発端ともなった不動産事業(子会社・リクルートコスモス)がもたらした深刻な財務状況の中、1992年に中内功氏率いる大手スーパーダイエーの資本参加を受け入れ、ダイエーグループ傘下で経営再建を進める決断を下します。これは江副氏の株式売却に伴うもので、リクルート経営陣と江副氏の間で意見対立も見られたものの、この意思決定によってリクルートは経営再建の道を歩み始めました。
ここでダイエーグループのちょっとした補足を。この時代のダイエーは1995年度の世界の小売業の中で売上高で4位になるほど飛ぶ鳥を落とす勢いで、日本のGMS(総合スーパー)を代表する企業でした。日本の小売市場におけるスタンダードを0から作ったヤバすぎる企業です。しかし、土地を担保にした拡大戦略がバブル崩壊とともに機能不全に陥り経営不振に。2001年に中内氏は責任をとって会長を退任し、同年産業再生法の適用を受けてリストラを進めて経営再建を図りましたが、2015年にイオンの完全子会社となりました。
B. OPT(Over Thirty Pension Plan)制度
経営再建の一環として進めたのが、組織・人事制度の見直しです。1997年にはOPT(Over Thirty Pension Plan)制度を導入。リクルートは人材の新陳代謝が激しい企業として有名ですが、30歳以上の社員が早期退職する際に退職金を割り増しするというこの制度によって、人員構成の若返りと固定費抑制を図った結果、「人材輩出企業」としての側面が自然と強まっていきました。
まさか、財務体質の抜本的改善の施策として作った制度が、人材の新陳代謝を活発にし組織の活性化につながるとは。おそらく、この際に支払われる退職金を自身の起業時に使ったりしていると予測されます。ただし、退職金の優遇制度は2021年に廃止されており、人事制度における方針転換を行なっているようです。リクルート出身者の出身者の企業一覧などもまとめたら面白そうです。
C. 新規事業(ゼクシィ・リクナビ)、インターネットへの対応
位田氏は不動産事業で膨らんだ負債の処理を進めつつ、情報誌を中心とした本業回帰を志向し、インターネットへの対応も進めていきました。その最中に誕生したのが、後の主力事業となる結婚情報誌「ゼクシィ」(1993年創刊)や、インターネットメディア「Mix Juice(現 ISIZE)」(1995年開始)です。
特に、マッチング&ソリューション事業の中核事業である「RB on the NET(現 リクナビ)」や「Digital B-ing(現 リクナビNEXT)」が生まれたのもこのタイミング(1996年)です。主要な就職情報サービスのオンライン提供を開始し、紙媒体からデジタルへの移行の第一歩を踏み出しました。
経営再建中でも、今にも残る新規事業が創出されたり、それまでの成功パターンを一種「自己否定」する姿勢こそが、リクルートという企業の底力を物語っているように感じます。
【第2章:続く経営再建、アナログからデジタルへの転換】
 筆者作成
筆者作成
3. 河野 栄子 (こうの えいこ) :1997-2004年 / 【続く経営再建、ホットペッパー】
 引用:https://www.nikkei.com/article/DGKDZO73131120R20C14A6NNMP00/
引用:https://www.nikkei.com/article/DGKDZO73131120R20C14A6NNMP00/
経営再建は、同社初の女性社長・河野氏に引き継がれました。
【在任期間】:8年・1997年6月~2003年5月:代表取締役社長・2003年6月〜2004年3月:代表取締役社長兼CEO
【経歴】
・1946年1月1日 兵庫県生まれ・1969年3月 早稲田大学教育学部国語国文学科卒業
◆日産サニー共立販売:9ヶ月
・1969年4月 日産サニー共立販売入社
◆リクルート:50年以上
・1969年12月 株式会社日本リクルートセンター(現リクルート)入社 :営業畑を歩み、独自の「飛び込み営業」スタイルを確立しトップセールスとして活躍・1984年6月 当時最年少(38歳)で取締役に就任 :その後、常務取締役(1985年)、専務取締役(1986年)、取締役副社長(1994年)を歴任
◆リクルート社長
・1997年6月 位田氏の後任として代表取締役社長に就任 :リクルート初の女性社長として注目・2003年6月、代表取締役社長兼CEOに就任
◆リクルート会長・特別顧問
・2004年4月、取締役会長兼取締役会議長に就任
・2005年6月、特別顧問に就任
<経営者としての役割>
A. 財務体質の改善&女性活躍の象徴
社長就任時、リクルートはバブル崩壊と不動産事業の失敗により約1.4兆円もの有利子負債を抱えていました。本業(情報誌事業など)で高収益(営業利益率約30%)を確保・維持し、ノンコア事業からの撤退やリストラクチャリングを進めてその利益を借金返済に充てることで、有利子負債の大幅な圧縮を進めました。
また河野氏は、当時としては珍しい大手企業の女性トップとして、リクルートが「女性も活躍できる会社」というイメージを社内外に浸透させる上で象徴的な存在となったことも挙げられます。
B. ホットペッパー(2000年)
河野氏が社長に就任した1997年は、Windows95が発表されてから2年後ということもありインターネットが普及し始めた時期でしたが、巨額の負債返済に追われる中で、既存事業のオンライン化はそこまで進みませんでした。
その中で誕生したのが、2000年創刊の無料クーポンマガジン「ホットペッパー」。当初は地方都市(新潟・長岡・高松)の3か所でテスト的に開始し、その後全国の主要都市に展開していきました。飲食店や美容室など、地域密着型の中小企業を新たな広告主として開拓し、今では「ホットペッパーグルメ(2000年〜)」「ホットペッパービューティ(2007年〜)」など、我々の生活になくてはならないサービスになっています。ホットペッパーがメジャー化させたクーポンビジネスは景品表示法によって長らく規制されていましたが、1980年代後半から徐々に緩和。これを受けて、1990年代以降に様々なクーポンビジネスが誕生し、新しい集客手段として注目を集めていきました。
実は、このホットペッパーの元となったアイデアは、ローカル地域に「総合的な生活情報」を提供するための冊子として誕生した、1994年創刊の「サンロクマル(360°)」です。1990年代までのリクルートは、大都市における結婚、引越し、就職などの「大都市圏×ビッグイベント巨大広告」というのが勝利の方程式でした。そんな中、「地域×総合誌」という対極な立ち位置がこの雑誌でした。いわば究極の自己否定です。対象地域を札幌などの13エリアに絞り、想定読者を20〜30代の働く女性に設定したため、当初の主戦場は「エステ」でした。
しかし、「サンロクマル(360°)」の業績は思うように伸びませんでした。そこでホットペッパーはエステではなく、日常的に必ず行う「飲食」に着目。ここで重要視したのが、消費生活における「生活圏」です。人間の消費のほとんどは半径2キロの生活圏で行われていることを重要視し、「共通ストーリー×複数のバージョン」のモデルを開発し、地域ごとに数多くのバージョンを出すことによって、「狭域情報ビジネス」を成立させたのです。
このホットペッパー事業は従来のイベントにフォーカスしたリクルートの事業ドメインを日常的なコンテンツにまで拡張する突破口となりました。このホットペッパー事業は、現在においてはマッチング&ソリューションセグメントの中核事業となっています。リクルートの歴史において、日常生活に溶け込むことのできた当事業は、かなりの影響を及ぼしたといっても過言ではありません。おそらくこれがないとAirレジも誕生しなかったことでしょう。
以下の記事がとても面白いのでおすすめです。これは、後述する「リクルートの持続的成長の源泉とは:C. 連続的自己否定」で詳しく触れます。
C. 人材派遣業へ注力開始(1999年)
リクルートが子会社「シーズスタッフ」を設立して人材派遣業に参入したのは1987年とかなりのパイオニアでした。1999年に人材派遣子会社の商号を「リクルートスタッフィング」に変更し、人材派遣事業に積極投資を行なっていきます。同社は首都圏を主要拠点として、事業展開においては専門分野に特化するのではなく幅広い業種を募集し、全方位における派遣ニーズを汲み取る形で、売上成長を実現していきました。
4. 柏木 斉 (かしわぎ ひとし) :2004-12年 / 【経営再建完了、ITへの本格シフト、M&A推進、急成長の礎】
 引用:https://cocre.jalan.net/cocre/camp/tanebists/
引用:https://cocre.jalan.net/cocre/camp/tanebists/
長引いた経営再建がやっと完了したのがこの時代。そして、リクルートはIT企業への本格的なシフトを行なっていきます。私は、柏木氏が現在のリクルートにおける大きな転換点になったと考えています。
続きは後編で!
もしよろしければ、シェアもしていただけますと幸いです。
また、私のXでは、ショートな内容で社会やビジネスに関する情報を発信していますのでぜひフォローしていただけますと幸いです。
Views: 0