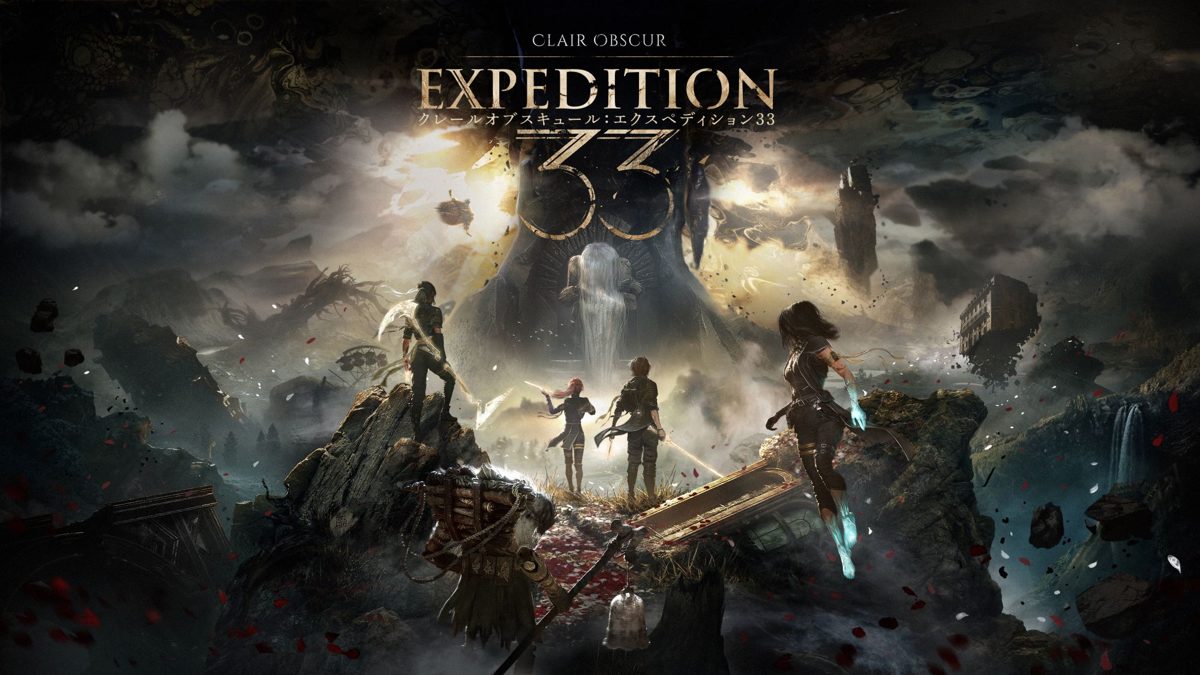『Clair Obscur: Expedition 33』はJRPGのようなターン制バトルに、パリィや回避といったリアルタイムアクションを組みあわせたフランス産ゲームだ。ボス戦ではまるでソウルライクのように、何度もやられながら敵の攻撃モーションを覚えていくこともあった。パーティ編成とビルドを変えて、なんとかボスを倒したときもある。達成感と戦略性が両立したバトルは本作の大きな魅力である。
ゲームの世界観は20世紀初頭あたりのフランスの時代と、ファンタジーが融合している。33歳以上の人々が消失するという独特な設定も興味深い。世界観が魅力的な一方、ストーリーそのものは伏線が感じられない唐突などんでん返しがあり、JRPGの悪いところまで真似していると感じた展開も悪目立ちしてしまった。
バトルがJRPGに似ている一方、後半になるほどストーリーはJRPGでは体験できないような独自の視点から描かれる物語になっていく。ゲームは全体的に見過ごせない問題点がいくつかあるが、尖った魅力とメッセージ性があり、強く印象に残る作品となっていた。
消失する人々の心情を丁寧に描くオープニング

本作は、19世紀末から20世紀初頭あたりのフランス・パリの時代「ベル・エポック」をモチーフとしたファンタジー作品だ。この世界では、マップの最北端にモノリスという構造物がある。モノリスにはペイントレスと呼ばれる謎の存在がいて、年に一度とある数字を書いている。この数字は呪いの数字となっていて、その年齢以上の人々は世界から存在が消されてしまうという設定がある。この現象は作中で「抹消」と呼ばれ、呪いの数字は毎年1ずつ減っていく。主人公たち遠征隊33のメンバーは、この悲劇を止めるためにペイントレスを倒すのが目標となる。
数字のカウントダウンが起こる日には、人々が街で祭りのようなものを開催するようだ。オープニングではメインキャラクターのギュスターヴが元恋人のソフィーと再会し、街を散策しながら思い出を作っていく場面が描かれている。この日は数字のカウントが34から33になる。ソフィーは33歳なので、彼女にとって人生最後の日である。


オープニングは世界観の説明としてよくできており、死ぬ間際の人々の心情が丁寧に描かれている。上記画像のようにオープニングではインタラクトできる部分が多く、この世界の過酷さと儚さが伝わってきた。
オープニングを中心に、音楽の演出も効果的に機能している。本作の楽曲はピアノやストリングスを使ったものが中心で、ボーカルやコーラスまで入ってドラマチック。オープニングのカットシーンでは、ピアノをバーンと叩くような音で人々の感情を表現している部分もあった。一部のボス戦ではロックやファンクのような曲調まであり、楽曲の数と質が両立していた。

オープニングは、世界を旅する動機付けとして完璧と言える出来だ。この出来事をきっかけにして、ギュスターヴは遠征隊33のメンバーとしてペイントレスを倒すことを誓うのだ。しかしながら、ギュスターヴはまたしても悲劇に遭遇してしまう。

旅を始めたばかりの遠征隊33だったが、どう見ても33歳以上としか思えない謎の男性ルノワールと遭遇する。そして、ルノワールの攻撃で部隊が壊滅してしまう。なぜ、彼は33歳以上なのに生きていられるのだろうか。なぜ、人間が人間を攻撃してくるのだろうか。ストーリーの序盤はルノワールを追いつつ、生き別れになった遠征隊33のメンバーを探すことになる。立て続けに起こった悲劇によって、なんとしてもルノワールを止めたいという気持ちにさせられた。

ゲーム全体としてはルノワールや世界崩壊の謎を追いつつ、ペイントレスの討伐を目指す物語である。完璧に思えるオープニングには胸が熱くなったが、ゲーム中盤あたりからはストーリーに問題点が出てきた。この問題点や本作のメッセージ性については後述する。
達成感と戦略性が両立し、気持ちよさまであるバトルシステム
本作のいちばんの魅力と言えるのがバトルシステムだ。システムの基本は行動順がきたキャラからコマンドを選択する、JRPGのようなターン制タイムラインバトルになっている。普通のJRPGと大きく違うのは、敵の攻撃をすべてパリィや回避でやりすごせるところだ。敵の攻撃は一撃が重く、ある程度パリィや回避をするのが前提のバランスである。
パリィはジャストタイミングでないと成功しないが、回避についてはタイミングがすこしズレていても成功するという違いがある。「それなら回避だけでいいのでは」と思うかもしれないが、パリィはリスクが大きいがリターンも大きいのがポイントだ。
敵の攻撃をパリィできればカウンター攻撃ができるし、スキルの発動に必要なアクションポイント(AP)も獲得できる。回避は敵の行動をやりすごせるだけで、リスクはすくないがリターンもない。本作はターン制バトルでありながら、リアルタイムでリスクとリターンを天秤にかけ、パリィと回避どちらかを選択していくのだ。このリスク・リターンの選択がたまらなく魅力的で、私は本作のバトルを最後まで飽きることがなかった。

また、ゲームが進んでいくと「ジャンプ」と「グラディエントカウンター」という新たな防御手段まで登場する。強敵の場合はパリィも回避もできない攻撃をたまにしてくるようになり、敵の攻撃予兆にあわせてこれら2つの防御手段まで使っていく。
足元をすくうような攻撃はジャンプでのみ回避できる。敵の大技「グラディエントアタック」には、グラディエントカウンターのみで対応できる。これらの特殊な攻撃は受けてしまうと致命傷になりうるが、対応できるとこちらも派手なカウンター攻撃ができるので、その瞬間はかなり気持ちよさがある。


無限にビルドがあるというほどではないものの、かなり自由にパッシブスキルをセットできるところにもハマった。本作では武器のほかに3つの装備品が付けられて、その装備品にはそれぞれパッシブスキルが付いている。
装備をつけたまま戦闘をしていくとこのパッシブスキルが習得でき、その装備を外しても使えるようになる。習得したパッシブスキルは装備品とは別枠でセットができ、キャラの成長とともに得られるポイントを支払うとセットできる。たとえば、自身のHPが減っているほど火力が上がるアクティブスキルを持っているキャラに対して、体力が減っているほどクリティカル率が上がるパッシブを付与することなどができる。パッシブでキャラの長所をさらに強化したり、短所を補ったりできるのだ。パッシブは強いものほど必要なポイントが大きいので、頭を悩ませることになる。


ゲーム中盤あたりになってくるとセットできるパッシブスキルが増えていき、チーム編成を考えるのがたのしくなってくる。私の場合は敵を火傷(毒のように持続ダメージを与える状態異常)にするチーム構成にしてみたり、1人のメインアタッカーにすべてを捧げるようなチーム構成を組んでいた。
ゲーム後半は敵の攻撃が激しいので、私の場合は防御力を確保するビルドにしていた。敵の攻撃をすべてパリィする自信があるならば、攻撃力に寄せたビルドでもよいだろう。無限にビルドがあるというよりは、プレイヤーの得意な部分を伸ばし、苦手な部分を補えるようなシステムである。

本作のボス戦では、まるでソウルライクのような体験ができる。最初は不可能に思えたボスでも何回かやられることで、敵の攻撃のモーションを覚えて攻略できるようになるのだ。パーティ編成とビルドを変えるのも重要で、バトルは全体的に達成感と戦略性が両立している。バトルについては、ゲームをクリアした今でも飽きないほどの魅力が詰まっていた。
唐突などんでん返しなど、見過ごせない問題点あり
本作には、いくつか見過ごせない問題点がある。ストーリー途中では、唐突などんでん返しのような展開があった。伏線があるならそれでもいいのだが、あまりにも唐突な展開に私は戸惑ってしまった。この唐突などんでん返しの展開は、プレイ開始から数時間後にすぐにやってくる。そこからはクライマックスまで唐突な展開が続き、ラスト数時間でようやく「解答編」がある感じだ。本作のストーリー構造を「起承転結」でたとえると、「承」を飛ばして「転」までいったような格好である。ストーリーの流れとしては起→転→転→承→結といった形で、キャラのバックグラウンドや世界構造の深堀りをするタイミングが遅すぎるのだ。
本作は「終わってみるとよかった」とは思える魅力があるものの、プレイ時間の多くは唐突な展開に振りまわされることになる。私の場合、プレイ時間28時間のうち15時間ぐらいはストーリー展開にイライラしていた。レビュー記事の都合上、クリアを目的としてプレイしていたのでよかったものの、普通のプレイヤーは唐突な展開の連続によって途中で脱落してしまう可能性があるだろう。

また、どんでん返しに関連するもの以外でも、唐突なストーリー展開が多かった。本作ではJRPGのようなワールドマップがあり、そこでは乗り物として巨人が出てくる。この乗り物を手に入れるために、ストーリー性があまりないお使いクエストをする場面があった。さらには精霊のような存在が作った村にたどり着くと、なぜか闘技場でトーナメントが始まった。
JRPGの悪いところまで真似していると思える、水増しのような展開が多めなのだ。ゲーム中盤では突然、「先に進むためには、2体のボスの討伐が必要」とも告げられてしまう。そんな設定があったなら、もうすこし伏線となる描写をわかるように入れてほしいと思ってしまう。

そのほか、一部のバトルやサイドコンテンツもストレスになることがあった。一部のボスは即死攻撃をしてくるのだが、この攻撃の防御を1回ミスっただけで致命傷になってしまい、そのあとの戦闘のやる気がそがれてしまう(しかも、その攻撃モーションが嫌らしい)。「即死」と表現したが、この攻撃は正確には「戦闘から除外」するものだ。戦闘から除外されたキャラを戦闘中に復帰させる手段はないので、食らったらどうしようもないのである。
サイドコンテンツについてはストーリー性があまりなく、高難易度のものが多かった。サイドコンテンツのボスはたどり着いた時点ではかなり強く、スルーするしかないケースが多い。本作はワールドマップでのファストトラベルが存在しないので、途中でサイドコンテンツを回収するのも困難だった。ラストダンジョン到達時には世界中を移動できるようになるが、サイドコンテンツは2周目やクリア後のやり込みプレイを前提にしていると思えた。
問題点はあるが、尖った魅力とメッセージ性で強く印象に残る作品に
本作のストーリーは最終的にJRPGの真似ではなく、フランス産ならではの視点からJRPGの王道を紐解き、独自の視点に落とし込んだような展開を見せる。世界を救う物語でありながらも極めてパーソナルな視点になっていく点はJRPGっぽいが、JRPGでは絶対に体験できない物語になっていて、最後にはキャラと作品のメッセージ性に共感できた。私は作中で頻出する、「明日は来る」というセリフが印象に残った。
タイトル名の「Clair Obscur」とは、美術における「明暗描法」を意味している。人は誰しも、人生や心のなかに「明」と「暗」の部分を抱えていると思う。作中とは違い、私たちは33歳で世界から消失することはなく、ある意味無限の時間を持っている。この無限に感じられる時間を活かして、私たちは過去の「暗」の部分を受け入れながら、未来の「明」を探していくべきではないか。それこそが、本作のメッセージ性なのではないだろうかと感じた。ゲーム全体に見過ごせない問題点はあるが、その尖った魅力とメッセージ性によって、本作は私の人生のなかでも強い印象を残すゲームのひとつとなった。

『Clair Obscur: Expedition 33』はJRPGのようなターン制バトルに、パリィや回避といったリアルタイムアクションを組みこんだゲームだ。バトルは一部のボスが使う即死攻撃にはイライラさせられたものの、クリアしてもまったく飽きないクオリティだ。一方でストーリーは唐突などんでん返しや、水増しのようなクエストといった問題が目立った。全体的に見過ごせない問題点がいくつかあるものの、尖った魅力とメッセージ性で印象に残るゲームとなっている。
Views: 1