🧠 あらすじと概要:
映画『花束みたいな恋をした』のあらすじと記事の要約
あらすじ
『花束みたいな恋をした』は、大学で出会った二人の主人公、麦と絹の恋愛を描いた物語です。彼らは互いに共通の趣味を持ち、若いころの文化的な生活を楽しむ中で恋に落ちます。しかし、社会人としての責任や忙しさが彼らの生活に影響を及ぼし、次第にすれ違いや孤独を感じるようになります。物語は、彼らの関係の変化や個々の成長を通じて、恋愛の複雑さを探ります。
記事の要約
記事では、映画『花束みたいな恋をした』を通じて、「働いていると本が読めなくなる時代の流れ」について考察しています。著者は、主人公・麦の姿を現代の若者の象徴と見なし、社会人になることで文化的な趣味が失われることへの共感を示しています。特に、働くことが読書や創造的活動を「ノイズ」にしてしまうことについて深く掘り下げています。
著者は、作品を観た時期によって感じ方が変わり、自身の過去と今の状況から映画が持つメッセージに共鳴することを強調します。また、社会や時代が個人の思想や行動に与える影響についての考察を通じて、自己実現や幸福を追求する中で陥りがちな「ワーカホリック」について言及しています。
最後に、恋愛に関する結論として、対話の重要性を指摘。相手とのコミュニケーションを持ち続けることが幸福な関係を築く鍵であると結論づけています。全体を通じて、時代の流れに飲み込まれつつも、自らの幸せを見つけることの重要性が強調されています。
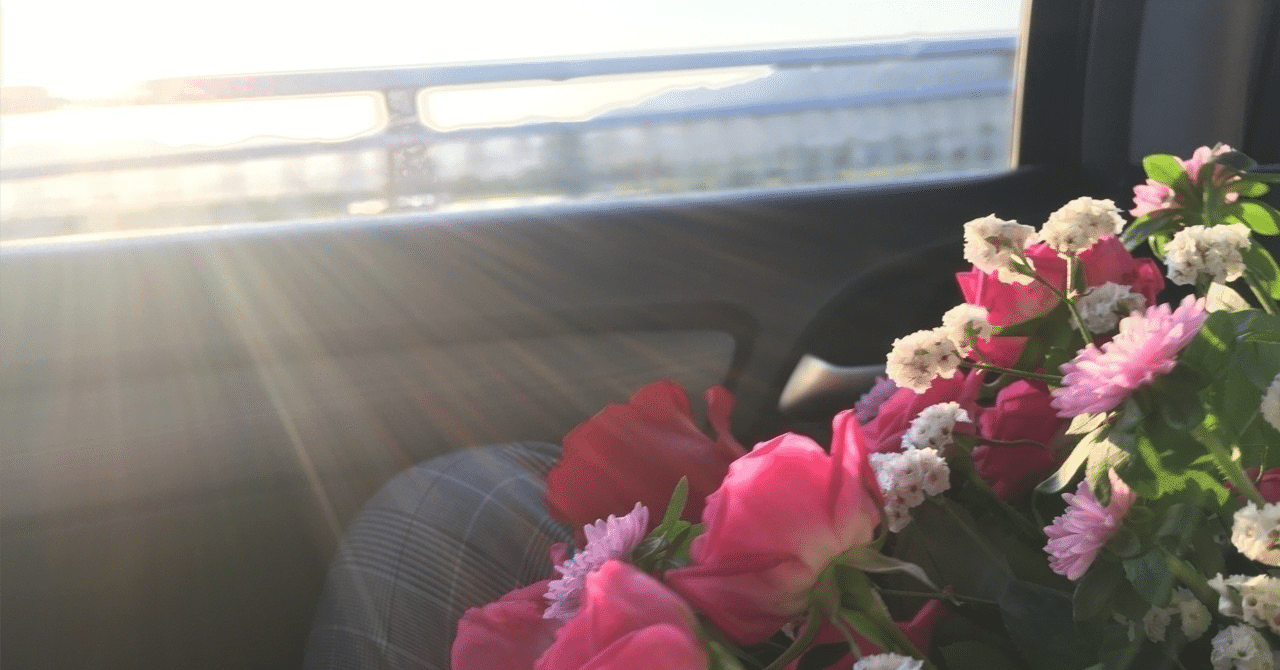
映画が流行った公開時期に、みんなが自分の姿と重ねていたりカップルで観ていろんな論議を飛び交っていたのも記憶に新しいですよね。流行りもすぎた今、この映画を見たいと思った理由、それは三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』がきっかけでした。もともと文化的な生活を送っていた主人公が社会に出て本や漫画が読めなくなり、パズドラしかできないよと言ってる姿が今の現代の若者の姿として象徴的だとたびたび登場していたため、どのくらい共感度高いかな?と興味を持ちました。好きを仕事にすること諦め、社会で責任を負うことで本を読めなくなった「麦」という人物像から客観視するヒントが、得られそうとだなと。
Amazonプライムで見れるよ!さあもう一度!
全体感としての感想
大学生〜社会人なりたての頃に見ていたらもっと違うことを思ったはず。見る人のフェーズで感想が大きく変わりそうな作品だなと思います。自分自身が社会人麦の状態(会社で自分の時間をほとんど奪われ、パズドラしかできなくなるブラックな時代)を経て、かつ、それがワーカホリックであったことを認識して脱却しようとしている今だからこそ、感情移入しすぎず客観的に見れる部分があって良かったです。
とってもありきたりな感想ですが、どんなに価値観が近いと感じる人でも、すれ違いが続けば戻れないほどに離れてしまうこともあるのだなと、環境が変化することによる影響の大きさに、現状良好であるものも永遠ではない不安を感じました。
労働と読書の両立
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』のなかでは、働いていると本が読めなくなる理由、パズドラしかできなくなる背景について、端的にはこう書かれています。
本を読むことは、働くことの、ノイズになる。
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
パズドラならできるし、自己啓発本なら読めるのは、ノイズがないから。盲信的に自分の置かれた環境のなかでより良い状態を作るためには、すでに知っているコントローラブルな娯楽をする、明日からすぐ使えるほしい情報を取りに行く。その傾向を私もずっと辿ってきたし、辿っている。よくよく分かる…。映画のなかで、学生時代は余白があり世界を知ることを楽しんで本を読めていたのに、社会人になると時間的にも精神的にも余裕がなくなってビジネス本しか読めなくなる典型的な姿が細かいところまでうまく表現されている感じました。そして、その状態はきっとワーカホリックと呼ばれるもので、
ワーカホリックになってしまう背景には、本人の意思とは別に世の中の考え方の流れ、世相が大きく関わってるよなと本と映画を通じて改めて感じたのです。
社会の世論と自分の思想について
どこまでが世論や環境、時代によって作られた思想で、どこからが自分の本当に思考して持っている思想なのか。
映画のなかでも、麦が学生のときは言われても反抗していた思想に社会に出てからはどんどん染まっていってしまう姿が描かれていますね。
私が以前に言われて、ピンとこなかったこと。
「〇〇ちゃんって、リベラルと資本主義が染み付いた思考してるよね」という私を熟知している人からのご意見。その時は、ほーん、そうなん?くらいの受け取りでしたが、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んでいるうちに、( ゚д゚)ハッ! 確かに!!仕事において自己実現したい、人と違う自由な生き方がしたい、自分の人生は自分で選択したいし、人生の責任は自分で負わなければいけない、どの考え方も自分が考えてたどり着いたような風でいて、その時代における流れにまんまと乗せられていただけなのか!
ということに気付かされたのです。
どういう世相になっているのか、時代別での流れを三宅さんはこの一節にわかりやすくまとめてくれています。
1990年代以前の<政治の時代>あるいは<内面の時代>においては、読書はむしろ「知らなかったことを知ることができる」ツールであった。そこにあるのは、コントロールの欲望ではなく、社会参加あるいは自己探索の欲望であった。社会のことを知ることで、社会を変えることができる。自分のことを知ることで、自分を変えることができる。
しかし90年代以降の<経済の時代>あるいは<行動の時代>においては、社会のことを知っても、自分には関係がない。それよりも自分自身でコントロールできるものに注力したほうがいい。そこにあるのは、市場適合あるいは自己管理の欲望なのだ。
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
世界は自分の力ではどうにもならなくて、個人の人生にとってはノイズを除去し、コントローラブルな部分を自分の行動で良くしていく必要がある。
読書は知らなかったことを知ることにつながり、世界のアンコントローラブルなものを知ることより、市場適合や自己管理することを重要視する。そんな考え方が90年代以降、私たちが生きているこの時代なんですね。
私は自分の意思で、自分の選択で、そう考えていたと思っていたのに。本に、こういう時代背景だからこういう思想が流行っていたんですって各年代の私が辿ってきた思考回路が全部書いてある。
「私は私!あえてこうしてるの!人と違うでしょ!すごいでしょ!」とドヤってたものが実は周りにお膳立てされて手のひらで転がされてるだけだった、みたいな感じがあってちょっと恥ずかしいですね。。。(こ、これがノイズか、、、笑)
90年以前の歴史や過去のベストセラー本などを読むたび、なぜ自分には日本を変えてやるんだ、という志や気概を持てないんだろう、とずっとモヤモヤしていたのが、それもまた時代における世相の違いなのか、と腑に落ちる部分がありました。と同時に、中学生の頃から自己啓発本やビジネス本ばかりに読んできた私は、かなり色濃くその時代ごとの市場適合や自己管理の欲望を植え付けられてきていたと認識。中学の頃からビジネス本読んでる意識高い系だと自分を誇っていたけれど、蓋をあけてみたら、あの頃からただ余裕がなくて自分がコントロールできる環境をいかによくできるか、を考えたほうが楽だっただけなんだなと。
そしておそらくその自己形成期に「流行っていた」が故に最新情報としてインプットされ続け、影響を受け続けた思想が新自由主義や資本主義のものだったのだなと理解しました。
好きなことで食っていく自己実現の形について
好きなことを活かせるとか、そういうのは人生舐めてるって考えちゃう。
坂本裕二『花束みたいな恋をした』
これ、麦は言ったとき、どんな気持ちで言ったんだろう、と見ながら胸が苦しくなったんですよね。好きなこと、イラストで食っていくのが難しいことだと知って、生活のため、絹と一緒に過ごすために選んだ道であって、本当は好きなことを活かしたかったし、やりたいことをやりたかっただろうな、と。
できない悔しさと嫉妬、もうその道はないんだと言い聞かせているような言葉だと思うけれど、いざ口にしたら、きっと出てきた言葉が言霊のように自分に返ってきて想いの分だけ重く聞こえたじゃなかろうかと思ったり。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』のなかでは、「自己実現系ワーカホリック」というものが取り上げられています。
好きなことを仕事にして自己実現しなくてはいけない、夢を追わなければいけない、という世の中の論調ででそのまま仕事にした結果、種類によっては給料も低く、長時間労働を選ぶことになってしまう危険性があることについて触れられています。
私はその世相にまんまとしっかり乗せられて育ってしまったため、「やりたいことをやらなきゃいけない」、「夢を追ってなければいけない」、けれど「やりたいことがわからない」ことに悩まされ、そんなこと気にしなくていいとわかってるのに「好きなことを仕事にできていない」ことに罪悪感や劣等感に揺られながら今日まで過ごしています。
麦が陥った状態はきっと同様の板挟みで、イラストで食っていくに進んでいたら、自己実現系ワーカホリック(薄給長時間労働)に進むことになり、
ほかの仕事で就職して全力で働くことになったのも、責任という面だけでなく「好きなことを仕事にできていない」ことへの苦しみや嫉妬と、「仕事のなかで自己実現をしていかなければいけない」という切迫感からくるものものでもあったのではないかと想像します。
つまり、あの映画の中において、そもそも麦が得意で好きなものは「イラストを描くことだ」が前提となった時点でどちらの道を選んでも長時間労働のワーカホリックになることは避けられなかったのではないかと考えます。理想的にはもちろん、趣味としてのイラスト、で趣味で自己実現するために仕事をほどほどにやり、全身を突っ込まない。が正解なんでしょうけれど。
でもね、できないんですよ、気付けないんです。だって世相に流されるものですから。気づいたら資本主義に染まってるんです。
常に、資本主義は、「全身」を求める。⋯⋯全身、コミットメントしてほしい。ーーそれが資本主義社会の、果てしない欲望なのだ。
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
皮肉なことに、ノイズを除去して、自己啓発本やパズドラをやっている間は自分がワーカホリックに陥っていることにも気付けないし、資本主義を植え付けられ続けちゃうんですよね。
私が自分がワーカホリックであることを気づいてそこから脱そうと思えたのは、仕事がすべてではない、持続的な働き方が大切である、という新しい時代の世相によってもたらされたものです。だから、多分麦もちょっとだけ生まれる年が遅かったり、コロナでリモートワークになってみたり、もうちょっと長く2人の関係が続いたうえで、今の2025年のビジネス本を読んだら、
同じように、「そうか〜持続的に生きるためにはもうちょい仕事はセーブしてイラストは趣味や副業に、絹ちゃんとの時間大切にしよう。うん。」ってなってる気がするんですよね。
結局、どう頑張っても時代の流れにどんぶらこと流されてる。
歴史を知り、流されてることを理解し、そのうえで流れに乗っても乗ってなかろうが「自分の幸せ」を確立させられるか。きっとそれが大事なんだろうなと思うのです。
おまけ:恋愛面 麦と絹のハッピーな世界線はあったか?
さて、それを踏まえて、あの時代の流れのなかでの麦と絹はそれでもハッピーエンドになる世界線があったんでしょうか?
よく言われるのは、麦と絹では育ったバックグラウンドに格差があり、男女での責任感にも差が大きくあって、その根本の違いは埋まり得ない、というご意見だと思うんですが、私はハッピーエンドになれる道、大いにあると思います!
キーとなるのは、「対話」ではないかと思っていて。
対話によりお互いの価値観をあわせ続けること、これがすれ違いを回避できたかもしれない唯一の方法だったのではないかと思うのです。
社会人になった麦と絹の間でなくなったもの、それは、一緒に映画を見に行けなくなった、ゲームができなくなった、そういう物理共有よりも、
「駅から家までの河原で話しながら歩いて帰る30分の対話」じゃないかと。
時間がなくなって、遊びに行く余裕がなくなって、お互いの時間が取れなくなる、とっても分かるけれど、長い人生において一番大事なことはなんなのか。2人の幸せとはどういう状態で、目指す方向性に今向かえているのか。
それに立ち戻る時間とすれ違いを埋め合わせるための向き合いが必要だったのでは、なんて思うんです。難しいことだけれど、家庭も仕事と同じく目的からすり合わせていくことを大切にしていこう、と改めて心に誓ってみたり。…これも時代の流れがそう言ってるんですかね。笑
あなたはどう思いますか?笑
Views: 0



