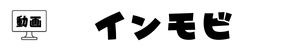🧠 あらすじと概要:
あらすじ
『フレンチ・ディスパッチ』は、ウェス・アンダーソン監督によるオムニバス映画で、架空の雑誌「フレンチ・ディスパッチ」の最終号を巡る短編が描かれています。作品は、編集部の記者たちの個性的なストーリーを通じて、彼らが報じた異なるテーマ—画家の物語、学生革命、警察のストーリー—を展開します。各エピソードは独自のスタイルで語られ、ビジュアルやキャラクターが緻密に構築されています。
記事の要約
本記事では、『フレンチ・ディスパッチ』を観た感想を述べています。作品に触れ、最初はその忙しさや色彩に圧倒されるものの、次第に魅了されていったと語っています。ウェス・アンダーソン特有の「秩序を愛する混沌」に惹かれ、特に学生革命の話に共鳴を感じるという内容です。また、作品が示す「書くこと」や「描くこと」の重要性についても考察され、映画を通じて得た感情や思索が表現されています。最後に、映画の印象を「少し変な映画」としつつも、大変良かったとの感想で締めくくられています。

一杯だけ、と言いながら注ぎすぎたのはグラスが悪い。あと、注いでくれる人がいないのも悪い。
一人で飲むと量のリミッター壊れがちになる、国のせいかもしれない。
手元のグラスをくるりと回して、テレビのスイッチを入れる。選んだのは『フレンチ・ディスパッチ』。
ウェス・アンダーソンの“雑誌の最終号”のような映画。
正直、最初の10分で後悔しかけた。画面が忙しい。色が多い。誰も説明してくれない。みんな早口で、目は合わない。「これは眠れない夜に観る映画じゃない」──そう思いかけたのに、
なぜかブルゴーニュが喉を滑ったあたりから、私は完全にこの“紙面のなかの世界”に落ちていった。
ウェス・アンダーソンの映画って、”秩序を愛しすぎた混沌”みたいなところがある。すべてが整いすぎていて、すべてがどこか狂っている。今回も例に漏れず──編集部の部屋は美しく、記者たちは偏屈で、
書かれた記事たちは誰にも読まれなさそうな偏愛に満ちている。
でも、そういうものにこそ心を寄せたくなる夜が、確かにある。理屈じゃない。こちらも偏屈なまま生きているからだ。他人に届かなくても、「書くこと」「描くこと」が存在する、
そんな世界に身を沈めたくなる夜がある。
記事は3本。画家の話。革命の話。警察の話。
どれも奇妙で、不恰好で、でも愛おしい。
とくに、学生革命を描いた記事がよかった。若者たちが、よくわからないまま政治に火をつけて、よくわからないまま恋に落ちて、よくわからないまま詩を書いていた。
そういう不器用なまま走る姿に、つい笑ってしまうのに、どこかまぶしくも見える。
私にもああいう時期が…なかったな。だいたい詩より就活を選んできたのが私の歴史である。
でも、詩のほうが人生には正解だったのかも、という顔だけはしょっちゅうしてきた。
気がつけば、ワインはすっかり空いていた。『フレンチ・ディスパッチ』の最後のページが閉じられるとき、編集部の仲間たちが机を囲んで、ただ静かにコーヒーを淹れていた。
なにかを主張するでもなく、ただ「今号の仕事は終わったね」と言っている。
誰に読まれるかじゃない。自分たちがちゃんとやったと思えるかどうか。
たぶん人生も、そういう感じでページが閉じられるときがある。
…というわけで、寝る気配はまったくないけど、映画は良かった。明日になったら、誰かに言いたくなる感じ。たぶん言わない。「ちょっと変な映画だったよ」って言って終わると思う。
そのほうが、映画にも、夜にも、ちょうどいい気がした
Views: 0