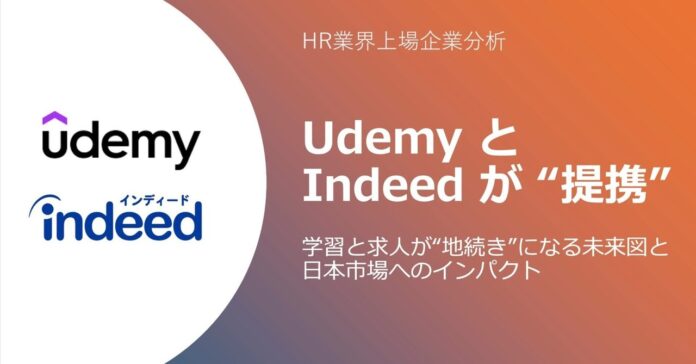🧠 概要:
概要
2025年6月3日に発表された「Udemy」と「Indeed」の戦略的パートナーシップは、学習と雇用を結びつけ、スキルベースの採用を推進することを目指しています。本提携は、主に米国を中心に展開され、日本市場での影響も注目されています。
要約の箇条書き
- 提携の発表: 2025年6月3日、UdemyとIndeedがパートナーシップを締結。
- 目的: 学習と雇用を結びつけ、スキルベースの採用を促進し、キャリア向上を支援。
- 主な特典:
- Udemyの30日間無料パーソナルプランを提供(新規ユーザー対象)。
- Indeedのキャリアサービスを割引価格で利用可能。
- Udemyのスキルと求人要件を自動で連携。
- 専門職向けのキャリアアクセラレータの強化。
- 狙い: Udemyは受講者の増加を狙い、Indeedはスキルギャップを解消し、LinkedInに対抗。
- 日本市場への影響: 個人の学習投資とスキル評価がまだ低いため、短期的なインパクトは限定的。
- 業界の可能性: 人手不足と人的資本の可視化が進めば、スキルベースの採用が加速し、類似サービスの拡大が期待される。
- 競争環境: LinkedInとの競争が激化する中、UdemyとIndeedは独自の強みを活かす必要がある。
- 現状の課題: 日本ではスキル習得が直接的に評価されにくく、市場の成長は限られている。
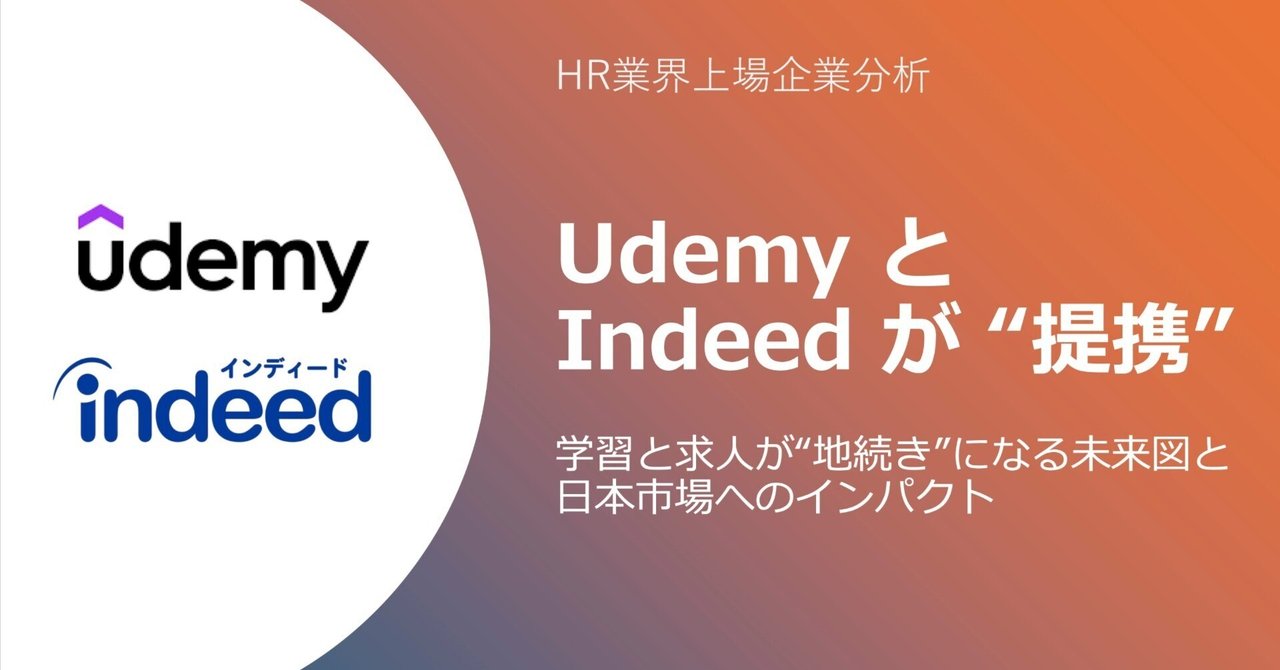
2025年6月3日、オンライン学習プラットフォーム「Udemy(ユーデミー)」と求人検索エンジン「Indeed(インディード)」が戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。
Udemyは世界有数のオンラインスキル開発プラットフォーム、Indeedは世界最大規模の求人サイトであり、この連携によって「学習」と「雇用」を結びつけ、スキルベースの採用によるキャリア向上支援を目指すとされています。
Udemyの公式FAQによれば、この特典は主に米国など一部地域で開始され、日本やアジアでは当初対象外ですが、将来的に拡大される可能性も高く、日本国内でもリリース直後から業界関係者の注目を集めています。
この記事ではUdemyとindeedの「具体的な提携内容」、「提携の狙い」、そして、特に日本のHRマーケットに上記提携が展開した際に「国内のHR業界に起きるインパクト」について考察します。
30秒で読めるサマリー
2025年6月3日、オンライン学習のUdemyと求人検索のIndeedが提携し、「学習→応募→採用」を一気通貫で支援する仕組みを発表。
①Udemyパーソナルプラン30日無料、②Indeedキャリアサービス割引、③修了スキルと求人要件を自動連携、④専門職向けキャリアアクセラレータ拡充が柱。
Udemyは受講者数拡大、Indeedはスキルギャップ解消でLinkedInに対抗する狙い。
日本では個人の学習投資とスキル評価文化が弱く短期的インパクトは限定的だが、人手不足と人的資本開示が進めば、スキルベース採用が加速し類似サービスが一気に拡大する可能性がある。
提携の具体的な内容
今回の提携によりIndeed利用者とUdemy利用者の双方に新たなサービス連携が提供されることになります。
主な内容は次の4つです。
① Udemyの学習コンテンツの無料提供(Indeed→Udemy)
-
Indeed上で新規にUdemyを利用する求職者は、Udemyのパーソナルプラン(月額定額制)を30日間無料で試用できます。
-
これにより技術系・ビジネス系・ソフトスキル系を含む1万2,000以上のコースが受講可能となり、そのうちAI関連の講座800以上も対象となります。
② Indeedキャリアサービスの割引提供(Udemy→Indeed)
-
Udemyで学習するプロフェッショナルは、Indeedが提供するキャリアサービス(履歴書レビュー、面接対策、個別キャリアカウンセリングなど)を特別価格で利用できます。
-
これにより、学習成果を効果的にアピールできるよう支援します。
③ スキルマッチ型求人応募機能
-
Udemyで習得したスキルや修了証明に合致する求人情報をIndeed上で検索・応募しやすくなる仕組みを提供します。
-
学習した内容と実際の求人要件を結びつけることで、求職者の応募成功率向上を図ることが狙いです。

④ キャリアアクセラレータ(今後対応予定):
-
Udemyが展開する「キャリアアクセラレータ」(特定職種向けに講座・実践課題・面接対策を組み合わせたプログラム)もパーソナルプランに含まれており、米国市場ではデータサイエンティストやフルスタックエンジニア向けのコースが強化されております。
-
汎用性の高いスキル開発にとどまらず、専門職系のキャリア開発にも力を入れる計画です。
上記サービスはIndeedの専用ページ(「Indeed + Udemy Career Hub」)やUdemyの特設ページを通じて提供され、これらを通じて、「学習から就職まで」一貫したキャリア支援エコシステムが構築されることになります。
今回の提携の狙いとは?
Udemy × Indeed。それぞれの提携によるシナジー・メリット
では、今回の提携の狙いは具体的にどのようなものがありそうでしょうか?
① Udemy側の狙い
まず、Udemy側としては、求職者に対して自社学習プラットフォームへの導線を強化し、受講者数・契約数の拡大を狙っていると予想されます。
具体的には転職やキャリアチェンジを検討するタイミングで学習を促し、無償トライアルから有料サブスクへ転換させることでLTVを底上げし、企業向けのみならず個人向け学習市場での競争力を高めることが目的となります。
実際、CMOのジェネファ・マーフィー氏は「適切なスキルと機会が結び付くとキャリアに革命的変化が起こる」と語り、スキル獲得直後に求人応募まで誘導できる導線は求職者にとっても“学んでも活かせない”リスクが下がり、自己投資に踏み出しやすくなります。
そして、実際に就職した後も継続的に学び続ける可能性が高く、その点で契約継続も狙えるでしょう。
② Indeed側の狙い
そして、Indeed側は、スキルギャップを自社サービス内で解消してから応募させる仕組みを獲得することで求人検索・応募のプラットフォーム価値を高めることが狙いとなります。
求職者側からすると、企業が明示したスキル要件に合わせて応募できるため、ミスマッチの少ない効率的な就職活動が可能になりますし、企業としては、スキルタグを使ったフィルタリング精度が上がり、採用効率が向上します。
また、特にIT人材やデジタル人材の不足が叫ばれる中、企業は応募者の裾野を広げる必要に迫られています。従来は学歴や職歴で候補者を絞っていた場合でも、Udemyで学習した成果を基準にスキル基準で候補者を発掘できれば人材プールの拡大も可能になります。
上記のことが実現できれば、現在世界最大規模の求人サイトであるindeedの更なる提供価値向上につながることは言うまでもありません。
競合ベンチマークはLinkedin – 競争の激化へ
また、グローバルで見た競合としては、LinkedInの存在が挙げられます。
LinkedInは職業SNS・求人プラットフォームとして世界的に利用されていますが、2016年にLynda.comを買収し、「LinkedInラーニング」というオンライン学習サービスをリリースしており、求人・プロフェッショナルネットワークと学習機能をワンストップで提供してきました。

LinkedInではユーザーが受講したコースや取得したスキルをプロフィールに表示したり、スキル評価テストを受けてバッジを得たりする仕組みが既に存在し、企業側もそれを参考に人材を評価できるようになっています。
つまり、今回のUdemyとIndeedの提携は、LinkedInが進めてきた「プラットフォーム内での学習と採用統合」に対抗・追随する動きと見ることができます。
UdemyとIndeed側の強みとしては①コンテンツ量(Udemy講座の網羅性)と②求職者トラフィック(Indeedは月2.5億ユニーク)を別事業者同士で束ね、両社のユーザーデータを相互補完できる点にあります。
逆に、inkedInは自社で学習コンテンツを内包している強みがありますが、今回IndeedがUdemyという外部プラットフォームを取り込んだことで、ユーザーの学習データを採用に活用する競争が一層激化することが予想されます。
日本国内に展開された際の影響・インパクトの予測
現状の国内市場だとインパクトは限定的
では、一方で日本国内に展開された場合の市場へのインパクトはどうなるでしょうか?
率直にいうと、現状の日本国内のマーケット状況だとこのモデルを持ち込んでも短期的インパクトは限定的と見ています。
理由としては、日本の個人向け社会人教育市場が小さすぎることです。日本国内の社会人教育市場はほとんどが法人向けで構成されており、個人でも資格取得などの一部市場を除き、マーケットがないに等しい状態です。
実際、PwCの調査でも、世界平均で約半数が自己研鑽に積極的なのに対し、日本ではわずか2割に留まっております。

そして、オンライン学習大手Schooの売上構造を見ると、2025年9月期2Q時点で全社売上の91%が法人向けリカーリング収益であり、個人向けは1割未満にとどまりまるなど、市場の観点からも法人向け市場が圧倒的に強いことがわかります。

最大の要因はスキル習得が評価されづらい日本の労働市場
一番大きな要因としては、実態として今の日本では学習してスキルを身につけても直接的に評価されづらい点です。
企業の人事評価も面接の採用時も今の日本は保有しているスキルではなく、業務での実績とか経験年数を見る傾向が依然として強く、従業員や求職者からすると、学習する動機づけを得られづらい状況です。
ただ、人によっては、日本でもshe likesのような個人向けスキル支援サービスは成長を見せている、マーケットの伸びも期待できるのではないか?という方もいらっしゃるかもしれません。
実際、政府のリスキリング助成金の波に個人向けキャリア開発サービス(she likes、ポジウィルキャリアなど)は伸びていると見ていいでしょう。
ただ、この領域は自分のキャリアを明確に変えたい!というニーズの強い層をターゲットに高単価で販売し、それを助成金で安くすることで事業を伸ばしています。
例えば、she likesだとリモートワークの仕事をできるようになりたい子育て女性層、ポジウィルキャリアだと今の会社よりかなりキャリアアップした会社に転職したい層がターゲットです。
一方で、その危機感を持った層はかなり限定的で、欧米ほどのマーケットサイズは期待できません。
今後の展開可能性とまとめ
ただ、日本全体の人手不足の急速な進展によって、企業側の人事評価や採用基準が変化したり、近年の生成AIの発展によって、求められる能力が大きく変わることが日本のHR環境の分岐点となるでしょう。
そして、人的資本可視化の流れもあり、自社独自のスキルマップを作成し、それに連動した人事施策を模索する企業も徐々にではありますが増えてきている印象です。
ですので、日本の企業(大手、グローバル企業を除く中小とかでも)に、欧米のようなスキルベースの採用・教育モデルが浸透し、従来の学歴・職歴重視からの転換が促進される分岐点が可能性は高いです。
そのタイミングでは、日本のHRマーケットの特に大手採用企業(パーソル、マイナビ、ビジョナルなど)から主に個人に向けた採用と教育が連動したサービスが立て続けにリリースされることになるでしょう。
しかし、実態として多くの企業で現状の日本的な採用慣行、評価慣行が続く限りはあまりインパクトはないですし、UdemyやIndeedも日本で積極的には展開しないことが予想されます。
Views: 0