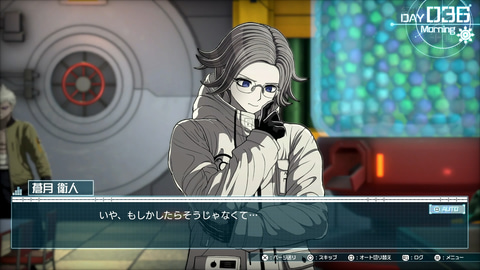アニプレックスは、Nintendo Switch/PC用アドベンチャー「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」(以下、「ハンドラ」)を4月24日に発売する。本作は「ダンガンロンパ」シリーズや「超探偵事件簿 レインコード」などで知られる小高和剛氏と、「極限脱出」シリーズ、「Ever17」を手がけた打越鋼太郎氏らによる新作タイトルだ。
今回はゲームの発売に先駆けて製品版を先行プレイさせていただいたので、早速レビューしていきたい。なお、本稿執筆にあたってはネタバレに配慮する関係で、ストーリーについては冒頭部分にのみ言及する。また、ゲームの流れなどはこちらのプレビュー記事にて紹介をしている。
【『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』ストーリートレーラー(Nintendo Switch/Steam)】
体験版からの期待を裏切らない完成度。シミュレーションRPG×ADVも見事に両立
「ハンドラ」は人類の敵「侵校生(しんこうせい)」と戦うために、「東京団地」から集められた15名の学生が、謎のロボット・SIREI(シレイ)によって「最終防衛学園」へと集められる。プレーヤーはそんな少年少女たちで結成された「特別防衛隊」(以下、「特防隊」)の1人、澄野拓海の視点から、100日間の日常を体験していくことになる。
本作はマルチエンディングを採用することが発売前から公表されていた。初めての100日間を終えて、先にゲーム全体の感想を言ってしまえば“最高だった”という感想以外に言葉が見つからない。出だしからベタ褒めだが、一部好みが分かれそうなメタいギャグと下ネタを除き、多くのプレーヤーにおすすめできる作品だと思う。
ゲーム冒頭の7日間を体験できる引き継ぎ可能な体験版が配信されているが、Steamのユーザー評価は「圧倒的に好評」であった。体験版ではプロローグから始まり、同じ学園に集められた者同士、戦う決意を決めた者とそうでない者との間に緊張が走る。そうこうしているうちにも侵校生は攻めてくるし、誰も予想だにしていなかった展開へと物語は波及していく。先が非常に気になるところでそのまま7日目を終えていくのだが、製品版を遊んだ所感としては、体験版をプレイしたユーザーたちの期待を裏切ることなく、ノンストップにエンディングまで駆け抜けてしまえるほどの手応えが確かにあった。
骨太なADVとシミュレーションRPGの二面性を備えるところは上手く調和している。これら2つの異なるジャンルを配合しているのにも関わらず、チグハグさを感じることがないのだ。学園を守らなければならない物語の一貫性と、問答無用で次々に襲い来る侵校生たち、そして侵校生を率いる部隊長が持つ得体の知れなさに“戦わざるを得ない”納得感がまた強い。大群で押し寄せる侵校生を物語上の単なるエッセンスとせず、シミュレーションRPGのバトルパートに違和感なく差し込んでいるのが上手い。
総じてストーリードリブンなゲームの方向性と物語の演出が、プレーヤーを「ハンドラ」の世界に夢中にさせてくれるわけだ。プレイ時間が伸びてくるほど、バトルパートを如何に効率重視で攻略するか、プレーヤー自身も侵校生を無慈悲に殺戮しまくる戦闘マシーンに調教されているかのよう……。詳細は後述するが、バトルパートの軽快さと取っ付きやすさもパズルゲームのような感触で、とりわけ物語を重視したいシミュレーションRPGビギナーから見ても、かなり触りやすいはず。
仲間の死すらも「ナイスDEATH」。戦略的な“やりすぎ”を楽しめるバトルパート
「ハンドラ」のバトルパートは、特防隊メンバーを指揮するシミュレーションRPGを採用している。3人~5人のパーティ編成で臨む形式ではなく、グリッド状のフィールドでキャラクターを駒として動かし、学園を守るバリア装置を破壊されないよう、敵の殲滅を目指していくのだ。言うなれば「戦略ゲーム」の側面があるわけだが、本作のバトルパートはシミュレーションゲームが苦手なプレーヤーでも比較的遊びやすい。
まず、シミュレーションRPGにしては珍しく、キャラクターに「レベル」の概念が存在していない。そのため、物語で発生するバトルにおいて、レベルを最低限幾つまで上げておかなければならないということは起きない。ゲーム序盤と終盤で、キャラクターごとの戦闘力が著しく変化しないことから、「成長<戦略」を重きとしている。
逆に言えばキャラクターのレベルが存在しないために、躓いた際の救済措置が無いようにも思えてくるだろう。ただ、これに関してはキャラクターの成長要素が全くない訳ではないので、ある程度事前に準備を進めておけば、苦戦しつつもなんだかんだクリアできたくらいの温度感で乗り越えられる。それでも、バトルパートの存在が苦手に感じるプレーヤー向けは、毎ターンキャラクターのHPと状態異常が全回復する難易度「SAFETY」が用意されている。これならどんなステージでもほぼ確実に攻略できるので、安心してほしい。
特色は他にも挙げられる。例えば、キャラクターの基本性能が一人ひとり高めな傾向なのである。学園を守らなければならない15名の学生は、「我駆力(がくりょく)」と呼ばれた潜在的な力を使い、それぞれが自分だけの能力「学生鎧(クラスアーマー)」と「学生兵器(クラスウェポン)」を具現化して戦う。これにより、単騎で無数の侵校生を相手取れるほどの戦力になっている。
この設定をバトルパートのゲームバランスにも落とし込んでいるので、ゲーム中は1人で大量の侵校生を撃破していく爽快感が味わえる。当然、キャラクターごとに同じ武装は存在せず、それぞれが「特異科目」という固有能力を持つ。皆、役割や使用感が異なるので、戦況に応じて使い分けていくのが攻略の基本となる。
本稿の冒頭ではバトルパートが「パズルゲームのような感触」と紹介していた。この文意が指し示すこととは別の意味なのだが、戦況を「設問」に見立て、使うキャラクターを采配する「解答」として当てはめれば、ある意味これもパズルゲーム的だとは言えそうだ。どのキャラクターも性能が得意分野ごとに大きく尖っているから、「この状況ではこのキャラクターをこう使おう」と、足りないピースを戦略で埋めていく感覚に近い。本作は役割の被るキャラクターが誰1人いないので、よりそういった性質は強いだろう。
バトルパートのパズルゲームらしさはAPを考慮した点にあり
さて、パズルゲームのような感触という点ついてだが、ターン制でありながら、特防隊全体の行動コスト「AP」がある分だけ、任意キャラクターを行動させられるという根本的なバトルシステムの仕組みにある。
出現する侵校生にはいくつかのタイプがあり、もっとも弱い敵はほとんどの攻撃で即死する。しかし、それ以上の強さを持つ敵を倒すとAPを1回復できるのだ。どのキャラクターも複数の敵を巻き込む範囲攻撃スキルを持つ場合が多いので、敵複数体を同時攻撃し、上手い具合にAPを回復させながら敵戦力を効率良く減らしていく。攻撃範囲に多くの敵を捉えて、一気に戦力を削り、再行動でまた多くの敵を倒す……。そんな様子と爽快感がどことなくパズルゲームにおけるコンボを想起させ、プレイ中はとても気持ちが良い。敵を殲滅する過程で「如何に少ない行動回数で多くの敵を屠るか」が要になり、自然とプレーヤーも特防隊メンバーのように、侵校生を殺戮しまくっているわけである。
もちろんこの連続行動には制約も課せられている。キャラクターは行動すると疲労状態に移行し、2回目の行動から移動距離が1マスに制限されてしまう。サポート系のキャラクターであれば、この状態異常は回復できる。だがそうなるとサポートキャラクターの行動でAPを余分に消費するので、そうすべきかどうかも戦況次第。APは次ターンに持ち越せるので、あえてターンを終了する選択も取れる。
物語上で発生するバトルについては、敵の援軍がやって来るウェーブ制が基本。敵を全滅させたとしても、ウェーブの数だけバトルが続く。次の戦いで味方キャラクターの体力は全回復し、倒れた仲間も復活するが、この連戦のウェーブ制すらもバトルを有利に進める上で、利用できる要素だったりする。
キャラクターは瀕死状態になると、残りの体力と引き換えに「決死必殺」という技が使用可能だ。体力を引き換えにするのでその戦いでは死亡するが、次ウェーブでは復活する。面白いのは味方が死亡しても「ナイスDEATH」としてカウントされ、ステージのクリア報酬が逆に増える点だろう。もはや仲間の死亡ありきで勝利をもぎ取るのが前提である。バトルパートはこうしたバランスなので、手堅く防衛戦を繰り広げようが、ガンガン攻め立てようが自由なプレイスタイルで楽しめた。
たとえ敵の密集地帯に仲間を突っ込ませることも、必ずしもデメリットとは限らない。確かに倒されればこちらの戦力は減るし、仲間を倒した敵がパワーアップするなんてデメリットもある。その反面、ナイスDEATHのカウントは増えるほか、必殺技を使うかそのバトル中限定で仲間を強化できるなど、戦局を大きく揺るがすための「VOLTAGE」ゲージが増えるメリットは見逃せない。仮に瀕死で生き残れば退却させるだけだし、あるいは敵を減らすかボス敵を削るために決死必殺を使うのもアリだろう。
「ハンドラ」のバトルパートは、全体的に緻密な難易度バランスを謳う戦略ゲームらしい戦略ゲームではなく、誰でも気軽にシミュレーションRPGの戦略的な楽しさを味える方向性、といったところだ。ある程度大雑把なプレイでも、防衛対象のバリア装置さえ守って敵を倒し切ればクリア可能な難易度感である。
最終防衛学園での自由時間をどう過ごすかはプレーヤー次第
物語主体のADVパートでは、100日目をゴールとして1日ずつ日常が進行していく。敵が学園に攻めてくるまでは、ある程度期間に猶予があり、その間は拓海を操作して学園内の仲間たちと交流したり、訓練を行ったりして「自由時間」を過ごせる。自由時間は午前と午後に分けられ、何かしら特定の行動を行なえば時間が経過する。
自由時間中、学園内に暇を持て余している仲間がいると、彼らと「学究活動」として交流できる。キャラクターのことをより深く知れるちょっとしたイベントで、読み終えると拓海の「成績」がアップする。成績は、バトルパートにおける各キャラクターの学生兵器の強化(各スキルの強化)を行なう際に必要なパラメータの値だ。本作ではレベルがないとは言え、学生兵器を強化すればバトルをより有利に進められるので、積極的に上げていた。なお、成績は仲間にプレゼントを贈るか、図書室で本を読んでも伸ばせる。
ちなみに筆者がプレイ中に印象的だったキャラクターが、何故か常にトマトの被り物を被っている少女・大鈴木くららだ。大財閥の跡取り娘で、周りの特防隊メンバーを強烈に見下している。とにかく棘のある人物なのだが、表情豊かなトマトの被り物が非常に鮮烈。バトルパートでは、防衛対象のバリア装置を回復できたり、敵を攻撃する砲台や仲間にシールドを付与するオブジェクトを設置できる。彼女で防衛に徹すればピンチでもリカバリーが効きやすい。性格はアレだがバトルとカレー作りにおいてはとても強力な人物である。交流を通して、性能以外にもキャラクターの魅力を発見していく楽しみがある。
「探索」ではボードゲーム風のゲームプレイが展開
自由時間中に午前のみ行える行動「探索」では、パーティメンバー数人と、ボードゲームのようなマップを探索する。学生兵器などの強化や仲間に贈るプレゼント制作に必要な資材を収集していくというもので、こちらは体験版でも簡単に触れることができた。物語を進めるとこれまで行けなかったエリアを探索でき、レアな資材を回収しやすくなる。ただし、その分危険度の高いイベントも発生しやすい。
探索中は止まったマスによって、侵校生とのバトルが度々発生することもある。ただ、バトル前にイベントマスで出現した選択肢などで、ダメージを受けてしまうと、その消耗している状態から戦闘開始になるため注意が必要。探索中に仲間が倒されると物語の都合上、復活できないことから、全滅の可能性を考慮しないとならないだろう。といっても、探索中に全滅すると探索が強制終了して獲得アイテムが半分失われるだけなので、正直そこまでリスキーという感じではない。
探索はアイテム収集の側面が特に強く、学生兵器の強化といった育成関連に関わる部分だ。ところが、世界観の考察といった観点から、自由に学園外を見回れる要素となる。考察好きのプレーヤーなら、ぜひあちこちを探索しつつ、なぜ世界がこうした有様なのか、考えを巡らせてみると、本作の世界を深く楽しめるはずだ。
続きが気になる好奇心と、先を知る恐怖心が混在するシナリオ
小高氏の代表的な作品と言えば、やはり「ダンガンロンパ」シリーズが挙げられるだろう。同シリーズが放つ、デスゲームの疑心暗鬼な空気と、キュートで邪悪なマスコットキャラクターのDNAは「ハンドラ」にも依然として受け継がれている。少年少女が見ず知らずの地で100日過ごす理不尽さを濃密に演出するのに、一役買っている。
また、全てではないものの、SIREIやNIGOU(ニゴウ)から世界の現状について明かされ、今まで東京団地で過ごしてきた少年少女の既成概念がことごとくブチ壊されていく様もニヤリとできる。多くの秘密が紐解かれていく様相に、筆者はときにほくそ笑み、ときに予想を超えたタネ明かしでショックを受けることも。
小高氏と打越氏らが手がけるシナリオは“常に不穏”だ。それが物語を読み進めたくなる原動力でもあり、プレーヤーの潜在的な恐怖を刺激する魅力でもある。知らないものはわからない、わからないものは怖い、怖いけども知りたい。そんな感情がグルグルと脳裏で渦巻き続ける。正直、初めての100日間を終えた後でさえ、この感情の着地点がいまだに定まらない。なので、せめて自分自身が納得するまで遊び続けたいと思える魔力がある。それがマルチエンディングたる醍醐味だろうが。
「ハンドラ」の体験は、神の視点であらゆる謎を考察するプレーヤーと、何も知らない拓海たち特防隊のメンバーが、世界の秘密を手探り的に解き明かしていくところがポイントだ。一度のプレイで現実とゲーム内、2つの観点を楽しめる、いわばミステリー作品のような構造が遊び手を惹きつける。
しかし、「ハンドラ」の世界にはあまりにも得体の知れない要素が多く登場するため、それが先に書いた“常に不穏”であることを後押ししているように思う。未知なる存在、謎の現象、異様な光景……etc。プレイ中は知らないものをこれから知っていく好奇心、そしてその答えを知った後に待つ衝撃への恐怖心が忙しく交錯する。その心理的な狼狽えが娯楽らしい心地良さでもあり、本作の醍醐味とするところでもある。
主人公・拓海の描き方もニュートラルで好ましい。自己主張が強い熱血漢なんて柄ではなく、物語を通して精神的な成長こそすれども、やはり一介の高校生でしかない部分が随所に見られる。拓海以外は口の悪さと行動が真逆な光のヤンキーだったり、情緒不安定な地雷系のメンヘラだったり、緊張すると嘔吐を繰り返すメカニック少女など、個性がきわ立つ者ばかりだ。それでも皆一様に不安を抱えているが、意見や思想の食い違いから衝突すること多い。しかもそれぞれのメンバーたちが終始奔放な性分で、イマイチまとまりがない感じ。拓海自身も特別何かができるわけではなく、常に彼は彼なりの不安を1人抱えて葛藤する様子が描かれる。
そんな拓海は戦う力を手にする以前、東京団地で平凡な生活を送っていたごく普通の少年だ。幼少期の頃から幼馴染の少女・柏宮カルアと家族ぐるみな付き合いではあったが、彼女とは言わば“友達以上恋人未満”の関係を続けていた。だが、哀れにも彼の日常は侵校生によって容易く壊されてしまう。想像を超えた出来事に理解が追いつかないものの、カルアを守るために決意を固めて戦火の中へ飛び込んでいった。「ハンドラ」の物語はこの冒頭プロローグを起点に大きく動き始めていく。
拓海は、主人公ゆえに物語を動かすための舞台装置的な役割を最低限になっているが、良くある“特別な主人公”としてヒロイックになり過ぎることはない。そんな人物なので周りに対する強い影響力や強固な信頼感も持ち合わせておらず、特防隊メンバー同士の関係性がそれなりにフラットだ。
なので、主人公キャラクターであるのに対し、拓海はどちらかと言えば没個性気味なメンバーの1人といった感じである。それは恐らくプレーヤーが自然と感情移入できる、丁度良い距離感のキャラクター性なのではないかと思う。謎多き物語を楽しむ上で、彼の凡庸性と素朴な問い掛けは、プレーヤーに思考させる余地を与える。拓海の存在が決してノイズになっておらず、彼の悩みと過去を含めて、シナリオを読み解くための触媒になっている。彼が物語のどんな作用をもたらすかは自分の目で確かめてもらった方が良いだろう。
アニメ作品を見るかのように最後までしっかり楽しめる「ハンドラ」の世界
「ハンドラ」には本稿で紹介し切れていないネタがまだまだある。それはゲームの楽しみを損なわないために敢えて配慮しているのだが、完全新作タイトルとしてしっかり最後まで楽しむことできるゲームなのは疑いようのないところだ。
ゲーム全体を通してADVパートが約7割、バトルパートが約3割という構成で、初めの100日間を終えるまではおよそ20時間ほど。基本は物語を中心に自由時間を絡めたゲームデザインになっている。最後まで遊び切れば、クセの強いキャラクターたちの魅力も、一層深まることだろう。まるでアニメ作品を視聴するかの如く、一気に物語を読み進めたくなる「ハンドラ」の世界を、ぜひ堪能していただきたい。
Views: 0