🧠 概要:
概要
この記事では、音楽プロジェクト「PAPILLON」とその特異な運営モデルについて説明されています。特に、メンバーが流動的に変わるという点に焦点を当て、音楽における属人性(アーティストの個性や神話)について歴史的な視点から考察しています。読者に対して、属人性の有無が音楽活動にどのように影響するかを問いかけ、次回の投稿では「属団体性」に基づいたアプローチについて掘り下げる予告がされています。
要約の箇条書き
- プロジェクトの紹介: PAPILLONは毎回異なるメンバーで構成される音楽プロジェクト。
- メンバーの流動性: メンバーが入れ替わることで、各メンバーの負担を軽減し、持続可能な活動を目指している。
- 属人性とは: 音楽における属人性は、アーティストとその作品の結びつきに関するもので、時代によって変遷してきた。
- 歴史的背景:
- 17世紀以前: 音楽は共同体の財産で、作曲者は重要視されなかった。
- 18世紀〜19世紀初頭: 音楽家としての個性が強調され、属人性が現れ始めた。
- 19世紀後半以降: アーティストが神話的存在として語られ、音楽そのものよりも物語性が重視されるようになる。
- 現代: ファンとの近い接触が重視され、個々のアーティストが小規模なコミュニティの中で神話的存在として認識される。
- 次回の投稿: 属人性を解放し「属団体性」で勝負するPAPILLONの目指す方向性について掘り下げる予定。
- メンバー募集: PAPILLONは現在メンバーを募集しており、興味のある人はDMでの連絡が推奨されている。
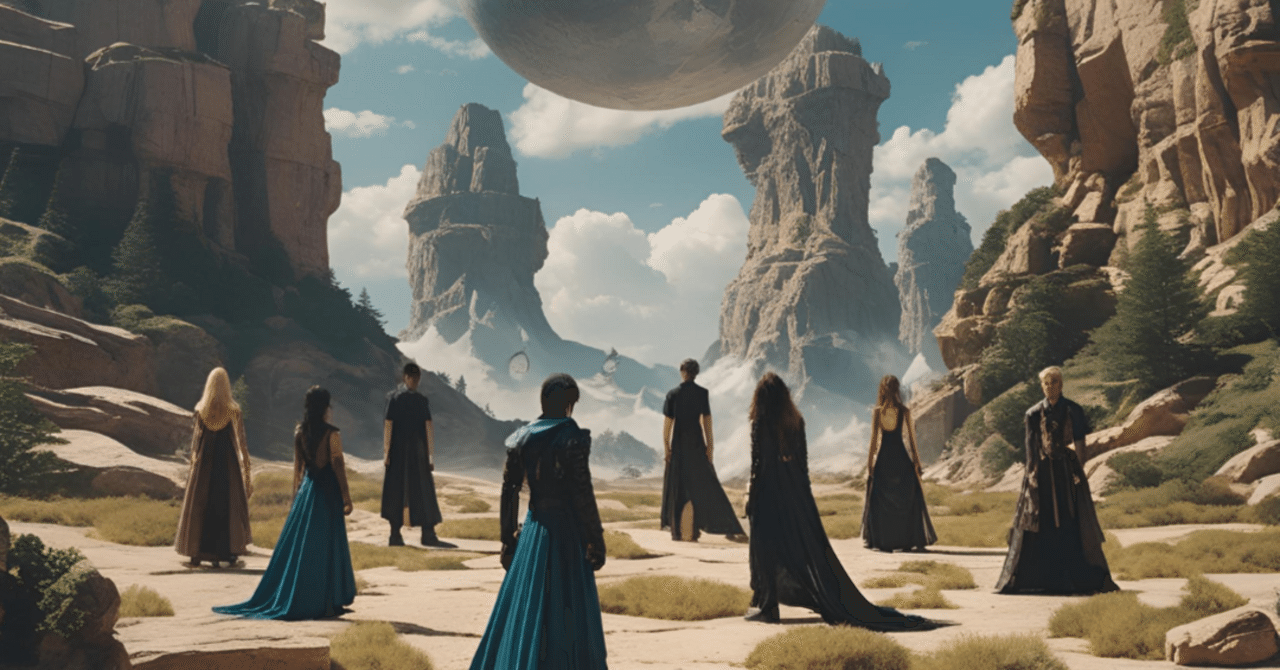
メンバーが毎回変わるってどうなの?
こちらが今日のテーマです。
これは以前僕が投稿したPAPILLONの概要を説明した記事に記載されている、PAPILLONはメンバーが流動的なチームであるということへの疑問です。詳しくは該当の記事をご確認頂きたいのですが、具体例としては以下です。例 楽曲①の制作はメンバーA.B.Cで行う。 X月Y日のライブはメンバーB.D.E.Fでバンドで出演する。
X月Z日のライブはメンバーAが弾き語りで出演する。
このように、その時活動出来るメンバーが入れ替わりながらPAPILLONの活動を前に進めます。僕はこれをすることで、各メンバーの負担が過剰になることを回避し、持続可能な活動を実現出来ると考えています。
しかし、現代のポピュラー音楽シーンではそのような形態のアーティストの事例が少なく、「そんなこと出来るのか?」「どんな風になるか?」という質問を頂きます。また「音楽に属人性は不可欠」と考える人もいるようです。
音楽における属人性
先ほどの質問に答えるためには音楽と属人性について掘り下げて知る必要があると思い、まずいつから音楽の属人化が始まったのか調べてみました。
~17世紀以前(バロック以前)
-
民謡や地域的な音楽は、多くの場合「作者不詳」であり、共同体の共有財産だった。
-
音楽は宗教儀式や祝典、舞踏、娯楽などの「機能的」役割が主で、「誰が作ったか」はあまり重視さなかった。
-
聴衆も「この曲を誰が書いたか」より、「儀式が荘厳に進むか」「踊りやすいか」といった実用的な観点で音楽に接していた。
…この時代までは、どうやら音楽と個人(アーティスト)というのは紐づいていなかったと言えます。というかアーティストという概念がなさそう。
18世紀後半〜19世紀前半(ロマン派)
-
この時期から、「音楽家=芸術家」としての個性が強調され始めた。
-
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの登場。「職人としての作曲家」から「個性を表現する芸術家」へと作曲家像を変えた。聴衆は「ベートーヴェンの作品」を聴きたがるようになり、ここに「属人化」が現れた。
-
フランツ・リスト、ニコロ・パガニーニなどの超絶技巧の演奏家の登場。聴衆は「リストの演奏」「パガニーニの奇跡」を見に来るようになった。
…どうやら音楽の属人化が始まったのはこの時代からのようです。またアーティストという概念も芽生えつつあったようです。ただ、まだ現代の音楽シーンの属人性とは少し違うように見えます。良い意味で「音楽の中身重視」みたいなところが。
19世紀後半以降(アーティスト神話)
-
アーティストが「神から選ばれた存在」「苦悩の中から真理を紡ぎ出す天才」として語られる。
-
マスメディア・大衆文化の中でアーティスト像は「物語」として、彼らの生い立ち・苦悩・成功譚が編集され、あたかも神話のように展開される。
-
レコード産業がアーティストを「商品化」する過程で、その人の「物語性」を構築した。(ジョン・レノン、マイケル・ジャクソン、レディー・ガガ、など)
…この時代になるとかなり属人化していますね。しかももはや音楽自体はあまりフォーカスされず、ドラマチックな部分に聴衆が憧れを抱くという構図が出来ています。(彼らの音楽を批判する意図ではないです)
現代(神話から共感へ)
-
「遠い存在」としての神話ではなく、距離の近い神話が成立。
-
ファンとの「素の接触」(インスタライブなど)が神話を支える一方、神話が崩壊しやすい側面もある。(日常や舞台裏がSNS等で暴露されやすい)
-
大衆における共通の神話より「私だけの推し」「私だけが知ってる魅力」に価値が置かれている。
…現代では皆さんもご存じの通りアイドル・VTuber文化が隆盛で、その潮流を踏まえると属人性はまだあるようですが、20世紀的な神話信仰ではなく、小規模なコミュニティのなかでの、身近な神話といった形で紐づいているようです。うーん、こちらもやはり音楽そのものがフォーカスされているようではなさそうです。(彼らの音楽を批判する意図ではないです)

音楽における属人性とは
これまでの時代を踏まえると属人性のあり方も変遷があるようです。が、あえてまとめるならば音楽における属人性とは「アーティスト神話」だろうと思います。この神話を売りにしたい場合は属人性を用いて音楽活動をするのでしょう。
売れないミュージシャンが「いつかスターになってやる!」と言っていたとしたら、まさに自分が神話になろうとしている意志が見えます。
そしてその神話にはニーズがある、ということも事実です。
属人性から属団体性へ
さて、音楽と属人性について掘り下げてきました。歴史的な経緯を見てみると属人性がなかった時代もあったことから、属人性は音楽に必須ではないようですし、属人性の形そのものが今なお変化し続けています。
ただ、これだけでは最初の問「メンバーが毎回変わるってどうなの?」の答えとしては不十分でしょう。
次回は、PAPILLONが目指す状態、属人性から解放され属団体性で勝負するということについて掘り下げていき、答えに辿り着きたいと思います。
ぜひ、次回もチェックして頂けますと幸いです。
PAPILLONはメンバーを募集しています。概要についてまとめたスライドをご参考になさって頂けたら幸いです。
なお、PAPILLONは僕一人で動き始めておりまして、僅かですが楽曲の配信もやっております。もし良ければ、こちらもお聴き頂いて僕の現在地を知って頂けたら幸いです。
PAPILLONへの参加に興味がある方は是非ご連絡下さいませ。
返信に数日お時間いただくこともあろうかと思いますが、まずはカジュアルにお話出来れば幸いです。
ご連絡はインスタのDMだと助かります!こちら↓
https://www.instagram.com/papillon_fujirock_project/
読んで頂きありがとうございました!
それでは!
//www.instagram.com/embed.js
続きをみる
Views: 0



