🧠 概要:
この記事の概要は、デジタルマーケティングにおける重要なポイントを反映しつつ、それに潜む落とし穴について触れています。「デジタルマーケティングの落とし穴」という書籍の内容を通じて、数字やデータのみに依存せず、顧客の心理や現場の状況を考慮することの重要性が強調されています。
### 要約(箇条書き)
– デジタルマーケティングは便利だが、数字だけでは本質を見失う危険がある。
– PDCA(計画・実行・評価・改善)は重要だが、データの解釈には限界がある。
– 売上データ(POSデータ)は表面的な結果しか示さず、本当の理由は別にある。
– ABテストは「顧客との対話」として捉えるべきで、予測には限界がある。
– OODAループ(観察→情勢判断→意思決定→行動)は、変化の速い現代には有効な戦略。
– 売り場は衛生的で、商品の比較がしやすく、価値が伝わり、不安が解消される必要がある。
– 記憶の減衰率を理解し、記憶に残る体験を提供することが重要。
– メルマガは質が求められ、受け手の期待を理解することが大切。
– 組織の空気や誠実さがマーケティングの成果に影響を与える。
– 問題解決には真因追求が有効で、再現性のあるアプローチが必要。
– デジタル化は効率化に過ぎず、その先にある価値創出が求められる。
– 顧客の気持ちを想像し、データと人間をバランスよく考えることがマーケティングにおいて重要。
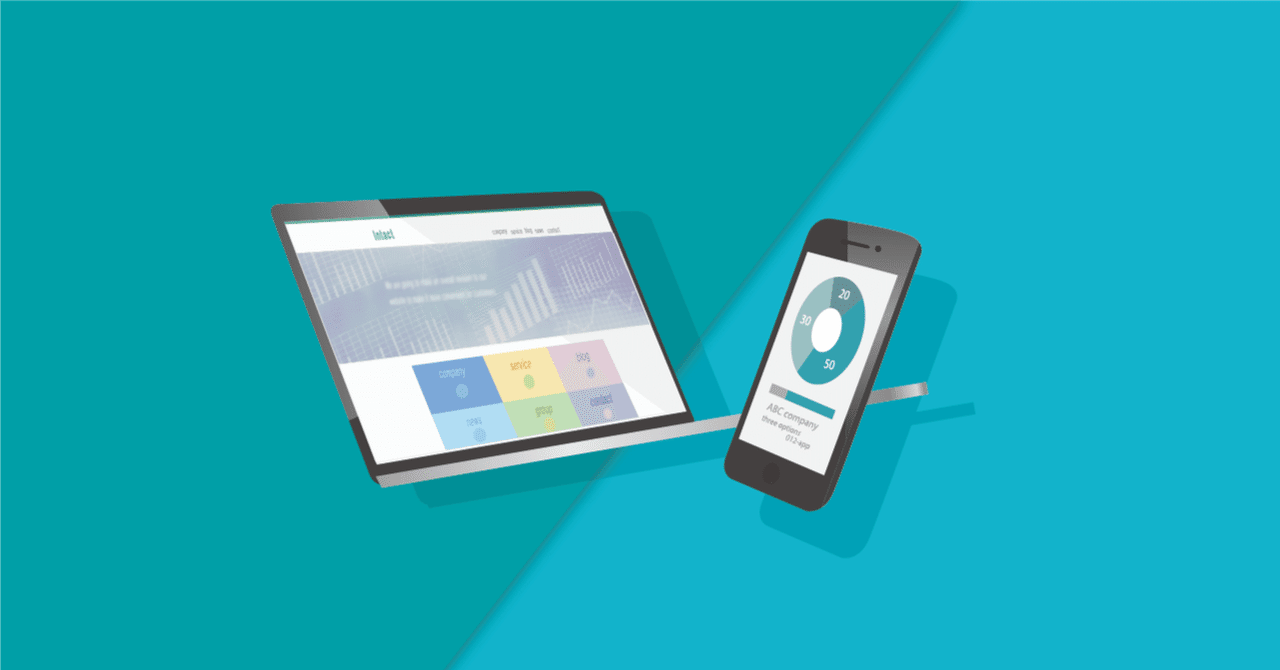
データは便利。でも、それだけじゃ足りない
──『デジタルマーケティングの落とし穴』の感想。
いわゆる「デジタルマーケティング」をやるのはそんなに難しくないです。便利なツールも増えたし、数字で説明できるから強い。でも、「数字を見てればマーケティングがわかるようになる」って思っていたら、それはちょっと違うかもしれません。
この本は、そういう「便利すぎるツールや考え方に飲み込まれそうになってる人」にこそ刺さる一冊です。数字の裏側にあるなぜ?を大事にしたい人におすすめです。
POSデータは教えてくれないこと
本の序盤で、著者は「PDCAの限界」について触れています。といっても、PDCAが悪いって話ではないんです。むしろ、それしかやってないことが危ない。特にPOSなどの販売データを中心に分析していると、わかった気になるんですよね。でも、「売れた理由」や「売れなかった理由」までは見えないんです。
たとえば、POSの数字を見て「この商品、今月は売れてるな」と思っても、それがキャンペーンの影響なのか、隣の競合店が在庫切れだったからなのか、たまたま週末の天気がよかったからなのか……理由はいくらでもあります。でも数字は「結果」だけを教えてくれるので、その背後にある「文脈」までは拾ってくれません。
著者は、小売業で40店舗の売り方がバラバラだったのを統一して、ようやく「検証できる状態」にしたそうです。全店舗で同じPOP、同じ陳列、同じ価格。そうすることで、「売れた/売れなかった」に意味が出てくる。まずは比較可能な状態を作らないと、どんなに分析しても空振りになるよ、という話が響きました。
ABテストは、賭けではない
マーケティングでよく出てくる「ABテスト」。これも誤解されがちなワードです。「どっちが数字良くなるか比べるやつでしょ?」って思ってる人は多いですよね。でも本書では「ABテスト=顧客と対話する手段」として語られていました。
この視点は新鮮でした。つまり、「こっちの文言のほうがクリックされるかな?」という問いかけを、お客さんに投げかけている。その結果として、反応をもらう。ABテストってただの確率勝負じゃないんですね。
さらに印象的だったのが、「プロでも当てられるのはせいぜい7割」という話。新人のバイトが当てる確率が5割、現場の担当者が6割、著者でも7割。逆に言えば、どれだけ経験を積んでも3割は外れるってことです。つまり、「失敗しながら学ぶのが当たり前」なんですよね。マーケティングにおいて100%はありえない。それを前提に試して学ぶスタンスが大事なんだと改めて思いました。
PDCAに飽きたらOODA
PDCAに対するもう一つのアプローチとして、本書ではOODAループが紹介されています。これは軍事戦略の世界で有名な概念で、「Observe(観察)→Orient(情勢判断)→Decide(意思決定)→Act(行動)」というサイクルです。
この中でも特に重要なのが「観察(Observe)」。最初にちゃんと見ないと、以降の判断や行動が全部ズレます。たとえば、売り場の様子をパッと見て「売れてないな」と思っても、実はPOPが外れてただけとか照明が暗かったとか、別の要因が隠れてることってありますよね。
観察って地味だけど超重要ですし、数字を追いすぎると逆に「現場を見る目」が鈍ってしまうことがあります。「数字には出てこない情報」を拾える人が、現場では強いんだなと実感しました。
OODAは、環境がコロコロ変わる現代に向いている考え方です。今の時代は半年後の市場なんて読めないことばかり。だからこそ、判断→実行のスピードと柔軟さが勝負になる。そんな気づきを与えてくれる章でした。
快適な売り場って、なんだ?
売り場づくりの話もとても実践的でした。どんなに素晴らしい商品を置いても、売り場がぐちゃぐちゃだったら意味がない。じゃあ「快適な売り場」ってどんな場所?という話になります。
本書では、以下の4つが「快適な売り場」の条件として挙げられていました。
-
衛生的に整っていること
-
商品やサービスを比較しやすいこと
-
価値がきちんと伝わっていること
-
不安や疑問が解消されていること
どれも当たり前に見えて、実際にはぜんぶ揃ってる店って少ないですよね。
印象的だったのは「卵と牛乳を最安にした話」。生活必需品の価格にこだわることで、「この店は安い」という印象を植え付けたというエピソード。価格競争の話に見えますが、「信頼」の話でもあると思いました。
記憶に残る体験をつくる
「記憶の減衰率」って知ってますか? 人間は20分後には約6割のことを忘れるらしいです。1時間後には半分以下、1日後には2〜3割しか残らない。マーケティングって「伝えること」だと思いがちですが、「覚えてもらうこと」のほうがはるかに難しい。
なので「どうやって記憶に残すか」がテーマになります。単に目立つだけじゃダメで、「その人にとって意味のある体験かどうか」が重要なんですね。どんなに派手なキャンペーンを打っても、「あ、なんか見た気がする」で終わってしまっては意味がない。
それに関連して、著者は「人は無意識にウソをつく」とも言っていました。アンケートで「このサービスは良かったです」と答えても、本音は「なんとなく印象がいいからそう書いた」だけかもしれない。言葉と行動にはズレがある。そのズレをどう観察するかが、マーケティングには問われているんだと思います。
メルマガって、実はすごい
ある時、「配信数が少ない!」というお叱りが届いたそうです。普通なら「またクレームか…」と受け止めがちですが、著者はその声の裏にある期待に注目しました。
「いつ届くかな」「今日のおすすめあるかな」って、毎日チェックしてくれているお客さんがいる。そういう人たちにとって、メルマガは情報ではなく、習慣なんですよね。
そして、著者は安易に「じゃあ頻度を増やそう」ではなく、「どの層に」「どんな内容を」「どんなリズムで」届けるべきかを考えます。内容やトーンによっては、逆効果になることもあるからです。
マーケティングにおいて量より質という言葉はよく聞きますが、メルマガはまさにそれが問われる媒体。自社のファンとどう向き合うかが、そこに現れるんだと思いました。
組織が病むとき
後半では、マーケティングの話から少し離れて「組織の空気」についても言及されています。とくに印象的だったのが、インテグリティ(誠実さ)の話。
誠実さって、ふだん言葉に出すことはあまりありませんが、組織がうまくいってないときに欠けているのは、たいていこれなんですよね。著者は、インテグリティを欠いた人の特徴をいくつか挙げています。
-
弱みにばかり目を向ける
-
自分の仕事に高い基準を持たない
-
有能な部下を恐れる
-
「誰が正しいか」にこだわる
どれも、組織のなかで地味に効いてくる悪い空気をつくる原因です。「頭は切れるけど誠実じゃない人」は、一見有能に見えるので周囲が何も言えなくなってしまう。でも、時間が経つとチームが機能しなくなる。
マーケティングの現場もけっきょくは人と人との連携で成り立っている。分析ツールや広告運用のスキルだけじゃなく、「一緒に働きたいと思われる人かどうか」って、本当に大事な要素だとあらためて感じました。
「なぜ?」を深掘るスキル
この章では、いわゆる「真因追求」のプロセスが紹介されています。売れなかった商品の理由を探るとき、よくやりがちなのが「勘と経験だけで語る」こと。でも、それだとチームで共有できないですし再現性もない。
著者は問題をいくつかの視点に分解して、データを拾いながら変化のあった部分を探すアプローチを紹介しています。そこから共通項を洗い出し、最も影響のありそうな要素を絞っていく。
つまり、「気づき→仮説→検証→絞り込み」という、ちょっと理系っぽい思考法。でも、これがあると納得度が違いますし、「ああ、この商品って、〇〇が弱かったのか」と次に活かせる学びが深くなります。
また、こういう分析ができると、「売れなかった理由」を個人のせいにしなくてすみます。「なんであの人はうまくやれなかったんだ?」じゃなくて、「構造として何がまずかったか」に目を向けられる。これも、健全なマーケティング組織には大事な視点だと思います。
「デジタル化=効率化」じゃない
本のラストでは、デジタル化と生産性についても触れられていました。ここはマーケティングというより経営の話に近いですが、考えさせられる内容です。
よく「デジタル化=効率化」と捉えられがちです。たとえば業務を自動化したり、紙の書類を減らしたり。でも、本当に大事なのは「それで生まれた時間で何をするか」なんですよね。
著者は、デジタル化の効率向上とあわせて、「データ分析による粗利向上」や「新しい価値の創出」も提案しています。つまり、時間を空けるだけで満足しない。「空いた時間で価値を上げようよ」と。
この視点があるかどうかで、組織のデジタル活用の成熟度はまったく違ってきます。「手間が省けました」で終わってしまったら、もったいない。そこに、もう一歩踏み込めるかどうかが問われているんですね。
おわりに:デジタルの時代に、人を見る
『デジタルマーケティングの落とし穴』は、「データの使い方を間違えると、本質を見失うよ」というメッセージがじわっと伝わってくる本でした。
便利なツールや指標はたくさんあります。でも、それだけを信じて動いてしまうと、「お客さんが本当に何を思っているのか」「なぜそうしたのか」が抜け落ちてしまいます。
著者は、「お客さんになりきる」ことの大切さを何度も語っています。数秒の観察でタイプがわかるようになる、という話はちょっと職人芸っぽいですが、それくらい人を見る力が大事だということ。
結局、マーケティングって「誰かの気持ちを想像すること」なんですよね。そういう意味で、この本は数字と人間、デジタルと現場、両方をバランスよく見つめるための道しるべになると思いました。
Views: 0

