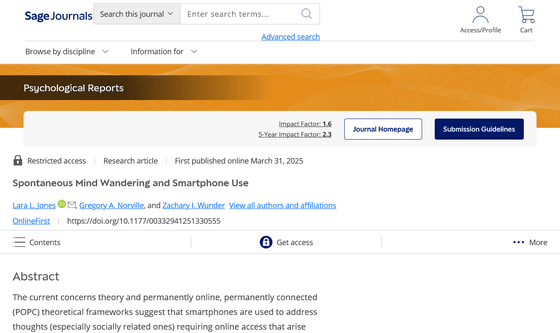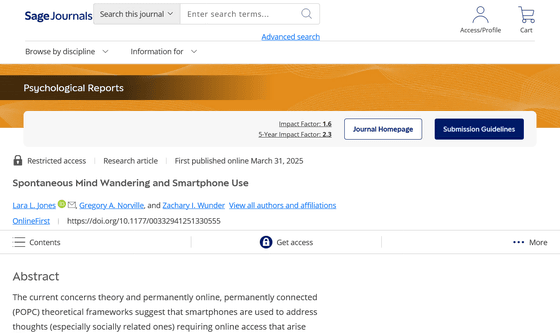

マインドワンダリングとスマートフォン使用頻度の関係
2025年07月27日、アメリカのウェイン州立大学の研究者たちが、マインドワンダリング(思考の逸脱)とスマートフォンの使用頻度との関連を示す新しい研究結果を発表しました。
マインドワンダリングとは?
マインドワンダリングは、タスクに対して意識が散漫になる現象です。例えば、読書中に別のことが頭に浮かび、内容が入ってこなくなることです。この現象は、注意力の低下やパフォーマンスの向上を妨げる要因とされています。
研究の背景と方法
過去の研究では、マインドワンダリングがスマートフォンの使用と関連していることが指摘されていましたが、多くはアンケート調査に基づいていました。今回の研究では、ウェイン州立大学の研究者たちが、188名のiPhoneユーザーを対象に、実際のスマートフォン使用データを収集しました。これにより、より客観的な証拠を得ることができました。
主要な発見
-
ソーシャルメディアの使用: 参加者は、ゲームや教育アプリよりも、ソーシャルメディアアプリに平均週17時間を費やしていました。これは、常にオンラインでいることにより、他の考えが浮かびやすくなる「オンライン警戒」の状態を引き起こすことが示唆されています。
-
非意図的マインドワンダリング: 分析によると、オンライン警戒度が高い参加者は非意図的なマインドワンダリングの傾向も高く、これはソーシャルアプリの使用時間の増加に繋がります。一方、意図的なマインドワンダリングとは関連しない結果が得られました。
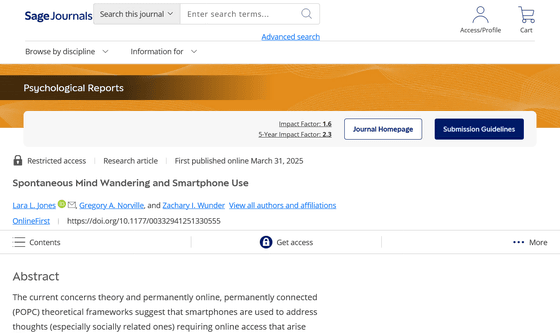
スマートフォン通知の影響
さらに、スマートフォンの通知が、使用時間の増加やオンライン警戒を高める要因であることも示されました。これは、ユーザーが頻繁にチェックすることで、思考の逸脱を誘発する可能性があると考えられています。
今後の課題
この研究は相関関係を示唆していますが、因果関係は明確ではありません。今後の研究では、リアルタイムで思考や行動を追跡する方法が求められています。また、マインドワンダリング中の具体的な思考内容の解析も重要でしょう。
この研究は、現代のデジタルライフにおける注意力の管理や、効率的な時間の使い方を考えるきっかけを与えてくれるものです。スマートフォンの使い方と私たちの思考パターンの関係を深く理解することが、今後の重要なテーマとなるでしょう。

🧠 編集部より:
「マインドワンダリング」は、タスクから注意が逸れてしまう自然な思考の流れを指します。最近の研究では、集中力が欠けやすい人々は、スマートフォンを頻繁に使用する傾向があることが分かりました。この研究は、アメリカのウェイン州立大学の心理学者たちによって行われ、特にソーシャルメディアアプリの利用時間が多いことが関連付けられています。
研究の背景と方法
この研究では、188人のアメリカの学部生を対象に、iPhoneの「スクリーンタイム」機能を利用してスマートフォンの使用データを収集しました。調査期間には新型コロナウイルスの影響で、通常よりもスマートフォンの使用時間が増加している可能性がある点が指摘されています。
マインドワンダリングの種類
研究では、意図的なマインドワンダリング(「退屈だから他のことを考える」)と非意図的なマインドワンダリング(「気が付くと他のことを考えていた」)を区別して評価しています。興味深いのは、非意図的なマインドワンダリングがスマートフォンの使用頻度と強く関連していることです。
オンライン警戒
研究では「オンライン警戒」という用語が導入されています。これは、常にオンラインで繋がっている状態を意識することを指し、これが非意図的なマインドワンダリングを引き起こす要因となる可能性があります。通知の受信も、この警戒度を高め、さらにスマートフォンの使用時間を増加させる要因になっています。
重要な注意点
ただし、研究は相関関係を示すもので、因果関係までは明らかにされていません。つまり、「マインドワンダリングが多い人がスマートフォンを多く使う」のか、「スマートフォンを使うことが多いためにマインドワンダリングが増える」のかは不明な状態です。今後はリアルタイムで思考を追跡する研究が期待されています。
さらに知りたい方へ
- マインドワンダリングについてのWikipedia
- 研究論文「Spontaneous Mind Wandering and Smartphone Use」
- Psychological Study on Mind Wandering
この研究を通じて、私たちの生活におけるデジタルデバイスの影響を再認識する機会となります。是非、自身のスマートフォンの使い方を見直してみてくださいね!
-
キーワード: マインドワンダリング
※以下、出典元 ▶ 元記事を読む
Views: 0