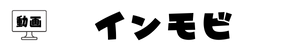関東は、陸側のプレートの下に、海側のフィリピン海プレートと太平洋プレートが沈み込む複雑な地下の構造になっているため、「地震の巣」が複数あると言われています。
地震学が専門で東京科学大学の中島淳一教授は、東京湾北部で2000年以降に起きたおよそ8000の地震を解析しました。
その結果、震源は直径20キロほどの円のような形に分布していて、深さ60キロから70キロほどの、フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界付近に斜めに連なっていることが分かりました。
その傾斜は、太平洋プレートが沈み込む角度よりも急で、プレート上に盛り上がった部分があることを示しているということです。
関東の沖合には、「海山」と呼ばれる盛り上がった地形が多く存在し、大きさが似ていることから中島教授は、沈み込んだ「海山」にひずみがたまることで地震を多発させている可能性があると分析しています。
中島教授は「この周辺ではマグニチュード7クラスの地震が明治時代に起きている。地震活動の解析などを通じて大きな地震が発生する可能性が高い場所を絞ることにつなげたい」と話しています。
Be the first to comment