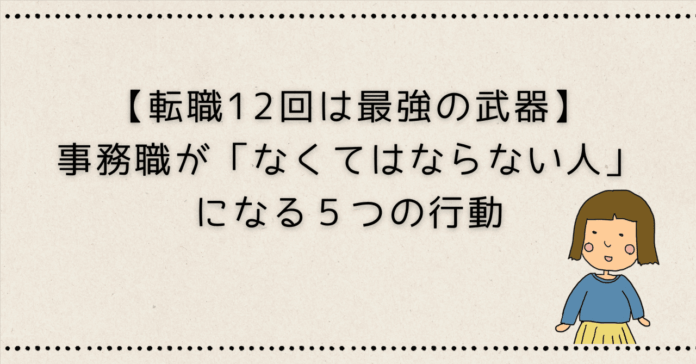🧠 概要:
この記事の概要は以下の通りです。
概要
著者ペルッコは、転職回数が12回を超えるワーママで、「事務職がなくてはならない人」になるための5つの行動を紹介しています。彼女は特別なスキルではなく、社会人としての「当たり前」を徹底的に意識することで職場に必要とされる存在となりました。ワーママとしての経験が、仕事での評価や人間関係を築く上での強みとして機能したことを述べています。
要約の箇条書き
- 著者の背景: 転職12回以上のワーママ、独自のキャリア形成術を紹介。
- 目的: 事務職が「なくてはならない人」になるための5つの行動を提示。
- 「当たり前」を重視: 特別なスキルでなく、当たり前の行動を高水準で維持することが重要。
- 転職の成功要因:
- 早いレスポンス: 素早い返答で信頼感を築く。
- 考えを伝えつつアドバイスを求める: 自分の考えを含めた質問で相手の時間と信頼を得る。
- 笑顔で対応: 人間関係を円滑にする。
- 頼まれたことを「+1」で遂行: ニーズを先読みし、一工夫を加える。
- 人間らしさを含むコミュニケーション: 親しみやすい雰囲気がチームワークを高める。
- 子育ての影響: ワーママとしての経験がプロフェッショナルとしてのスキルに寄与。
- キャリアに対するメッセージ: 転職回数や年齢に不安を持つ必要はなく、基本的な行動が市場価値を生む。
この記事は、特別なスキルがなくても、社会人としての基本を徹底することで職場での存在価値を高められるという励ましのメッセージを伝えています。
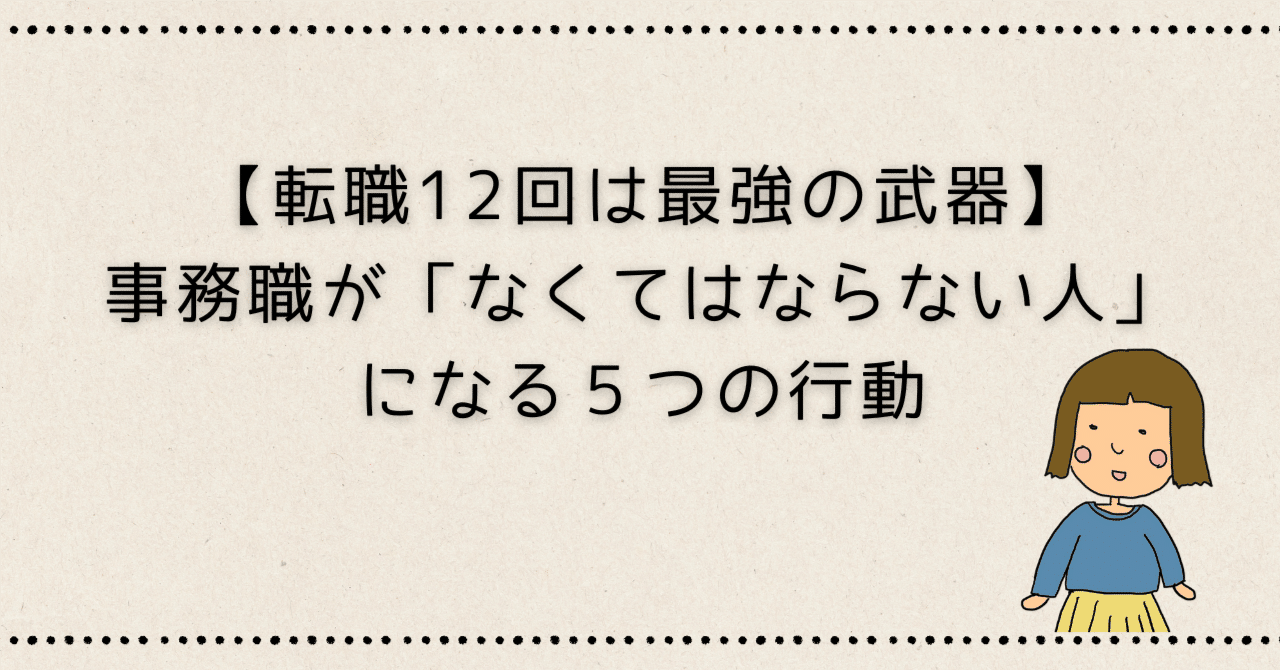
こんにちは!ペルッコです。
転職回数2桁越えの私がこれまでの経験から得たものを少しづつ紹介していきたいと思います。
今回は私が ” 事務職が「なくてはならない人」になる5つの行動 ” を紹介します!
「居ると助かる」存在になる
「え、また辞めたの?」「どうしてそんなに転々とするの?」――そう言われた回数は、もう数え切れません。履歴書だけを見れば、「すぐに辞める人」「問題がある人」と思われても仕方ないと思います。特に、私のように特定の「専門スキル」と呼べるようなものがない、いわゆる事務職のキャリアだと、40代にもなって転職回数ばかりが増えているなんて、自分でも「この先、大丈夫なのかな…」と不安になることもありました。でも、不思議なことに、私は40代に入っても幸いなことに職に困ることなく、むしろ直近の2回は「一緒に働きたい」と声をかけていただき、リファラル(紹介)で転職を決めることができたんです。
なぜ、こんな私でも、職場に必要とされ、時には「即戦力だね!」と言われるまでになったのでしょうか? 答えは、特別なスキルや輝かしい実績ではありませんでした。
結論:「社会人としての”当たり前”」を意識しまくった結果である
結論から言うと、私が転職を繰り返しながらも職に困らなかった理由、そして新しい職場で「即戦力」として受け入れられるようになった理由は、
「社会人としての当たり前」だと多くの人が分かっていること、あるいは「別に大したことないよね」と思うようなことを、どんな時も徹底的に、そして揺らがず意識し続けた結果だと思っています。「そんなの当たり前じゃん」――そう思われたかもしれません。でも、考えてみてください。あなたがこれまで出会った職場で、「この人、すごく当たり前のことを、当たり前にやってくれるな」と感心した経験はありませんか? 残念ながら、その「当たり前」を、忙しい時も、人間関係がうまくいかない時も、体調がすぐれない時も、「揺らがずに、高いレベルで継続できる人」は、実はそう多くないのです。私は、転職を繰り返す中で、良くも悪くも様々な職場や文化を見てきました。そこで気づいたのは、どんなに優れた専門性を持っていても、この「当たり前」のレベルが低い人は、チームワークを乱したり、信頼を得られにくかったりするということです。逆に、突出したスキルはなくても、「当たり前」の質が高い人は、どこへ行っても重宝され、自然と周りから頼られる存在になっていく。私の場合は、まさに後者を目指し、「当たり前」を磨き続けることに意識を集中させてきました。特に、私がこの「当たり前」を「揺らがずに徹底する」ことができるようになったのは、一児の母になった経験が非常に大きいです。子育ては、本当に自分の感情や都合だけではどうにもならないことばかり。予期せぬ事態の連続で、常に冷静な判断力と、相手(子供)に伝わるコミュニケーション、そして何があっても投げ出さない粘り強さが求められます。感情的になりたい瞬間も多々ありますが、それでは物事が前に進まない。どうすれば子供が納得するか、どう伝えれば理解してくれるか、どうすれば次に繋がるかを常に考え、自分の言動をコントロールする必要があります。
この「感情に流されず、目的に対して最適なアプローチを考える」という思考回路は、まさに仕事で「当たり前」を徹底するために必要なことでした。
ワーママとしての経験は、私のキャリアにおける、予想外の、しかし最大の強みになったのです。
では、具体的に私がどんな「当たり前」を意識しまくってきたのか、5つのポイントに絞ってご紹介します。
具体的に意識した5つの行動!
1. レスポンスは、とにかく早く
「確認しました」「〇〇(いつ頃)までに返信します」――たったこれだけの連絡でも、相手にとっては大きな安心感に繋がります。もちろん、すぐに完璧な回答ができないことの方が多いです。でも、ボールが自分にあるまま止まっている時間を極力短くする意識を持つことで、周りの人の思考や作業も止めずに済みます。特に、依頼した側は「ちゃんと届いているかな?」「いつ頃できるかな?」と少なからず気にしているものです。そこに素早く反応するだけで、「あ、この人は仕事が早い」「頼んだらすぐに動いてくれる」という信頼感に繋がります。
私の場合は、メールやチャットの通知は常に気にかけるようにし、内容をざっと確認したら、たとえ詳細な返信は後になるとしても、まずは「承知しました」「ありがとうございます、〇日までに〇〇します」といった一報を入れることを徹底しました。特に新しい職場では、このスピード感が「即戦力らしさ」として評価されることが多かったです。「分からないことはすぐに聞く」「進捗をこまめに報告する」といった、当たり前のコミュニケーションの第一歩が、この「素早いレスポンス」なのです。
2. 迷った時は、考えを伝えた上で「アドバイスいただけませんか」の魔法の言葉を使う
仕事に慣れないうちは、判断に迷うことや分からないことだらけです。そんな時、「どうすればいいですか?」と丸投げするのではなく、「〇〇について、△△な状況だと理解しています。今の私の考えでは、A案とB案が考えられるのですが、それぞれのメリット・デメリットは□□だと思っています。この場合、〇〇さんの視点から見て、どちらの方向性で進めるのが良いか、あるいは他に良いアイデアがあるか、アドバイスいただけませんか?」と質問するようにしていました。ただ質問するのではなく、「現状の理解」「自分の考え」「考えられる選択肢」「それぞれの考察」を一旦相手に提示した上で、「アドバイスを求める」という形を取ることで、相手は「この人は何も考えずに聞いているわけではないな」「ここまで自分で考えているなら、的確なアドバイスをしよう」と思ってくれます。これは、相手の時間を無駄にしないための配慮でもあり、自分自身の思考整理にもなります。この方法は、子育てで「魔の2歳児」や反抗期と向き合う中で磨かれたように思います。「あれしなさい!」と一方的に命令しても子供は動きません。子供の状況や気持ちを推測し、「〜な状況だよね? △△したい気持ちかな? でも、〜だからこうするのはどう? それとも、別の方法が良い?一緒に考えようか」と、子供の思考を促しつつ、選択肢を与えたり、一緒に解決策を探ったりするコミュニケーションに似ています。相手を尊重し、思考の過程を見せつつ、より良い解に導いてもらうこのスキルは、職場でも絶大な効果を発揮しました。
3. 頼まれごとをされた時は、笑顔で対応する
これも本当に当たり前のことですが、忙しそうにしていたり、眉間にシワを寄せたりしている人には、なかなか気軽に頼みごとをしようとは思えませんよね。逆に、少し忙しそうでも、話しかけられた時にサッと顔を上げて、ニコッと笑顔で「はい、何でしょう?」と答えてくれる人には、安心して話しかけられます。頼まれた仕事の内容にかかわらず、まずは「はい」「承知いたしました」と、気持ちの良い返事と笑顔を心がける。これだけで、「この人は引き受けてくれた」「嫌な顔をしない人だな」という印象を与え、人間関係を円滑にします。もちろん、内容によってはすぐに難しいことや、対応できないこともあります。その場合も、笑顔で「承知いたしました。ただ、今〇〇の件があるので、△△時頃に着手できますが大丈夫でしょうか?」など、代替案や状況を丁寧にお伝えすれば、相手は納得してくれます。子育て中は、どんなに疲れていても、子供が話しかけてきたら(可能な限り)笑顔で応える、ということを自然とやっている方も多いのではないでしょうか。親の表情は子供にとっての安心材料だからです。これは職場でも同じです。その笑顔は、周りの人にとっての安心材料になり、ポジティブな空気を作り出し、結果として自身に対する信頼と働きやすさに繋がります。
4. 頼まれたことを「+1」で遂行する
頼まれたことだけを、言われた通りにやる。もちろん、それはプロとして最低限必要なことです。でも、「即戦力」や「気が利く人」と見なされる人は、頼まれたことの「プラスアルファ」が自然とできています。
この「+1」というのは、何も大げさなことではありません。例えば、資料作成を頼まれたら、ただ言われた内容を文字にするだけでなく、 見る人が分かりやすいように、少し太字や色分けをする 、関連する過去の資料データも一緒に添付しておく 、会議で使うと分かっている資料なら、人数分の部数や、プロジェクター投影時の見えやすさも意識する といった、相手や、その先の利用者が「どうだったら助かるか」をほんの少し想像して、一工夫を加えることです。この一工夫は、必ずしも相手から指示されたわけではありませんが、これがあることで相手は「あ、そこまで考えてくれたんだ」「頼む以上のことをしてくれた」と感じ、仕事の質を高く評価してくれるようになります。これは、子育てで言うなら、「着替えを持ってきて」と言われた時に、着替えだけでなく、靴下と下着もセットで用意しておく、とか、「喉乾いた」と言われる前に、そろそろかな?と飲み物を用意しておく、といった先回りの気遣いや、「これがあると、後が楽になるかな」と考えて準備しておく姿勢に似ているかもしれません。相手のニーズを一歩先読みする思考は、仕事でも日常生活でも活きるスキルです。
5. 何気ない会話でも、ほんの少しの「人間らしさ」を含ませる
最後のこれは、スキルというよりは「人柄」や「雰囲気」に関わることかもしれません。仕事中のコミュニケーションは、業務連絡だけになりがちですが、そこにほんの少しだけ、あなたの「人間らしさ」や「ユーモア」を含ませることで、ぐっと周りの人との距離が縮まります。例えば、会議の中で発言するときに敢えて会話口調を入れると少し柔らかくなるので取り入れてみたり(やり過ぎは🙅♀️)、休憩中に最近あった面白い出来事をシェアしたり。堅苦しいビジネスチャットの合間に、可愛いスタンプを一つ挟んでみたり、といった小さなことです。これによって、あなたは単に「仕事をする人」としてだけでなく、「感情を持った、親しみやすい人」として認識されるようになります。これが、職場の雰囲気を和ませ、チームワークを高め、結果として「この人と一緒に働きたいな」という気持ちに繋がり、リファラルでの転職など、キャリアの良い流れを引き寄せることに繋がるのだと感じています。
子育てを通じて、子供と良い関係を築くためには、真面目な話ばかりでなく、一緒に笑ったり、ふざけ合ったりする時間がいかに大切かを学びました。職場も同じ。人間関係は、業務効率だけでなく、個人の働きがいにも大きく影響します。完全なプライベートを持ち込む必要はありませんが、ほんの少しの「隙」や「遊び心」を見せることは、あなたの魅力を引き出すことになります。
まとめ
私が転職11回というキャリアでも職に困らず、新しい場所で即戦力として必要とされてきた理由は、特別なスキルがあったからではなく、「社会人としての当たり前」だと言われるような基本的な行動を、誰よりも、そしてどんな状況でも「揺らがずに」やり抜くことを徹底したからだと考えています。
素早いレスポンス、考えを添えた質問、笑顔での対応、プラスアルファの気遣い、そして親しみやすい人間性。これらはどれも、今日から意識すればできることばかりです。そして、これらの「当たり前」を継続する力は、子育てのような、マニュアル通りにいかない、感情のコントロールと臨機応変な対応が求められる経験を通じて、図らずも私の中に培われていたものでした。
「自分には専門スキルがないから…」「もう若くないから…」「転職回数が多いから…」と諦める必要は全くありません。これまでの社会人経験や、もしかしたら子育てや介護といったプライベートの経験を通じて培ってきた、どんな環境でも役立つ「当たり前をやり抜く力」こそが、揺るぎない市場価値なのです。
もし今、転職活動に不安を感じていたり、ご自身のキャリアに自信が持てなかったりしても、大丈夫です。これまでの経験は、決して無駄ではありません。むしろ、様々な環境に適応し、人との関係を築いてきたあなたの経験こそが、これからの時代に求められる「即戦力」としてのポテンシャルなのです。
まずは、今日ご紹介した5つの「当たり前」を、日々の仕事や、もし可能であれば今のうちから転職活動の準備として意識してみてください。きっと、周りの見る目が変わるのを感じるはずです。
このでは、私の転職経験や、ローキャリアでも自分らしく働くための考え方について、これからも発信していきます。もしこの記事が少しでも励みになったなら、「スキ」や「フォロー」をいただけると嬉しいです。
皆様のキャリアが、希望に満ちたものになるよう、心から応援しています!
#転職 #ワーママ #転職回数多め #ローキャリア転職 #仕事 #転職体験談 #40代転職 #40代キャリア
Views: 0