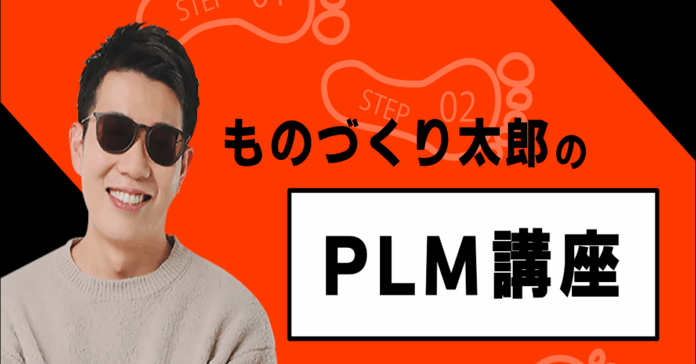🔸 ざっくり内容:
日本の製造業は「すり合わせ」や「現場力」が強いという高い評価を得ていますが、設計、製造、調達などのプロセスが分断されており、多くの手作業が必要とされています。この問題を解決するために、PLM(プロダクトライフサイクル管理)の導入が求められています。
本連載では、製造業に精通したものづくりYouTuber、ブーステックの永井夏男氏が、PLMの必要性とその導入方法について解説します。特に第2回目では、日本の製造業がPLM導入に失敗する理由について詳しく掘り下げます。この指摘は、製造工程の効率化や情報共有の重要性を再認識させるものであり、業界関係者にとって非常に参考になる内容です。
PLMを導入することで、製品の企画から廃棄までを一貫して管理できるため、分断を解消し、効率的なものづくりが可能になります。次回以降の内容にも注目が集まります。
🧠 編集部の見解:
この記事のテーマは、製造業における「すり合わせ」や「現場力」といった日本特有の強みが、実は分断を生んでいるという点ですね。筆者が感じたのは、これまでの日本の製造業の枠組みが、時代の変化についていけずにいるのではないかということです。
### 感想
製造現場でのコミュニケーションがしっかりしているのは良いことですが、設計と製造がしっかり連携できていないと、結局「人力」に頼る部分が増えてしまいます。これでは生産性も低下しますよね。PLM(Product Lifecycle Management)の必要性が語られることで、今後の製造業におけるシステムの重要性が増すのではないかと期待しています。
### 関連事例
たとえば、自動車業界では、トヨタの生産方式が有名です。しかし、近年ではテスラのように、デジタル技術を駆使して効率化を進める企業も登場しています。これがいい刺激になって、従来の手法にも新しい風を吹かせる可能性がありますね。
### 社会的影響
これにより、製造業がもっと効率化され、コスト削減や迅速な市場投入が可能になれば、消費者にも良い製品が届くようになるはずです。また、国内外の競争も激化し、結果的に企業の成長につながるでしょう。
### 豆知識
実は、PLMの概念は1960年代から存在していて、当初は航空宇宙産業でのリーダブルな製品管理システムとして始まりました。今では、ほぼすべての製造業で導入が進んでおり、特にアメリカやドイツの企業はこの分野で先行しています。
日本の製造業がこの波にどう乗っていくのか、今後の動きに注目です!
-
キーワード:PLM
※以下、出典元
▶ 元記事を読む
Views: 2